2011年04月30日
熊本で負のスパイラルに陥りました!
 いやはや・・・。どこに落とし穴があるか分からない。
いやはや・・・。どこに落とし穴があるか分からない。熊本のマンションからバスに乗って通町筋に出てきた。バス代は200円ポッキリというのが嬉しい。典型的なお上りさん気分。がしかし、財布の中を見ると、130円と万札しか入っていない。
通町筋からは市電に乗って新水前寺駅前電停まで乗るつもりだったが、電車の料金は150円。1万円札はたぶん運転手が嫌がるに違いない。何とか50円玉が欲しいと思った。
それならと思いついたのが、上通・八起堂でのたばこの購入。1万円札で1箱というのも何だから、2箱買うのはどうか。いや、それも何となく気が引ける。
それで隣のまるぶん書店に入る。
この連休中に本は読むだろうが、あんまり買いたくない。「文庫本みたいな安価なものを一冊だけ。衝動買いはダメ」と思っていた。しかし、書店に入ったという行動自体が敗北を意味していた。
購入した書籍は、以下の通り。
■和田秀樹『脳科学より心理学 21世紀の頭の良さを身につける技術』ディスカバー携書(2011年4月15日第1刷)
・私自身、小分類では心理学系のマーケッター及びリサーチャーの末端に分類されると思うので、読まねばなりますまい。「20世紀型科学としての脳科学の限界が推測される一方で、ソフトを扱う心理学の可能性が見直されてきている。」。この一文にわくわくしてしまう。
■Newton別冊「ニュートンの大発明 微分と積分」ニュートンプレス(2011年5月16日発行)
・発明とか発見、何かに気づいた時の喜びは何ものにも代え難いものがある。20数年前、Macintoshの統計解析ソフト「Statview」を操作していて、アンケートの複数回答の処理に悩んだことがあった。選択肢を1つだけ入力する単一回答の操作は簡単にできるが、例えば10ある選択肢のうち3つとか5つとかを入力する方法はどうするのか。大学の先生に聞いても、研究者の頭は整理されているので単一回答の入力機能だけで十分との回答。英語の解説書を読んでも、複数回答の処理とかはどうも書いてなさそう。たぶん少なくとも三ヶ月は頭から離れなかったが、ある夜中、『選択されていたら「1」、選択されていなかったら「0」とすればいいやん!』と閃いた。まだ母集団推計やカイ二乗検定、分散分析程度の解析知識しかなかった頃、多変量解析をする時にけっこう使われている「ダミー変数」という考え方を自分が勝手に思いついたことに感動した。自分の話が長くなったが、天才たちがどのようにして数式を編み出していったか、そんなことが書いてありそう。それと、数Ⅲの参考書をよく開いている娘の関心を惹きたいという思いもある。
ということで、書店にて多少散財。それでも100円玉1枚、10円玉5枚、計150円をズボンのポケットにしまい、はれて通町筋電停に向かった。すると、何やら人がいっぱい。整理係のアルバイトのおじさんみたいな人(緊急雇用対策か?)までいる。しかも、昭和の高度成長期みたいに電車が数珠つなぎになって次々と走ってくる。1台目はパスし、2台目に乗るが、やはり満員。「連休って、市電に乗る人が多いのか?」と思いながら運転手席の方を見ると、「29日、30日は無料」と張り紙に書いてある。
つまり、“タダ!”。わざわざ150円用意したのに。しかも約1時間半あまりの時間と書籍購入費を浪費したと思っていると、新水前寺駅前電停に到着。すると、ぽたっぽたっと雨が降り出し、直後、稲光と雷鳴がほぼ同時に炸裂!スコールのような雨の中を申し訳程度の傘をさして歩くこと10分。ずぶ濡れ。
電車がタダという情報を持っていなかったためだと思われる全くのシナリオなしの行動と負のスパイラル。マイナスのスパイラルの渦にはまり込み螺旋状に陥っていく罠にはまり込んでしまった。
たぶん、このことを書いた後は、上昇気流に乗っていくものと、おおよそ判断できるものである。
Posted by わくわくなひと at
18:27
│Comments(5)
2011年04月25日
福岡・博多“流通戦争だよ全員集合!”既に終了!
 不覚でした!
不覚でした!この一つ前のブログで、大塚ムネトさんがそろそろ“かぶりもの”演劇を企ててるかも?と書きましたが、つい数日前まで、やってたんですね。
ぎんぎら太陽’Sからのメールもいただいてましたが、中身を確認する余裕がありませんでした。
こんな内容です。やはりパルコも新人として登場してました。
怒濤の新企画!春・夏・秋と短編集を連続上演
「流通戦争だよ全員集合!」
いよいよ街が動き出す2011年がやってきた!この福博に果たして何が起きるのか…?
そこで今年は、タイムリーな街ネタを春・夏・秋と連続上演。街の変化を「すぐに舞台化する
体制」で臨みます。さあギンギラと一緒に街の目撃者になろう!
あっという間に終わる小ネタから、約20分の北海道版ミニ開拓史、パルコキャラ発表会な
ど、楽しさを集めた短編集。上演時間は60分を予定しています。
作・演出 大塚ムネト
■上演を予定している内容
①新キャラパルコ発表会
ギンギラ展の会場とパルコHPで募集した「新キャラパルコ案」を集計。ついに、ギンギラ初の「公募キャラ」が登場します!
②短編「北海道版開拓史」
JRの再開発で街の中心が変わった札幌。北海道にも「街を支えた方の熱い物語」があった!現地取材を元にした「北の物語」。
③最新「街小ネタ」も登場予定
いよいよ完成した新博多駅に、閉店が決まった専門店街などの最新「街小ネタ」も登場予定です。何が出るかはお楽しみ!
出演者
大塚ムネト 立石義江 杉山英美 上田裕子 中村卓二 古賀今日子
中島荘太 石丸明裕 /他
日時 2011年4月22日(金) 開場13:30 開演14:00/開場19:00 開演19:30
4月23日(土) 開場13:30 開演14:00/開場17:30 開演18:00
4月24日(日) 開場13:30 開演14:00/開場17:30 開演18:00
会場 西鉄ホール
〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目11-3ソラリアステージ6F
TEL092-734-1370
入場料 全席指定¥3,000 (金曜昼のみ「平日昼の特割料金¥2,000」)(税込)
発売日 3月19日(土)10:00~
発売方法 ◆ピクニック
(郵送販売のみ)
◆チケットぴあ
◆ローソンチケット
◆e+ イープラス
◆ちけっとぽーと
092-715-0374
0570-02-9999(Pコード:410‐507)
0570-084-008(Lコード:87878)
http://eplus.jp/(PC&携帯)
092-716-8022(ソラリアプラザ店1F)
092-235-7223(福岡パルコ店5F)
※店頭混雑時電話に出られない場合があります。
主催・企画制作 ギンギラ太陽’s、アンミックスエンタテインメント、ピクニック
出演協力 che carino!/che carina!、パブリックチャンネル、
お問合せ ピクニック 092-715-0374http://www.picnic-net.com
※未就学児童のご入場はお断りいたします。
※車イスでご来場予定のお客様はピクニックまでご連絡下さい。
Posted by わくわくなひと at
10:45
│Comments(0)
2011年04月23日
天神のパルコとTSUTAYAが垂れ幕でエールを交換!
 今日は天神の福岡ビルの9階に用事がありました。大名の事務所から福岡ビルに行く時は、いつもなら岩田屋の地下に行って、それから地下街を通って福ビルの地下から上の階に昇っていきます。
今日は天神の福岡ビルの9階に用事がありました。大名の事務所から福岡ビルに行く時は、いつもなら岩田屋の地下に行って、それから地下街を通って福ビルの地下から上の階に昇っていきます。今日はなぜだか地上を歩いて行きました。9時半過ぎだったので岩田屋が開いてなかった。それだけのことかも知れません。それでも、たまにはいいものです。面白いものに出会えます。
福ビルの2階と3階には、今月に入ってTSUTAYAがオープンしました。私が贔屓にしていた丸善跡にすっぽりTSUTAYAが入りました。
地上の渡辺通りの交差点から福ビルを見ると、こんな垂れ幕がかかっていました。
「パルコさん お向かいから笑顔と希望をお届けして参ります!」
ということはと思って、ふり返ってパルコのビルと見ると、
「TSUTAYAさん、ようこそ天神交差点へ!」。
福岡には、かぶりもの演劇があります。岩田屋、三越、大丸、イムズ、ソラリア、ミーナ天神のビルを真似たかぶりものを頭の上に載せて行う演劇があります。川端にあった玉屋も着物を着て登場していましたね。ギャングのような西鉄バス軍団が天神界わいは我がものとばかりに会場を走り回ります。心の狭い経営者ならば、怒るようなネタもありますが、それができるところが“芸所”博多のDNAか?
この演劇の影響か、一年以上前に、「イムズよ・・・」「ソラリアよ・・・」という向かい合うファッションビルが垂れ幕でエールの交換をしていました。
今度は、TSUTAYAとパルコがエールの交換を始めました。
それで思い出したのが、かぶりもの演劇の新作がそろそろ出そうという予感です。
今度は恐らく阪急、JRアミュプラザ、新幹線のかぶりものも登場することでしょう。何とかムネトさんが今ごろ面白いストーリーを考えていることと思います。

Posted by わくわくなひと at
23:07
│Comments(2)
2011年04月21日
小池真理子と宮本輝 蛍の表現を比べてみたくなりました!
 小池真理子『水底の光』文春文庫(2009年8月10日第1刷)の「闇に瞬く」の中に、蛍のことが書いてありました。
小池真理子『水底の光』文春文庫(2009年8月10日第1刷)の「闇に瞬く」の中に、蛍のことが書いてありました。少し歩くと、川が近づいてきたのがわかった。やわらかなせせらぎの音が大きくなってくる。河鹿の鳴き声がそれに混じる。
黒々と闇にのまれた木立を抜け、右に折れると、とたんに視界が開けた。「いるいる!」と泉が声を押し殺しながら言ったのと、中空を流れるように飛び交う無数の蛍の明滅を奈々子が目にしたのは、ほとんど同時だった。
星のごとく瞬く光は優しくおぼろに淡く、それでいながら、闇に確実に照り映えて、川面を映している。月の光のようである。右に左に、上に下に、音もなく蛍は流れ、その不規則な、つかみどころのない光の群れは、幾条もの細い髪の毛ほどの筋と化して闇に消えていく。
川幅はせいぜい六、七メートル程度で、対岸の木立の輪郭もなぞることができる。闇に目が慣れるにつれ、闇が闇ではなくなっている。濃い闇の中に、うすぼんやりと明滅する蛍がとけて、闇自体が水墨画のような淡さを伴うものになりつつある。
それで宮本輝『螢川』(昭和52年)の以下の一節を味わいたくなりました。
千代とて、絢爛たる螢の乱舞を一度は見てみたかった。出逢うかどうか判らぬ一生に一遍の光景に、千代はこれからの行末をかけたのであった。
また梟が鳴いた。四人が歩き出すと、虫の声がぴたっとやみ、その深い静寂の上に蒼い月が輝いた。そして再び虫たちの声が地の底からうねってきた。
道はさらにのぼり、田に敷かれた水がはるか足下で月光を弾いている。川の音も遠くなり懐中電灯に照らされた部分と人家の灯以外、何も見えなかった。
せせらぎの響きが左側からだんだん近づいてきて、それにそって道も左手に曲がっていた。その道を曲がりきり、月光が弾け散る川面を眼下に見た瞬間、四人は声もたてずその場に金縛りになった。まだ五百歩も歩いていなかった。何万何十万もの螢火が、川のふちで静かにうねっていた。そしてそれは、四人がそれぞれの心に描いていた華麗なおとぎ絵ではなかったのである。
螢の大群は、滝壺の底に寂寞と舞う微生物の屍のように、はかりしれない沈黙と死臭を孕んで光の澱と化し、天空へ天空へと光彩をぼかしながら冷たい火の粉状になって舞いあがっていた。
四人はただ立ちつくしていた。長い間そうしていた。
(中略)
その時、一陣の強風が木立を揺り動かし、川辺に沈澱していた螢たちをまきあげた。光は波しぶきのように二人に降り注いだ。
英子が悲鳴をあげて身をくねらせた。
「竜っちゃん、見たらいややァ・・・・・・」
半泣きになって英子はスカートの裾を両手でもちあげた。そしてぱたぱたとあおった。
「あっち向いとってェ」
夥しい光の粒が一斉にまとわりついて、それが胸元やスカートの裾から中に押し寄せてくるのだった。白い肌が光りながらぽっと浮かびあがった。竜夫は息を詰めてそんな英子を見ていた。螢の大群はざあざあと音をたてて波打った。
Posted by わくわくなひと at
18:09
│Comments(0)
2011年04月21日
小池真理子『水底の光』~一瞬の心もようを素直に正直に表現
 小池真理子『水底の光』文春文庫(2009年8月10日第1刷)。「オール讀物」に2004年から2006年に掲載された6つの短編がおさめられています。
小池真理子『水底の光』文春文庫(2009年8月10日第1刷)。「オール讀物」に2004年から2006年に掲載された6つの短編がおさめられています。短編 はあまり時間がとれない時に、一服の清涼剤として読むといいですね。がちがちになった脳細胞がストレッチされるような気分になれます。小池さんの作品は男女のことが多いようですが、その中でも自然描写で「はっ」とする表現に出会えます。こんな自然の感じ方とか表現の仕方があるのか、そんな驚きに応えてくれるところがいいですね。
あとがきに、こんなことが書いてありました。
・・・短編は、私の場合、「その日その時」の一瞬の自分自身の心もようが、大きく影響する。・・・その時、流れ続けている何かは、思いの外、素直に正直に、表現されてしまうらしい。
そうなんだろうと思います。本人が思ってもみなかった素直さと正直さ。だから、覗いてみたくなります。
後はメモっておきたい箇所です。
「パレ・ロワイヤルの灯」
「僕はりえをものすごく愛している。こんなに女の人を愛したことはないし、これからもないよ。でも悲しいね。腹立たしいね。僕はこんなに愛しているきみを幸せにすることができない」と。
・・・
幸せにする、というのはどういうことなのだろう。あれからずっと、わたしは考えている。
「闇に瞬(またた)く」
水音の中に、時折、河鹿が鳴く声が混じる。野鳥の囀りも遠くに聞こえる。水の匂い、湿った夏の緑の匂いが部屋の中にまで漂ってくる。
・・・
雨はやまなかった。小降りになったかと思うと、再び雨足を強め、緑滴る小さな庭先の木々の葉をたたいた。開け放した窓の向こうから、水の匂い、土の匂いがしとどに部屋の中に流れこんできた。
「愛人生活」
なだらかな丘が幾重にも連なる遙か向こうに、小さく扁平に街並みが拡がっている。夜ともなれば、街の灯はちかちかと星のように、音もなく瞬く。
・・・
日の光も射していないというのに、木々や草が瑞々しく雨に濡れ、空気そのものが淡く発光しているかのように、あたりはうすぼんやりと明るかった。
遠く近く、野鳥の囀る声が聞こえてきた。木の葉から滴り落ちる雨が草を打ち、大地を打った。音とも呼べない音が、まるで谷間に谺する水音のように響いていた。
・・・
「予定調和の中にある人生はつまらない。こうしてああして、ああやって、こんなふうに年老いて死んでいく・・・・・・それが見えてしまうのはたまらなく退屈なんだよ。そんな人生を送らなくちゃいけなくなったら、俺は迷わず自殺するね。死んだほうがましだ。ただのエゴイストだ、どうしようもない男だ、って女房にはさんざん罵倒されたけど」
「ミーシャ」
左知子の目は、上野駅を出た新幹線の窓の外の、雑然とした都会の夜の風景を見ている。居酒屋やスナック、英会話教室、ラブホテル、サウナ、いろいろなネオンが折り重なるようにして煌めいているのが見える。なのに心の中にある目が溶け始め、裂けていき、そこから記憶という記憶がどっとあふれ出してくる。現実に目にしている街の夥しい明かりの群れに、記憶の中の映像が静かに重なっていく。
・・・
・・・その笑い声も、話し声も、左知子にとっては水の中で聞く音のように実感がない。
Posted by わくわくなひと at
17:27
│Comments(0)
2011年04月21日
【熊本市電】健軍町だけでは水前寺に行くか分からない
 旅行者向けの案内やサインは難しいですね。
旅行者向けの案内やサインは難しいですね。昨日のこと。通町筋から味噌天神まで熊本市電に乗りました。
私の前に並んでいた老夫婦(60歳代くらいか)とおぼしき方たちが、健軍町行きの電車にいったん乗って、慌てて降りられました。私のすぐ前だったので、「水前寺公園には行かへん」?と聞こえました。「あ!関西方面からの方々だ」と思って、「水前寺に行きますよ」と声をかけましたが、ドアが閉まって出発進行です。何だかばつが悪かったですね。
確か市電の行き先表示(電車の顔の上の表示)は、「健軍町」としか書いてありません。地元の人には水前寺公園前を通って健軍町に至ることは分かりますが、初めて訪れた人はそこまでの情報はありません。電車の路線図やほかの表示を見れば、当然、分かることですが、そこまで見ない人も多いようです。
実は、昨日の件で二度目です。二三週間前には同じ通町筋の電停で、「健軍行き」の電車に乗っている時、「これ熊本駅に行くんでしょう?」と聞かれました。その時は、「熊本駅は反対方向ですよ」と伝えましたので、その方は無事「熊本駅」行きに乗られたことと思います。
観光客など、よその人が行く場所は、サブタイトル扱いでもいいから、表示しておいた方が不安にならずにすみますけどね。
サインや表示は、大都市になるほど工夫されているようです。東京の地下鉄に乗っても、どこの出口が目的地に一番近いかすぐ分かるような表示やサインが整っています。確か福岡市営地下鉄でも、「福岡空港行き」のほか「博多駅」を経由することが分かる表示がありますし、九州大学や福岡県庁方面に行く貝塚行きに間違って乗らないような表示や放送がくどいようにしてあると思います。
熊本市も政令市になって大都市の仲間入りをしますので、このあたりの工夫は日々重ねていかれることと思います。九州新幹線が全通して、確かに関西弁を話される方を熊本でもよく見かけるようになってきました。
Posted by わくわくなひと at
13:17
│Comments(0)
2011年04月20日
天草のイルカウォッチングが大阪大の研究報告書に
 大阪大学の大学院生から、A4判、100ページあまりの研究報告書が送られて来ました。
大阪大学の大学院生から、A4判、100ページあまりの研究報告書が送られて来ました。これを見てすぐ思い出しました。去年の夏だったか、天草のイルカウォッチングの話を聞きたいと、大阪大学の大学院生が訪ねてきました。
このブログではありませんが、私のブログや以前の職場の研究レポートを読んで、わざわざ九州まで来たということでした。たいした話はしませんでしたが、大学院生からみると、私は“話しやすい人柄”と手紙に書いてあり、どんな感じで何を話たんだろうと思い出そうとしましたが思い出すことはできませんでした。
この冊子は、大阪大学工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻・都市再生マネジメント領域「まちづくり天気図」(平成22年度大学院教育改革支援プログラムイノベーションリーダー養成プログラム、2011年2月)と題したものです。
日本各地で展開される、さまざまなまちづくり・地域活性化の取り組みの中で、ひときわ個性的で魅力的な“元気な”まちづくりを進めている地域の一つとして、天草市五和町二江のイルカウォッチングの取り組みが紹介されていました。
同じ熊本県でも黒川温泉は、本や論文によくとりあげられています。黒川温泉の物語は再生の話です。イルカウォッチングは、今までになかったものが、平成4年に突然(消費者から見れば)立ち上がって、今では地域の重要な産業になっている事例です。
なぜだか分かりませんが、本や論文にはなっていません。私は膨大な思い出と当時のいくばくかの資料やメモを持っていますので、死ぬまでに書くかもしれません。論文よりも小説になりそうなネタもあります。
それはともかくとして、自分の話したことや関わったことの一部が論文や活字になっていると、嬉しいですね。
大学院生が書いたレポートのタイトルと小見出し等は、以下の通りです。
「イルカウォッチングでつくる交流のまちづくり -熊本県天草市五和町二江 通詞島」
(知見のみ抜粋~)
□知見
●地元産業従事者とウォッチング業者の連携
イルカウォッチングでは収入に不安要素のある漁師と船を持たないウォッチング業者のニーズがうまく噛み合い、更に漁船を利用することが本物という更なる価値を生むこととなった。
地域の活性化を行う上でいかにして地元住民を巻き込むかは大きな課題である。五和町の中でも通詞島では漁業従事者が大半であり、その人々を上手く巻き込みWIN-WINの関係を構築した点は継続性を考えた場合重要な要素である。
●身の丈に合った儲け方
観光地化を行う際にはそれに反対する勢力が必ずといっていいほど存在する。五和町でも様々な抵抗勢力があった。
しかしマスコミへの露出を多く行う等して先手で対策を行っていたことにより、順調にイルカウォッチング事業を進める事ができた。
従事者が事業を積極的に行える環境を作り上げる事も、地域で前例のない取り組みを行う上で必要なことである。
●まとめ
今回の調査を通して地域資源を活かした観光地化の可能性を大きく感じることができた。地理的に不利な地域でも、信念を持って継続することにより小さな積み重ねが大きな結果を生み出す事ができることに、我々人間の可能性の大きさを垣間見ることができた。
しかし一方で観光のみにまちづくりが偏る事に問題もあり、いかに地域住民が参加するまちづくりに繋げていくことができるかが継続するにはポイントになってくる部分であろう。

Posted by わくわくなひと at
18:58
│Comments(0)
2011年04月13日
紙製じゃばらファイルのフェチになりました!
 今日も博多駅界わいに出没してしまいました。
今日も博多駅界わいに出没してしまいました。何しろ師匠のU先生が博多駅で数時間過ごして新大阪に戻るということですので、博多駅の改札口でお出迎え。その後は博多駅のゆったりしたラウンジで打合せを行う予定でした。
それで、さっそく博多駅のアミュプラザにある博多駅前が展望できるティーラウンジに案内しました。ところが、そのお店は満員かつ行列。困ったなぁと内心と思いましたが、U先生の様子はそうではなさそうでした。それはアミュプラザに東急ハンズがあったからです。何か気になる商品があったのでしょう。数分間、先生を見失ってしまいました。
先生はまず文具売り場に行かれ、この間、東京の東急ハンズになかったので注文したファイルがあるかどうか見てみたいということでした。「うん。うん。博多にもないぞ」と一人納得した様子。「一度、東急ハンズで○○○(聞き取れず)のファイルを買ったんだけど、書棚をこのファイルで揃えたくなっちゃってねぇ。この店は面白よ!」だそうです。
その後、バッグ売り場に立ち寄られ、リュックを一生懸命見ておられました。「今のリュックがそろそろいたんできたんでねぇ」。
結局、駅前のホテル日航のティーラウンジで打合せをし、その後、新大阪へ向かわれるU先生を見送りました。
そして、再びアミュプラザの1階を歩いていると、「Smith」という文具店がありましたので、ほんのちょっと立ち寄りました。そこで、また紙製のじゃばらファイルに出逢いました。このファイルは先週末、東急ハンズで購入したものよりも一回り大きいサイズ。じゃばらの収納ファイル数は20あり、それぞれファイルの縁にA~Z、1~31までの文字がふってあります。たぶんメーカー名だと思いますが、VARIOSと書いてありました。値段は2,730円で外国から輸入しているものなので、展示品しかないということでした。こうなったら買いです(半分、頭の中で馬鹿じゃないか!という声も聞こえました)。
むふふ!先週、購入したモレスキンのじゃばら紙ファイルは手帳機能として使います。そして、今日、購入したVARIOSはレポートや報告書を書いていくために必要な各種ドキュメントを入れておいて、机の横に置きながら頭の中を整理していく時に使う予定です。しかも大名だろうと熊本だろうと持ち運び可能です。
うん、これはおしゃれだし、ゆるーい頭も少しはシャープになりそうな予感です。

Posted by わくわくなひと at
21:58
│Comments(0)
2011年04月13日
稲原豊命写真展 6日から熊本市現代美術館で開催中
 卒業した大学の文学部の先輩から原稿用紙とパンフレットが突然送られてきました。
卒業した大学の文学部の先輩から原稿用紙とパンフレットが突然送られてきました。昔ながらの原稿用紙に万年筆で書き慣れた文字が綴られていました。同僚から、「そろそろ万年筆にこだわったらどうだ」と指摘されている私としては、心が揺さぶられます。原稿用紙に肉筆。その人のエネルギーや思いが伝わってきます。人生の晩年を意識するような齢となり、何を残すかという思いも、頭の片隅に思う浮かぶようになってきています。味気ない電子データと比べると、肉筆には本人が滅びたとしても感じる人には伝えられるものがあると改めて思いました。
中身を読むと、何と「サイクル-環の江津湖」と題した写真展を熊本市現代美術館で開催すると書いてあります。5月8日までの開催です。
この哲学科の先輩(ちなみに私は同じ文学部でも史学科です)は、いつも福岡と熊本で美少女の写真を撮っていると思っていました。私が遭遇するのは、天神西通りの岩田屋本館前で、カメラと三脚を持って、じっと街行く人を眺めている先輩の姿です。それが、ここ十年程江津湖の写真を撮っていたというので、驚きました。ここのところ雑誌「NO!!」のホームページで400字のエッセイを載せているそうです。少し覗いてみると、先輩らしくモノクロ写真に独特の視点での文章を綴っています。最近は何でも4色、美術書になると5色の印刷とか、世の中、色だらけですが、モノクロ写真は何かを語りかけてくるような感じがしますし、自分の想像力が刺激されます。エッセーには、メタファーを意識しながら写真を撮る。最近、そんなことをしているようなことが書いてありました。
パンフの裏には、こんなことが書いてありました。
夏の日の午後、江津湖で写真を撮っていた。あちこちでガサガサ、ゴソゴソ音がする、水辺では大小の魚が急いで一方向に泳いでいく、葉っぱの裏を見るとたくさんの虫たちが一斉にどこかに移動していく、ガサゴソの音の原因がこれだったんだと思う間も無く、私の頭にポツリポツリと雨が!その雨は瞬く間に激しい夕立となった。
すごい、自然は本当にすごい、江津湖には全てがある、この日から私の江津湖通いが始まった。
春に花が咲き、夏に茂り、秋に枯れ、冬に落ちる、それはもう人の一生の様。
こんなに街の中心部近く、こんなに自然そのままの草木や湧き水、こんなに四季の変化に富んだ公園、全国を撮影で回った私も他に知らない。
ここには人生がある、サイクルがある、環がある。
(以下略)

Posted by わくわくなひと at
02:07
│Comments(0)
2011年04月11日
【津軽百年食堂】もう少し弘前の自然を描写して欲しかった?
 津軽を舞台にした古い食堂の創作物語「津軽百年食堂」を観てきました。監督は大森一樹、主演はオリエンタルラジオの二人。ヒロインは熊本市立京陵中学出身の福田沙紀。来月閉館になる「シネ・リーブル博多駅」で、ひっそりと公開されていました。
津軽を舞台にした古い食堂の創作物語「津軽百年食堂」を観てきました。監督は大森一樹、主演はオリエンタルラジオの二人。ヒロインは熊本市立京陵中学出身の福田沙紀。来月閉館になる「シネ・リーブル博多駅」で、ひっそりと公開されていました。観客は私も含めて4人。男性1人、女性3人。席数はたぶん50以上あった中で、ひっそりと、隣の新博多駅の賑わいが嘘のように静かな映画鑑賞をしました。
日本人の心と味がテーマ。人間ドラマとしては気負いもなく、ごくふつうのその辺に居そうな人たちの心温まる物語でした。そんなに興奮することもなく大げさでもない。少し目頭が熱くなる程度。映画というよりもテレビドラマの秀作という感じでしたね。
好き嫌いがあると思いますので、おせっかいになりますが、個人的には森沢明夫の文章から感じる自然の脈搏というのか?そういうところをもっと表現して欲しかったと思いました。
例えば原作には、こんな文章があります。
「桜の花びらが地面に着地するときの、はらり、という音が聞こえそうなくらいに雑音がない。ただ、二人の足音だけが、妙に大きな音になって辺りに響き渡っていた。」
映画で表現するのは難しいと思いますが、人によっては映像と音で表現できそうな感じがします。映画には満開の桜、弘前城、私にはキリマンジャロみたいに見えた八甲田山(?)がたくさん出てきます。わざとかも知れませんが、カメラで言えば28ミリ、35ミリ、50ミリのレンズで覗いたような映像がたくさん出てきました。“はらり”という音はカメラで言えば接写リングを付けて撮るような感じでしょうか。実は、静寂を語るというか、いてつく寒さと雪、それだけに待ち遠しい満開の桜の季節、そんなことを期待して映画を観ている自分に改めて気づきました。
「窓を開けた。すうっと流れ込んできた空気は、ひたひたに水分を含んでいて、首筋にひんやりとまとわりついた。少し埃っぽいような雨の匂いを大きく吸い込む。」
これを映像でどう表現するんだろうと、期待していました。監督の好みや作風が違うということでしょう。
それで思い出したのが、スピルバーグの「プライベートライアン」の一場面。葉っぱにぽたっぽたっと雨粒が落ちてきて、それがやがて滝のような雨になり、水たまりを軍靴が踏みしめていく。確か水たまりに兵士の姿がうっすらと映っている(神宮外苑での学徒出陣の記録映画にも、こんな表現がありました)。
これはスピルバーグが黒澤明など日本人から学んだ表現方法だと思うのです。勝手に、こんな映像を期待していましたので、不足を感じたのでしょうね。
それにしても映画を見終わった後、鰯の煮干しで出汁をとった「津軽そば」は無理ですが、無性にそばを食べたくなりました。
いつか弘前に行って津軽そばをいただきます。

Posted by わくわくなひと at
20:38
│Comments(0)
2011年04月11日
東急ハンズでモレスキンの紙ファイルをゲット!
 一昨日、博多駅の阪急、東急ハンズなどをチラ見しました。
一昨日、博多駅の阪急、東急ハンズなどをチラ見しました。もともとの目的は丸善にありましたが、期待はずれ。ジュンク堂みたいな感じで、これだったら天神のジュンク堂でいいかなと思いました。丸善は、やはり東京駅の前にある本店?ですね。丸松本舗とかあって知的オーラに満ちています。かつて丸善があった天神の福ビル2階には、15日か何だかTSUTAYAができるそうです。大名の事務所からは、この店が一番近くて便利なんで、ひょっとすると最寄りの書店になるかもです。
ところで今年に入って手帳に悩んでいました。A4判の仕事上重要な紙を手帳に挟む習慣がついてますので、ずっとA4判の手帳はないか探していました。でも、お気に入りのものはないので、1月からB5判の手帳を使ってきました。不満を持ちながら仕方なくです。
しかし、東急ハンズに行って、モレスキンのA4判紙ファイルを見て、閃きました。
すべて紙製で中身がジャバラ状になって6つのファイル収納袋が付いていました。これにA5判の手帳をしまい、仕事上重要な紙は他の5つの収納袋に入れとく。外側は黒色で例のモレスキンですので頑丈。手帳売り場の大人のこだわり文具コーナーでの出逢いです。
手帳はA5判のLACONICを買いました。これにアポイントやto do listを書いておけば、十分役立ちそうです。それと、この手帳の表紙に頻繁に連絡をとりあう人々の名刺とかポストイットに書いたような覚書が挟めるようになってますので、けっこう解決したかな?
これとは別に伝統的なCOACH(昔のCOACHのデザインで今のとは全然違う)の革製A4判仕事ファイルを持っています。とてもトラッドで格調高くお気に入りですが、これをバッグにしまうと重い。紙製のモレスキンファイルはずいぶん軽くて頑丈ですので、そのあたりの悩みも解決です。
Posted by わくわくなひと at
12:41
│Comments(2)
2011年04月06日
クッキーにしちゃいましたシリーズ!勢揃い
 あや3様のリクエストにお応えして、「クッキーにしちゃいましたシリーズ」が勢揃いした写真を掲載します。
あや3様のリクエストにお応えして、「クッキーにしちゃいましたシリーズ」が勢揃いした写真を掲載します。先日の「はーとアラウンド」びぷれす販売会では、「辛子蓮根」がトップで売り切れ。これに次いで「しょうが」(テルサ&ライン工房)、「塩トマト」(同)、「ブルーベリー」(同)、「みかん」(同)、「とんこつ」(テルサ&なずな工房)の順で売れたそうです。
どれも、よく売れたのには違いありませんし、おかげで売り場が活気づいたそうです。
通常は熊本テルサで売ってるそうです。
Posted by わくわくなひと at
17:11
│Comments(6)
2011年04月06日
これ博多駅でも売れそう!辛子蓮根クッキー
 クッキーしちゃいましたシリーズの「辛子蓮根」をいただきました。
クッキーしちゃいましたシリーズの「辛子蓮根」をいただきました。同僚たちが先日「びぷれす熊日広場」で展示販売していたものを、少しわけてもらいました。
「ホテル熊本テルサ」と「なずな工房」のコラボ商品です。
辛子蓮根とクッキーというと別物のようなイメージですが、実に相性がいい。
クッキーというと甘い感じですが、素材の醍醐味を堪能できる、うっすらとした味付け。
つまり、オヤジ的には何が言いたいかというと、ビールのつまみとしてもいけそうということです。オヤジ的には1袋140円だと、1,000円分くらいは買いだめしますよ。
まだ、あんまり出回っていないようですけど、これは博多駅に置いていても、お土産として、飛ぶように売れそうな予感がしました。
この“しちゃいましたシリーズ”には、ほかに「ブルーベリー」「とんこつ」「みかん」「塩トマト」「しょうが」があります。みんな熊本が誇る素材を使って、しちゃってます(何で東京弁風か知りませんが?)。
Posted by わくわくなひと at
15:37
│Comments(4)
2011年04月04日
便座上げとけって言ってんだろがっ!東東京人の反乱
 「文藝春秋」四月特別号の「百二十万人が読んだ芥川賞二作品の波紋」は、けっこう面白かったです。
「文藝春秋」四月特別号の「百二十万人が読んだ芥川賞二作品の波紋」は、けっこう面白かったです。朝吹真理子「きことわ」と西村賢太「苦役列車」。対照的な作品・作者で“社会現象”を巻き起こした両作へのさまざまな感想や意見が載っていました。
一番印象に残ったのは、作家の桜庭一樹(女性)さんの感想でした。
「便座上げとけって言ってんだろがっ!」
西村賢太氏のデビュー作『どうで死ぬ身の一踊り』は、北町貫多シリーズの一作目である。読んでから五年が経つというのに、未だ忘れられぬのが主人公のこの台詞だ。
男性がトイレを使った後に便座が上がっているのがいやだわ、と女性から不満を聞くことは多々あるが、男性側からの「女ども、便座上げとけ!」という発言は、初耳だった。
・・・
(と、ごちゃごちゃと理屈っぽく書き連ねてきましたが、一言で言うとファンなんです・・・。大好きなんだよ、もー)
・・・
確かに初耳でした。なよなよしたモヤシのような東京人ではなく、東東京の「うるせぇバカやロー」という男気を感じてしまいました。そういう、しょうもない男に惹かれる桜庭一樹さんの屁理屈もあったもんじゃねぇ「大好きなんだよ、もー」という表現もいいですね。
明治学院大学教授の原武史さんは、まさに「東東京の反乱」を書いていました。
・・・(苦役列車の)主人公が生まれたのは、「江戸川区のはずれ、ほぼ浦安寄りの町」である。母親の仕事の都合で町田に住んだこともあったが、東京の西側より東側に愛着をもっている。映画を見るなら上野、風俗に行くなら新宿か池袋と決まっている。
・・・
東東京の反乱
新宿や渋谷から西に向かって延びてゆく鉄道の沿線には、「まともな両親のいる家庭環境で普通に成長し、普通に学校生活を送って知識と教養を身につけ、そして普通の青春を今まさに過ごし、これからも普通に生きて普通の出会いを繰り返していく」「人並みの生活」がある。それに対する主人公の嫌悪は「徐々に暴力の衝動を伴う憎しみ」へと変わる。「苦役列車」のラストに近い場面である。
この場面を読んだとき、私の脳裏にはなぜか、二・二六事件で杉並区上荻窪にあった教育総監の渡辺錠太郎邸を襲撃する青年将校たちが浮かび上がった。あるいは、浅草で映画を見てから井上準之助を暗殺した茨城県出身の小沼正を思い浮かべた。昭和初期のテロやクーデーターも、西東京に対する東東京の反乱といえなくもないのだ。それから半世紀あまりがたっても、基本的構図は変わらなかった。
ずいぶん前ですが、東京に6~7年ほど住んでいました。いわゆる東東京の標的とも言うべき下北沢周辺です。週に1~2回、家庭教師で西東京から東東京の亀有あたりに行ってましたが、東東京はワイルドで生命力あふれた人たちがたくさんいて嫌いじゃありませんでした。
東東京と西東京の人や生活の違いは、確かに感じていました。口頭ではよく話題になっていましたが、識者が活字にしているのは確か初めて読んだような気がします。
地方の人がイメージしている東京人は、西東京人のイメージが強いような気がします。しかし、あの有名な寅さんは、まぎれもなく東東京人ですよね。
Posted by わくわくなひと at
15:26
│Comments(2)
2011年04月03日
NO!!のフリーペーパーを久留米でゲット!
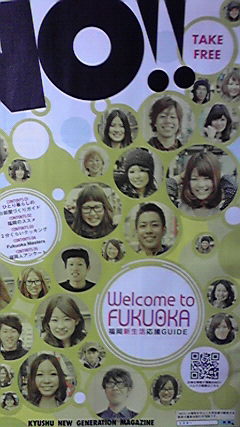 同僚が西鉄久留米駅で「NO!!」のフリーペーパーをゲットしました。
同僚が西鉄久留米駅で「NO!!」のフリーペーパーをゲットしました。「NO!!」はもともと熊本発祥の若者向けの冊子でしたが、今では福岡を中心に九州全域で販売する冊子に変貌しています。
今も頑張っていると思いますが、この冊子を創刊した人が大学の先輩で哲学おじさんです。超たまぁに飲みに行った経験がありますが、「何で会社やってんの?」と根源的な問いをしてくる人です。ときどき天神西通りの岩田屋本館近くで美少女の写真を撮っていますが、この数ヶ月見かけていませんね。こっちも大名、天神近辺をうろうろしていないからだと思います。
「え!NO!!もフリーペーパーになったんか?」と思いましたが、久留米でゲットした冊子は福岡で大学や専門学校の生活を始める人向けの「福岡新生活応援GUIDE」らしいです。読者大量参加型の月刊誌は、九州全域で販売されているらしい。
それにしても最近、報告書づくりばかりで、外部の人と接する機会がめっきり減っています。同僚が持ってきた話は、福岡のビジネスホテルが東日本の方々で満杯になっている、外資系を含む東京を拠点としていた企業が福岡に本社機能を移そうとしているなどです。
震災や原発の影響は西日本の経済まで大きく変えていく前触れが聞こえてくるようになりました。
街に出て、たくさん驚きたい。しかし、報告書づくりが終わらないと春は訪れません。
Posted by わくわくなひと at
14:52
│Comments(2)
2011年04月03日
博多阪急カード顧客分布 仮説思考が面白い!
 昨日2日付けの西日本新聞に、「九州・山口の博多阪急カード顧客分布」が載っていました。
昨日2日付けの西日本新聞に、「九州・山口の博多阪急カード顧客分布」が載っていました。来館者700万人を突破。この数字は想定していた300万人の2倍以上だそうです。売り上げも目標比20%超となったもようと、書いてありました。
まあ、ここまでは新聞でよく見かける内容ですが、「九州・山口の博多阪急カード顧客分布」は面白いですね。20万人を獲得した会員の地域別顧客分布は、「山口県から福岡、佐賀、長崎各県辺りに偏っており、必ずしも新幹線鹿児島ルート沿線が多くはなっていない」という結果です。ちなみに熊本県内は荒尾市、熊本市、宇城市のところだけが500人未満のメッシュとなっています。荒尾の人はもともと福岡に近い。熊本市と宇城市は、“つばめ族”と言われた人たちでしょうか。
これは新幹線鹿児島ルートが開通する前の私の皮膚感覚による商圏と一致しています。これがどう変わるか注目していましたが、まだ変化していない。新幹線の乗車率は震災の影響もあって伸び悩んでいるそうです。それにも関わらず目標以上の業績を確保したということですから、阪急さんが目標の370億円をゆうにこえる「400億円もいけると思います」と豪語したというのもうなずけました。
こうすればこうなるという仮説。仮説を立てるから、改めて気づくことがあるという典型的な事例だと思います。
それにしても、博多阪急はよくこんな内部の分析資料を公表しましたね。それだけの自信と西日本新聞の記者への信頼があったからでしょうか。
Posted by わくわくなひと at
14:25
│Comments(3)



