2011年06月30日
感動や考えたことが質を変えて私の中に生きる・・・山本安英
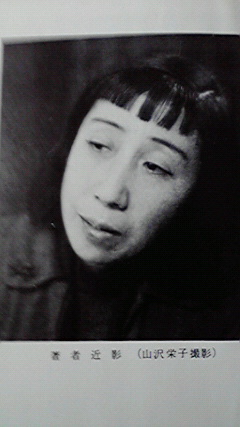 茨木のり子さんの随筆だったか、木下順二作「夕鶴」を演じてきた俳優、山本安英さんのことが書いてあり、この人の文章を読みたいと思っていました。
茨木のり子さんの随筆だったか、木下順二作「夕鶴」を演じてきた俳優、山本安英さんのことが書いてあり、この人の文章を読みたいと思っていました。しばらく山本さんのことは忘れていましたが、中井正一さんの『美学入門』に『鶴によせる日々』の一節が引用されていました。流れるようで肩に力が入らず、極めた人の落ち着いた文章。「ぜひ読んでみたい」。そう思いました。
それでアマゾンで検索すると、札幌の古本屋さんに一冊あることが分かり、早速注文しました。そして、今日、届きました。
山本安英『鶴によせる日々』未来社(1975年2月15日第2刷、1958年3月20日第1刷)。本のデザインや装丁も明るい色だけど落ち着いています。意味は分かりませんが、“戦前の山の手文化”という言葉が浮かんできました。戦前の山の手の家庭を描いた直木賞作家の中島京子さんのことも浮かんできました。
書名には、こんな思いが込められているそうです。
『夕鶴』についてはIの「私と人生」を讀んで頂きたいと思ひますが、これは全國各地にある鶴の恩返しの民話に取材された戯曲です。すべての人間の心の底にある純粋さ、「鶴」によって象徴されるそのやうな「純粋」を、近代的な感覚を通してゆたかな詩と幻想の世界の中にくつきりと描き出された美しい作品ですが、「あらゆる人の心の奥に気づかれずにそつと棲んでゐる鶴」といふテーマによせて、「鶴によせる日々」といふこの署名はつけられてゐます。
私も、“心の奥”。このところ、いや十年以上、これを追っています。どんな仕事も突き詰めると、これがテーマではないでしょうか。
少しずつ読んでいきたいと思いますが、待ちきれず、「思ふままのことを -序にかへて 1950年1月初旬 山本安英」を読みました。
すべては舞蠆の上で動いてしやべつてゐる私に集約されなければならない。日常の生活の中ではげしく感動し一所懸命考へたことどもが、質を変へて今演技してゐる私の中に生き、そのことによつて今扮してゐるその人物を私が眞にゆたかに演じ得た時、初めて私は本当に「感動した」ことになり本当に「考へた」ことになり、そしてそのやうに感動し考へることによつてのみ私の本質は成長する、つまり俳優としての私は本当に成長する―さういう風に私は思ふのです。
本を読む。激しく感動し一所懸命考えたうえで、質を変えて私の中に生き、それが仕事なり何なりに活かされて初めて、本当に「感動した」、本当に「考えた」ことになる。
本当に感動したり考えたりすることとは、こんなことなんですね。「感動した」「考えた」とかよく使う言葉ですが、プロとしての並々ならぬ“覚悟”と生き様が伝わってきました。“質を変へて今演技してゐる私の中に生き”。いろんなものを見たり聴いたりして、ある時、閃きがあり、それは見たり聴いたりして感動して考えたことが、質を変えて、これまでにないものが私の中で生まれてくる。そうなりたいし、安英さんに憧れます。
これから読んでいきますけど、柔らかい優しい文章ですが、何か凄そうです。
ところで、『夕鶴』を書かれた木下順二さんは、熊本ゆかりの方ですね。いつだったかバスで京町のクランクを通りすぎる時、「木下塾跡」?という石柱が目に入ってきました。木下さんのご先祖が開いておられた塾(江戸時代から明治の初めころまで)が、ここにあったのかと思い妙に感動したことを思い出しました。

Posted by わくわくなひと at
20:31
│Comments(2)
2011年06月25日
“美にうたれる”・・・中井正一『美学入門』を読む
 阿修羅像を見て感動して以来、頭のどこかで“美”というものや、なぜ阿修羅像に衝撃を受けたのかが気になってきた。
阿修羅像を見て感動して以来、頭のどこかで“美”というものや、なぜ阿修羅像に衝撃を受けたのかが気になってきた。そういうこともあり、『美学入門』と書かれた背表紙に反応してしまった。中井正一『美学入門』中公文庫(2010年6月25日初版)という文庫本である。
「美しいこととは何であるか、芸術とは何であるかを考えたずねてゆくことが美学なのである。」と最初の頁に書いてあった。
しかし、次の頁に「第一に自然の美しさとは何であろう。空、海、山河、あの大自然の美しさ、鳥や花、あるいは人の体の美しさでもやはり自然の美しさなのである。それらのものがなぜ美しいのであろう。この問題はまだ解けきれてはいない。実に数千年の間、人々はこの難しい問題の前にわからぬままに頭をたれているのである。しかし、いろいろの疑問をなげかけている。この疑問の数々が、美学の歴史にほかならないともいえるのである。」とも書いてあった。つまり、永遠のテーマについての入門書が本書の中身ということらしい。
昨日、大牟田から天神に向かう西鉄電車の中で読了した。美をテーマにした哲学や歴史観が見事にまとめられている。この文庫の底本は、1951年、河出書房「市民文庫」と書いてあるので、ずいぶん前の文章ではある。しかし、今、読んでも今日的な内容であり、その思索の深さと教養の幅に驚いてしまった。
この本で「こうして、すべての研究が国家的なスケールでもって、部署的な組織でもって、構成されようとしているのである。ここに新しく機械時代の認識論の基礎が生まれ出ようとしているともいえる。何びともが、その組織に属することによってのみ、その対象の感覚的素材もはじめて適格に把握し得るという段階の文化が出現しようとしているのである。」と予言のように書いてあったが、今はまさにそうなっている(なろうとしている?)。しかし、システム化やプロジェクト化がうまくマネジメントされて進む中で、一人ひとりは部品と化し、思索力や教養の幅、人の力は中井さんにはるかに及ばないのではないかと思ってしまった。
著者の中井さんは、戦前は京都大学文学部大学院の教授で、日本史の教科書にも出てくる滝川事件とも関係ある方である。戦後は国会図書館や尾道市立図書館長を務められ、この本を書かれた翌年52歳で亡くなられたと解説に書いてあった。
以下は書き留めておきたい内容。美学そのものの内容より、特に認識論や独創性に関係する部分に、つい関心がいってしまった。見出しは個人向けの引き出し用(中井さん作ではありません)。
11頁 美にうたれる
・・・自然の景色の中につつまれ、「ああいいな」とうっとりとその中に吸い込まれていくことがある。この時私たちは、宇宙の秩序の中につつまれることで、その中に引き込まれて、自分の肉体もが意識しないけれども、じかに、直接に響きあっているのである。美に打たれるというこころもちはこんなことではあるまいか。
12頁 「しづかに観ずれば、物、皆自得す。」(芭蕉)
芭蕉が、「しづかに観ずれば、物、皆自得す。」といっているように、この時、物、皆の姿が、しみじみと芭蕉に伝わり、それを追求するために、年老いた彼をして、死を賭して旅に出しむるほど、美は強い力を持っているのである。
22頁 「ああこれだ」といえる充ち足りたこころ
この探し求めることの自由、そして探し得た時の「ああこれだ」といえる充ち足りたこころ、これがみんな、芸術家のもつ、自由へのもがきから生まれるのである。本当の自分にめぐり逢ったという自由への闘いなのである。
この境地を、芸術の美しさを求める苦しみというのである。人々は、その芸を見、聞いて、その芸術家を打ったものが自分に伝わり、また、芸に打たれるのである。
25頁 「しびれるようなよろこび」
・・・万人が見て、仰いでいよいよ高く感ずる、何ともいえない芸道を感ずる、芸の鬼といった凄みを感ぜしむることになるのである。この世界が本当は、自分が本当の自分にめぐり逢うかどうかを、定めることの出来る世界なのである。ほんとうの幸福、芸術だけにあるところの「しびれるようなよろこび」は、ここから生まれるのである。芸術のいわゆる醍醐味という世界である。
31頁 中宮寺の観音のような古代の微笑の数々
私も、戦争に反対したというので、特高に引っ張られて・・・突然、私には、この現実が巨大というか「現実とはそんなものだったのか」そうだったのか、自分の前にそそり立ったのを憶えている。それは巨大な現実ともいうべき世界が、眼前に現われた思いであった。そして突然、古代の微笑の数々が、例えば、中宮寺の観音のような、古代の彫刻によく彫られているほほえみが、自分の眼の前を横切ったように思ったのであった。
43頁 さらさら流れる水のような美しさ
日本人の美の理想は、芭蕉にいわしむれば、浅い川を流れる水のように、あくまですがすがしく、清らかで軽くて、とどこおりなく、明るくて、さやけさとでもいうようなものが、美しいとされるのである。もったいぶったものは、それがちょっとであっても、臭みとか、重みとかいって嫌うのである。万葉の「さやけさ」、中世の「数寄」あるいは「わび」あるいは「物のあわれ」、さらには江戸にいたっていう、「いき」にしても、皆、とどこおるもの、もったいぶるもの、野暮なものから脱け出して、さらさら流れる水のような美しさが、よろこばれるのである。中国の美しさから、日本の美しさに移るとき、ちょうど、いかめしい、重たい「漢字」の美しさから、さらさら流れる「仮名書き」の字の美しさにうつったような、そんな軽みが日本特有の美しさとして現われるように思われる。
茶室の柱や屋根は、ギリシャ建築の柱のように、いかめしくもなければ、教会建築のように、天を貫いてもいない。実に寂かに、軽く、宇宙の今と、ここに静まりかえっているといった感じでそこにあるのである。
48頁 「ハハア、これか」とわかること
誰がどういった、こういったと理屈をこねるよりも、この困難な訓練の中に飛び込んでみると、それらのもののいったことの中の、一番本当のことが「ハハア、これか」とはじめてわかって来るのである。行動と実践が大切だというのはこのことである。・・・
・・・
この訓練と行動を尊ぶ心は、実は、大きな現実への信頼があってはじめて出来ることである。現実の中に「論理的なもの」「正しいもの」が必ずひそんでいることを、信頼し切っている証拠なのである。
これは大変なことなのである。自分の肉体を信じ、この世界を信じ、歴史を信じ、人類全体を信ずることなのである。
50頁 「あっ」と叫ぶようなめぐり逢い
だから芸術は、時間だろうが、空間だろうが、光だろうが、音、言葉など、何でも媒介として、人々の感覚にうったえるもの全部を、生きている色々の調子で、どんなにでも変えてくるのである。しかし、これらのものを、自由に変える奔放自在な欲望が生まれ、またそれらのもを変える権利をもったものは、それを生みだすものが、つまり自分が、「今」と「ここ」に本当に生き、「あっ」と叫び声をあげるような生命にめぐり逢った時だけなのである。・・・
56頁 打ち寄せる波のような新しい自分とのめぐり逢い
美とは、自分にまだわからなかった自分、自分の予期しなかった、もっと深いというか、もっと突っ込んだというか、打ちよせる波のように、前のめったというか、自分が考えている自分よりも、もっと新しい人間像としての自分にめぐり逢うことである・・・
64頁 それはすでに止まれるもの
・・・例えばベルグソンの哲学のごとき、生命は常に脈動し、飛躍しておるものであるにもかかわらず、われわれがそれを捕えて見るとき、あるいは考えてみるとき、それはすれに止まれるもの、いわゆる過去のものとして捕えられるのである。・・・
65頁 真のリアルはリアルを超えるときも
・・・真にリアルであるためには、われわれはリアルを越えなければならないときもあるのである。→スピルバーグの戦争映画のスローモーション?リアルさを強調した映画でリアルさを感じないことがあるのは、このことか。
133頁 自分から抜け出したい自分の弱さ
自分から抜け出したい自分の弱さにあきあきしていながら、しかも、脱出しきることの出来ない嘆き、これが現代の自我の本当の姿ともいえるのである。そこには、一刻一刻と流れ去りつつある自分があるだけであって、本当の自分というものに巡り会えないでいる。こんな心持ちがいうにいえない現代の「不安のこころ」である。シュールリアリズムの芸術の底を流れる寂しさも、かかるものがその底を流れている。
プルーストがいつもいうところの「認識の達しない深みにおいて、自分自身に巡り会う」という言葉は、こんな淋しい魂が、今こそ、本当に生きているという時間を持ちたいという願いのあらわれである。彼が「時間から解放された一瞬間は、汝の心のうちに、時間界から解放された人間を創造した」といっているのもそれである。こういう時間をもちたいというのが現代人の切実な願いとなって来ているのである。
135頁 知識は死んだ時間、意志は未来の世界
・・・要するに、もはや、知情意といったような自分の中に三つの玉のような、「魂」がごろごろところがっているというような考え方は、もはや、私たちに用の無いものとなってしまったのである。むしろ「知識」とは、流れている時間を、ふりかえって、記憶として、固定してみる立場であって、もはや、死んだ時間である、・・・味気ないものであり、こわばった影の世界にしかすぎないと、考えられるのである。それに反して、「意志」の世界は、丸い玉のような魂でなく、時間でいうならば、未来のような世界である。存在でいうならば、これから可能な世界である。つまり、丸い玉(魂)ではなくして、それは、時間の中に、ばらばらにときほぐされてしまっていると考えられるべきである。
136頁 「はっ」と思うような美しい瞬間
日本の芸術論の中に、「人の神(シン)を見ること飛鳥の目を過ぐるが如し、その去ること速かなれば速かなるほどその神(シン)いよいよ全し」というような言葉があるように、「はっ」と思うような美しい瞬間、それをむしろ、現代では、芸術的時間とか、「永遠の一瞬」とか言って、特別の芸術の世界と考えるのである。ここでも、環状は、もはや「魂」ではなくして、時間の中に、ときほぐされて、とけ込んでしまっているのである。
かく考えてくると、もはや、知情意は、認識能力としての、「魂」の力ではなくして、時間の三つの姿と変わってしまっている。したがって、三つの「魂」を握りしめている自我は、分裂してしまって、時間の中にばらばらになり、宇宙の中に色々な角度で関係をする時間の在り方の中にとけ込んでしまうのである。芸術論も、その線にしたがって、その姿を変えて来たわけである。
「造化にしたがい、造化にかえる」とか、「竹にことは竹にならえ」など芭蕉がいっているが、何か造化に、今しも随順した、うちのめされた、「ああ、お前もそうだったのか」と手をさしのばしたくなる造化に触れた時、人々は、一つの長い息を吐くのではあるまいか。「寂かに観ずれば、物皆自得す」というここともちもそれはあるまいか。これは深浅もあり、大小もあろうが、多かれ少なかれこんな心持のあるとき人々は大いなる時間が、宇宙と共に流れており、それは時計で、はかりようもないと思わざるを得ないのではあるまいか。こんな心持ちを、ハイデッカーは「生きた時間」といっているのであろう。
・・・
山本安英さんの『鶴によせる日々』を読んでいると、次の文章にであった。
「しんとした空気の中に、さらさらという流れの音にまじって、何やら非常に微かな無数のさざめきが、たとえばたくさんの蚕が一勢に桑の葉を食べるようなさざめきが、いつの間にかどこからともなく聞こえています。
知らないうちに流れのふちにしゃがみこんでいた私たちが、ふと気がついてみると、そのさざめきは、無数の細いつららの尖からしたたる水滴が、流れの上に落ちて立てる音だったのです。そう思ってそこを見ると、その小さい水玉たちは、僅か三四寸の空間をきらめいて落ちて行きながら、流れている水面にまた無数の微かな波紋を作って、この美しい光の交響楽は、ますますせんさいに捉えがたいせんりつを織り出しているのでした。そうしてその、きらめきわたる光りの帯をとおして、澄み切った水の底に、若い小さい芹の浅緑が驚くほどの鮮やかさでつつましく見えていました。」
山本さんは、いつ思い出しても、夢ではないかと思われる美しい童話の世界だったと思いかえしている。そして、それをいかに演劇の世界に生かすべきか、または、この世界を知ったものが、いかに演劇の中で「生きて行く」べきかを思い悩んでいる。
まことに、ワイルドの言葉のように、
「今、見ていることが、一等神秘だ」
と思われる瞬間がある。神秘と思えるほどあざやかな現実が突如眼前にあらわれることがある。山本さんの場合も自然を通して認識の達しない深みにおいて、自分自身にめぐりあっているのではあるまいか。
それは、逆説的にいえば、また同時に、そのめぐりあったとは、その自分に袂別し、自分と手をわかち、新しい未来の中に、または永遠の中によろけ込む自分の中に見い出す新鮮さに身ぶるいを感触したことなのかもしれない。
自然はときどき、自分に、そんな飛躍をあたえてくれるスプリング・ボードなってくれることがある。
「袂別する時に、はじめて、ほんとうに遇えたのだ。」といえるような弁証法的な自分への対決を、自分に強いるときがある。
「美のもろさ」とはそれである。美は、飛んでいく鳥が、目をかすめるほど、たまゆらを閃くものであるというのはそれである。そこにはじめて、ほんとうの「今」があるのではあるまいか。
逆にいうならば、この「今」がなければ、美はないではあるまいか。私は俳句で、「季」が大切にされるのは、この「今」を大切にすることであると信じている。
150頁 見事な西欧に対する歴史観
1500年-1900年の時代とは、欧州の各国民がローマ法王の権力からのがれて、それぞれの民族がそれぞれの特有の生き方で民族化してゆき、商業が封建的な習慣をゆり動かし、さらに金融的な体制をととのえて行った時代である。あらゆる機構が商品化された時代である。この商品化された巨大な流れの中に、ローマ法王からのがれて、新大陸にメイフラワー号で上陸した人々から生まれ出たアメリカが、1950年代に至って、世紀に新しい担い手になってくるということを、幾人の人が予見し得たであろう。
これまでの世界の支配には、何か固有名詞、すなわち一ないし数名の英雄の名前が記されていたのであるが、1950年のこの変革には目立つ固有名詞がないのである。むしろ、大いなる機構が、その変革を行いつつある。そこに機械時代とでもいわれるものの本質があるのである。人間が機構を支配するか、機構が人間を支配するかという不安を感じるところまで、時代が移り変わっているのである。
Posted by わくわくなひと at
19:57
│Comments(0)
2011年06月20日
うなぎの大新!うなぎの三助、山ウニ豆腐
 今日は熊本の街中、下通と駕町通りを結ぶ筋にある「うなぎの大新」で夕食?しました。
今日は熊本の街中、下通と駕町通りを結ぶ筋にある「うなぎの大新」で夕食?しました。「大新」さんが新市街にあるころからのファンでして、うな丼をいただきました。
いつものことで、いっしょに、甘辛く煮た肝も頼むのですが品切れ。
「あらっ!」と思って、壁のメニューを見ると、「山ウニ豆腐」とあるじゃないですか。
モロミ漬けのウニのような味わいの豆腐。こらぁうまそうだと一つ頼みました。
「うまい、うまい」。本当うまいものをいただくと幸せ感が満ちてきます。
そしたら、お店の笑顔たっぷりの女性が「うなぎの三助」をプレゼントしてくれました。
一目見ただけで、「いよいよビール」という気持ちになってきます。
適度に油が乗っていて、極上の焼き鳥という感じ。
「ビールか日本酒でいただいたら、さぞ・・・」。
ここはぐっと我慢。今日は仕事します。
写真は食べかけです。
夢中になって食べていたので、ブログ向けの写真のことは忘れていました。
あまり意識してなかったけど、大新さんのつまみの美味感は凄いかも知れません。
Posted by わくわくなひと at
19:49
│Comments(0)
2011年06月16日
人は言葉より多くのことを知ることができる・・・暗黙知
 マイケル・ポランニー『暗黙知の次元』ちくま学芸文庫(2007年10月20日第四刷、2003年12月10日第一刷)を読みました。電車の中で、日本酒のように、ちびりちびりと読んでましたので、一月はバッグの中に入れっぱなしでした。最近は文字の出力が多くて、入力は少なくなっています。
マイケル・ポランニー『暗黙知の次元』ちくま学芸文庫(2007年10月20日第四刷、2003年12月10日第一刷)を読みました。電車の中で、日本酒のように、ちびりちびりと読んでましたので、一月はバッグの中に入れっぱなしでした。最近は文字の出力が多くて、入力は少なくなっています。随分前、野中郁次郎氏の知識創造関連の本の中に、ポランニーの暗黙知のことが引用されており、驚きと新鮮さを感じて流し読みしたことありました。
それから10年近く経って、今度は“創造性や独創性”というテーマを何となく頭の片隅に置いて読んでみました。
序文の「・・・私は科学を感覚的認識の一変種と考え、・・・」という一節から痺れました。この文章は1966年に書かれているのです。原発を支えてきた科学に対しての懐疑が広まっている、2011年の今なら、けっこう出逢う一節かも知れません。
それと訳者あとがきも面白かったです。
ポランニーの英語は諦めの悪いしろものと書いてありました。
ある漠たる「予期」を持って思考を始めるのだが、その進行過程でさまざまな要素が付加されて、段々に一つの全体的な意味が達成されていく。・・・潜在的な意味に誘われて、前のめりに頭を働かせるのだが、確たる正否については、とにかく書いてしまわないと分からない。だから読者もいっしょに動かないといけない。そういう文章であったと思う。
「わかりやすく。」「結論は最初に。」などテクニックばやりの文章術やプレゼン術が花盛りです。でも、自分で独創的に考えて書いていくというのは、こんなことでは?と思って、「いいぞ!」と拍手したくなりました。
暗黙知とは、こんなことらしい。
第1章 暗黙知
・・・私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる。・・・認知の多くは言葉に置き換えられないのだ。・・・すなわち、私たちが、その方法以前に、言葉にできるより多くのことを確かに知っていた、ということである。それだけではない。私たちが警察の方法を用いることができるのは、自分が記憶している顔の特徴と、コレクションの中の特徴を、照合するやり方を心得ている場合に限られるのである。しかも私たちは、どういうふうにして照合したのか、言葉にすることはできない。まさにこうした照合のやり方こそ、言葉にすることができない認識が存在することを示している。
このことは言われてみれば、確かにそんな気がするというものです。「科学という感覚的認識の一変種」にとらわれてきた身には、そんな感覚があったはずなのに、ポランニーのように文字や言葉にすることができませんでした。
114頁
・・・誰かを見るということは、無限に存在するその人の精神と肉体に隠れた働きをも見るということなのだ。知覚とはかように底なしに奥深いものなのである。なぜなら、私たちが知覚するのは実在(リアリティ)の一側面であり、したがって数ある実在の側面は、いまだ明かされざる、おそらくいまだ想像されざる、無限の経験に至る手掛かりになるからである。・・・
このことはグループインタビューをマジックミラー越しに聴いて見ているときに感じていました。発言や人の動きや表情、そしてエネルギー・・・。そんな諸々のことを知覚しているうちに、頭の中にいろんなことが浮かんできます。私のその時のメモの中で最も大切なものは、発言内容ではなく、そんな刺激を受けて自分の頭に浮かんだことなのです。それが思いもよらぬ発見につながっていきます。発言内容であれば、何度でも再生できますので、どうでもいいのです。
45頁
・・・ある理論について真の認識が初めて確立されるのは、それが内面化され、経験を解釈するために縦横に活用されるようになってからだ・・・
“わかった”“腹の底からわかった”と思う瞬間は、読んだり、聞いたりした時点ではないですね。そのことについて自分が腹一杯経験していて右往左往したり悩んだりしていて、一文に出逢う。一文に出逢って何となくわかったつもりでいて、似たようなことを経験した瞬間に、「あの人が言ってたのは、こんなことだったのか」と思ったりします。
57~58頁
・・・チェスのプレイヤーたちは、名人が行った勝負を何度も繰り返しては名人の精神の中に入り込み、名人の頭の中にあったものを発見しようとする。
もう少し話を敷衍しよう。上述の二つの事例で、私たちは包括的存在を構成する諸要素の中に入り込む。そのとき、私たちは、包括的存在の首尾一貫性を説明してくれる何ものかに出逢っている。最初の事例では、私たちは身体を巧みに操る個人(person)に出逢い、後者の事例では、精神を巧みに操る個人に出逢っているのだ。
・・・技量を振るっている当人自体、その技量に組織されている個々の要素については、きわめて曖昧にしか語れないものなのだ。・・・さらに科学的探求の場合と同じように、このとき利用される手掛かりの多くは、それが何であるか、最後まで特定されないだろうし、意識に上がらずに終わる可能性だって大いにある。私たちが、技能とかチェスの勝負の秘められた構造に入り込み、その背後にいる個人の力を認識するようになるのは、そういう事情を含んだ努力を介してのことなのである。歴史家が歴史的人物を研究するときも、これと同じ方法が採られるだろう。
暗黙知の習得方法について書いた一文です。消費者の分析合宿で名人と同じ問題について考える。震えるくらいの感動と発見があります。
以下は仕事上?いや自分の研究テーマ上?メモっておけば何らかの啓示を受けそうな文章です。ポランニー風に言えば、今は言葉にできないけれど、隠れた実在(リアリティ)を感じているのかも知れないし、そんなものはなにもない妄想かも知れません。
127頁
・・・つまりそれは科学者の行為なのである。しかし彼が追求するものは彼の創意によるものではない。彼の行為は、彼が発見しようとしている隠れた実在による影響を受けるのだ。科学者は問題を洞察し、それに囚われ続けて、ついには発見へと飛躍するのだが、それらはすべて、始めから終わりまで、外界の対象からの恩義を被っているのだ。したがって、こうしたきわめて個人的な行為においては、我意が存在する余地はまったくない。独創性は、あらゆる段階で、人間精神内の真実を増進させるという責任感によって支配されている。その自由とは完全なる奉仕のことなのだ。
36頁
・・・私たちは、身体的過程が知覚に関与するときの関与の仕方を解明することによって、人間のもっとも高度な創造性を含む、すべての思考の身体的根拠を明らかにすることができるだろう、と。・・・
46頁
言うまでもなく、すべての研究は問題から始められねばならない。研究が成功するのは、問題が妥当な場合に限られるのだ。そして問題が独創的である場合に限って、研究もまた独創的でありうる。・・・問題を考察するとは、隠れた何かを考察することだからだ。それは、まだ包括されていない個々の諸要素に一貫性が存在することを、暗に認識することなのだ。この暗示が真実であるとき、問題もまた妥当なものになる。そして、私たちが期待している包括の可能性を他の誰も見出すことができないとき、それは独創的なものになる。偉大な発見に導く問題を考察するとは、隠れている何かを考察することだけではなく、他の人間が微塵も感づき得ないような何かを考察することでもあるのだ。
・・・
・・・もし何を探し求めているのか分かっているのなら、問題は存在しないのだし、逆に、もし何を探し求めているのか分かっていないのなら、何かを発見できることなど期待できないからだ。
49頁
どうやら、ある発言が真実だと認識するということは、言葉として口にできる以上のことを認識することらしい。しかもその認識による発見が問題を解決したなら、その発見それ自身もまた範囲の定かならぬ予知を伴っていたことになるだろう。
50頁
・・・暗黙知によって、以下の諸点のメカニズムが明らかにされるのだ。(1)問題を妥当に認識する。(2)その解決へと迫りつつあることを感知する自らの感覚に依拠して、科学者が問題を追及する。(3)最後に到達される発見について、いまだ定かならぬ暗示=含意(インプリケーション)を妥当に予期する。
127頁
・・・つまりそれは科学者の行為なのである。しかし彼が追求するものは彼の創意によるものではない。彼の行為は、彼が発見しようとしている隠れた実在による影響を受けるのだ。科学者は問題を洞察し、それに囚われ続けて、ついには発見へと飛躍するのだが、それらはすべて、始めから終わりまで、外界の対象からの恩義を被っているのだ。したがって、こうしたきわめて個人的な行為においては、我意が存在する余地はまったくない。独創性は、あらゆる段階で、人間精神内の真実を増進させるという責任感によって支配されている。その自由とは完全なる奉仕のことなのだ。
146頁
次に、人間が思考することによって、どのように革新が達成されるか検証してみよう。この過程もまた、ある潜在的可能性(ポテンシャル)の現実化として記述することができる。問題を見て、それを追求しようと企てることは、そこに到達できると信じて、ある範囲の潜在的可能性を見ることなのである。
Posted by わくわくなひと at
01:33
│Comments(0)
2011年06月13日
今月の「はたらく仲間のうた」は熊本の人の作品!
 大名と熊本の事務所で「はたらく仲間のうた」カレンダーを愛用させていただいております。
大名と熊本の事務所で「はたらく仲間のうた」カレンダーを愛用させていただいております。今月は「うたっているフクロウ」という絵で、熊本の緒方愛さん(るぴなす)の作品です。
熊本の方の作品というだけでなく、正直、今年の「はたらく仲間のうた」の絵の中で一番心に残る作品です。フクロウの顔が何とも可愛いですね。後ろで見ている太陽の顔は何となくムンクの絵を思わせてしまいます。
何ヵ月前だったか長崎市内の中華街の鼈甲屋さんに立ち寄った時、フクロウのブローチが並べてありました。
「不苦労(フクロウ)」=苦労せず!ということで縁起物だそうです。
今月は毎日のように、緒方さんのフクロウの顔を眺めていますので、何となくやさしい気持ちになることができます。謝!謝!
Posted by わくわくなひと at
18:41
│Comments(0)
2011年06月08日
舞妓・芸妓さんもコカコーラの綾鷹を選んだ!
 コカコーラさんがペットボトルのお茶市場を激しく攻めているようですね。
コカコーラさんがペットボトルのお茶市場を激しく攻めているようですね。先の日曜日、天神の三越ライオン広場で人の列ができていて、駆け足に近いような速さで動いていっていました。
何だろう?と思って見たところ、コカコーラのペットボトルのお茶「綾鷹」のサンプリングをやってました。
当然、その列に加わりました。1人につき1個の小さめのペットボトルと、名刺の1.5倍ほどの大きさのパンフをタダで配ってます。何個くらい配ったのでしょうか。1,000個くらいあっと言う間という感じのさばきかたでした。
私の場合は濃いお茶派ですので、そこまでの入れ込みはありません。確かに「綾鷹はけっこうおいしい」という話も、たまに耳にします。
いただいたハンドチラシには、こんなことが書いてありました。
舞妓・芸妓さんが選んだ
「急須でいれた緑茶にもっとも近いのはどれ?」
お茶は、くらべてわかる。
日本全国
綾鷹試験
2010年11月24日~同26日までの3日間。京都の舞妓・芸妓さん100人を対象に、製品名を隠した味覚調査をした結果も書いてありました。
京都の舞妓・芸妓さん
100人中57人が
「急須でいれた緑茶に
もっとも近いお茶」
と答えました。
ペットボトルのお茶と言えば、伊藤園さんの「おーいお茶」です。これにサントリーの「伊右衛門」が激しく追い上げていることだろうと思います。
このトップグループに巨人のコカコーラが全国に何万とある自販機網をちらつかせながら、スピードを上げてきたというイメージです。
日本全国
綾鷹試験
全国の緑茶をよく知っている層の調査結果を消費者に知らせていく大キャンペーンのようですね。
「ペットボトルで急須でいれたようなお茶を飲みたい」
この潜在的なニーズに気づいたコカコーラさんの商品は、どこまで消費者に浸透するか?
たまには日経MJでも読んで、動向を知りたくなってきました。
Posted by わくわくなひと at
15:06
│Comments(0)
2011年06月05日
福岡パルコは帽子の宝庫かも?
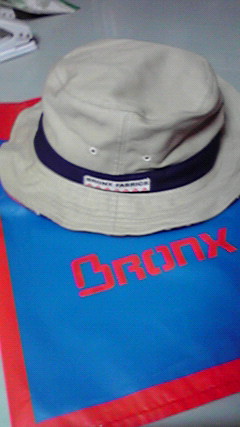 ジュンク堂で夏用の帽子をなくして、しばらく我慢していました。
ジュンク堂で夏用の帽子をなくして、しばらく我慢していました。しかし、雨が降ってきたときに眼鏡が濡れるのが嫌ですし、だんだん日射しが強くなってきていますので、帽子を買うことにしました。
買うとしたら、「これは絶対欲しい」という帽子に限ります。そうでないと、最初はかぶっていても後でかぶらなくなりますから。
それで最初、大名の帽子屋さんに立ち寄りました。少し気に入ったのがありましたが、「これしかない」というレベルではないので保留。ミーナ天神のユニクロ、無印、AOKIに行き、その後、ソラリア地下の無印にも行きました。
その後、バブリーなVIORO?にも行きました。すごいお金がかかってそうな店の中をいくつか見て回りましたが、当選確実はなし。おしいものは確かにありましたが、今ひとつ。
次に、こうなったら岩田屋。紳士向けのところでいくつかかぶってみましたが、何かおかしい。
うーん。次はパルコ。ポールスミスの店に行きましたが、しっくりくるのはありません。
上の階に上がると、帽子専門店がありました。いろいろ目移りするほどの数。ハンチング帽でけっこう合いそうなものがあり、買うか買うまいか、だんだん追い込まれてきましたが、仕事の間でも使用するという条件がありますので断念。7,000円台ということも衝動買いできなかった理由の一つです。
さらに上の階へ行って、絶対ではありませんが、保守的というかコンサバ、トラッドの定番のようなデザインの帽子に目がいきました。
もうこの辺で折れるべきということで、買うことにしました。値段も3,000円でしたので、「やっぱりやめた」ということになってもダメージは少ないということも買う理由になりました。
「BRONX」というお店がオリジナルでつくった帽子です。
それで気づきましたが、パルコにはけっこう帽子を置いている店が多いですね。
明らかにほかの店よりも多く置いてあるような気がしました。
Posted by わくわくなひと at
16:47
│Comments(2)
2011年06月03日
こらぁっぅ えすか!真夏の天神にホラーハウス出現
 何となく西日本新聞夕刊を眺めていたら、最後のテレビ面下の三段広告に目が止まりました。
何となく西日本新聞夕刊を眺めていたら、最後のテレビ面下の三段広告に目が止まりました。なにやら気持ち悪い手がいくつも。
真夏の天神にホラーハウスが出現!!
天神ホラーハウス
最恐!
こっちにおいで
トンネルの先の都市伝説!!
さぁ、早く・・・
こっちにおいで・・・
こらぁ えすか!(熊本市よりも北側で育った九州人には分かる言葉)
私は絶対行きません。
今年の7月16日から8月14日まで。天神のソラリアステージ6階の西鉄ホールが会場だそうです。
私には関係ありませんが、ロングコース当日800円、ショートコース600円とうのも嬉しい限り。
私は決して行きませんが、このところ博多駅に客を奪われている天神界隈の新手の客寄せ策だと思います。
問い合わせは東映となっていますので、ちんけな仕掛けではなさそう。
こっらぁ~けっこう震えあがりますよ。
小さい文字で、こんなことも書いてありました。
通りすがりの人々を誘い、恐怖の闇に引き込む悪意。
いったいここで何が起こったというのか。
ひとたび足を踏み入れたら、引き返せない恐怖の連鎖。
ふたたび陽の光を見ることができるのか。
それはあなたの運しだい。
ひとつだけ忠告しておく。
漆黒の闇から、あなたを見ているその者の憎悪の理由を
たずねてはいけない。
気味が悪い。帰ろう。でも、知りたい。暗い道の先に、誘う声が聞こえる。
こっちにおいで・・・とね。
私も、ひとつだけ忠告しておく。
博多駅に行かず、「(しゃっち)こっちにおいで」と言われても、
そんなものは知りたくない。
重ねて申す!決して行きません。
Posted by わくわくなひと at
20:29
│Comments(2)
2011年06月02日
miniの4ドアに乗ってみました!
 単なる通りすがりの者ですが、miniのプレゼンがソラリア?の1階であってました。
単なる通りすがりの者ですが、miniのプレゼンがソラリア?の1階であってました。これでも、mini cooper のオーナーですので、ついつい寄り道してしまいました。
前からヨーロッパでは4ドアタイプが売られてましたが、日本では売ってませんでした。
年配ですので、2ドアは少し恥ずかしい気持ちもあり、4ドアに興味を持ってきました。
そして、ついに間近で4ドアを見て、ほんの少しコックピットに乗ることもできました。
今、乗っているcooperは、8年目。ハイオクで燃費が気になること以外は力もあり、コーナリングもGがかからず、すいすい走れます。競争しているわけではありませんが、追随者をぶっちぎる時はいつも曲がりくねった道です。あっと言う間に追随者を突き放すことができます。坂道もぐんぐん這い上る。時速200キロは出そうです。
4ドアの新タイプは、既存のminiより一回り大きくて車高も高い。ゴーカード感覚はなさそうです。
BMWグループですので、BMのオフロード車に何となく似てますね。
顔も既存のとは違って、miniにBMの血が入ったハーフという感じです。
顔は既存の顔、しかも今のminiが出たばかりの初代タイプが自分の好みです。
同じminiでも最近のタイプは円満な感じがいくぶん少なくなった表情をしています。
8年目となった今の車が好きだから、少なくとも後2年は愛用することでしょう。
その後、4ドアにするか?コンパティブルにするか?馬力は強いのがもちろんいい。
Posted by わくわくなひと at
19:54
│Comments(4)
2011年06月02日
トイレ完備で飲んでも安心して乗車できるJR
 今日、JR大牟田駅の看板に目がとまりました。
今日、JR大牟田駅の看板に目がとまりました。JRでは、全列車にトイレを完備しています。
お酒などを飲んでも安心して、ご乗車預けます。
有明2枚きっぷ
大牟田←→博多 1,500円
大牟田駅ではJRのホームの奥に西鉄大牟田駅のホームがあります。
西鉄のホームではJRのホームから見えるように、こんな看板が出ています。
天神へお出かけなら西鉄電車で 1,000円
福岡都心へ快適なアクセス 特急約60分
競争心まんまん!競争しながら、互いにサービスがよくなると、いいですね。
JRは値段は高いがトイレがある。西鉄は値段が安いけど、トイレがない。
たま~に大牟田の新栄町あたりで飲むことがあります。
このとき天神行きの最終電車は、確か22時45分。少し早い時間ですよね。所要時間は特急ではなく急行なので約60分ちょっと。
これに対し、JRは23時17分。各駅停車の博多行きで着は0時46分です。
さて、どちらを選ぶか?
それともう一つ。
大牟田で飲んで熊本に向かう時は、ちょう余裕です。午前1時8分初の特急有明があります。
Posted by わくわくなひと at
14:47
│Comments(0)
2011年06月01日
ついに出た!博多~熊本往復つばめ格安切符
 JR九州さんが仕掛けてきましたね。
JR九州さんが仕掛けてきましたね。今日1日付け西日本新聞経済面のベタ記事に、「買い物券セットつばめ格安切符 JR九州発売へ」がありました。
JR九州は31日、博多ー熊本往復の九州新幹線「つばめ」(各駅停車)指定席と、新博多駅ビル内にある専門店街アミュプラザ博多の買い物券(1500円分)をセットにした5500円の企画切符「ビックリつばめ2枚切符」を、6月9日~7月19日の期間限定で発売すると発表した。
つまり、「乗車率が23%と低迷する「つばめ」のてこ入れが狙い。片道当たりの乗車料金は2千円となり、福岡ー熊本の高速バスと同額になる。新幹線開通で高速バスに流れた客を呼び戻す狙いもある。」ということ。
九州新幹線が全通して3カ月余り。これまで5回乗りましたが、「さくら」ばっかりで「つばめ」は乗ったことがありません。福岡ー熊本間はしょっちゅう行き来してますので、5回というのは少なすぎる。後は高速バスや西鉄で大牟田まで行って熊本ライナーに乗り換えていることが多いですね。
高速バスの客は確かに変化しました。私の場合、天神のバスセンターから乗り降りします。新幹線開通前は、ほとんどの乗客が天神で乗り降りしていました。ところが開通後は、博多駅前のバスセンターで乗り降りする人が相当増えています。それも、若い女性たちで、熊本行きのバスに乗る時は大きな買い物袋を下げている人が多い。どうやら、この若い女性たちは新幹線には興味がなく阪急や東急ハンズなどお店がお目当てらしい。ここが一般の男と違うところで、けっこう男の場合は新幹線に乗ることが目的である人が多いと思います。
「さくら」の方が本数も多いし、博多ー熊本の所要時間が40分以内。これに比べ各駅停車の「つばめ」は51分かかり、朝夕を除けば1時間に1本しかありません。
私が乗った感じでは、「さくら」は70%くらいの乗車率で盛況ではないでしょうか。確かに、これに比べ「つばめ」は少なそうな感じでした。しかし、「さくら」のシートは横5席、「つばめ」は横4席。車内のインテリアも「つばめ」の方が豪華な感じがします。
「片道2000円なら」と、もっと気軽に新幹線が使おうという気分になりました。必ずアミュプラザ博多の買い物券1500円が付いてきますが、そのくらいの買い物はしそうです。もう一つ確認したいのが、1500円の買い物券が飲食に使えるかどうかです。飲食だったら、わざわざモノを買わなくても、博多駅でそこそこのものを食べることは日常ですので、何の不足もありません。
「利用前日までに購入、予約が必要。」というのは、ちょっとひっかかります。面倒、しゃあしい・・・。
駅に行って即効で「つばめ」に乗れるということにしてもらいたいですね。
この切符、必ず一度は買うことになるでしょう。
代替サービスにどう対抗してお客さんを増やしていくか、これはマイケル・ポーター的な経営戦略論の視点でみても面白い事例です。
Posted by わくわくなひと at
15:55
│Comments(4)



