2011年05月30日
基本理念やビジョンづくりは男向きの仕事?女性経営者は?
 アラン・ピーズ&バーバラ・ピーズ『嘘つき男と泣き虫女』主婦の友社(2005年12月31日第7刷、2004年4月20日第1刷)を、やっと読み終えました。
アラン・ピーズ&バーバラ・ピーズ『嘘つき男と泣き虫女』主婦の友社(2005年12月31日第7刷、2004年4月20日第1刷)を、やっと読み終えました。電車に乗った時、何となく気が向いた時に、ちびりちびり読んでいきましたので、読み終わるまで数ヶ月かかりました。
「なるほど、なるほど」という感覚的記憶だけで、中身はほとんど覚えていません。最後の最後である「訳者あとがき」を読んで、以下のところに、ひっかかるところがありました。
本書にもあるように、男は問題点を解決することを何よりの生きがいにしている。ただしその前に、全体像や基本理念を理解しておくことが大前提で、そういう抽象的なところから入らないと、具体的な解決策に進めないのだ。逆に理念さえ押さえておけば、細部はどうでもいいと思っている。
・・・
いっぽう女は、他人とのつながりを求め、コミュニケーションを充実させることが生きる目的だから、血の通わない冷たい機械とのお付きあいは、必要最小限にとどめておきたい。箱の中身や仕組みはもちろん、全体像や理念については、はっきり言って興味はゼロ。使いかたを誰かに習うときも、とにかく、「いまやりたいこと」を実現してくれる方法さえわかればよい。このとき教えるのが男性だと、お得意の理念から入ろうとするので、「いま、このコピーが取れればいい」という女性と衝突する。ついでながら、女性は人間にかぎらず、「つなぐ」ことが好きなようで、AV機器の配線が得意な人もけっこう多い。
経営とかマネジメントというと、「理念やビジョンが大事」とか「事業計画が大事」と、ことさら強調されます。行政の助成金とかは、ほとんどが、しっかりした事業計画をつくることが条件となっています。
私も素直に大事だと思うし、日常業務の合間に事業計画を固めていく作業を正直うざいと思うことがありますが、全体像やビジョン、戦略を考えるのは嫌いではありません。確かに“細部はどうでもいい”と思っているところも認めます。
気になるのが女性経営者たちです。私が知っている女性経営者たちで、全体像とかビジョンとかを好きこのんで語っている人を知りません。それでも、この厳しい時代に、がむしゃらに営業してマンションの最上階の部屋を買ったり、事務所を二倍の広さに拡張している女性経営者もいます。私が事業計画やビジョンを作っているという話をしようものなら、「まだすることはいっぱいあるんじゃない?」と変人か暇人扱いされているようです。
社内の女性を見ても、何か行き当たりばったりでやっているようですが、納品という最後の仕事までに帳尻を見事に合わせていく人もいます。それに比べ私の場合は、8割くらいできてゴールが見えてくると、エネルギーが落ちていくことを自覚しています。一長一短を補え合えるのが組織という会社の強みだと思います。
『嘘つき男と泣き虫女』の内容がおおかたの男性と女性にあてはまるとしたら、世の経営者やマネジメントの本のほとんどは男性向けということになりはしないでしょうか。
これだけ女性経営者が増えてきている時代ですので、女性向けのマネジメントの本も、いずれたくさん出てくることと思います。教条的になりすぎた感じがするマネジメントの常識を、女性経営者にぶっ飛ばしてもらいたい。そんな妄想も浮かんできました。
Posted by わくわくなひと at
16:07
│Comments(2)
2011年05月28日
あと○○円で、くじがひけます!・・・セブンイレブンの増収策
 昨日のこと、晩酌のつまみとビールを買いにセブンイレブンに行きました。
昨日のこと、晩酌のつまみとビールを買いにセブンイレブンに行きました。つまみを買いすぎたかな?ビールとトロピカーナのオレンジジュース、それに、つまみあれこれで1,200円余りになったかと思います。
それでレジに行ったところ、「あと百数十円で、くじが2回ひけます」と言われました。
油断していました。ハッ!として、今、買わなくてよいタバコを1箱買いました。
当然、くじは2回ひきましたが、ダブルスカ!まあどうでもいいけど、そんなもんだろうと家路につきました。
そして今日、またしてもセブンイレブンに行きました。今度は別の店です。
いろいろ買ってレジに行くと、「あと10円で、くじがひけます」と言われました。
またタバコが思い浮かびましたが、「いや、けっこうです」ときっぱり。
何と意志が強いことか。
それにしても、店員の「あと○円で、くじがひけます」は、これまでなかったことではないでしょうか。それも、特定の店だけでなく、サンプル数2軒だけど、同じような言い方をしています。
私の記憶が正確ならば、今まではそんなことは言ってなかったと思います。レジで○○円を支払うことになって、「くじを2回ひいてください」と言われ、「ああ!そうなん」と思って、くじをひいてたような感じです。
それが、たぶんどこのセブンイレブンでも、同じように「あと○円で、・・・」と言ってそうです。
店員の教育が徹底してそうなので、全国に数万軒あるセブンイレブンで、私のように虚を突かれて、つい買い足してしまう人が続出しているに違いないと妄想しました。
このキャンペーンは昨日からで6月19日までだそうです。想像するに、全国数万軒あるセブンイレブンの売上は10%増はいっちゃってるかも知れません。
なかなかの知恵者ですが、昨日から数日間は売上増が続き、消費者が慣れてくる従って売上増は緩やかになりそうです。しかし、知恵者のセブンイレブンは、第二弾の仕掛けを考えているかも知れません。
Posted by わくわくなひと at
13:22
│Comments(3)
2011年05月23日
福岡のビジネスパーソン向けマガジン「OPEN」
 今日23日付け西日本新聞夕刊を息抜きに何となく見てました。
今日23日付け西日本新聞夕刊を息抜きに何となく見てました。それで、1面から、ふわふわと見出しだけ、特に記事までは読みませんでした。そして、最終面のテレビ面の下の大きな広告に目が止まりました。
大きな文字で、OPEN。
何だろうか?と思い見ていくと、PDは「福岡のビジネスパーソンのためのプレミアムグルメマガジン」となっています。
「こんなマガジンがあるんだ!」と思って眺めていくと、vol.14となっています。定価300円。福岡市内各コンビニエンスストア、九州一円各書店及び山口県の一部書店で売ってるそうです。発行は、株式会社ルネサンス・プロジェクト(福岡市中央区)となっています。
エリア特集は「大人の血がざわめく街 薬院・警固四つ角」。表紙の写真は、薬院・警固四つ角にある「博多忘我 西はら」の主人となっており、酒と肴がかくも絶妙なるその訳は・・・となっています。
確かに、うまい店はオヤジが詳しいと思います。そんなオヤジだけが知っている店がたくさん載ってそうな感じですね。
でも、ふつうのオヤジが、こんな本は買うかな?よく見かける、うまいものの蘊蓄を饒舌に語る30歳代くらいの男性が買うのか?グルメな女性もネタ仕入れに買っているかも知れません。
ビジネスマンではなくビジネスパーソンだから、男性向け限定ではなく、ターゲットを広めにして成り立っている冊子かも知れません。
男性向け雑誌の経営は、本当、難しいと言われてますから、売れ行きがどんな案配か気になるところです。
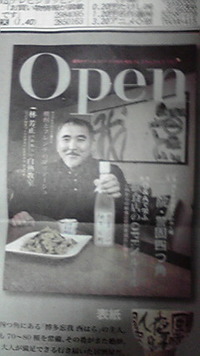
Posted by わくわくなひと at
18:31
│Comments(2)
2011年05月21日
ギンギラ劇団に阪急と新博多駅が登場!
 ギンギラ太陽'sのかぶりもの演劇に、阪急デパートと新博多駅が登場するそうです。
ギンギラ太陽'sのかぶりもの演劇に、阪急デパートと新博多駅が登場するそうです。題して「博多駅がやって来る ヤア!ヤア!ヤア!」。7月8日から10日、天神の西鉄ホールで開演されます。
この4月から「街の動きと同時進行の物語」をやっていて、天神の仲間としてパルコが初登場した4月の第1弾は大好評完売だそうです。
第2弾は、どうなるか。DMの絵を見ると、阪急デパートが新幹線のN700系に乗って博多駅にやってきています。驚いていそうなのが、岩田屋、三越、天神コア。大丸とエルガーラは、怒って何やら叫んでいます。パルコは愛嬌をふりまいている。ソラリアは冷静に観察しています。昔あった川端の玉屋デパートと井筒屋博多駅店の姿もあります。西鉄バス軍団がラッパを吹いているのは何を意味しているのか?
みんなが馴染みのデパートや交通機関がすべてキャラになって、どたばた劇を繰り広げる。
何か面白そうだけど、行けるほどの余裕があるかどうか。悩んでます。
Posted by わくわくなひと at
15:12
│Comments(5)
2011年05月09日
アマゾンからガードナーの中古本を中心に購入!
 12月発表という、ある目標が決まったので、それに照準を合わせて、本の買いあさりが始まりました。でも、この辺で小休止しときたいと思います。
12月発表という、ある目標が決まったので、それに照準を合わせて、本の買いあさりが始まりました。でも、この辺で小休止しときたいと思います。ここ2、3日で、アマゾン経由の中古本が次々と到着。後で何が何やら分からなく恐れがありますので、購入本の概要を記録しておきます。
■ハワード・ガードナー『芸術、精神そして頭脳 創造性はどこから生まれるか(ART,MIND AND BRAIN A Cognitive Approach To Creativity)』黎明書房(1991年1月10日初版)
【読みたい箇所】
・偉大な学者たち-ジャン・ピアジェ、ピアジェとチョムスキーの論争、クロード・レヴィ=ストロース-芸術の構造化、エルンスト・カッシラー-シンボルによる認知へのアプローチ、スザンヌ・ランガー-『シンボルの哲学』再考、ネルソン・グッドマン-美的シンボル、エルンスト・ゴンブリッジ-美術の歴史的展開とその解釈
・子どもの芸術的発達-芸術的創造性の謎、芸術的能力はどのようにして育つのか、知能を内蔵する玩具、テレビの影響はテレビによるものなのか、口述筆記の諸問題など。
・創造性の最高峰-成人期の創造性、モーツァルトの作曲流儀など
■ハワード・ガードナー『MI:個性を生かす多重知能の理論(Intelligence Reframed Multiple Intelligences for the 21st Century)』新曜社(2008年12月20日初版第5刷、2001年10月20日初版第1刷)
【読みたい箇所】
・精神測定学小史、知能についてカギとなる三つの疑問、創造性と知能、リーダーシップと知能、創造性とリーダーシップ、ロールシャッハテストを超えて、知能の評価、残された謎-研究課題など。
■ハワード・ガードナー『多元的知能の世界 -MI理論の活用と可能性-(MULTIPLE INTELLIGENCES The Theory in Practice』日本文教出版(2003年9月25日初版)
【読みたい箇所】
・文脈の中での評価:標準テストに対する代案
■ハワード・ガードナー『知的な未来をつくる「五つの心」(FIVE MINDS FOR THE FUTURE)』ランダムハウス講談社(2008年4月23日第1刷)
【読みたい箇所】
・熟練すること、統合すること、創造すること、尊敬すること、倫理にかなうこと
・題材を学ぶことと、熟練すること、発想を熟練させるには、学問的に熟練する、「熟練」のもう一つの意味
・統合のさまざまな型、効果のある統合、行きすぎの統合
・創造性の概念を見直す、あらゆる年齢祖の創造者を育てる、ビジネスの世界での創造性、大小集団が発揮する創造性、統合と創造のかかわり、創造性に影響する三つの新要素
■本田惠子・日能研『脳科学を活かした授業をつくる 子どもが生き生きと学ぶために』C.S.L.学習評価研究所(2006年6月1日初版第1刷)
【読みたい箇所】
・右脳型の子どもと左脳型の子ども、マルティプルインテルジェンスとは?、MIを活用する効果、認知構造の理解
・自分の暮らすの生徒の認知傾向を知る、伸ばしたい知能に上手に働きかけるには?
■ダニエル・ゴールマン『SQ 生きかたの知能指数 ほんとうの「頭の良さ」とは何か』日本経済新聞出版社(2007年1月5日1版1刷)
【読みたい箇所】
・感情のプラス・マイナス、ラポールの秘訣、ミラー・ニューロン、心の行間を読む能力、最高の力が出るスイートスポット、社会的知性を最高する
Posted by わくわくなひと at
16:31
│Comments(0)
2011年05月07日
ちくま学芸文庫などを大量買い!
 昨日の夜と今日の遅い朝、ちくま学芸文庫のマイケル・ポランニー『暗黙知の次元』をぱらっぱらっとめくっていました。以前、読んでいる本ですが、もう一回読みたくなりました。
昨日の夜と今日の遅い朝、ちくま学芸文庫のマイケル・ポランニー『暗黙知の次元』をぱらっぱらっとめくっていました。以前、読んでいる本ですが、もう一回読みたくなりました。文庫本の後ろの頁には、よく他の本の宣伝が載っています。これにも惹かれてしまい目を通したのが、いけませんでした。10冊くらい読んでみたくなりました。
もういけません。天神のジュンク堂書店にいけば、ちくま学芸文庫のコーナーだけで3つくらいの書棚があります。やむを得ず行くことになりました。
大名から行きますので、その前に福岡ビルの「TSUTAYA天神駅前福岡ビル店」が立ちはだかっています。TSUTAYAは警固の方にも大きいのがあります。そして隣のビルには西日本一の規模と言われるジュンク堂書店があります。そういうポジショニングですので、巨大な古本屋となっています。「発売後3カ月以内の本(本体価格)の20%以上で買取」をうたい文句にしていますので、新刊本が安く手に入る巨大古本屋さんなのです。
ちくま学芸文庫は文庫本といっても、安くて1冊700円、高いのは1,500円は下らない。というわけでTSUTAYAで手に入るものは手に入れて、残りの新刊本はジュンク堂でいうシナリオができました。
まあ、ちくま学芸文庫という地味でマニアックな文庫本ですので、古本には期待しておりませんでした。よく売れているのはありましたが、目的とする本はありません。それよりも大学の教科書みたいな専門書が安く手に入るかも知れないと思って、心理学のコーナーを見ました。
今、創造性の測定尺度の調査研究というのをテーマにしていますので、読んでみたい本がありましたよ。どれも1冊500円で、計1,000円。
■渡辺洋『心理検査法入門』福村出版(1997年4月20日第4刷)
・ウェクスラー知能検査、Y-G性格検査、テイラー不安検査、ロールシャッハテストなどの理論と概要が学生さん向けに解説されています。定価本体2,600円。
■中丸茂『心理学者のための科学入門』北大路書房(2003年5月20日初版第3刷)
・心理物理学、認知心理学、行動分析学などのパラダイムに関する考察が書かれています。
さて、本丸のジュンク堂書店では、ちくま学芸文庫の書棚に前に少なくとも40分ほど立っていました。それで10冊くらいを籠に入れて、椅子に座って、本当に今買うべきかどうか本をめくりながら吟味しました。それで購入決定に至ったのは、次の本です。しめて7,000円余を散財!
その後、ジュンク堂書店を出たところで、愛用の帽子を忘れていることに気づきました。夢中になって本を吟味していたからと思われます。すかさず20分ほど前に座った場所に戻りましたが、女性が座って本を読んでいて帽子らしきものはありません。カウンターに帽子をなくした旨、伝えましたが、今のところ、忘れ物の中にはないと言われました。
すると、カウンター近くのところで『アイデアのちから』というタイトルが目に入りました。「ううん、これも買い」。本体価格1,600円也。
■ウンベルト・マトゥラーナ/フランシスコ・パレーラ『知恵の樹 生きている世界はどのようにして生まれるのか』ちくま学芸文庫(2009年4月20日第6刷)
・序文-知恵の環 浅田彰、<いかにして知るのか>を知る、神経システムと認識、<言語域>と人間の意識など。
■養老孟司『唯脳論』同(2010年10月20日第18刷)
・一連の脳ブームの端緒を拓いたスリリングな論考。
■モーリス・メルロ=ポンティ『メルロ=ポンティ コレクション』同(2010年7月10日第9刷)
・表現としての身体と言葉、言葉の問題、問い掛けと直観、絡み合い-キアスム(「見えるものと見えないもの」から)など。
■C.G.ユング『変容の象徴 上、下』同(上1992年6月26日第1刷、下2007年6月30日第5刷)
・人間の無意識の世界から紡ぎだされた象徴的主題とそれを核として形成された神話的なイメージや象徴的表現の分析による心の構造の探求。
■中条省平『小説家になる!』ちくま文庫(2006年11月10日第1刷)
・物語の構造分析、マンガに学ぶ、三島由紀夫の『月』を読む、岡本かな子の『鮨』を読む、川端康成の『眠れる美女』を読む、室生犀星の『蜜のあわれ』を読む、フロベールを読むなど。
■チップ・ハース/ダン・ハース(解説・勝間和代)『アイデアのちから』日経BP社(2011年3月17日第1版第8刷)
・記憶に焼きつくアイデアの六原則、創造性の体系化など。
Posted by わくわくなひと at
21:14
│Comments(0)
2011年05月07日
デンターシステマEX デザインが変わったので見落とし!
 この1年半ほど、ライオンさんの「デンターシステマEX」という歯磨きを愛用しています。マルチ効能がうたい文句の歯磨きで、その効能のほどは分かりませんが、歯の状態は悪化していないように感じています。
この1年半ほど、ライオンさんの「デンターシステマEX」という歯磨きを愛用しています。マルチ効能がうたい文句の歯磨きで、その効能のほどは分かりませんが、歯の状態は悪化していないように感じています。それで、最近、残り少なくなったので、赤坂駅の近くにあるドラッグイレブンに行きました。歯磨きコーナーに何分間か立っていましたが、「デンターシステマEX」が見つかりません。さては、このドラッグストアはライオン系の歯磨きが置いていないのかと思ってあきらめました。まだ1週間くらいはもちそうという状況もありました。
昨日の夜、今日の朝、「残り少なくなってきたな」という思いがつのります。何か嫌な気分を引っ張ったままでした。
そして今日は天神の本屋さん巡りをした後、アールグレイがなくなっていることを思い出しました。セブンとかファミマとかに行きましたが、アールグレイのティーパックはありません。この紅茶が醸し出す、イランイランのような刺激が好きなのです。何としても欲しくなったので、天神から赤坂まで歩き、サニーに入りました。
サニーでは、「デンターシステマEX」のことを思いだし、歯磨きコーナーに行きました。「あぁ、やっぱりここにも置いてない。ひょっとしてライオンさんの工場は東北にあって品不足になっているのか?」。そこまで思いました。
そこで「あっ!」です。「ひょっとして、これがデンターシステマEX?」。商品を手にとってまじまじと商品説明を読んで、デンターシステマEXであることを確認しました。
年取ったからでしょうか。新しいデザインに変わっているので、商品のイメージが固定化していて判別できなかったというわけです。
確かにイメージは踏襲されていますし、従来品の素人くさいデザインよりも大幅に洗練されました。
ひょっとしてドラッグイレブンにも置いてあったのかも知れません。もう少しで違う商品にスイッチするところでした。もちろんトワイニングのアールグレイも買いました。
Posted by わくわくなひと at
20:05
│Comments(2)
2011年05月05日
130%ピンクグレープフルーツ これは何だ!
 セブンイレブンで“ぎょっ”とする商品に出会いしました!
セブンイレブンで“ぎょっ”とする商品に出会いしました!「130%ピンクグレープフルーツ」。「これは何だ!」と思いましたね。
おいしさ
ギュ~つ、
超果汁!
濃縮還元
果汁率100%の可溶性固形分(果汁の濃さの単位)の基準値に対して1.3倍になるように濃縮還元したことから、130%と表現しております。
高梨乳業株式会社(横浜市)
飲んでみました。「ウォー」というほどではなく、夏みかんを搾ったジュースのような感じでした。
130%は目立ちます。いつ発売されたのか知りませんが、トライアルは増えるでしょう。後は「また飲みたい」と思わせるかどうかですね。
それと濃縮もので買ったものがもう一つあります。
これも店頭で「あれ!」と思いました。ミニサイズです。
KAGOME 超濃縮
野菜一日
これ一本
ここまでなら伊藤園さんにも似たような商品がありますが、ヤクルトくらいの大きさになっていて驚きました。
「このサイズで野菜1日分350g分使用」
技術屋さん、やりましたね。125mlに350g分の野菜を封じ込めてしまいました。
私の場合、野菜ジュースを飲むのは、「外食ばっかりで野菜が不足している」という脅迫観念を抱いた上での行動です。好きで買ったり飲んだりしているわけではありません。
以前のサイズだと、全部飲むのに苦痛を感じていました。
それでも、「仕方なかんべ」と思って飲んでおり、充足されていないニーズを持っていたんですね。
これだと、せいぜい二口分くらいだから、お腹もたぷたぷした感じになりません。
他の競合品を駆逐してしまうヒット商品になるかも。
Posted by わくわくなひと at
20:48
│Comments(2)
2011年05月03日
精神科医・和田秀樹、脳科学を斬る!
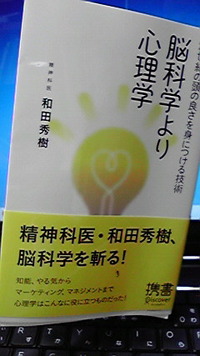 和田秀樹『脳科学より心理学 21世紀の頭の良さを身につける技術』ディスカバー携書(2011年4月15日第1刷)。
和田秀樹『脳科学より心理学 21世紀の頭の良さを身につける技術』ディスカバー携書(2011年4月15日第1刷)。帯に「精神科医・和田秀樹、脳科学を斬る!」と書いてある通り、一頃、流行した脳科学の限界を指摘した本です。確かに一年半くらい前に本屋さんに行くと、茂木健一郎さんの本をはじめ脳関係の本が棚にあふれていました。茂木さんの本の中には小林秀雄賞を受賞した『脳と仮想』(新潮文庫)など凄い本があるのに、一年半くらい前、どの本だったか「何か伝わってこないな」と思いながら読み進んでいくと、最後に、茂木さんが言ったことの聞き書きという本もありました。“わかりやすい”ということに単純にこだわった結果でしょうが、その人が著す一行一行には何千行に相当する知識や経験が背後にあることでしょうから、「どうかな?」と思っていたら、ブームが去っていったような感じです。
和田さんの本に書いてあった脳科学の限界は、確かにその通りかなと思って読みました。1980年代に心理学ブームもありましたが、ブームが過ぎ去ると、「心理学=いかがわしい」というイメージさえ残ってしまいました。脳科学が発展するには時間がかかるし、検証や実験が非常に困難という弱点がある。だから、脳そのものをのぞき見るよりも、人の意識や行動の実証研究を積み重ねてきた心理学がもっと頑張る必要があるし、人々も心理学の誤解に基づく情報に惑わされずに、もっと活用すべきという内容だったと思います。
私の場合、この本は別の目的で読みました。私のような者には荷が重い“創造性を測る尺度をつくる”というミッションを持っているからです。精神科医や心理学関係の人たちが、今、どのような問題意識を持ってどのようなことを考えているかを知りたいと思って読みました。あまり驚いたり、感動したりということはなく、たんたんと読みました。
以下は自分のためのメモです。
・心理学者にとって、テストというのはまさに命です。(29頁)
■陰山英男先生の「百マス計算」
陰山先生は百マス計算だけをやっていたわけではなくて、授業の最初の5分ぐらいそれをやったあとは、ふつうの授業をなさっていました。ただ、百マス計算をやったあとのほうが生徒が授業に集中するようになるというメリットがあったのです。(59頁)
■ロンドン大学のエレノア・マグアイナー博士(認知神経学)による画期的な発見
・・・博士は、それまで加齢とともに減少するだけだと思われていた脳の神経細胞が、トレーニングによって新生し、増加することを発見しました。これは、この10年で、脳科学における最大の発見のひとつです。(60頁)
■脳科学とされているものの一部は、認知科学
生きた脳を使った研究ができないこと、基礎研究と治療薬の完成には非常に長い時間がかかること、この2つの脳科学の限界に対して注目されてきているのが、いわゆる認知科学と呼ばれるものです。
ものすごく大雑把な言い方をすれば、いわば脳科学と心理学の折衷の学問です。
一般的には、認知心理学ととても近いものとされますが、その違いは、認知にまつわる仮説を立て実験をし、そしてそこでソフトがどうなっているかを考察するのが認知心理学だとしたら、認知科学の場合は、さらにそこで、脳の生物学的なものがどうなっているかも調べます(そういう意味では、茂木健一郎氏が言っているのは、脳科学というより、認知科学と言うべきでしょう)。(71頁)
■心理学のほうが実証的。脳科学こそ、仮説と空想と思いつきの世界
そして、心理学のテストがどこまで当てになるかというのは、そのデータの蓄積量に比例します。
だから、ひょっとしたら、ピネーの知能テストも、ピネーが開発した時点では、そんなにあてになるものじゃなかったかもしれませんけれど、それが何千人、何万人、何千万人と受けているうちに、信頼性が高まってきたのです。だいたい、この年齢の標準の知能はこういうものだということが、わかってきたのです。
同じように、ロールシャッハのあんなインクのシミでもかなり標準化されてきているわけです。
心理テストというのは、一見いかがわしく思われるかもしれないけれど、統計学として考えれば、結構あてになるテストも多いのです。
これに対して、脳科学というのは、実はそのあたりの検証がほとんどなされていません。(87~88頁)
■ビネー式知能検査の値である知能指数(IQ)=頭の良さ?
ビネーがつくった知能検査、そこから算出されるいわゆる知能指数(IQ)は、知能のごく一部しか計測していない、世の中を発達させるためにもっとも重要な創造力や、社会に出てからもっと役立つ論理性のような知的能力については計測できないなど、さまざまな批判を受けながらも、長い間、子どもの「頭の良さ」と同一視されてきました。
すでにお話ししたように、それは、ビネーが考えた「この年齢ならばこのぐらいのことができるであろう」という事柄のセットで、いわゆる知的障害かそうでないかを判断するためのものでした。
知能指数というのは、「こういう問題ができるのは平均して何歳何ヵ月」として統計的に算出される精神年齢を実年齢で割ったものです。つまり、5歳0ヵ月で5歳0ヵ月のことができれば、知能指数は100、7歳0ヵ月のことができれば140。つまり、ビネーの知能検査における知能指数から生まれてきた頭の良さとは、要するに、発達の早さでした。
それが子どものほんとうの頭の良さを示すかどうかはともかくとして、莫大なデータの蓄積により標準化も進み、とくに就学前の幼児に対して、ふつうの学校で教育効果が得られるかどうかを見分けるには、とても便利だったのです。(93~94頁)
■WAIS(ウェクスラー成人知能検査、Wechsler Adult Intelligence Scale)
WAISのように、16歳以上を対象とした成人向けの知能テストもつくられ、データを蓄積して標準化もかなり進んでいますが、子ども向けのビネー式知能検査ほどには普及していません。
それより、学力テストとその総まとめである学歴のほうが、判別法としては便利だし、ある意味、過去のデータから信頼性もそれなりに得られているからです。
・・・
以後の年代に対してあまり優れたテストが生まれていないのは、知能検査でなくても頭の良さを推測する道具があるため、なかなか使われない→そのためデータが蓄積しない→その結果、データに偏りがあり信頼性が高まらない、という理由によります。(94~95頁)
■成人用知能検査、WAISの限界
幼児の発達の具合を検査する以外に、知能検査が一般に用いられる場面としては、認知症の検査があります。ところが、もっとも一般的な成人用の知能検査、WAISは、認知症の判別に適していないのです。少なくとも初期認知症の場合は、WAISの点数が落ちません。
なぜかというと、WAISは、おもに理解力を検査するテストだからです。初期の認知症では、記憶障害と記憶に基づく高次の判断力の障害はあるものの、理解力は落ちていないからです。
・・・
ともかく、こうした理由で、WAISは中程度以上の認知症にはそこそこ使えるのですが初期の認知症の診断には使えません。そのため、新しいテストがいくつも開発されてはいますが、残念ながら、初期認知症の診断用として、これだ!というものはまだ出てきていません。(96~97頁)
■ガードナーの多重知能
さて、ビネー式知能テストやその流れを汲む知能検査に対して、1980年代、ハワード・ガードナー(ハーバード大学教育学大学院教授)という人が、多重知能(Multiple Intelligences、MI、「Frame of mind」で提唱。邦題『MI:個性を生かす多重知能の理論』、新曜社、2001年10月)という考えを言い始めました。つまり、知能というのは1種類ではない、というのです。(98頁)
・・・
実は、アメリカは、日本以上に学歴社会で、日本以上にインテリが素直に尊敬する国だと思うのですが、そのアメリカの、しかも、最高のエリート校のハーバード大学の教授が多重知能といって、言語的知能・論理数学的知能・空間的知能といった従来の「知能」に加えて、音楽的知能・運動的知能・社会的知能・実存的知能の4つをあげたのです。(100頁)
■ダニエル・ゴールマンのEQ
ガードナーの多重知能論は、ビネー以来の知能に対する定義を変え、やがて、ダニエル・ゴールマン(これも彼がまとめただけで提唱者ではないのですが)のEQ(Emotional Intelligence Quotient、心の知能指数)理論へと引き継がれていきます。(101頁)
■知識が先か?創造が先か?認知心理学が明らかにしたこと
こうして、認知心理学の中では、やはり、たくさん知識がインプットされている人の方が賢いということで、再び知識が重要視されるようになってきました。ちょうどそのころ、たまたまドラッカーが知識社会というような言葉を使ったことも含めて、80年代、特に90年代ぐらいから、知識というものに対する再評価が高まってきたのです。
それと同時に、人間とコンピュータの違いについても、いろいろなことが明らかになってきました。たとえば、人間の重要な能力のひとつに、いわゆるヒューリスティックス(heuristics、必ず正しい答えが導けるわけではないが、ある程度のレベルで正解に近い解を得ることができる方法)=「推論」があります。不十分な知識からでも、それを加工応用して、答えを出すことのできる能力です。
つまり、材料がないかぎりはヒューリスティックスもできませんが、材料をもとに、それを加工応用して答えを出す能力は、人間はコンピュータと比べて優れているとされたのです。
・・・
認知心理学の研究が進むにつれ、知識、すなわち基礎学力が大事だということがあらためて認識されました。
さらに、その知識をもとに推論させる教育が、初等・中等教育の基本中の基本とされました。(106~107頁)
■「メタ認知」と「メタ認知的活動」
コンピュータなら、同じ情報をインプットして同じ演算ソフトをインストールすれば、同じ問題に対してつねに同じ答えを出します。
ところが人間というのは、そのときの気分やまわりの意見、新たに得た情報など、いろいろな条件によって、同じ問題に対する答えを変えてしまいます。たとえば、落ち込んでいるときには悲観的な推論をする、ハッピーなときには楽観的な推論をするといった具合に、ヒューリスティックスがはげしくぶれてしまうわけです。
そこで、そこをコントロールする必要が出てきます。正しい解を出すには、自分の推論が、気分やまわりの意見などに影響されて、ふだんとは違う状態になってはいないか、おかしくなってないか、あるいは、そもそも自分の知識が偏っていないかなどをチェックする必要があるわけです。
このように、自分の推論が歪んだものになっていないかどうかをチェックするのがメタ認知です。要は、自分の認知状態を認知するということです。
・・・
つまり、自分の認知状態にまつわる知識を得たら、その知識をもとに、自己修正、自己改造をしていくということで、これを、メタ認知的活動と呼びます。(109~110頁)
■「認知的成熟度」
次に、もう一つ重要なポイントとして、認知的成熟度という概念があります。そして、その代表的なものが、曖昧さに耐える能力です。
たとえば、答えがAかBかはっきりしない状況では、だれでも不安になります。そこで、その不安を解消するために、とりあえず決断してしまう。けれども、ここで即断即決しないで、その中間にあるさまざまな可能性を考えられる人もいます。そして、そういう人のほうが、認知的成熟度が高い、とされるのです。(112~113頁)
・・・
既存の知識が疑えない状態のまま勉強していても、認知的成熟度は高まりません。あまり賢くもなりません。
つねに新しい知識を得、その知識によって既存の知識を疑ってみる、・・・(114頁)
■並列思考
いろんな知識が入ってきたときに、なんでも、すぐさま、既存の知識との整合性をつけようとするのではなく、こういう考え方もありうるなと、受け入れるのです。それまで自分が持っていた知識を否定する必要はありません。否定することなく受け入れるのです。これを私は、並列思考と呼んでいます。(119~120頁)
■逆行抑制
心理学の考え方に、逆行抑制というものがあります。新しいことを覚えると、それまで覚えていたことを忘れてしまう、ということ。実際には上書きされたせいで、頭の中から引き出せなくなる現象です。
・・・
つまり、何か新しく上書きしたときには、積極的に、その前のものを引き出してやる訓練をしないと、知識というものはどんどん埋もれたままになっていってしまうのです。ちょうど未整理を未整理な状態のまま、どんどんどんどん積み上げていくのと同じです。(120~121頁)
■和田式「知的体力」
1 仮説力(知性や知識)
くどうようですが、心理学というのは、仮説を立てて、それを検証する、一定以上の確率が得られたら、それを「こうすればこうなる」と示す実証的な科学なのです。
そういう意味では、心理学というのは、統計学であるという人もいます。ともなく、心理学において言われていることは、一定以上の確率があるというだけであって、決まったわけではない。
・・・1つめの仮説がだめだったときに、次の仮説が立てられる知性と知識です。(129頁)
2 体力(資金力も含む)
・・・失敗しても失敗しても、この次はこれ、この次はこれと次々と仮説を立て、実験を重ねていく。何年も何十年も重ねていく。仮説を立てられるだけでなく、実際に実験を重ねられた人だけが成功するのです。それには、文字どおり体力がいるし、もちろん、資金的な体力も不可欠です。(130頁)
3 精神力
精神力は、答えのないものに答えを見出そうとするときには、とくに重要です。(131頁)
■スキーマからの脱却
いま、「答えのないところに答えを求める」と言いましたが、そのことを別の側面から見て、心理学的な言い方をすると、「スキーマからの脱却」ということになります。もっとわかりやすい言い方でいえば、頭の柔らかさです。
ここでいうスキーマとは、いわゆる「概念」、これはこうである、という物事に対する定義、心象のことです。複雑なことの答えを自分なりに自動的に出せるような認知の図式と言えるものです。(133頁)
スキーマの4つの特徴
①一致情報への選択的注意
たとえば、血液型がA型の人は真面目で几帳面だというスキーマを持っている人は、実際にA型の人がいると、その人のなかで自分のスキーマと一致している情報にのみ注意を向けるので、結局、その人の真面目な面しか見なくなってしまうということです。
②不一致情報の無視
A型なのに時間に遅れてきたとか、机が散らかっていたりする人がいると、それは一時的なことなんじゃないかとか、こいつはA型にしては珍しい例外なんだということにして、自分のスキーマとの不一致情報を無視してしまいます。
③一致情報の記憶の促進
自分の経験のうち、スキーマと一致した情報を記憶に残るけど、不一致情報は忘れられやすい、ということです。当たっている部分しか記憶に残らないのだから、血液型判断や占いは、それを信じる人にとっては「よく当たる」ということになります。
④一方向への記憶の歪み
たとえばA型の人が本を持っていたとき、それをシステム手帳だと思い込んでしまって、やっぱりA型は几帳面だよね、みたいな方向で記憶されるということです。
つまり、うまくいっているかぎりにおいては、スキーマを疑う必要はないのだけれど、一方で、どんなに成功していたとしても、それまでのスキーマどおりにはいかなくなってしまうことが起こりうることは知っておかないといけないということです。
うなくいかなくなったときに、自分のスキーマが疑えるだけのメタ認知を働かせることが重要だということです。(134~137頁)
Posted by わくわくなひと at
17:58
│Comments(5)
2011年05月02日
急須でいれたような、にごりの旨み~綾鷹
 「急須でいれたような、にごりの旨み」。
「急須でいれたような、にごりの旨み」。ペットボトルのお茶「綾鷹(あやたか)」のキャッチコピー(USPまたはPD)です。
たぶんテレビで見たり、店頭で目にされた方は多いと思います。
販売者は、コカ・コーラカスタマーマーケティング(株)となっています。
何か記憶に残るし、「それなら買ってみようか」と思ってしまいました。冷たいお茶ではありませんが、急須で入れた熱いお茶で満足した記憶を刺激されます。
自分と言えば、伊藤園かサントリーの濃い目のお茶のユーザーです。ペットボトルお茶のシェアは詳しく知りませんが、一年以上前は伊藤園の「おーいお茶」がトップで、サントリーの「伊右衛門」が2番手で続く展開だったと記憶しています。コカ・コーラもペットボトル入りのお茶を出していましたが、たぶん伊藤園やサントリーには及ばなかったと思います。
日本でコカ・コーラと言えば、圧倒的な自販機による販売力で有名です。飲料関係で新しいカテゴリーの新商品が出て、新たな市場が出来上がっていると、似たような商品を出して追撃してくる。場合によっては、宣伝と販売力により、トップシェアをとってしまうほどのすごいメーカーさんです(ふつうは先行逃げ切りが多い)。
個人的には、「コカ・コーラ」は凄いと思いますが、他のコカ・コーラ商品に特段お気に入りはありませんでした。しかし、この「急須でいれたような・・・」は予感ですが、トップをとるぞという意気込みが伝わってきました。
アイデアレベルや発想の仕方は京都の老舗が厳選したお茶をペットボトル製にしたというサントリーの伊右衛門と同じです。
ペットボトルに小さく商品コンセプト(C=I+NCN+B)とおぼしきことも書いてありました。
■アイデア(I)
・綾鷹は、上林春松本店が厳選した国産茶葉を使用し、急須でいれたような「緑茶本来の味わい」を目指して開発しました。
■新カテゴリーネーム(NCN)
・急須でいれたようなペットボトルのお茶?(急須のペットボトルお茶市場が出来上がった場合)
■消費者ベネフィット(B)
・綾鷹独自の「にごり」がもたらす、ふくよかな旨みと香り豊かな味わいをお楽しみ下さい(・・・の味わいを楽しむことができる)。
綾鷹もそうですが、今後のコカ・コーラさんの動きには、いやでも関心を持ってしまいそうです。
Posted by わくわくなひと at
16:01
│Comments(2)
2011年05月01日
ものづくり、技術、マーケティング、イノベーションを考える
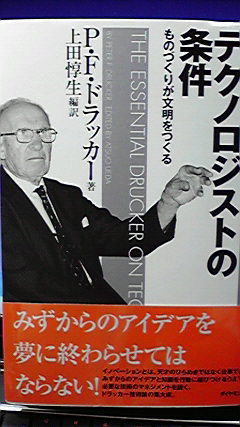 「あれを買いたい。あの本が欲しい。」などという所有(have)ニーズは、移ろいやすい。Haveニーズの上位の目的であるdoニーズやbeニーズは、そうそう変わらない。
「あれを買いたい。あの本が欲しい。」などという所有(have)ニーズは、移ろいやすい。Haveニーズの上位の目的であるdoニーズやbeニーズは、そうそう変わらない。連休中に3年先を見通した事業計画の骨子を固めることにした。このため4月下旬に、自分たちが行ってきたこと(作ってきた市場)、自分たちの技術や強みを明文化する作業をしていた。この作業で当面の自分のhaveニーズが変化していたのだろう。たくさん持っているし、けっこう読んできたドラッカーの著作の一つを見て驚いてしまった。
その一つとは、P・F・ドラッカー『テクノロジストの条件 ものづくりが文明をつくる』ダイヤモンド社(2011年2月24日第4刷、第1刷2005年7月28日)。帯には「みずからのアイデアを夢に終わらせてはならない!イノベーションとは、天才のひらめきではなく仕事である。みずからのアイデアと知識を行動に結びつけるうえで必要な技術のマネジメントを説く。ドラッカー技術論の集大成。」と書いてある。
“ものづくりが文明をつくる”。“みずからのアイデアを夢に終わらせてはならない!”。“みずからのアイデアと知識を行動に結びつけるうえで必要な技術のマネジメントを説く”。我々が今やっていることは、アイデアや技術をマーケティングに結びつける仕事そのもの。まさしく、この『テクノロジストの条件』は、ドラッカーのさまざまな著作の中から、自分が今取り組んでいるテーマに沿って編集し直した本だった。
まだすべてを読んでいない。今回は目次を見て、読みたいところから読んでいった。自分の内なるニーズを確認し整理したいからである。
読み進むうちに、今、自分たちが行っている事業活動がまさしくアイデアや技術をマーケティングやイノベーションに結びつけ、“ものづくり日本の復活”、そして日本発の技術を商品にしていく手法(キーニーズ法)を、アジアをはじめとする世界に普及していける、という確信に近いものを得ることができた。
■1日目
日本の読者へ-なぜ技術のマネジメントが重要なのか
プロローグ 未知なるものをいかにして体系化するか
【メモ】
・「大切なことは答えではなく問題である」
・イノベーションとは、未知なるものへの跳躍である。目指すところは、新たな見方による新たな力である。その道具は科学的であり、プロセスは創造的である。
・フランスの偉大な物理学者アンリ・ポワンカレは、科学上の発見に果たす直観の役割をはじめて指摘した。彼が取り上げたのは無意識かつ予見不可能なひらめきだった。
・イノベーションとは何も新しいことではない。新しいことといえば、ひらめきによって行なっていたことを体系的に行なうようにしたことだけである。そして、天才しか行なえなかったことを普通の人間が行えるようにしたことである。
Part1 文明の変革者としての技術「1章 仕事と道具」
Part2 技術のマネジメント「6章 ベンチャーのマネジメント」
【メモ】
・ベンチャーが成功するには四つの原則がある。第一に市場に集中すること、第二に財務上の見通し、特にキャッシュフローと資金について計画を持つこと、第三にトップマネジメントのチームを、それが必要となるはるか前に用意しておくこと、第四に、創業者である起業家自身がみずからの役割、責任、位置づけを決めることである。
・ベンチャーが成功するのは、多くの場合、予想もしなかった市場で、予想もしなかった客が、予想もしなかった製品やサービスを、予想もしなかった目的で買ってくれるときである。
・成長は余剰の発生ではなく、債務の発生と現金の流出をもたらす。ベンチャーは成長が健全で早いほど、より多くの資金上の栄養を必要とする。・・・ベンチャーはキャッシュフローの分析と予測と管理を必要とする。・・・ここでいう予測とは、希望的観測ではなく最悪のケースを想定した予測である。
・成功しているベンチャーは、みずからの資本構造を超えて成長する。これもまた経験則によれば、売上げを40パーセントから50パーセント伸ばすごとに、それまでの資本構造では間に合わなくなる。
■2日目
Part4 世界観の転換「13章 分析から知覚へ」
【メモ】
・コンピュータは、17世紀末のドゥニ・パパンの時代に始まった機械的世界観という分析的プロセスの究極の表現だった。コンピュータは、パパンの同時代人で友人だった数学者ゴットフリート・ライプニッツの発見、あらゆる数字はデジタルすなわち1と0で表現できるという発見に端を発していた。その後、バートランド・ラッセルとアルフレッド・ホワイトヘッドの『数学理論』(1910~1913年)が、ライプニッツの発見を論理に発展させた。その結果、データとして示すことさえできれば、あらゆるコンセプトが1と0によって表現できることになった。
・情報は分析的であっても意味は分析的ではない。知覚的である。
同「14章 知識の意味を問う」
【メモ】
・ヨーロッパも研究の成果をあげている。しかし技術格差が生じたのは、それらの研究成果を製品化し、マーケティングすることに失敗したためである。技術格差とはマネジメント上の失敗である。これこそヨーロッパにとって政府予算よりも大きな弱みである。金はつけることができる。しかし、科学上の成果を経済的な事業に転換する能力、すなわちマネジメントとマーケティングの能力を金で買うことはできない。
現代社会は、みずからの知識の基盤として理系、文系両方の人を必要とする。特に理系のことがわかる文系の人を必要とする。専門分野や方法論しかわからない人ではなく、知識を仕事に適用できる人を必要とする。新しい知識を生み出す人だけでなく、新しい知識を日常の活動に適用できる人を必要とする。
同「15章 ポスト資本主義社会の到来」
【メモ】
・われわれがこの転換期のさ中にいることは明らかである。もしこれまでの歴史どおりに動くならば、この転換は2020年までは続く。しかし、この転換はすでに、世界の社会、政治、経済、倫理の様相を大きく変えた。
■3日目
Part3 イノベーションの方法論 「9章 方法論としての起業家精神」
・それ(技術のダイナミクスの分析)は起業家として、次のような問いかけを行なう者がよくなしうるものである。「新産業や新プロセスの機会はどこにあるか」「いかなる新技術が市場のニーズに対応して大きな経済的影響をもたらすか」「まだ経済的影響をもたらしていない新知識は何か」「産業、プロセス、生産性に反映されていない新知識は何か」「新技術を意味あるものにすることのできる、いかなる新しい見方、コンセプトが生まれているか」「それらはいかなる種類の新技術に影響を与えるか」
・あらゆる製品に二種類以上の顧客が存在するがゆえに、それらの顧客すべての観点に立つことが必要である。・・・顧客の関心は常に、この製品あるいはこの企業は自分に何をしてくれるかである。
・新しいものには、既存の市場はない。・・・新技術は新市場を必要とする。
・売上げを増やし、雇用をもたらすものは技術であるとされている。だが技術は可能性を教えるに過ぎない。可能性を顕在化させるものはマーケティングである。マーケティングによるイノベーションである。・・・マーケティングとは、技術変化を経済的に意味あるもの、欲求の満足へと転換することである。
・起業家たる者は、イノベーションのための組織をつくり、マネジメントしなければならない。新しいものを予期し、ビジョンを技術、製品、プロセスに転換し、かつ新しいものを受け入れる人間集団をつくり、マネジメントしなければならない。
・トップの仕事は、アイデアを具体的な仕事の提案に転換させることである。出てきたアイデアを正面から取り上げるに値するものにするためには何が必要かを考えることである。取り上げるわけにはいかないなどといってはいられない。
同「10章 イノベーションのための組織と戦略」
・トップの地位にある者が、アイデアを正面から取り上げることを自らの職務としている。多くの場合、優れたアイデアは非現実的に見える。優れたアイデアを手にするには、多くの馬鹿げたアイデアが必要であり、両者を簡単に見分ける手段はないことを知らなければならない。いずれもが実現性のない馬鹿げたものに見え、同時に素晴らしいものにも見える。したがって、アイデアを奨励するにとどまらず、出てきたアイデアを実際的、現実的、効果的なものにするには、いかなる形のものにしなければならないかを問いつづけなければならない。荒削りで馬鹿げたアイデアであっても、実現の可能性を評価できるところまで練らなければならない。
同「11章 既存の企業におけるイノベーション」
・しかし、この10年間広く喧伝されてきたこれらの経営戦略論の多くが、分析から自動的に行動プログラムがもたらされるとしている。これは考え違いであり、それらの経営戦略論を採用した多くの企業と同じように失望させられるだけである。分析から得られるものは診断にすぎない。その診断にさえ判断が必要である。さらには事業、製品、市場、顧客、技術についての知識が必要である。
分析に加えて経験が必要である。高度の分析手法を手にしただけのビジネススクールを出たての若者が、コンピュータを駆使して事業、製品、市場について意思決定が行えるなどという考えはまやかしである。私がレントゲン写真と名づけたこのライフサイクル分析にしても、正しい答えを自動的に出すためのものではなく、正しい問いを知るための道具にすぎない。
・計画があって、はじめてイノベーションのための予算も立てられる。さらに重要なこととして、いかなる能力の人材がどれだけ必要となるかも明らかにできる。実績のある人材を配置し、必要な道具、資金、情報を与え、明確な期限を設けて、はじめて計画を立てたことになる。
・起業家的な企業では二つの会議を開く。一つは問題に集中する会議であり、もう一つは機会に集中する会議である。
・必要なことは測定ではなく判断である。判断といっても主観ではない。定量化できなくともよい。判断さえできれば、主観や推測ではなく知識にもとづいた行動が可能となる。
・イノベーションは小さく始め、大きく実を結ばせなければならない。しかしそのためには、そもそものはじめから、小さな特殊製品の開発や既存製品の若干の充実といったことではなく、大きな新事業を生むべきものとしてスタートさせなければならない。
・既存の企業がイノベーションを行なうことができるのは、市場や技術について卓越した能力をもつ分野においてのみである。新しいものは必ず問題に直面する。そのとき事業に通暁していなければならない。多角化は市場や技術について既存の事業との共通性がないかぎり、うまくいかない。
Posted by わくわくなひと at
20:10
│Comments(6)



