2011年08月21日
生きた野菜をいただく!「縁側カフェ」菅の伝統料理
 今日は仕事でほんのほんの少しだけお手伝いさせていただいている山都町菅地区に行ってきました。
今日は仕事でほんのほんの少しだけお手伝いさせていただいている山都町菅地区に行ってきました。「縁側カフェ」って聞いたことがありますか?
菅地区の農家の軒先や縁側で、あたたかいお茶とお茶うけを、のんびり、ゆったりといただける古里ならではのおもてなしです。
今日はあいにくの雨でした。菅地区に至る途中の山道では、ものすごい雨が降ってきました。山深い、そのまた奥座敷のようなところです。農林水産省の棚田百選にも選ばれた美しい棚田が広がる中、ここでの長い長い人々の営みを感じさせる家屋や神社などがポツン、ポツンと見えてくる。昔、中国の古典に書かれていた桃源郷とは、こんなところではなかったかと思うほどです。
この菅地区では「縁側カフェ」に続いて、里山レストランを開設するための準備が進められています。廃止された小学校跡の給食施設を活用して、レストランの目玉となる料理の研究が進められています。
今日はその試食会にご招待いただき、菅地区の食材を使った伝統料理を楽しませていただきました。
棚田の掛け干し米のにぎりめし、煮しめ、カボチャのサラダ・・・。野菜はすべて朝採り。何か食べ物が生きている感じがして、血液がきれいになっていくような気分になりました。その間、外は嵐のような雨が降ったかと思うと、そのうち薄明かりが差しこんできて、肌にほんの少し冷たさを感じる程度の心地よい風がゆったりと流れてきます。稲が長い波長のようにゆっくり、ゆったりと揺れています。緑のじゅうたんに囲まれた静かなたたずまいの家屋や神社、祠なども、空気が雨で洗われたためか、くっきりと見えてきます。やや遠くに見える幾重にもつならなる山々からは湯気のようなものが湧き、景色全体がゆっくりと動いているように見えてしまいます。
試食会に招かれた地元の方々、そして料理をつくってもてなすおばちゃんたち。だれもが屈託のない笑顔で穏やかな会話を繰り返しています。時間はゆっくり流れ、ある意味、長く過ごしたように感じました。
帰り道でふと思いました。菅地区の入り口にある鮎の瀬大橋は、桃源郷と現実世界を区別する関所ではないかと。それから山をいくつ越えたでしょうか。街に帰ってくると、ワープして現実に戻り、夢から覚めたような気分になってしまいました。


Posted by わくわくなひと at
20:24
│Comments(4)
2011年08月17日
月のポケットに入れられる自分 主体性とはつまらないものである
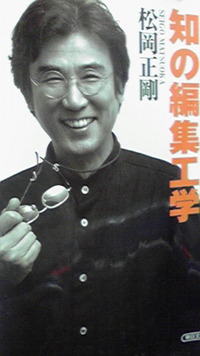 松岡正剛『知の編集工学 情報は、ひとりでいられない』朝日文庫(2005年12月20日第2刷、2001年3月1日第1刷)の282ページ。こんなことが書いてありました。
松岡正剛『知の編集工学 情報は、ひとりでいられない』朝日文庫(2005年12月20日第2刷、2001年3月1日第1刷)の282ページ。こんなことが書いてありました。私はかつて、「お月さまは自分をポケットに入れて歩いていた」という稲垣足穂の『一千一秒物語』からとった一文を、誰かれなく自慢げに御披露していたことがある。この一文はたいへん香ばしい自己言及をしているからだ。
むろん、こんなお月さまは、ありえない。ありえないにもかかわらず、この一文は、そんなお月さんがありそうな雰囲気を、つまりは編集的な現実感をもっている。私たちが、その「不飽和」なところをメタレベルで補っているからだ。そして、そこが<エディトリアリティ>を感じるところなのである。
私たちは、このお月さまの一文が醸し出してみせたような香ばしいメタゲームを、ときにはたのしむ必要がある。思考は、メタゲームに戻るべきどきがある。それは思考が香ばしい矛盾に浸るときである。それは、なんであれ、<エディトリアリティ>を私たちがほしくなるときなのだ。
それにしても主体性とはずいぶんつまらないものである。
いたずらに肩肘が張っているし、相手には優位に立たなくてはならず、もっと厄介なのは主語的な首尾一貫性にいつもびくびくしていなくてはならない。こんなことは子供の頃や初恋の頃からこっぴどく懲りているはずのことである。それなのに、ついつい整合的な自分づくりをさせられてきた。
私たちは葛藤や矛盾に満ちたものであり、自分の中に「あてどもないもの」や「まぎらわしいもの」をいっぱい抱えている存在である。しかしそれだけでは仕方がないために、いささか非論理的な「見当」と「適当」をうけいれてきたわけだ。
このことは、“対外的な私”という点から見ると、いかにも自己分裂的に見えてしまうことになりかねない。そこで、たいては慌てることになる。たいていは首尾一貫性をとりもどす方向に調整をする。社会や会社は、すぐにそのことを要求してくる。しかしそうではなく、もっと葛藤と矛盾と不飽和に満ちた「奥」の方へ進んでみたらどうなのか。メタゲームとは、その「奥」の領域で待っている「私自身のためのエディトリアル・ゲーム」のことなのである。
何かわかったようで分からない難しい文章ですが、何か感覚に訴えてきます。特に「いたずらに肩肘が張っているし、相手には優位に立たなくてはならず、もっと厄介なのは主語的な首尾一貫性にいつもびくびくしていなくてはならない。」。こんなオヤジはけっこう見かけますし、いつも格好ばかり気にして可愛そうとも思うことがあります。
これからはビジネスも論理的だけでは通用しないという予感がしています。非論理的な驚くべきアイデアが突然降りてくる!それが世の中をリードしていくような感じがしています。
Posted by わくわくなひと at
13:39
│Comments(0)
2011年08月15日
「バカ売れ」タイトルを見積書にも書き込む!
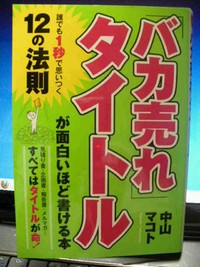 最近、凄いコピーの本がたくさん出回っています。そんな本の一つ『「話し方」「伝え方」ほど人生を左右する武器はない!』を買ったついでに、こんな本もついで買いしました。
最近、凄いコピーの本がたくさん出回っています。そんな本の一つ『「話し方」「伝え方」ほど人生を左右する武器はない!』を買ったついでに、こんな本もついで買いしました。中山マコト『「バカ売れ」タイトルが面白いほど書ける本』中経出版(2011年7月18日第1刷)です。
この作者はもともとマーケティング・リサーチャーから出発し、今では広告プランナー、販促プランナー、コピーライターとして活躍しているそうです。私の知り合いにも、コピーライターあがりのマーケティングプランナーがいますが、そのコピーにはけっこう“うなり”ます。一言ケチをつけるとすれば、マーケティングというなら、そもそも売れる商品づくりのプロセスにもっと突っ込んでもらいたいとは思っていますが・・・。
まあそれはともかく「バカ売れ」タイトルを書くための秘訣がわかりやすくまとめてある本でした。これを読んだからと言って、すぐ「バカ売れ」タイトルが書けるとは思いません。でも、この本に書いてあることを意識して試行錯誤していくと、たまには「バカ売れ」タイトルが書けるようになりそうな感じはしました(後、1週間もしないうちに秘訣は忘れてしまいそう)。
それよりも何よりも、この本でびっくりしたことが一つありました。見積書にも「バカ売れ」タイトルを書くことです。これは目からウロコです。
「特別袋とじ 勝負見積書を書くときに読むページ」というのも、ふざけてんだか知りませんが、面白かったですね。中山マコトさんのようになるためには、「読み手をワクワクさせようとか、ビックリさせよう」といつも思っているという心のメカニズムがぜったい必要だと思いました。
私も、けっこうイタズラ心を持っている方なので、相手次第ですが、いつかやってみます。行政とか固いところは、騒動になるかも知れません。
以下は中山さんの本から拾った事例です。
■リサーチ会社の見積「ツナ缶に関する調査、お見積り」
↓(修正)
■「御社のツナ缶、●●を1年以内にTOP3シェアに復活させる。そのための活動概算費用!」
■『日本一の食品会社社長から、「御社にお願いして本当に良かった」と言われた販促技法のご紹介』
■「一流市場調査会社の調査企画部長よりも調査に詳しいコピーライター」
■「完璧にリサーチを実施した上で、有効な販促プランとコピーをお出しします」
■『●●の市場実態に関して、7日以内に可能な「ご報告」と「結論」に関するお見積り』
■「売上V字回復のための、マナー講座実施費用」
■「この金額で、御社の経営課題がすべて明らかになります(コンサルティング費用)」
■「概算費用ですが、アクションプラン、デザインまですべて含まれています」
■「他社よりも高い」パンフレット印刷費用お見積り
■「クオリティを無視した安いだけの見積り」
■「中国市場で確実に失敗する方法」
■「絶対採用されない見積り」・・・仕事によっては、捨てることで手に入るものもあります。たとえば、無理に獲得しようとしないで、自分の考え方をしっかりと伝える。闇雲に安くして仕事を引っかけに行くよりも、多少高めであっても、考え方というか、ビジネススタンスをちゃんと伝えよう・・・そんな意図だったので、「採用されない」というコトバを使いました。
■「1円たりとも安くはできません」・・・「これ以上下げるくらいなら、受けないほうがいい!」という時の見積書
■「食べられないアイスクリームのご提案」・・・飲む感覚のアイスクリーム
■「まずいから売れる●●のご提案」・・・おいしいものだけが売れる時代ではなくなってきた。
■「●●の工事に関する、あいまいなお見積り」
■「●●の印刷に関する、あり得ない見積り」
■「●●のリサーチに関する見積り(誤差大)」
■「このくらいの予算でできるはず!基礎化粧品パッケージデザイン」
■「見積りとなっていますが、確定金額です!」
■「この価格でお受けします!●●印刷費」
■「●●についての見積り。他社との明確な違いが最低3カ所」
■「お客さまの声ではありません。お客さまの叫びです」
■「売上を一気に下げるご提案」・・・ふざけるな!と怒鳴られそうだが、中身を読みたくなる
■「イメージダウンを実現するための戦略のご提案」・・・同上
■「リピーターを削減するご提案」・・・同上
■「さ~、新機軸による新たな販促、初のご提案です」
■「発表!当社初の新発想をお届けします」
■「いよいよ、●●初!××を使った広告システムが誕生しました!」
■「新技術で御社の売上を劇的に上げるプロジェクト、お見積り」
■「新たなマーケットを掘り起こすためのDM作成費用お見積り」
■「ご紹介します!新商品開発のためのリサーチプロジェクトお見積り」
■「御社のお客さんは●●と言っています」
Posted by わくわくなひと at
19:09
│Comments(2)
2011年08月15日
相手の話を聞く!これが話上手の基本
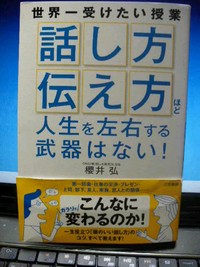 一昨日、TSUTAYAを覗いて、出来心で購入した一冊。櫻井弘『「話し方」「伝え方」ほど人生を左右する武器はない!』三笠書房(2011年2月15日第1刷)です。
一昨日、TSUTAYAを覗いて、出来心で購入した一冊。櫻井弘『「話し方」「伝え方」ほど人生を左右する武器はない!』三笠書房(2011年2月15日第1刷)です。TSUTAYAの店頭の一番目立つところに10冊以上平積みされていた本です。自分の周りにも「話し方」や「伝え方」を勉強したいと思っている人がいるし、こんなに平積みされているということが非常に気になりました。
2月15日第1刷?今は8月?本屋さんが売りたい本なのか?マージンが高いのか?委託ではなく買い取り?TSUTAYAと言えば日販系の本屋さん?いろいろ詮索しました。
「世界一受けたい授業」「こんなに ガラリと 変わるのか!」「この1冊だけで、あなたも、今すぐ、話し上手になれる!」・・・。
この本を手にとってもらうためのコピーがこれでもかというほど書き込んであります。本当に売れているのか?平積みは在庫一掃を狙っているのか?
1時間半もあればサラッと読める本です。最初から期待はしていませんでしたが、「今すぐ、話し上手になれる!」わけではありません。でも、『「話し方」「伝え方」ほど人生を左右する武器はない!』ことは「そうだろうな」と思いました。
・・・いいコミュニケーションができないのは、必ずしも「心の持ちよう」に問題があるのではなく、自分の口から最初に発せされる言葉が原因になっていることが多いからです。
これはどうかな?と思いました。コヴィーの7つの習慣とは違う。どちらが先かという話でしょうが、「心の持ちよう」に問題があると、最初はうまくいっても長いお付き合いや信頼を得られないじゃないかと。しゃべりがたいへんうまいけど、半年や一年くらい経つと、誰からも信頼されないキャラの人を知っているから、そう思うのか?
そんな信頼を得られない人に限って本人はしゃべりがうまいと勘違いしているようです。でも、この本を読んでいくと、こういう人は「話し方」「伝え方」の下手な人として扱ってあるようです。
こんな人の特徴として、「話が簡潔でない」「ネガティブな言葉をけっこう使っている」「人の話を聞かず、自分の話たいことだけ話している」「自分の話が終わると、人の話はおかまいなく隣の人と話をはじめる」などがあげられます。
会話の基本は、まず相手の話を「聞く」ことから始まります。
これには大賛成です。書いてあることに問題はないと思います。ただ、コピーが大げさ過ぎます。この本を読んでガラリとは変わりませんでした。ガラリと変わる人は、こういう本を読んで、話し方教室など他人から指摘を受けて訓練する、行動する人たちではないでしょうか。
この本は、客寄せのためのフレーズが凄すぎたので今ひとつ信頼できませんでしたが、それでも少しは役だったと思います。感謝です。
Posted by わくわくなひと at
17:23
│Comments(0)
2011年08月12日
視ること、それはもうなにかなのだ。―梶井基次郎
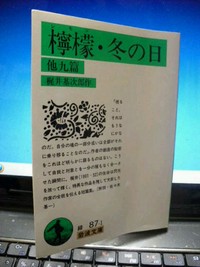 周期みたいなものがあって、論文とか思想とかのジャンルに近いものを読みたくなる時期があります。しばらくすると、今度は肩の力を抜いて柔らかい小説みたいな文章を無性に読みたくなるときがあります。
周期みたいなものがあって、論文とか思想とかのジャンルに近いものを読みたくなる時期があります。しばらくすると、今度は肩の力を抜いて柔らかい小説みたいな文章を無性に読みたくなるときがあります。今の気分は肩の力を抜いて少しずつ、「ちびり、ちびりやれる」小説がいいですね。しかも、多くの時間は割けないので短編、小池真理子の掌篇くらいの小説が今の自分に合っているかと思います。
梶井基次郎『檸檬・冬の日他九篇』岩波文庫(2009年5月25日第53刷、1954年4月25日第1刷)は、手のひらにのるくらいの掌篇を集めた文庫本です。53刷ですから、相当読まれている文庫本です。
それで「ちびり、ちびり」読んでいますが、メモしておきたい箇所に出会うことができました。今の自分は“聴く”“視る”など五感を糸口とした人の心の化学反応に興味があることに改めて気づきます。
「ある心の風景」より
川のこちら岸には高い欅(けやき)の樹が葉を茂らせている。喬は風に戦(そよ)いでいるその高い梢に心を惹かれた。やや暫らく凝視(みい)っているうちに、彼の心の裡(うち)のなにかがその梢に棲(とま)り、高い気流のなかで小さい葉と共に揺れ青い枝と共に撓(たわ)んでいるのが感じられた。
「ああこの気持」と喬は思った。「視ること、それはもうなにかなのだ。自分の魂の一部分あるいは全部がそれに乗り移ることなのだ」
喬はそんなことを思った。毎夜のように彼の坐る窓辺、その誘惑―病鬱や生活の苦渋が鎮められ、ある距りをおいて眺められるものとなる心の不思議が、此処の高い欅の梢にも感じられるのだった。
Posted by わくわくなひと at
21:41
│Comments(2)
2011年08月11日
子ども・初心者向け=くだいた本、やさしく書いた本ではない
 なだいなだ『心の底をのぞいたら』ちくま文庫(2006年5月10日第16刷、1992年1月22日第1刷)。一月前ほどに読んでいましたが、「そうか!なるほど」と思うことがたくさん書いてありました。
なだいなだ『心の底をのぞいたら』ちくま文庫(2006年5月10日第16刷、1992年1月22日第1刷)。一月前ほどに読んでいましたが、「そうか!なるほど」と思うことがたくさん書いてありました。この本はもともと1971年に筑摩書房が刊行した「ちくま少年図書館12」の内容を文庫本にしたということです。
「著者自身による解説」をみると、
『子供向けの入門書、それぐらいなら平凡な臨床医のぼくにも書けそうだと思って、気軽に引受けた。しかし、このシリーズの本が次々と出はじめると、ぼくは後悔した。松田道雄氏の「恋愛なんかやめておけ」や藤森栄一氏の「心の灯」といった作品の持つ衝撃力に、子供の本というものを安易に考えていたぼくは、突きとばされたような気分だった。そして、いわゆる「くだいた本」「やさしく書いた本」を書いてはなるまい、と思ったのである。
「心の底をのぞいたら」は、だから、心理学の入門書ではない。ぼくが、心理学をどういうものと思っているか、を書いた本である。心理学の入門書として読むなら、こんな不完全な本はない。また、こんなにもかたよった本はないだろう。・・・』
この考え方には同感します。若いころに、子供向けだから入門者向けだからといって短絡的に「くだいて、やさしく書きなさい」とよく言われてきました。そう言う人の書いた文章を読んで、文章は平易に書いてあるが何も伝わってこないと思うことが少なくなかったようです。
なだいなださんの文章を読んで大学の講義を思い出しました。決して教科書のように定説ばかりを語るのではなく、研究者が思い悩み発見したことを語る時のエネルギーと衝撃を思い出しました。
子どもにこそバランスはとれていないかも知れないけれど、仮説を立てたり発見したりする時のエネルギーと衝撃を伝えるべきではないかと思いました。
次のおばけの話は、妙に印象的でした。そう言われればそうだなと。
(40頁)
おばけの話が人間によって作られたのは、昔だ。しかし、昔といっても、それほど大昔のことではない。かなり文明が進んできてからだ。それは、おばけの着ている服装を見てもわかる。原始時代のおばけなんて話は、あまり聞かない。はだかの女のおばけが出て、それが毛皮のこし巻きをしていたなんていわれても、あんまりこわくない。その時代には、人間がおばけを考えださなかったのだろう。「聖書」にも、おばけの話はないようだし、ギリシャ時代の本にも、怪物の話はあっても、おばけの話はない。そして、怪物もただこわがられることはなく、人間がたたかって勝ったり負けたりしている。
おばけらしいおばけが出てくるのは、中世になってからのようだ。宗教が、死んだあとの人間の生活を教え、いま自分の生きている世の中での道徳を、死んでからのちの生活のためにたいせつにするように教えたことと、おばけとは関係があるにちがいない。おばけの話は、よく聞くと、とても道徳的で、お説教くさい。おばけは、死んだものが復讐することで、正義を教えるようになっていたり、死者に対する儀礼をおもんじさせる意味があったりする。
後は、個人的な備忘録です。
(18頁)
・・・意志の強さや弱さを測るものさしはない。意志のかたさや、やわらかさを調べる機械があるわけではない。人間のやっていることや態度を見ていると、ただ、そんな感じがしてくるのだ。だから、お酒がやめられないでいる人を見ると「あの人は意志は弱い」という。そして、その人が、ある日から、ぷっつりとお酒を飲まなくなると、「あの人は、あんなに好きだったお酒をやめるなんて、たいへんに意志の強い人だ」という。意志が、ほんとうに、強かったり、弱かったりするものだったら、何十年も弱かったものが、一日で手品みたいに強くなるはずはない。木が鉄に変わるような、手品みたいなことが起こることはない。強い、弱いは、たとえで、その人の与える感じを説明することばであるだけだ。
(55頁)
・・・あるものは、人間は努力しだいで成功すると信じている。そう信じることで、安心している。
君は、それをどう思う。これは、ある意味ではいいことだ。人間は信じることで安心できるし、よい行動をするように仕向けられる。しかし、つごうの悪い面も持っていると、ぼくは思う。正直者はけっして不幸にならないと信じているものは、不幸になった人間は、不正直だと思うことになるからだ。人間は努力しだいで、かならず成功すると思っている人間は、失敗して苦しんでいる不幸な人間を、みんな努力のたりないなまけものだと、きめてしまう。こうした考えが、この世の中の不幸な人たちを罪のない、ただ運の悪いだけの人たちとして、みんなで助けて平和な世界を作ろうとするのを邪魔するのである。
Posted by わくわくなひと at
16:54
│Comments(0)
2011年08月10日
とちゅうで おべんとうを 3かい たべるくらい とおいところ
 今日は熊本市黒髪の「トトハウス(Thoth House)」さんに行ってきました。
今日は熊本市黒髪の「トトハウス(Thoth House)」さんに行ってきました。お名前を聞いただけでは何屋さんか分かりませんが、まちづくりやワークショップの専門家さんです。
1時間ほどおじゃましてお話しをして、お土産をいただきました。
何と絵本『ちゃいろにわとりのちゃーぼう』(さく:まえだよしお え:ひらかわきみえ、トトハウス、2006年11月6日第1刷発行)をいただきました。
話しの舞台は阿蘇郡西原村の俵山近くの前田邸周辺。そこで飼われているニワトリの小さな冒険物語です。
作者の前田さんのお話を聞くと、実に子どもの思いにせまった物語です。子どもがにわとりのちゃーぼうになりきって物語に入っていけるように工夫されています。それと、驚くほどセリフが真に迫っていると思いました。固くなった大人の言葉ではない新鮮さがありますし、スゥッと心に入ってくるセリフです。
ちゃーぼうが「とちゅうで おべんとうを 3かい たべるくらい とおいところ」に冒険に行こうとします。
凄い表現だと思いませんか。作者の前田さんが実際に子どもの会話からひろった素直で飾り気がなく腹の底から伝わってくる言葉です。
これはお年寄りの言葉ですが、これに近い表現を作者が耳にして童話の中のセリフにしたそうです。
「としをとったら、はげぼう だろうが、しわくちゃだろうが、そんなことは どうでもいい。あしさえ たっしゃなら それで じゅうぶん。わかい うちから どんどん あるけ。」
童話や絵本のもう一つの楽しみ方があることを初めて知りました。それは作者の話を聞いて、もう一度、絵本を開いてみることです。大人になると、こういった手続が必要なくらい、心の中が曇りガラスになっていることにも気づきました。
この絵本の問い合わせは、トトハウスさんにどうぞ!
〒860-0862 熊本市黒髪5丁目4-45
℡:096-341-1231
http://thothhouse.com/modules/tinyd0/
Posted by わくわくなひと at
19:31
│Comments(0)
2011年08月07日
つながろうとする言葉 奇妙な「力」 情報連鎖の感覚
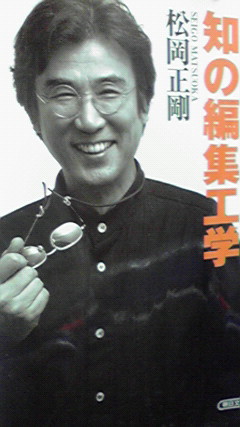 Facebookの凄さに驚いています。今までは仕事つながりの会話がほとんどでした。ところが、facebookに登録してみたら、昔、夜を徹して話していた友達とつながったり、コンピューターが未だ太刀打ちできないリサーチ分野の話しで盛り上がったり、知り合うことやつながることはまずなかったろうと思われる人たち、それも夕立の範囲くらい狭いけれど同じ空の下で暮らしている人たちと話す機会ができたり・・・。環境やネットワークが激変しそうです(仕事が疎かにならない程度に)。と言いながらも、今、facebookでつながっている人たちは、氷山の一角くらいでしょうか。氷の海から浮かんできた人たちだけが盛んにやりとりしている。そんな印象を持っています。ネットにつながって情報発信していない人は数十倍くらいいるかと思います。恐らく今、表に出てきている人は私のような中小零細企業の経営者や自営業など自由というか自己責任で情報発信ができる人に限られている。それか組織の掟などは関係ない実力のあるスーパー勤め人たちがほとんどだと思います。
Facebookの凄さに驚いています。今までは仕事つながりの会話がほとんどでした。ところが、facebookに登録してみたら、昔、夜を徹して話していた友達とつながったり、コンピューターが未だ太刀打ちできないリサーチ分野の話しで盛り上がったり、知り合うことやつながることはまずなかったろうと思われる人たち、それも夕立の範囲くらい狭いけれど同じ空の下で暮らしている人たちと話す機会ができたり・・・。環境やネットワークが激変しそうです(仕事が疎かにならない程度に)。と言いながらも、今、facebookでつながっている人たちは、氷山の一角くらいでしょうか。氷の海から浮かんできた人たちだけが盛んにやりとりしている。そんな印象を持っています。ネットにつながって情報発信していない人は数十倍くらいいるかと思います。恐らく今、表に出てきている人は私のような中小零細企業の経営者や自営業など自由というか自己責任で情報発信ができる人に限られている。それか組織の掟などは関係ない実力のあるスーパー勤め人たちがほとんどだと思います。つい最近までコンピューターやITと言えば、機器などのハードの世界でした(もの自体のオタク的な世界は嫌いじゃありません)。もともとそれはおかしいと思っていました。今はまさに一人ひとりが持つ情報のやりとりやコミュニケーションが主役になってきたと実感しつつあります。機器やシステムなどのハード先行の一輪車走行だった情報社会が、これまでの歴史が示すように人同士の交流という車輪が加わり、いわゆる文化を形成できる二輪車走行になってきたような感じです。
そんな中で、松岡正剛『知の編集工学 情報は、ひとりでいられない』朝日文庫(2005年12月20日第2刷、2001年3月1日第1刷)の三分の二を読みました。2001年に書かれた文章ですが、情報というものについて考え抜いた内容であり、やっと時代が松岡正剛に追いついてきたという感じがしました。セイゴーさんは、こう言ってます。
「私は、明日の日本には、これまでの真似事とはまったく別のパラダイムを導入するしかないとおもっている。そのパラダイムは、まず<情報化>と<編集化>を切り離さないこと、すなわちハードとソフトを切り離さないこと、ついでは経済と文化を切り離さないこと決めてかかることである。
経済と文化が歩みより、そこに<情報文化技術>という新しい展望が萌芽するときに、そしてそれが漂流しはじめるときに、初めてIT社会の「華」と「悪」が同時に姿をあらわすのではないかと考えたい。」
それと、以下の文章は驚くべき視点だと思いました。セイゴーさんの意図とは違うかも知れませんが、事業計画や人生設計と言えば「あなたの強みを生かせ」と言われ続けてきました。しかし、こんな処し方もありそうだし何か豊かさを感じてしまいます。
弱さを起点に考えてみたい
たんに弱者に気配りしようというものではない。それもあるけれど、むしろ自分の強さのレベルで相手に向かうのではなく、自分の弱さのレベルで対象と柔らかく接することが、かえって情報交換をなめらかにするということなのである。やたらに強がっているだけでは本当の情報はやってこない。「強がり」はたんに情報システムを強靱な“物理”にするだけである。
・・・
私たちの脳や精神(心)はもともとノンリニアである。どこにも立派な「論理」など宿ってはいやしない。論理は外にかっこよく取り出して見せるときの好都合な言説上の武装というものだから、論理はリニアを好んできた。
けれども、そうやって取り出した論理が、仮にもほんとうに論理だというのなら、それはそれでまた、もはや編集不可能なものなのだ。つまり、それはそこで一巻の終わりになってしまっているものだ。私は、そのような剛直な論理をいまさらソフトウェアにつかおうとはおもわない。コミュニケーションにつかう気もおこらない。
→鎧を捨てて自分の弱さのレベルで対象と柔らかく接する、コミュニケーションするという解釈でよろしいか?
・・・
編集は勝利や結果や無矛盾を求めない。編集は葛藤や弱点や矛盾を新たな展望に変換するためのものである。なぜ、そんなふうに言えるのか。編集は「弱さ」を起点に逆上するものであるからであり、しかも、「弱さ」は「強さ」の欠如ではないからだ。
これは来るべき<自発性の社会>ともいうべきものが、ひょっとして私たちの身近にまで到来していることを告げているのかもしれない。ただ、方法がまだ見つかっていないだけなのである。
それとこれにも驚きました。今、自分がときどきやっているエクササイズと同じことをセイゴーさんが2001年ごろやっていたのです。
いままさに自分のアタマの中で動いている編集プロセスをリアルタイムで観察しようというエクササイズである。すなわち、自分のおもいが流れているままに、そのプロセスを同時に観察するということだ。次々に進む「注意」の移ろいを観察しようというのである。
・・・
大事なことは自分自身をそうとうにゆるませるということ、フラジャイルな自由編集状態にしていくということである。ともかく思考したりしていては、もう遅い。発想をしても遅れてしまう。ただ五感を開くしかない。けれども、ボーッとしていてもダメだし、メディテーションに入ってしまうようではダメなのだ。
もう一つ。これはセイゴーさんの試みより早い1980年代からグループ(ダイナミック)インタビューの要約筆記で使われている方法です。
五、六人でミーティングをしているときがいいだろう。
各自の発言から喚起されたモノやコトを連続的にトレースしつづけるというエクササイズだから、ノートやノートパソコンには絶対に頼らないようにする。ノートやキーボードではとうていまにあわない。
ただし、やみくもに臨んでも見当がつきにくいから、いったんミーティングのビデオを撮って、それを眺めながら各自の発言をトレースしつつ、アタマに浮かぶことを同時に加えていくとよい。こうすると、どこで何が加わりどこで何が編集されていくか、だいたい見当がつく。
後は備忘録です。ここ4、5年くらい脳科学の本で書かれていることを2001年の段階でセイゴーさんは書いていたんですね。
ひとつの言葉は別の何かの言葉につながろうとしている
『ひとつの言葉はつねに別の何かの言葉とつながろうとしている。「きっと」という言葉はいつまでも「きっと」だけでいられることは少なく、ついつい「きっと会おうね」とか「きっと晴れだよね」というふうに結びつく。・・・』
何かハッとする文章です。「言葉というもの、けっこうぐらぐらとしていて、単独でいることはできないのである。不安定なのだ。何かと化合したがっているようなのだ。だから連想ゲームが成立しうるのだ。」。
自分のアタマの中と相手の言葉とのアクロバティックな連携 奇妙な「力」 情報連鎖の感覚
『ともかく私たちは、そのような情報連鎖の感覚をつかって、自分のアタマの中と相手の言葉とのアクロバティックな連携をなんとなく編集しながら、「リンゴ」がいつしか「桃太郎」になるというこの顛末を、連想ゲームとしてたのしんでいる。私が注目したいのは、その奇妙な「力」である。そして、この情報連鎖の感覚をいささか自覚的に再活用することが、これから少しずつ説明する<編集技術>というものになっていく。』
・・・このことは一部の企業ですが、商品コンセプトを開発しているプロセスで情報連鎖の感覚(AHA感覚)をいささか自覚的に再活用するようになってきています。そして、一部の企業が再活用している場面では、「アマタの中の情報回路そのものを加速するパイディア※1とルドゥス※2・・」を体感しながら仕事が続けられています。
※1)即興的興奮
※2) 無償の困難に向かっていきたいという態度
口をとじる山口百恵 歯をむく松田聖子・・・情報は行先をもっている
『さらにはゲーム(連想ゲーム)を観察してみると、ひとつの言葉がもうひとつの言葉を相手にして「一対の関係」に入るということに、言葉というものの本来の動向が見えてくる。たとえば「口をとじる山口百恵」という言葉が浮かべば、ふと「歯をむく松田聖子」という言葉もくっついてくる。すなわち、Aの情報はもうひとつ別の片割れのBの情報を求めて、その方向に向かって遊びたがっているように見えるのである。
情報が情報を呼ぶ。
情報は情報を誘導する。
このことは本書がたいそう重視していることだ。「情報は孤立していない」、あるいは「情報はひとりでいられない」ともいえるだろう。また、「情報は行先をもっている」というように考えてもよいかもしれない。
情報が情報を誘導するということは、その誘導にはおそらく柔らかい道筋のようなものがあるかもしれないということである。また情報に行先があるのなら、その行先をうまく予測しさえすれば、あらかじめ単語や概念のネットワークをつくっておくこともできるということだ。』
・・・「情報は行先をもっている」。凄い仮説です。将来のデータベース構築の基本原理みたいな話しですね。しかし、人間の頭は「0」か「1」だけではなく思考は直線的に進まない。非線形のアルゴリズム?というのでしょうか。それが奇妙な「力」、情報連鎖の感覚というのでしょうか。
考えるということの正体
『脳の中は、知識やイメージを無数の「図」のリンクを張りめぐらしているハイパーリンクなのである。これを<意味単位のネットワーク>とよぶことにする。コップはひとつの意味単位であり、ガラス製品もひとつの意味単位である。それが次々につながり、ネットワークをつくっている。けれども、そのネットワークは一層的ではない。多層的(マルチレイヤー的)で、立体的である。・・・
このような<意味単位のネットワーク>を進むことを、私たちはごく一般的に「考える」と言っている。「考える」とは、ひとまずネットワークの中の「図」のリンクをたどってみるということなのだ。ただし、ここでひとつ重大な問題が出てくる。それは、ネットワークを進むにしても、どの道筋を進むかということである。つまりどこで分岐するかということだ。それによって千差万別の考え方になってしまう。そこで、ある道筋を進んだとして、そこで「あっ、これはちがうぞ」とおもって、ひとつ手前の分岐点に引き返すということがおこることになる。もっと以前の分岐点にまで戻ることもある。何度も引き返しはおこることだろう。
このジグザグした進行が、「考える」ということの正体なのだ。それが<ハイパーリンク状態>である。思想とは、畢竟、そのジグザグした進行の航跡のことにほかならない。』
Posted by わくわくなひと at
21:34
│Comments(2)
2011年08月03日
「おい、神様に祈ったか?」稲盛和夫さんの金言
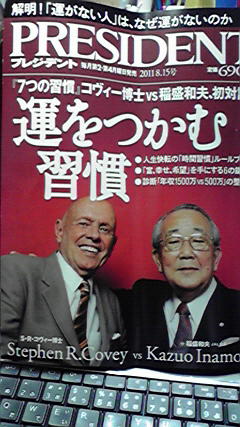 触覚というのか?関心がある情報は何となく目に飛び込んでくるものです。
触覚というのか?関心がある情報は何となく目に飛び込んでくるものです。先週末、福岡空港の売店で目に入ったのが「プレジデント」2011年8.15号です。
「『7つの習慣』コヴィー博士VS稲盛和夫、初対談!」というタイトルに目がとまりました。
飛行機の中で読むのにちょうどよい。たとえ居眠りしても、大丈夫そうだから、即刻購入しました。
『7つの習慣』のポイントとなるところの解説もちゃっかりいただきました。心と体に刻みつけるのに手ごろな量です。それと同時にJALをV字回復させた稲盛和夫さんの名言もたくさん書いてあったので、本当、得した気分になりました。
以下、稲盛さん語録です(独断でピックアップ)。
動機善なりや、私心なかりしか。
あまりのひたむきさに神様が哀れに思い、かわいそうだから注文をあげよう、と思われるくらい努力するしかない。
おい、神様に祈ったか?
※ある晩、セラミック製品の焼成炉の前で、呆然と立ち尽くしている技術者を、稲盛を見つける。その技術者は「万策尽きました」と泣いていた。そのとき、稲盛は思わず「おい、神様に祈ったか?」と声をかけたのだ。稲盛が言いたかったことは、神に祈るほど最後の最後まで努力したのか、ということだった。
魂をエンカレッジしないと、人間はどんどん利己的に動いていってしまう。
悩んで悩んで、苦しんで苦しんでいくときに、「ひらめき」言い換えれば「天の啓示」がある。
不可能を可能に変えるには、まず「狂」がつくほど強く思い、実現を信じて前向きに努力を重ねていくこと。
Posted by わくわくなひと at
13:03
│Comments(5)
2011年08月02日
人生の原則を本気で刻みつけるための『7つの習慣』
 スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』を読み始めました。まだ200頁そこそこですが、さすが全世界で2000万部という怪物本だけあって、けっこう衝撃を受けました。
スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』を読み始めました。まだ200頁そこそこですが、さすが全世界で2000万部という怪物本だけあって、けっこう衝撃を受けました。自分がここ数年追い求めていた課題に対する解決法が書いてありました。
何を追い求めていたかというと、けっこういろんな本を読みます。すると、「ぜひものにしたい」「頭や体に刻みつけたい」と思います。ところが数日も経つと、何のことだったか、すっかり忘れてしまうし、体も憶えていません。
人はどうしているのか?気になりましたので、読書会なんかで人の言葉とその後の動きなどを観察していました。けっこう偉そうなことを言っているが、その人が言葉通り実践しているかというと、そうでもなさそう。特に、その人が慌てた時などをつい見てしまうようなこともあり、見苦しいと思ったりしたこともありました。
この『7つの習慣』には体に刻みつける方法や考え方が書いてありました。自信はありませんでしたが、自分で自分をだますつもりでやっている方法が間違いではないことが書いてありました。つまり、本気で本や教えを身につけたいと思ったら、みんなやることなんですね。
何のことかというと、そうしたいと思ったことや自分への戒めを、いつも目に入る壁に貼っておくやり方です。
今、福岡の事務所に貼っているのは、「決意からすべては始まる」「『できない』では『できない』」「成功するまで続けて成功」というはがきです。今、このブログは熊本で書いていますが、全部、ちゅうに憶えています。
昔、経営戦略の授業で、こんな指摘があっていたことを思い出しました。
よく日本の会社の社長室に行くと、「和」とか「誠」とかの額縁が掛けてある。これが何の意味があるのか?これで売上や利益がとれるのか?これで社員がついていくのか?ダメですね。もっと具体的な目標やビジョンを描かないと・・・
当時の私は、「そうかもしれん」と思いながらも、それではと、模範解答として示された外国企業のミッションステートメントを見ても、何か心動かされるものはありませんでした。
それで『7つの習慣』を読むと、人の生き方に関わる原則が大事だと書いてあります。バカにされたはずの日本の社長さんは、たぶんご自分の経験から生き方の原則を壁に掛けられていたはずです。大学教授と名もない中小企業の社長さんと、どちらが経営や人生の生き方をよく理解されているか。中小企業の社長さんに1票ですね。
もう一つ。『7つの習慣』を読んで頭に浮かんだ人生の原則があります。
それは高校の時に教壇の中央に掲げてあった校訓です。この校訓は、けっこう厳しい時や決断の局面で頭をよぎります。別に憶えようと思って憶えてわけではありませんし、高校生の時は意味も何となくという感じでしたが、憶えているのです。明治の人たちが若い人たちに向けて人生で大事なことを教えてくれていたのです。
正倫理 明大義(倫理を正し、大義を明らかにす)
重廉恥 振元気(廉恥を重んじ、元気を振るう)
磨知識 進文明(知識を磨き、文明を進む)
これは、『7つの習慣』に書いてあった生き方の原則です。それがチンケな私の会社の意思決定にも役立っているのです。
「信頼という土台がなければ、永続的に成功することはあり得ない」とも『7つの習慣』に書いてあります。この校訓に書いてあることは、信頼という土台をつくるための生き方の原則であることを改めて理解したという気分です。
それと「第一の習慣」に書いてある「自己責任の原則」。「問題は自分の外にあると考えるならば、その考えこそが問題である。」。「人生の責任を引き受ける」。
このことは、会社を起業する時に、周りの先輩(刑事OB)から徹底して教え込まれた記憶があります。「決してだれかの責任にしてはいけない」「環境や景気のせいにしてはならない」「人から悪口を言われても、決してその人の悪口を言ってはならない」・・・。
今から思えば、これが経営者の第一原則だったわけで、先輩はそれを渾身のエネルギーで私に伝えていただきました。
心底から正直に「今の状況はこれまで私が行ってきた選択の結果だ」。まだ心底思っているか不安ですが、いろんな場面で、この言葉は浮かぶようになっています。
その分、サラリーマンの時と比べて、体と時間は別にして心は自由です。
ところで、コヴィーさんの写真を見て、ひょっとして宇宙人?と正直思いました。私は正直者でしょうか。宇宙から懲罰を与えられるかも知れません。
Posted by わくわくなひと at
22:42
│Comments(3)
2011年08月02日
ギョッ!本という怪物に囲まれる「丸善・丸松本舗」
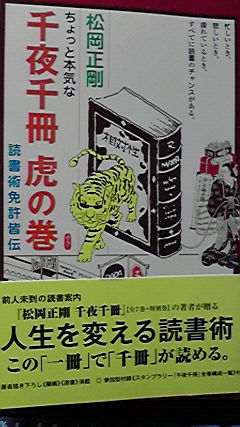 先週末、東京駅の近くにある「丸善 松丸本舗」に行ってきました。
先週末、東京駅の近くにある「丸善 松丸本舗」に行ってきました。実は昼食をとりながらの打合せでしたが、私のわがままで「丸松本舗」のあるビルの地階での喫茶にしてもらいました。
今、東京へ出向いた時の楽しみは、松岡正剛さんが入れ込んだ何万冊という本が売ってある「丸松本舗」に行くことです。
つまり、本はどんな情報も知識も食べ尽くす貪欲な怪物であり、どんな出来事も意外性も入れられる無限の容器であり、どんな遠い場所にも連れていってくれる魔法の絨毯なのです。(松岡正剛『ちょっと本気な 千夜千冊 虎の巻 読書術免許皆伝』18頁)
ただ今回は不用意でした。本という怪物を前にして、どう対処していいか分からない。何万冊という積み重ねられた本を見るだけで、何万という著者の得たいの知れないエネルギーを感じてしまいます。
そこには日常生活で感じる「ごまかし」「その場つくろい」「かっこつけ」「封建社会的な上下関係」などは存在しない。こういったことを題材にした本はあっても、著者が正面から真、善、美に対して格闘した存在感を肌で感じるものばかりです。
読書では、このように著者の異様な目に出会うことがとても大事なんです。そこでギョッとしたい。わかったふりをするのが一番つまらない読書法。読書はね、脱帽したり、投げとばされるのがいいんです。いや、読書で傷ついたほうが、世の中で他人に傷つけられたり、他人を傷つけたりしないかもしれない。(同36頁)
これは同感します。本を読んで「ギョッとしたい」「脱帽したい」「投げ飛ばされたい」。そう思います。だれかの著作を読んで「わかったふり」をしたり、「俺が一番知っている」という方にたま~にお会いしますが、「そう簡単に人や著者のことがわかるかなぁ?」と常々思ってきました。
「この本にこう書いてあることはこう解釈すべき」という話しは面白くありません(法学系ではないからか?)。そんなことはどうでもよくて、その文章を読んで自分の頭に浮かんできたこと、連想したことに興味がありますので、努めて本の端に書き留めるようにしています。
「エッ」とか驚きがあり、連想や妄想を楽しめるから、本はやめられまへん。
Posted by わくわくなひと at
14:23
│Comments(2)



