2010年12月29日
九州新幹線 博多-熊本3000円への報道と反応
 ついに決まりました!
ついに決まりました!九州新幹線博多-熊本間は、ネットの早期予約「早特」で3,000円也。駅などで買える2枚切符は3,500円と発表されていましたが、ネット予約であれば割引率は何と40%!3,000円で乗れるそうです。
昨日28日付け西日本新聞の福岡都市圏版は1面トップ。同日付けの熊本日日新聞も1面に載っていました。
そこで気になってくるのが、「ネット予約」の詳細です。このあたりは新聞を読み比べると面白いですね。想像ですが、記者発表の内容をまとめていくと、どうしても発表者側の視点や情報が多くなっていきます。そこですっぽり抜けがちなのが、実際に新幹線を利用する人のための具体的な情報です。
新聞各社の記事を読んでみて、利用者が実際に行動する時を想定した記事を載せていたのは西日本新聞でした。以下の一文です。
・・・最安値は、インターネットを利用した乗車3日前までの早期予約割引「九州ネット早特」(指定席)で、博多-熊本は片道3千円(割引率40%)・・・
・・・ネット予約は、同社ホームページで会員登録が必要。片道分から購入できる。予約時にクレジットカードで決済し、駅販売機で発券する。九州内のネット割引は、JR九州のクレジットカード会員に限定しない。
・・・ネット予約は同3月5日から受け付ける。
それと30面では、“3,000円”に対する人々の反応を丹念にひろってありました。
全日空、日本エアコミューター、南国交通、西日本鉄道、九州産業交通グループ、JTB九州、旅行雑誌「九州じゃらん」、鹿児島市民2人、鳥栖市の会社員、熊本市の整備士、筑後市の陶芸家、久留米市民、熊本市の主婦、鹿児島県内に実家がある福岡市の大学生
「バスや在来線に比べると「高い」という声も少なくない」という一般的な市民の反応もまとめてありました。これらの反応は、まだ九州新幹線博多-熊本間を経験していない人々の声としてインプットしましょう。
個人的な感想と予想です。
片道3,000円なら相当な需要を喚起できる。開業直後は「一度は乗ってみたい」と思う人たちがかなり利用する。それが一巡した後、どんなことが起きるか。博多-熊本が30分という利便性を一度体験してしまうと、高速バスの1時間半から2時間が苦痛に感じてしまう。そんな人たちがかなり出てきて高速バスから新幹線にシフトしていく。
この利用者の心の変化は東北新幹線などでも起こっていると、東京のシンクタンクの人から教えていただきました。ただ、そのような利用者の心の変化を誘うには熊本駅へのアクセスがよくないことが障壁となるかも知れません。同市東部地区と熊本駅は余りにも離れ過ぎています。高速輸送機関があれば、そうでもない距離ですが・・・。福岡都市圏は博多駅へ高速で大量の人々を運ぶインフラが出来上がっています。
そうは言っても、企業の交通費に関わる意思決定は、消費者よりも、もう少し時間がかかるような気がしています。
Posted by わくわくなひと at
15:43
│Comments(3)
2010年12月26日
面白小説が生き方を教えてくれる・・・児玉清さん
 12月5日、福岡県読書推進大会を兼ねた2010国民読書年の記念イベント「読書まつり」が福岡市天神のエルガーラホールで開催されました。その模様が今日26日付けの西日本新聞に載っていました。
12月5日、福岡県読書推進大会を兼ねた2010国民読書年の記念イベント「読書まつり」が福岡市天神のエルガーラホールで開催されました。その模様が今日26日付けの西日本新聞に載っていました。このイベントの中で、読書家として知られる俳優・児玉清さんの記念講演の要約がまとめられていました。
生で聞きたかったです。感動したかも知れません。今年を締めくくるのにふさわしい話が載っていました。
以前、このブログで紹介した河野多惠子『小説の秘密をめぐる十二章』文春文庫(2005年10月10日第1刷)で、「私は文学作品から、人生の指針や教唆を与えられたことは一度もない。」と書いてありました。しかし、これは創作者、小説家と言える人の言葉で、そうは言われても人生の指針や教唆を求めて小説を読み始める人は多いと思います。それも人生の指針を求めて読み始めて、夢中になり、「読んでいる間の歓びに加えて、読み終えた時の醍醐味がまた格別である。」を味わうのではないでしょうか。つまるところ書き手側からと読む側からと少し視点は異なるようだけど、本質の部分は同じことを言っているような気がしました。字面ではなく脳の奥深いところで、そんな感想が浮かんできました。
読書家としての児玉清さんのお考えは、以下の通りです。
C・Sフォレスターの海洋冒険小説、アリステア・マクリーンの戦争物などに夢中になりました。さらにケン・フォレットは、あらゆる階層の人物・風俗を詳細に描き出します。彼らイギリスの作家の面白小説は、不撓不屈の精神に満ちています。思うように演技ができず、荒れる気持ちを治めようのないときに本を開くと、たちどころに面白小説の中に引き込まれました。そこにはあらゆる冒険が待っていて、人生に対する勇気を得られるのです。
人間の生き方は誰が教えてくれるのか―私は面白小説、つまりフィクションだと思います。絶望があれば希望があるように、フィクションという仮想世界があるからこそ、現実の世界を見極められます。さらに面白小説は、世間のあらゆるものを取り上げ、さまざまな人間を描いています。人生は本の数だけある。本の中で人生を繰り返すことで、生きるとはどういうことか教えてくれるのです。
<参考>
■小説は人生の指針ではない(河野多惠子『小説の秘密をめぐる十二章』文春文庫)
いかに生きるべきかを人は小説に求める、という見方がある。作者もまた、いかに生きるべきかの追求のために書く、とも考えられているようである。実際、「いかに生きるべきか」や「この人を見よ」の姿勢の強い小説も珍しくないのだが、私はその種のものからは、人生の狭さ、人間というものの矮小さを感じさせられるだけである。
私は文学作品から、人生の指針や教唆を与えられたことは一度もない。もともと、期待したこともない。また、昔の若い人たちは教養のために文学を読んだが、今は教養のためには読まなくなった、とか。しかし、私は昔の若い人だったけれども、教養のために文学を読むことなど考えもしなかった。おもしろいからこそ読み、今もそうである。
おもしろい作品は、読んでいる間の歓びに加えて、読み終えた時の醍醐味がまた格別である。その作品の内容が、仮りに事柄上は荒々しくても、あるいは主人公の自殺をもって締めくくられていようと、人間というもの、自然を含めて此の世というものが、これほど深い味わいのあるものだったのかと、人間とこの世というものが、その作品を読むまえよりも新鮮さを帯びて感じされてくる。自分がこの世に在り、人間のひとりであることに、歓びと感謝の思いを惹き起こされる時さえある。一言でいえば、私はそのようなものこそ、よい作品であると思っている。
Posted by わくわくなひと at
14:01
│Comments(2)
2010年12月24日
熊日報道!片道3500円 新幹線・熊本-博多
 熊日新聞1面トップでした。西日本新聞3面にも載っていましたが、熊日さんの方が具体的な料金が書いていました。よく分かりませんが、JR九州さんに食い下がって具体的な料金を聞いた結果でしょうか?
熊日新聞1面トップでした。西日本新聞3面にも載っていましたが、熊日さんの方が具体的な料金が書いていました。よく分かりませんが、JR九州さんに食い下がって具体的な料金を聞いた結果でしょうか?今、在来線にある4枚切符、博多―熊本1枚当たり2000円の新幹線バージョンはあるのでしょうか?
取材合戦頑張ってください。
(熊本日日新聞)
来年3月に全線開業する九州新幹線鹿児島ルート熊本-博多の割引料金で、JR九州(福岡市)が2枚組切符を7000円(自由席)で販売することが23日、分かった。片道3500円と、正規料金4480円から22%の割引率となる。2枚組切符は熊本-博多で最も利用が見込まれており、高速バスに対抗して価格競争力を強化する。
(西日本新聞)
・・・博多―熊本は、自由席利用で「2割近く引く」と述べた。・・・博多―熊本は、自由席利用で正規料金が4480円。2割引きだと3580円となる。唐池社長は具体的な金額が明言しなかった。
Posted by わくわくなひと at
11:49
│Comments(5)
2010年12月21日
BHAG―組織を動かす大胆な目標「ビジョナリーカンパニー」
 ジェームズ・C・コリンズ/ジェリー・I・ポラス『ビジョナリーカンパニー 時代を超える生存の法則』の第四章と第五章から。
ジェームズ・C・コリンズ/ジェリー・I・ポラス『ビジョナリーカンパニー 時代を超える生存の法則』の第四章と第五章から。自分の力だけでなく組織で夢を追求するための仕掛け、BHAG(ビーハグ、Big Hairy Audacious Goals)という考え方は実に面白く必要だと思います。
以下は、個人的に特に記録しておきたい内容。
「第四章 基本理念を維持し、進歩を促す」から
・ビジョナリーカンパニーの基本理念は、進歩への飽くなき意欲と密接に関係している。進歩への意欲は、基本理念以外のすべての分野で、変化と前進を強く促す。進歩しようとする意欲は、探求し、創造し、発見し、達成し、変化し、向上しようとする人間の奥深い衝動から生まれる。
・新しいアイデアを「不可能だ」という理由でつぶしてはならない。われわれの仕事は、研究と実験を永遠に続け、研究の成果をできるかぎり早く製品に活かし、航空と航空機の新技術が当社と無関係に開発されていくことが決してないようにすることである。(ボーイング)
・基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みを整えることの大切さだ。
「第五章 社運を賭けた大胆な目標」から
・BHAG(ビーハグ、Big Hairy Audacious Goals)―進歩を促す強力な仕組み
・月旅行がそうであるように、本物のBHAGは明確で説得力があり、集団の力を結集するものになる。
・目標は鮮明であり、登るべき山がはっきりしていて、だれにとってもわくわくさせられるもの―BHAG
・BHAGは単なる目標ではない。社運を賭けた大胆な目標なのだ。「会社の資源をすべてつぎ込んでも、必ず完成させる」(ボーイング747)。BHAGと呼べるのは、その目標を達成する決意がきわめて固い場合だけである。
・企業がきわめて未来志向の動きをとるのは、収益性を最大限に高めること以外の点に事業の究極的な目標があると見ているときなのである。
・起業家のほとんどにとって、BHAGは事業に必ずついて回るものである。事業を立ち上げ、生き残れることだけは確かだと思えるところに達するだけでも、創業間もない企業のほとんどにとって、大変なことだからである。
・「インターナショナル・ビジネス・マシンズ」は1924年には滑稽とも思える社名だった。「あのちっぽけな会社に、なんという名前なんだろう」。現実にあるのは、噛みタバコをかんでいるような連中が、コーヒー・グラインダーや肉屋のはかりなんかを売っている会社だった。
・「参入したすべての市場でナンバー1かナンバー2になり、当社を、小さな会社のスピードと機敏さを持つ企業に変革する。」(ジャック・ウェルチ)
・「大衆のための乗用車をつくる。・・・価格がきわめて安く、まともな給料をとっている者なら、買えない者はおらず、家族とともに、神がつくった広大な土地で楽しむことができるようになる。・・・全員が自動車を買えるようになり、全員が乗用車を持つようになる。道路からは馬車が消え、自動車に乗るのが当然になる。」(ヘンリー・フォード)
・「皆はトランジスターは商売にならんと言っている・・・。だからこそ、トランジスターの事業は面白いんだ」(井深大)
・「ニューポートの小さな店を、五年以内にアーカンソー州で最高で、もっとも利益の多い雑貨店にする」(ウォルマート、サム・ウォルトン)
Posted by わくわくなひと at
22:25
│Comments(0)
2010年12月21日
カネ儲けを超えた価値観と目的「ビジョナリーカンパニー」
 一昨日、ジェームズ・C・コリンズ/ジェリー・I・ポラス『ビジョナリーカンパニー 時代を超える生存の法則』の第三章から同五章まで読みました。
一昨日、ジェームズ・C・コリンズ/ジェリー・I・ポラス『ビジョナリーカンパニー 時代を超える生存の法則』の第三章から同五章まで読みました。単なるカネ儲けではなく、「本当、この会社で仕事をしてよかった」と思えるような器をつくっていくには基本理念が必要ですね。この本にはいろんなビジョナリーカンパニーの理念が載っていますが、ソニーの理念や志が一番共感しました。
以下は、個人的に特に記録しておきたい内容です(本当な長々と記録していますが一部です)。
「第三章 利益を超えて」から
・基本理念、つまり、単なるカネ儲けを超えた基本的価値観と目的意識である。
・ビジョナリー・カンパニーにとって、基本理念は組織の土台になっている基本的な指針であり、「われわれが何者で、なんのために存在し、何をやっているのかを示すものである」。
・収益力は、会社が存続するために必要な条件であり、もっと重要な目的を達成するための手段だが、多くのビジョナリー・カンパニーにとって、それ自体が目的ではない。利益とは、人間の体にとっての酸素や食料や水や血液のようなものだ。人生の目的ではないが、それがなければ生きられない。
・「利益は会社経営の正しい目的ではない。すべての正しい目的を可能にするものである」(パッカード)。
・真の顧客に本当に満足してもらえれば、利益をあげられるようになる。
・理念が本物であり、企業がどこまで理念を貫き通しているかの方が、理念の内容よりも重要である。
・重要な問題は、企業が「正しい」基本理念や「好ましい」基本理念を持っているかどうかではなく、企業が、好ましいにせよ、好ましくないにせよ、基本理念を持っており、社員の指針となり、活力を与えているかどうかである。
■基本理念=基本的価値観+目的
・基本的価値観=組織にとって不可欠で不変の主義。いくつかの一般的な指導原理からなり、文化や経営手法と混同してはならず、利益の追求や目先の事情のために曲げてはならない。
・目的=単なるカネ儲けを超えた会社の根本的な存在理由。地平線の上に永遠に輝き続ける道しるべとなる星であり、個々の目標や事業戦略と混同してはならない。
(ソニーの設立趣意書より)
これらの人たちが真に人格的に結合し堅き協同精神を持って思う存分技術能力を発揮できるような状態に置くことができたら・・・・・・その運営はいかに楽しきものでもありその成果はいかに大であるか・・・・・・。志を同じくする者が自然に集まり、われわれの発足がはじまった。
(ソニー会社創立の目的より)
・技術者たちが技術することに喜びを感じ、その社会的使命を自覚して思いきり働ける職場をこしらえる。
(ソニー経営方針より)
・不当なるもうけ主義を廃しあくまで内容の充実、実質的な活動に重点を置きいたずらに規模の拡大を追わず。
・技術上の困難はこれをむしろ歓迎し量の多少に関せず最も社会的に利用度の高い高級技術製品を対象とす。
・一切の秩序を実力本位、人格主義の上に置き個人の技能を最大限度に発揮せしむ。
ソニーは開拓者。その窓は、いつも未知の世界に向かって開かれている。人のやらない仕事、困難であるがために人が避けて通る仕事に、ソニーは勇敢に取り組み、それを企業化していく。ここでは、新しい製品の開発とその生産・販売のすべてにわたって、創造的な活動が要求され、期待され、約束されている・・・。開拓者ソニーは、限りなく人を生かし、人を信じ、その能力を絶えず開拓して前進していくことを、ただひとつの生命としているのである。
ソニーは粗雑な電気座布団や和菓子をつくって現金収入を得ていたが(現実主義)、常に社会に貢献する製品の開拓者になることを夢見て、前進し続けた(理想主義)。
Posted by わくわくなひと at
15:56
│Comments(0)
2010年12月19日
「ビジョナリーカンパニー」 起業が先でアイデアは後から
 ジェームズ・C・コリンズ/ジェリー・I・ポラス『ビジョナリーカンパニー 時代を超える生存の法則』日経BPマーケティング(2010年11月2日1版42刷、1995年9月29日1版1刷)。ドラッカーの読書会や経営学の専門家などの間でよく話題になる本である。
ジェームズ・C・コリンズ/ジェリー・I・ポラス『ビジョナリーカンパニー 時代を超える生存の法則』日経BPマーケティング(2010年11月2日1版42刷、1995年9月29日1版1刷)。ドラッカーの読書会や経営学の専門家などの間でよく話題になる本である。3日前、TSUTAYAに立ち寄った際に、つい購入した。「経営理念は大事」と、いろんな人が言う。確かにそうだと思う。会社を立ち上げて今年の12月でまる3年。ありがたいことに年末の駆け込み需要に追われているが、正月休みも近くなったところで、会社について、少し立ち止まって考えてみたい。そんな気持ちから読む気分になったと思う。
この本を購入して自宅に帰って驚いた。M.E.ポーターなど経営戦略関係の本棚の中に、この本が並んでいた。ちょうど10年くらい前、経営戦略関係の修士論文を書いて、さらに経営学を勉強したくなり、この本も購入していた。経営学のいろんな論文に引用されているし、当時も「ぜひ読みたい」と思っていたことを思い出した。しかし、今は視点も立場も違う。
昨日の夜中に少し読んでみた。最初の「謝辞」から驚いた。この本が完成するまでに実に100人くらいの人が関わっていることがうかがえる。私が今非常に気になっているアメリカ人が得意とするプロジェクトマネジメントから生まれた本であることが分かった。
ビジョナリー・カンパニーとは何か?
「・・・ビジョンを持っている企業、未来志向の企業、先験的な企業であり、業界で卓越した企業、同業他社の間で広く尊敬を集め、大きなインパクトを世界に与え続けてきた企業である。重要な点は、ビジョナリー・カンパニーが組織であることだ。」
そして、多くの人々が参画した、このプロジェクトの成果として、「どのようにして会社がはじまったのか。小さな企業から世界規模の大組織に成長するまで、さまざまな困難をどう乗り切ったのか。そして、大企業になったとき、ほかの大企業と比べて際立っている共通の特徴とは何か。これらの企業の歴史から、このような会社を設立し、築き、維持したいと考えている人に役立ちそうな教訓を得ることができるのか。」という疑問に答えてくれるという。そして、巷でよく聞く経営に関する12の神話を崩していく。
私が昨日読んだのは2章まで。さっそく神話1の「すばらしい会社をはじめるには、すばらしいアイデアが必要である。」を崩してくれた。
「基本理念が必要である」。確かにそうであり、自分にはそうたいした内容のものはつくれない。つくれないということは、会社を経営する資格がないかも知れないという不安が常によぎっていた。しかし、これを読んで安心した。
(ヒューレット・パッカードの話)
「・・・最初に会社を始めることを決め、そのあとで、何をつくるか考えた。二人は、まず一歩を踏み出して、ガレージから抜け出し、電気料金を払えるようなになりそうなことを、手当たりしだいやってみた。」
「たまに、ビジネス・スクールで講演する機会があるが、会社をはじめたときに、なんの計画もなく、臨機応変になんでもやったというと、経営学の教授はあぜんとする。わたしたちは、カネになりそうなことは、なんでもやってみた。」
(ソニーの話)
「・・・井深大が一九四五年八月に会社を設立したとき、具体的な製品のアイデアはなかった。それどころか、井深大と七人の社員は、会社がはじまったあとで、どんな製品をつくるか、意見を出し合った。」
(ウォルマートの話)
「サム・ウォルトンも、すばらしいアイデアを持たずに会社をはじめた。自分の会社を持ちたいという強い意欲と、小売業に関するごくわずかな知識、そしてあふれんばかりの情熱だけで、事業を起こした。」
「やっぱりそうなんだ」と納得した。つまり、カリスマやビッグアイデアを思いつく人だけが起業の有資格者ではない。企業や経営の話、それもコンサルタントなどの話は、「結果から話をつくっている」ことが多いようだ。「先見性のある起業家が、製品アイデアや市場についてのビジョンを武器に会社を設立する・・・」という神話は、例外はあるにしても、経験も知識も限られた凡人にはあり得ないことではなかろうか。しかも、コンサルタントも含めて多くの人々は何が先見性であるかは見抜けないし、結果論で実績を見て賞賛するというパターンが余りにも多すぎる。うがった見方をすれば、卓越した企業を自分の商売ネタにしているだけではなかろうか?
しかし、そうは言っても、そろそろ自分の会社が位置づけられている市場のことや、自らの強みと弱み、自分の会社に求められていることなど、まる三年という時間が膨大な量を与えてくれたと自覚している。
次の飛躍のために、そろそろビジョンを描く作業を始める時期には違いない。第三者ではなく、起業や経営という日々の真剣勝負にさらされ思い悩むことが卓越したビジョン形成に至る唯一の道であることを改めて思い知ることができた。
Posted by わくわくなひと at
18:16
│Comments(9)
2010年12月17日
うまい!自立の店「ひまわり」のチョコカップ
 自立の店「ひまわり」パン工房(熊本市新町、YMCAフリースペース内)さんから、ちょっと早めのクリスマスプレゼントをいただきました。
自立の店「ひまわり」パン工房(熊本市新町、YMCAフリースペース内)さんから、ちょっと早めのクリスマスプレゼントをいただきました。おいしいものをたくさんいただきましたが、今日はその中の一つを紹介します。
「チョコカップ」です。チョコレートのカップケーキに、大きいアーモンドが4つものっています。
一口食べてみました。チョコレート味のふんわりケーキの味が口に広がります。超甘くもない、ほどよい甘露みたいな感じで、ほんのしばらくするとチョコやココアの味がしてきます。この味に慣れたころに、少しお口なおしといいましょうか。アーモンド味が口の中いっぱいに広がり、スイーツハーモニーをつくってしまいます。
これはうまい!私が言うのはおこがましいですが、洋菓子の味にそうとう詳しい方がつくられた逸品ではないでしょうか。不思議な感じですが、なぜだかイギリスやフランスを旅している時の気分を何となく思い出してしまいました。
辛党の私ですが、これなら「もう1個!」と言いたいですね。
Posted by わくわくなひと at
20:21
│Comments(5)
2010年12月17日
九州新幹線 博多―熊本 2枚切符で3,000円台
 今日17日付け西日本新聞1面(1面扱いは熊本版だけか?)に、「博多―熊本3000円台」「鹿児島中央9000円台に」「割引切符で検討」という記事が載っていました。
今日17日付け西日本新聞1面(1面扱いは熊本版だけか?)に、「博多―熊本3000円台」「鹿児島中央9000円台に」「割引切符で検討」という記事が載っていました。来年3月12日に全線開通する九州新幹線鹿児島ルートで、JR九州が実勢価格となる割引切符「2枚切符」(回数券)などの料金を、博多―熊本で片道3千円台、博多―鹿児島中央は9千円台で検討していることが16日、分かった。
正確な額ではありませんが、西日本新聞さんにすっぱ抜いていただきました。謝謝!です。それとも、JR九州さんが少し情報を流し、我々市民の反応を確かめるためのリークかも知れません。
11日付け西日本新聞の経済面には、唐池JR九州社長の会見時の一問一答形式のインタビュー記事で次の内容でした。
―割引しない区間もあるのか。
「博多―熊本のように競争が激しくない、あるいは競争がない区間は割引設定を控える」
ところが今日17日付けの記事には、こう書いてありました。
同社の唐池恒二社長は料金申請時の会見で「競合が厳しい区間では、競争力のある割引料金を設定したい」と述べていた。
うーん!JR九州さんの博多―熊本間の認識は、どちらなのか?
福岡―熊本は、高速バスが所要時間1時間40分、片道2千円で運行。九州新幹線は所要時間33分と優位だが、割高感を抑えるため料金差を縮める。
どうも今日のニュアンスでは、「博多―熊本のように競争が激しくない」とは認識していないような感じです。
ちなみに高速バスの実勢価格は4枚の回数券ですので片道1,600円です。「博多―熊本3000円台」だと新幹線の料金は倍以上になります。
さて、消費者はどう動くか?JR九州さんもバス、航空会社の動きも見られながら、申し訳ないほど神経をすり減らされていることと思います。
それと、次の秘策「4枚切符」「20枚切符」はいつ出て来るか?社員なら誰でも使える、もしくは2人まで使える博多―熊本間限定の法人定期などはできないでしょうか。
個人的には、この区間を週に3往復している時もあります。他の社員も動いていますので、お得感がある定期券なら飛びつきます。
Posted by わくわくなひと at
17:33
│Comments(2)
2010年12月15日
NEWS! きょうされんカレンダーが熊本の2作品を掲載
 「きょうされん」さんが、毎年、発行されているカレンダーがあります。
「きょうされん」さんが、毎年、発行されているカレンダーがあります。「はたらく仲間のうた」というタイトルで、障がいのある人たちが描いた作品集(きょうされんグッズデザインコンクール受賞作品集)のカレンダーです。
私の事務所でも、毎年、福岡と熊本の事務所のカレンダーとして使わせてもらっています。
来年、2011年の作品はどんなのが掲載されてくるか楽しみにしていました。手元に届いたカレンダーをめくっていくと、何と熊本県内の人の作品がそれも2つ載っていました。
ひとつは4月のカレンダーで、「ふれあいワーク」の猪口克巳さんの作品「ウミガメの赤ちゃん」です。もう一つは6月で「るぴなす」の緒方愛さんの作品「うたってるフクロウ」です。

このカレンダーは、月が代わるたびに、何か新鮮な感覚、見方を教えてもらうような気がしています。心の中がパッと明るくなるようなパワー、AHA体験のようなパワーを感じています。
Posted by わくわくなひと at
20:27
│Comments(2)
2010年12月15日
日本のゲーム産業は大丈夫か?NHKスペシャルを見て
 12日(日)にNHKスペシャルで「世界ゲーム革命」が放映されていました。内容はゲーム市場での日本のシェアが低下していること、カナダやアメリカなどでのゲーム産業が伸びてきていること、スピルバーグなどハリウッドとゲーム産業が融合を始めていること、日本では福岡のレベルファイブとジブリが手を組んで反撃に出ようとしていることなどでした。
12日(日)にNHKスペシャルで「世界ゲーム革命」が放映されていました。内容はゲーム市場での日本のシェアが低下していること、カナダやアメリカなどでのゲーム産業が伸びてきていること、スピルバーグなどハリウッドとゲーム産業が融合を始めていること、日本では福岡のレベルファイブとジブリが手を組んで反撃に出ようとしていることなどでした。すさまじい世界を垣間見た気分でしたが、一つ非常に気になることがありました。それはレベルファイブをはじめ日本のゲーム産業が労働集約型というか、一人の天才ややり手を中心に仕事が進んでおり、徹夜や残業によって何とか太刀打ちしていこうとしていることでした。福岡だけでなく世界的に有名なレベルファイブの日野あきひろ社長の疲れた姿が特に印象に残りました(世界を相手に“やるぞ”という気持ちを伝える内容でしたが・・・)。
アメリカやカナダでも一部の人はそうしているのかも知れませんが、ゲームづくりの分業が非常に進んでいることに大きな違いを感じました。ドラッカー『マネジメント 課題、責任、実践 上』で書いているように、“個々の作業を可能なかぎり単純に設計”するという思想、つまり、アメリカやカナダでは凡人でもクリエイティブな作業に参画できる仕組みが着々と作られていることをNHKのテレビで実感した次第です。
別の本で読みましたが、スターウォーズ以来のハリウッド映画づくりでのシナリオは、完璧な分業とグループワークで進められていると書いてありました。それに比べ日本の漫画や映画は大先生が中心となりその弟子が徹夜しながら作られているそうです。漫画や映画、ゲーム分野だけでなく、日本の多くの知識労働者は少なからず似たような環境に置かれているのではないでしょうか。
日本のクリエーターの多くは、残業や徹夜をしてすごい作品をつくっていくことに誇りを感じていることと思います。こういった天才や努力家の仕事のプロセスを分析し、凡人でも参画できるような“無味乾燥な”仕組みをつくっていくことに対して抵抗を感じる文化が日本にはあるのでしょうか?。
第2次世界大戦に関心のある方ならご存知だと思いますが、今度のNHKスペシャルを見て、零戦とグラマンの違い、日本の熟練設計者や熟練搭乗員と、アメリカの凡人設計者と凡人搭乗員の違いが頭に浮かんできました。ひょっとして、日本人は戦略的なプロジェクトマネジメントなどを設計し実践していくことに向いていないのか、それとも別の要因があるのか・・・そんなことが気になるようになりました。
今後、ゲーム産業をはじめとした日本の知識産業は、世界を競争相手に天才や努力家を次々と消耗させていき、シェアを落としていくことになるのでしょうか。
なお、福岡県は福岡市を中心にゲーム産業が集積しており、「福岡コンテンツ産業振興会」というリーディング産業育成プロジェクトが組織されています。今月の20日には博多駅近くに「福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター」がオープンします。福岡には多くの凡人が参画できるようなプロジェクトが芽生えていくことを期待しています。
Posted by わくわくなひと at
15:17
│Comments(0)
2010年12月13日
幕末・明治版・家政婦は見た!「女百話」を鹿児島でゲット
 今日は鹿児島中央駅横にある紀伊国屋に立ち寄りました。
今日は鹿児島中央駅横にある紀伊国屋に立ち寄りました。旅の途中だからバッグが重くなるにも関わらず、福岡のジュンク堂になかった(見つけきれなかった?)本がありました。
篠田鉱造『幕末明治 女百話(上)』岩波文庫(2009年7月9日第5刷、1997年8月19日第1刷、底本四条書房『幕末明治 女百話(前編)』昭和7年)と『同(下)』(2009年7月9日第4刷、1997年9月16日第1刷、『同(後編)』)です。
帯には「他では読めない」「岩波文庫/一括重版」と書いてあり、ますますその気にさせられました。
ジュンク堂で立ち読みしていて、加藤周一さんだったと思いますが、「『女百話』という面白い本がある。けっこう小説などの種本になっている。嘘だと思うなら岩波文庫の出版目録を見たらいい」というような文章を読みました。「うん!それなら読みたい」と10メートルほどあるジュンク堂の岩波文庫の棚を見ましたがありませんでした。
まえがき(今は実に危機一髪)に、こんなことが書いてありました。幕末・明治の“家政婦は見た”かな?、けっこう面白そうです。
女百話?本書の特色は百話のすべてが女性の唇頭から発している点にある、これをば単に面白い思い付だというて片付ける人があらば、それは余りに軽率である、著者の真意は猟奇に駆られたのでなく、他に意味があるであろう。全体女性は男性と異って語る機会を有たぬ、公然語ることは尚更である。随て女性の語ることには隠れたることが多い。尚歓楽の仕方も女性は男性と異っているし、趣味も同じく無い。女性は概ね感情的で、その歓楽は微に入り細に入る。男性が大まかに気にも留めないことを、女性はぬかりなく掴む。男性が聞き流しに附することを女性は遁さず記憶する。男性は多くの場合瑣事に頓着しないが、女性はかえってこれに興味を有つ。ともすると、男性は自分から成したことすら記憶しないことがあり、物の歓楽も往々にして放漫に流れる。だから男性に聞いて知り難いことが女性に聴いて委曲に分かることが往々にある。尚女性の一徳ともいうべきは、男性の立ち入り難い所に入り込んでいろいろの秘密に接し得ることがある。すなわち宮仕をするものでなければ、奥深い殿中のことが分らず、豪紳の家庭に住み込まねばその内政が分らず、寺院に立入らねば僧侶の内生活が分るはずなく、料理屋待合に居らねば客の秘密は知り兼ねる。しかるにこれらの内所には女性のみ立入る特権を有し、男性には絶対禁断の所である。ところで人情はオツなもので、どんなに鉄錠を卸している堅固の男性でも、女性に対しては誠に脆くともすると心を許して錠を外すことのあるのは珍らしくない。だから女性ほど人の秘密を知るに便利な立場にいるものはない。随って女性は男性の知らない多くの秘事を知っている。そして多くの場合直接本人より口ずから聴いたり現場を目睹しているから、その事実は概ね正確である。女性をして語らしむることが如何に意義あるかは、コンナ粗略な記述によっても思半ばに過ぐるものがあろう。
Posted by わくわくなひと at
15:54
│Comments(6)
2010年12月11日
九州新幹線博多―熊本間の割引設定を控え目?
 昨日、今日と九州新幹線の新料金の情報がたくさん流れてきました。
昨日、今日と九州新幹線の新料金の情報がたくさん流れてきました。個人的には博多―熊本間の料金がどうなるのか?が最大の関心事です。
熊日新聞の昨日10日付け夕刊に、同区間は「4,990円で、現行のJR利用より1,050円高くなる。」と書いてありました。現行と新幹線全線開業後の所要時間と料金の表は、分かりやすかったと思います。他紙はおそらく開業後だけの表で済ませていたと思います。
今日11日付け熊日新聞朝刊には、「熊本―肥後大津に快速」という記事が載っていました。熊本の事務所は「新水前寺駅」の近くですので朗報です。熊日新聞は、“快速の運賃は普通列車と同じ。”など、あんまりJRや鉄道に馴染みのない人でも分かりやすいように工夫しています。“新快速”イメージは、博多と飯塚方面を結んでいる福北ゆたか線の快速みたいな感じでしょう。ワンマン2両編成で「直方行き 快速」とかが走っています。
同じく11日付け西日本新聞は、1面、3面、15面に新幹線関連の記事を載せていました。圧倒的な情報量です。1面の記事は熊日新聞の夕刊とほとんど同じ情報でしたが、3面は飛行機、バスを意識したJR九州の競争戦略についての考え方、ライバルの航空会社やバス会社のコメントを載せていました。同じく3面には、料金に対する鹿児島、熊本、佐賀の人たちのコメントを載せていました。3面はマネジメントや経営などに関心のある方々には、読み応えのある記事だったと思います。マイケル・ポーターによる競争戦略の図式や料金設定の際によく使うコンジョイント分析の質問項目が頭に浮かんできました。
西日本15面の経済面は、唐池JR九州社長の会見時の一問一答形式のインタビュー記事が載っていました。見出しは「十分戦える」「KTXと連動も」でしたが、私が最も注目していることへの回答がさらりと書いてありました。
―割引しない区間もあるのか。
「博多―熊本のように競争が激しくない、あるいは競争がない区間は割引設定を控える」
ガビーン!そんなに安くならないことを示唆する発言です。現行では博多―熊本4枚切符は1枚当たり2,000円。これに事務所がある大名からは地下鉄赤坂駅または天神駅から博多駅まで200~250円かかります(博多―天神の100円バスもありますが、時間に余裕がある時だけで勘弁!)。計2,250円也。天神―熊本の高速バスは4枚の回数券で1枚当たり1,600円。事務所までは天神バスセンターから歩いて6分ですので、1,600円ぽっきりです。別の面ですが、西日本鉄道の竹島和幸社長は「安さを重視する人は高速バスを選んでもらえる」と静観と書いてありました。ひょっとして、西鉄大牟田線の高速化と熊本への延伸など秘策がありませんか?博多―熊本間の競争を烈しくできるのは西鉄しかありません。
弊社のような零細企業でも交通費は年間にすると、数百万円かかってます。そんなに安くならないとすると、時間がないときやくたばった時に総務部長に懇願して新幹線に乗れるということになりそうです。小倉や鹿児島での仕事の時はまさしく新幹線だろうと思います。
割引設定は控えると言っても、さて!どのくらいになるでしょうか。少し落ち込みました。月曜日は朝一でリレーつばめに乗り、新八代から新幹線で鹿児島行きです。午前9時過ぎには鹿児島中央駅にいると思います。
Posted by わくわくなひと at
14:47
│Comments(0)
2010年12月10日
九州新幹線「さくら」全駅に停車 17日ダイヤ発表
 今日10日付け西日本新聞・熊本版は1面トップで九州新幹線ネタでした。
今日10日付け西日本新聞・熊本版は1面トップで九州新幹線ネタでした。今、熊本にいるので分かりませんが、福岡都市圏では昨日の夕刊1面トップだったと想像します。
・・・JR九州が九州内で運行する新車両「さくら」の停車駅を列車によって変え、全駅に少なくとも1日上下各1本は停車させる方針・・・
各駅の地元の人々にとっては朗報です。
個人的には、以下の情報が大事でした。
■「つばめ」(各駅停車)は博多―熊本で58分
■17日に運行ダイヤ発表
■深夜・早朝の時間帯に博多―熊本間の在来線深夜特急存続
■通勤時間帯に博多―長洲間の特急を調整中
17日に運行ダイヤ発表が一番の注目です。
その前にスクープしてください。
Posted by わくわくなひと at
13:13
│Comments(0)
2010年12月09日
暮らしと“陰影”について考えたいと思います!
 今日は、久々に熊本の街中を歩きました。
今日は、久々に熊本の街中を歩きました。街中での用事を済ませ、一服所で、ふとこんな考えが浮かんできました。
「今、一番読みたい本は何だろう?」。
「松岡正剛や河野多惠子が激賞していた谷崎潤一郎、それも陰翳礼讃を読んでみたい」。こんな自分の気持ちを確認することができました。
中公文庫だから、書店を選ばない。どこにでもある。しかし、昔の本なので大きな書店の方が確実だと思いました。しかし、谷崎潤一郎の本はたくさん置いてあるのに、『陰翳礼讃』はありません。
それで、「これでだめならジュンク堂」と思い、中規模の書店を訪ねました。新潮文庫とか角川文庫のコーナーは広くとってありますが、中公文庫のコーナーが分かりません。書店の人に尋ねると、「そこです!」。私の目の前にこぢんまりとした中公文庫のコーナーがありました。
あまり期待しないで、“谷崎”を探しました。すると、一冊だけ、しかも『陰翳礼讃』中公文庫(2010年6月25日改版19刷、1975年10月10日初版/「陰翳礼讃」は「経済往来」昭和8年12月号と同9年1月号が初出)だけが置いてありました。“セレンディピティ?”。ちょうど私が買いに来るのを待っていたように、置いてありました。
“陰翳”。最近は、こんなことを感じることが少なくなってきています。夜の静寂(しじま)も蛍光灯やLEDなどで明々と照らされて、風情とか色香とかを感じにくくなっています。効率よく天井から明々と照らすのは昭和40年代くらいからでしょうか。文化を味わうなら間接照明がいいと思います。
もう一年以上前になりますか。九州国立博物館で阿修羅展がありました。たぶん、この展示は“陰翳”を相当考えてありました。大昔、奈良の興福寺で見た阿修羅にはさほど感動しませんでしたが、太宰府の阿修羅を見て鳥肌が立ってしまいました。確か藤原時代の興福寺がそうであったろう、金堂の陰影を再現するように心がけたと説明してあったような記憶があります。
谷崎の“陰翳”をこれから読んでいきます。日々の暮らしと陰影について考えていく、よいきっかけになりそうです。そう言えば、アバクロ福岡の店内も薄暗くしてあり、陰影というのを意識しているような感じです。
Posted by わくわくなひと at
19:32
│Comments(4)
2010年12月08日
アバクロAbercrombie & Fitchの香りをゲット
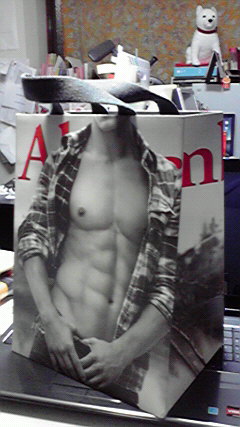 いつだったか?オープン日以来、久々にアバクロ(Abercrombie & Fitch NEW YORK)福岡に行ってきました。
いつだったか?オープン日以来、久々にアバクロ(Abercrombie & Fitch NEW YORK)福岡に行ってきました。店内はオープン時のざわつきはなくなっていましたが、入り口では胸をはだけたマッチョなイケメンが迎えてくれます。アメリカのチアリーダーみたいな雰囲気を持つ、スタイル抜群の店員さんたちの笑顔と声かけも変わりません。もちろん、ビートの効いた音楽と独特の香りも同じです。
嗅覚を活用したマーケティングにほんの少し関心を持っている私の今日の目的は、店内の香りを購入することでした。
8種類のコロンを売っており、その中で店内の香りと同じものを買いました。ついでに8つの香りをお店のお嬢さんに案内されながら試してみました。「これが大人の男性用です。」と、店内の香りよりももっと刺激的なものもありました。正直、途中で鼻が麻痺してしまい、お店の香りと同じ「フィアス コロン(FIERCE COLOGNE)」30mlを、6,400円で買いました。
小さいコロンでしたが、お馴染みのマッチョな男性の写真が貼ってあるショップ袋に入れてもらいました。デパートなどの袋と比べると分厚いし頑丈です。


そう言えば、アバクロショップ袋を下げて歩いている人をちらほら見かけるようになりました。
個人的に一番気に入っている香りは、ハイアットホテルの部屋の香りです。ラベンダーとイランイランを独自にミックスしているそうです。ハイアットもアバクロのように売り出せばいいと思いますが、いかがでしょうか?
Posted by わくわくなひと at
21:50
│Comments(2)
2010年12月08日
「まずみなさんを信用することから・・・」福岡新市長
 7日付け西日本新聞・夕刊1面に、高島・福岡市長が初登庁した記事が載っていました。
7日付け西日本新聞・夕刊1面に、高島・福岡市長が初登庁した記事が載っていました。記事の焦点は「副市長 当面2人体制」にあてられていましたが、むしろ記事の最後のところに書いてあったことが印象に残りました。
講堂では、職員約400人を前に「まずみなさんを信用することから始めたい」「あなた自信の中に『何も変わらない』とのあきらめはないか。勇気と覚悟を持ち、新しいチャレンジをしよう。責任は私が取ります」と呼びかけた。
この言葉を素直に読めば、市長自身に相当な覚悟があり、市役所を大改革するという意気込みを語ったのでしょうか。阿久根や名古屋と同じように予想するのは失礼でしょうが、この高島市長の挨拶からは何らかの前触れを感じてしまいました。
Posted by わくわくなひと at
00:08
│Comments(0)
2010年12月07日
2010年12月06日
さまざまな書籍にある“ひらめき”“独創”“メラキア”の記述
いろんな本で独創のプロセスやひらめきの瞬間などが解説されています。仕事の途中の原稿ですが、興味のある方はぜひご一読ください。
下條信輔さんは、脳内での“ひらめき”の組織化、脳内のひらめきや独創のメカニズムなどを解説するとともに、独創に必要なしつこさと執念、クリエイティブな人の思考方法を紹介しています。
茂木健一郎さんも、創造には経験と意欲が必要なこと、ひらめきの能力は習慣化できること、喜びと苦しみが表裏一体であることなどを解説しています。シカゴ大学の心理学者・チクセントミハイさんも、茂木さんと同様に、最良の瞬間は限界から生まれること、幸福感は意識も持ち方次第であるとしています。
こういった学者だけでなく小説家の河野多惠子さんも、小説家のひらめきや創造のプロセスを細かく描いています。芸術家の岡本太郎さんは、梅澤の言うメラキア的発想をする人だったことが著書を読んで分かりました。
■下條信輔『サブリミナル・インパクト -情動と潜在認知の現代』ちくま新書(2008年12月10日第1刷)
(脳内での“ひらめき”の組織化)
前意識の知は、意識の知と無意識の知の境界領域、またはインターフェースにあたります。人が集中して考えたり、あるいはぼんやりと意識せずに考えるともなく考えているときに、突然天啓が閃く。スポーツによる身体的刺激や、音楽による情動の高揚、他人がまったく別の文脈で言った何気ない一言などが、しばしばきっけかになるようです。こういう場合には、新たな知は外から直接与えられたわけではなく、といって内側にあらかじめ存在していたとも言えません。その両者の間でスパークし「組織化」されたのです。
(「あちらから」やってくると感じる理由)
突然「あちらから」やってくる。あるいは天啓のように「閃く」。・・・潜在認知の過程から顕在認知の領域に結果が読み出されるときに共通する「現象的な特徴」なのです。受け身の、また偶然を装った立ち現れ方をするのは、それが潜在認知の領域=私の中の他人の領域からやってくるからです。一方予感できるのは、それにもかかわらずその知が潜在的には知られているからです。このように考える以外には、「能動的なはずなのに受動的な立ち現れ方をする」という一見矛盾に満ちた奇妙な立ち現れ方を、理解する術はないと考えます。ただ、受け身の立ち現れ方をするにもかかわらず、飛び抜けた妙手は多くの場合、打たれたとたんにそれと認知されます。
(独創にはしつこさと執念が必要)
独創的な洞察の成立するメカニズムを理解するうえで、忘れてはならない要素です。それはしつこさや執念、これです。・・・独創的な洞察に至るには周辺/辺境を探索する必要がある。それも外界からの刺激と内的な欲求との間の「偶発的な」スパーク、というかたちをとることが多いので、探索 /接触の頻度が高いほどチャンスも多く到来する。・・・次に、自分のすぐ脇を大きい獲物(洞察のタネ)が泳ぎ去ろうとするとき、めざとくそれを見つけてキャッチする必要がある。それはいつ何時来るかわからない(来ないかも知れない)ので、目を光らせている持続的な執念が必要・・・
(クリエイティブな人の定義)
クリエイティブな人とは・・・「全体的な状況を把握し、顕在知(顕在認知過程)と暗黙知(潜在認知過程)との間を自由に往還しつつ、考え続けられる人(能力)」と答えてみることができそうです。
■茂木健一郎『脳を活かす仕事術 「わかる」を「できる」に変える』PHP研究所(2008年10月23日第1版第3刷)
(創造、経験、意欲の関係)
人間は外部からの情報を受け取った時、それを記憶として脳の側頭葉に蓄えていきます。第2章でも述べましたが、脳に入力された情報や記憶は、運動系の出力を経て「意味付け」をされて初めて、他の状況などに応用可能な「経験」となります。そして、側頭葉に蓄えられている「経験」が、意識を司る前頭葉の方針に従って編集される時、新しいものが生み出されます。つまり「経験」という要素がないと創造性は発揮できないのです。
次に大切なのが「意欲」です。
頭の中で、「これをやりたい」や「これがいい」といった意欲や価値判断を司っているのは前頭葉です。
アイデアが必要になった時、まず前頭葉が側頭葉に「こういうものが欲しいんだけど、何か役立ちそうな経験はない?」とリクエストを送ります。すると、側頭葉は一番近いものを出そうと、組み合わせや結びつきを変えたりと、試行錯誤を重ねます。そして、様々な記憶中から、「これはどうですか?」「こっちは?」と、次から次へと前頭葉に送っていきます。
前頭葉はそれをもとに「これは違う」「こっちはちょっと近い」と、価値判断をしながらやり取りを繰り返します。やがて「これだ!」というのが見つかった瞬間が、創造性を発揮してアイデアを生み出した時になるわけです。
■茂木健一郎『ひらめきの導火線 トヨタとノーベル賞』PHP新書(2008年9月2日第1版第1刷)
(習慣化によって高まる“ひらめき”の力)
・創造性は、経験と意欲が合わさって生まれる。私たちが生きていく中で得た知識や経験は、脳の中の側頭葉に蓄積される。それを、前頭葉で生まれる意欲や価値観が引き出してくれる。
・創造性を高めたければ、意欲と経験を結ぶ回路をうまくつなげるようにすればいい。回路は日々使えば使うほど太くなり、創造性は増強されていく。反対に、ごくたまにしか使わないと回路は細ってしまう。習慣化によって、だれもがひらめきの力を高めることができる。
(“ひらめき”と良質の喜び)
・考え続け、探し続ける過程は、とても苦しい。けれど、その苦しみを経てひらめきにたどり着いたときほど、脳が喜ぶことはない。お金をもらうより、社会的地位を得ることより、はるかに良質の喜びを脳にもたらす。
■茂木健一郎『欲望する脳』集英社新書(2007年12月25日第三刷)
(苦しみと喜びの深い結びつき)
人生においては、「苦しいこと」がしばしば「嬉しいこと」と深く結びついているのは、一体どうしてなのだろうか。もともとはつらかったはずの様々なことに慣れ親しむ。やがて、その苦しみの底からかすかな甘みが感じられてくるようになる。そして、ふと気が付くと、ある種の苦しみこそが人生の掛け替えのない喜びを導き出すための呼び水であることを知る。
元来、脳の中で「報酬」を表すドーパミンは、「サプライズ」を好むように設計されている。嬉しいことがたとえあったとしても、それが予想されたものであると効果がない。果たして与えられるのかどうか、わからない時にこそドーパミン細胞は盛んに活動する。その中に含まれている「情報量」が多くなれば、ドーパミンは放出されないのである。
■M.チクセントミハイ『フロー体験 喜びの現象学』世界思想社(2009年9月20日第10刷、1996年8月20日第1刷)
(限界から生まれる最良の瞬間)
最良の瞬間は普通、困難ではあるが価値のある何かを達成しようとする自発的努力の過程で、身体と精神を限界にまで働かせ切っている時に生じる。
(注意の集中と楽しみ)
意識が統制されている人を特徴づけるのは、思うままに注意を集中させる能力であり、気を散らすものに心を留めないこと、目標を達成するため注意を集中すること、目標達成の後まで注意を持ち越さないことである。これができる人は、日常生活の一般的な過程を楽しんでいるのが普通である。
(意識と幸福感の関係)
人は現実に「外」で起こっていることとは無関係に、ただ意識の内容を変えるだけで自分を幸福にも惨めにもできる。パーソナリティの力だけで、絶望的な状況を克服すべき挑戦対象に変えることのできる人々をだれもが知っている。障害や妨害にもかかわらず頑張り続けるというこの能力こそ、まさにその人に対し他者が尊敬の念を抱く最も大きな特質である。
■河野多惠子『小説の秘密をめぐる十二章』文春文庫(2005年10月10日第1刷)。
(小説家の“ひらめき”と喜び体験)
書きたい題材、モチーフがしっかり決まっているつもりでも、題なり、名前なりが定まらない時には、書きたい題材、モチーフが、まだ本当には生きはじめていないことが多い。だから、まだ書き出すのは早いのだ。題あるいは名前が作曲と演奏との拮抗で決定的に閃いた時には、書きたい題材、モチーフが本当に生きはじめたことを実感させるのであって、そういう喜びの体験こそが、創作というものを教えてくれる大きな機会の一つと言えるのである。
(小説家における創造プロセス)
創作衝動には二種の衝動がある。一つは、文学作品というものを書きたくてならない、憧憬と欲求不満が混合したような気持の蠢動である。その気持ちは、小説というものを書く以外に納まりようのないことを訴えてやまない。もう一つは、ある文学作品を書きたい気持ちの蠢動である。この場合には、既に書きたいことがある。モチーフ、つまり何故そのことを書きたいか、創作の動機が心を突き動かしている。その実感が鮮烈であればあるほど、創作意欲が掻き立てられる。創造力は具体的に作品を生み出す力のことで、創作衝動すなわち創造力ではないが、創作衝動がなければ創造力を示すことは不可能なのである。
・・・要するに、書きたいことの発見によって後者の意味での創作衝動(以下、この言葉は、すべてその意味)が発動するのである。ところが、それを発見する方法と言えるものはないのだ。ただ、文学作品の創作では、書きたいことは作者の心―精神に根ざしたものであってこそ、創作衝動はそれらしい力を示すのである。
例えば、自分の知っている人物でも、ひとの話で聞いた人物でも、誰でもよいが、ある人物のある行為を見るなり、聞くなりして、非常に興味を覚えたとする。それを作品に書きたいと思った時、<それ>は書きたいものなのか、書きたいことなのか。書きたいものと書きたいこととは丸でちがう。書きたいものとしてだけで書くのであれば、ただのお話にしかならない。その話をあれこれと作り変えても、作りものめいてゆくだけである。書きたいこと―自分の精神と切り結んだモチーフを得て創作衝動が発生している時には、事柄上はその話のままであっても、創造性が生まれて、ただのお話ではなくなる。あるいは、書きたいことから生じた想像力の支配によって、聞いた話とは全くちがうものになった作品には、作りものではなくて真実がある。また、ある人物の行為の話というような手がかりも、何かのヒントもなくて、突然モチーフを思いつく場合も勿論ある。そのモチーフが作者の精神に根ざしているものであれば、作品の具体的な構想はおのずから膨らんでゆくはずである。
(小説家における発想の転換や飛躍)
創作過程で終始、非常に意を用いるべきことは、モチーフの強い把握であり、その深く鋭い表現である。最も書きたいことは何か、どこに力点をおくべきか、とよく考えることで、その作品の創作の進め方がおのずから分かってくる。「筋」「起承転結」に囚われずに、転換も飛躍も自由に行えばよい。といっても、転換や飛躍が単なる思いつきや独りよがりであってはならない。モチーフの強い把握から促され、その深い鋭い表現のために生まれてきたものでなくてはならない。・・・導入部がしっかり書かれておれば、その作品で最も書きたいことは何か、どこに力点をおくべきかということが、その時もしっかり頭にあれば、導入部の<気配>が、次に書くべきブロック―つまり書きたいブロックを自然に告げ識らせてくれるのである。そして、そのブロックがモチーフの深い鋭い表現を担い得ておれば、そこから次のブロックが生まれてくる。先行のブロックとの間に飛躍や断絶があろうと(あるいはなくても)、「筋」「起承転結」指向ではあり得ない、本質的な脈略、呼応が存在する。
■岡本太郎『自分の中に毒を持て あなたは“常識人間を捨てられるか”』青春出版社(青春文庫)、1988年
(岡本太郎の逆説的発想法)
・・・ぼくはいつでも、あれかこれかという場合、これは自分にとってマイナスだな、危険だなと思う方を選ぶことにしている。誰だって人間は弱いし、自分が大事だから、逃げたがる。頭で考えて、いい方を選ぼうなんて思ってたら、何とかかんとか理屈をつけて安全な方に行ってしまうものなのだ。
かまわないから、こっちに行ったら駄目だ、と思う方に賭ける。
瀬戸内晴美はぼくに最初に会った頃、それを聞いてショックを受け、以来それを実行してきたと言っている。彼女はちゃんと食えているし、それ以上、堂々とやってるけれど、覚悟はそこにあるんだ。ほんとうに生きるっていうのは、そういうことだ。
(岡本太郎による非常識反転発想・メラキア的発想の例)
・まずくいった方が面白い
・失敗したらなお面白い
・つまらなかったらやめればいい
・三日坊主でかまわない
・三日坊主になるという“計画”をもったっていい
・うまくいくとか、いかないとか、そんなことはどうでもいい
・下手なら、むしろ下手こそいい
・行きづまったほうがおもしろい
・強くならなくていい
下條信輔さんは、脳内での“ひらめき”の組織化、脳内のひらめきや独創のメカニズムなどを解説するとともに、独創に必要なしつこさと執念、クリエイティブな人の思考方法を紹介しています。
茂木健一郎さんも、創造には経験と意欲が必要なこと、ひらめきの能力は習慣化できること、喜びと苦しみが表裏一体であることなどを解説しています。シカゴ大学の心理学者・チクセントミハイさんも、茂木さんと同様に、最良の瞬間は限界から生まれること、幸福感は意識も持ち方次第であるとしています。
こういった学者だけでなく小説家の河野多惠子さんも、小説家のひらめきや創造のプロセスを細かく描いています。芸術家の岡本太郎さんは、梅澤の言うメラキア的発想をする人だったことが著書を読んで分かりました。
■下條信輔『サブリミナル・インパクト -情動と潜在認知の現代』ちくま新書(2008年12月10日第1刷)
(脳内での“ひらめき”の組織化)
前意識の知は、意識の知と無意識の知の境界領域、またはインターフェースにあたります。人が集中して考えたり、あるいはぼんやりと意識せずに考えるともなく考えているときに、突然天啓が閃く。スポーツによる身体的刺激や、音楽による情動の高揚、他人がまったく別の文脈で言った何気ない一言などが、しばしばきっけかになるようです。こういう場合には、新たな知は外から直接与えられたわけではなく、といって内側にあらかじめ存在していたとも言えません。その両者の間でスパークし「組織化」されたのです。
(「あちらから」やってくると感じる理由)
突然「あちらから」やってくる。あるいは天啓のように「閃く」。・・・潜在認知の過程から顕在認知の領域に結果が読み出されるときに共通する「現象的な特徴」なのです。受け身の、また偶然を装った立ち現れ方をするのは、それが潜在認知の領域=私の中の他人の領域からやってくるからです。一方予感できるのは、それにもかかわらずその知が潜在的には知られているからです。このように考える以外には、「能動的なはずなのに受動的な立ち現れ方をする」という一見矛盾に満ちた奇妙な立ち現れ方を、理解する術はないと考えます。ただ、受け身の立ち現れ方をするにもかかわらず、飛び抜けた妙手は多くの場合、打たれたとたんにそれと認知されます。
(独創にはしつこさと執念が必要)
独創的な洞察の成立するメカニズムを理解するうえで、忘れてはならない要素です。それはしつこさや執念、これです。・・・独創的な洞察に至るには周辺/辺境を探索する必要がある。それも外界からの刺激と内的な欲求との間の「偶発的な」スパーク、というかたちをとることが多いので、探索 /接触の頻度が高いほどチャンスも多く到来する。・・・次に、自分のすぐ脇を大きい獲物(洞察のタネ)が泳ぎ去ろうとするとき、めざとくそれを見つけてキャッチする必要がある。それはいつ何時来るかわからない(来ないかも知れない)ので、目を光らせている持続的な執念が必要・・・
(クリエイティブな人の定義)
クリエイティブな人とは・・・「全体的な状況を把握し、顕在知(顕在認知過程)と暗黙知(潜在認知過程)との間を自由に往還しつつ、考え続けられる人(能力)」と答えてみることができそうです。
■茂木健一郎『脳を活かす仕事術 「わかる」を「できる」に変える』PHP研究所(2008年10月23日第1版第3刷)
(創造、経験、意欲の関係)
人間は外部からの情報を受け取った時、それを記憶として脳の側頭葉に蓄えていきます。第2章でも述べましたが、脳に入力された情報や記憶は、運動系の出力を経て「意味付け」をされて初めて、他の状況などに応用可能な「経験」となります。そして、側頭葉に蓄えられている「経験」が、意識を司る前頭葉の方針に従って編集される時、新しいものが生み出されます。つまり「経験」という要素がないと創造性は発揮できないのです。
次に大切なのが「意欲」です。
頭の中で、「これをやりたい」や「これがいい」といった意欲や価値判断を司っているのは前頭葉です。
アイデアが必要になった時、まず前頭葉が側頭葉に「こういうものが欲しいんだけど、何か役立ちそうな経験はない?」とリクエストを送ります。すると、側頭葉は一番近いものを出そうと、組み合わせや結びつきを変えたりと、試行錯誤を重ねます。そして、様々な記憶中から、「これはどうですか?」「こっちは?」と、次から次へと前頭葉に送っていきます。
前頭葉はそれをもとに「これは違う」「こっちはちょっと近い」と、価値判断をしながらやり取りを繰り返します。やがて「これだ!」というのが見つかった瞬間が、創造性を発揮してアイデアを生み出した時になるわけです。
■茂木健一郎『ひらめきの導火線 トヨタとノーベル賞』PHP新書(2008年9月2日第1版第1刷)
(習慣化によって高まる“ひらめき”の力)
・創造性は、経験と意欲が合わさって生まれる。私たちが生きていく中で得た知識や経験は、脳の中の側頭葉に蓄積される。それを、前頭葉で生まれる意欲や価値観が引き出してくれる。
・創造性を高めたければ、意欲と経験を結ぶ回路をうまくつなげるようにすればいい。回路は日々使えば使うほど太くなり、創造性は増強されていく。反対に、ごくたまにしか使わないと回路は細ってしまう。習慣化によって、だれもがひらめきの力を高めることができる。
(“ひらめき”と良質の喜び)
・考え続け、探し続ける過程は、とても苦しい。けれど、その苦しみを経てひらめきにたどり着いたときほど、脳が喜ぶことはない。お金をもらうより、社会的地位を得ることより、はるかに良質の喜びを脳にもたらす。
■茂木健一郎『欲望する脳』集英社新書(2007年12月25日第三刷)
(苦しみと喜びの深い結びつき)
人生においては、「苦しいこと」がしばしば「嬉しいこと」と深く結びついているのは、一体どうしてなのだろうか。もともとはつらかったはずの様々なことに慣れ親しむ。やがて、その苦しみの底からかすかな甘みが感じられてくるようになる。そして、ふと気が付くと、ある種の苦しみこそが人生の掛け替えのない喜びを導き出すための呼び水であることを知る。
元来、脳の中で「報酬」を表すドーパミンは、「サプライズ」を好むように設計されている。嬉しいことがたとえあったとしても、それが予想されたものであると効果がない。果たして与えられるのかどうか、わからない時にこそドーパミン細胞は盛んに活動する。その中に含まれている「情報量」が多くなれば、ドーパミンは放出されないのである。
■M.チクセントミハイ『フロー体験 喜びの現象学』世界思想社(2009年9月20日第10刷、1996年8月20日第1刷)
(限界から生まれる最良の瞬間)
最良の瞬間は普通、困難ではあるが価値のある何かを達成しようとする自発的努力の過程で、身体と精神を限界にまで働かせ切っている時に生じる。
(注意の集中と楽しみ)
意識が統制されている人を特徴づけるのは、思うままに注意を集中させる能力であり、気を散らすものに心を留めないこと、目標を達成するため注意を集中すること、目標達成の後まで注意を持ち越さないことである。これができる人は、日常生活の一般的な過程を楽しんでいるのが普通である。
(意識と幸福感の関係)
人は現実に「外」で起こっていることとは無関係に、ただ意識の内容を変えるだけで自分を幸福にも惨めにもできる。パーソナリティの力だけで、絶望的な状況を克服すべき挑戦対象に変えることのできる人々をだれもが知っている。障害や妨害にもかかわらず頑張り続けるというこの能力こそ、まさにその人に対し他者が尊敬の念を抱く最も大きな特質である。
■河野多惠子『小説の秘密をめぐる十二章』文春文庫(2005年10月10日第1刷)。
(小説家の“ひらめき”と喜び体験)
書きたい題材、モチーフがしっかり決まっているつもりでも、題なり、名前なりが定まらない時には、書きたい題材、モチーフが、まだ本当には生きはじめていないことが多い。だから、まだ書き出すのは早いのだ。題あるいは名前が作曲と演奏との拮抗で決定的に閃いた時には、書きたい題材、モチーフが本当に生きはじめたことを実感させるのであって、そういう喜びの体験こそが、創作というものを教えてくれる大きな機会の一つと言えるのである。
(小説家における創造プロセス)
創作衝動には二種の衝動がある。一つは、文学作品というものを書きたくてならない、憧憬と欲求不満が混合したような気持の蠢動である。その気持ちは、小説というものを書く以外に納まりようのないことを訴えてやまない。もう一つは、ある文学作品を書きたい気持ちの蠢動である。この場合には、既に書きたいことがある。モチーフ、つまり何故そのことを書きたいか、創作の動機が心を突き動かしている。その実感が鮮烈であればあるほど、創作意欲が掻き立てられる。創造力は具体的に作品を生み出す力のことで、創作衝動すなわち創造力ではないが、創作衝動がなければ創造力を示すことは不可能なのである。
・・・要するに、書きたいことの発見によって後者の意味での創作衝動(以下、この言葉は、すべてその意味)が発動するのである。ところが、それを発見する方法と言えるものはないのだ。ただ、文学作品の創作では、書きたいことは作者の心―精神に根ざしたものであってこそ、創作衝動はそれらしい力を示すのである。
例えば、自分の知っている人物でも、ひとの話で聞いた人物でも、誰でもよいが、ある人物のある行為を見るなり、聞くなりして、非常に興味を覚えたとする。それを作品に書きたいと思った時、<それ>は書きたいものなのか、書きたいことなのか。書きたいものと書きたいこととは丸でちがう。書きたいものとしてだけで書くのであれば、ただのお話にしかならない。その話をあれこれと作り変えても、作りものめいてゆくだけである。書きたいこと―自分の精神と切り結んだモチーフを得て創作衝動が発生している時には、事柄上はその話のままであっても、創造性が生まれて、ただのお話ではなくなる。あるいは、書きたいことから生じた想像力の支配によって、聞いた話とは全くちがうものになった作品には、作りものではなくて真実がある。また、ある人物の行為の話というような手がかりも、何かのヒントもなくて、突然モチーフを思いつく場合も勿論ある。そのモチーフが作者の精神に根ざしているものであれば、作品の具体的な構想はおのずから膨らんでゆくはずである。
(小説家における発想の転換や飛躍)
創作過程で終始、非常に意を用いるべきことは、モチーフの強い把握であり、その深く鋭い表現である。最も書きたいことは何か、どこに力点をおくべきか、とよく考えることで、その作品の創作の進め方がおのずから分かってくる。「筋」「起承転結」に囚われずに、転換も飛躍も自由に行えばよい。といっても、転換や飛躍が単なる思いつきや独りよがりであってはならない。モチーフの強い把握から促され、その深い鋭い表現のために生まれてきたものでなくてはならない。・・・導入部がしっかり書かれておれば、その作品で最も書きたいことは何か、どこに力点をおくべきかということが、その時もしっかり頭にあれば、導入部の<気配>が、次に書くべきブロック―つまり書きたいブロックを自然に告げ識らせてくれるのである。そして、そのブロックがモチーフの深い鋭い表現を担い得ておれば、そこから次のブロックが生まれてくる。先行のブロックとの間に飛躍や断絶があろうと(あるいはなくても)、「筋」「起承転結」指向ではあり得ない、本質的な脈略、呼応が存在する。
■岡本太郎『自分の中に毒を持て あなたは“常識人間を捨てられるか”』青春出版社(青春文庫)、1988年
(岡本太郎の逆説的発想法)
・・・ぼくはいつでも、あれかこれかという場合、これは自分にとってマイナスだな、危険だなと思う方を選ぶことにしている。誰だって人間は弱いし、自分が大事だから、逃げたがる。頭で考えて、いい方を選ぼうなんて思ってたら、何とかかんとか理屈をつけて安全な方に行ってしまうものなのだ。
かまわないから、こっちに行ったら駄目だ、と思う方に賭ける。
瀬戸内晴美はぼくに最初に会った頃、それを聞いてショックを受け、以来それを実行してきたと言っている。彼女はちゃんと食えているし、それ以上、堂々とやってるけれど、覚悟はそこにあるんだ。ほんとうに生きるっていうのは、そういうことだ。
(岡本太郎による非常識反転発想・メラキア的発想の例)
・まずくいった方が面白い
・失敗したらなお面白い
・つまらなかったらやめればいい
・三日坊主でかまわない
・三日坊主になるという“計画”をもったっていい
・うまくいくとか、いかないとか、そんなことはどうでもいい
・下手なら、むしろ下手こそいい
・行きづまったほうがおもしろい
・強くならなくていい
Posted by わくわくなひと at
18:55
│Comments(0)
2010年12月04日
深山幽谷の孤屋 妖艶な異次元の世界・・・泉鏡花「高野聖」
 泉鏡花『高野聖・眉かくしの霊』岩波文庫(2010年5月6日第86刷、1936年1月10日第1刷)。
泉鏡花『高野聖・眉かくしの霊』岩波文庫(2010年5月6日第86刷、1936年1月10日第1刷)。学生時代から一度は読みたいと思っていた小説。
飛騨から信州へ越える深山の間道で、丁度立休らおうという一本の木立も無い、右も左も山ばかりじゃ、手を伸ばすと達(とど)きそうな峰があると、その峰へ峰が乗り、嶺(いただき)が被さって、飛ぶ鳥も見えず、雲の形も見えぬ。
こんな深山幽谷のくだりからはじまり、旅僧の世界に引き込まれていく。この僧は深山の間道で蛇や山蛭に襲われながらも、山中の孤家にたどり着く。
そこで僧は女と出会う。
(何方(どなた)、)と納戸の方でいったのは女じゃから、南無三宝、この白い首には鱗が生えて、体は床を這って尾をずるずると引いて出ようと、また退った。
(おお、御坊様。)と立顕れたのは小造の美しい、声も清しい、ものやさしい。
昔風の美しい文章であり、読むのにやや集中力を必要とする。しかし、旅僧が女と出会ったところから、さらにもう一度、違う次元に引きずり込まれたような感覚に陥ってしまう。
妖艶な中年女の所作と、それに惑わされる僧の動きが見事。そのことを解説には「達せられようとして、刹那にはばまれる。・・・達せられぬ故に美しいのである。」と記してあった。
婦人(おんな)は何時(いつ)かもう米を精(しら)げ果てて、衣紋(えもん)の乱れた、乳の端もほの見ゆる、膨(ふく)らかな胸を反(そら)して立った、鼻高く口を結んで目を恍惚(うっとり)と上を向いて頂を仰いだが、月はなお反腹(はんぷく)のその累々(るいるい)たる巌(いわお)を照すばかり。
あり得る話ではないが、読む人に現実として迫ってくるような筆力に感服する。幾多の苦難を重ねながら、あちらの世界へ行き、再び元の世界に戻るという典型的な物語の構成になっている。
明治33年の作品。この調子だと、何度も読みかけて挫折している夏目漱石の『草枕』も、今ならじっくりと味わうことができるかも知れない。
Posted by わくわくなひと at
17:08
│Comments(6)
2010年12月03日
書くより書かないことの大切が伝わる大人の小説「切羽へ」
 井上荒野『切羽へ』新潮文庫(平成22年11月1日発行)。
井上荒野『切羽へ』新潮文庫(平成22年11月1日発行)。帯には「直木賞受賞作!」「どうしようもなく別の男に惹かれていく、夫を深く愛しながらも。」「繊細で官能的な大人の恋愛小説。」と書いてあった。
「明け方、夫に抱かれた。」から始まる。
このところ女性作家を続けて読んできたため、「あ!また・・・」と思い、しばらく読むのを抑えていた。
男性では書けないような官能小説だと思ったら、そうではなかった。“官能”をどうとらえるかだが、いわゆるエロではない。書きすぎていない。女性の揺れていく所作を繊細に描いた気品ある大人の小説だと思った。“抱かれた”という言葉を最初に読まされていたので、最後まで読んだところで、ずぅっと、“抱かれた”に引きずりこまれていた自分に気づいた。
山田詠美は「解説」でこう書いている。
「恋に落ちる時のめくるめくような思いは描かれない。その代わりに、二人の通じ合う際の何気ない所作が丹精を凝らして選び抜かれる。性よりも性的な、男と女のやり取り。・・・全編に渡って、書くより書かないことの大切さが伝わって来る。それは、行間を読ませるというような短絡的な技巧とは違う。井上荒野さんは、書いた言葉によって、書かない部分をより豊穣な言葉で埋め尽くす才能に長けた人だ。」
文章は小池真理子が好み。物語や登場人物は井上荒野がいい。ゆっくり話せる機会があるなら、井上さんと過ごしたいと思った。
全編にわたり北部九州弁の会話が繰り広げられる。たぶん長崎か?

Posted by わくわくなひと at
20:36
│Comments(4)
 歩道より少し高い位置、バスから天神コアのイルミネーションが見えました!
歩道より少し高い位置、バスから天神コアのイルミネーションが見えました!



