2010年01月31日
幸田文の『おとうと』と映画の『おとうと』
太い川がながれている。川に沿って葉桜の土手が長く道をのべている。こまかい雨が川面にも桜の葉にも土手の砂利にも音なくふりかかっている。ときどき川のほうから微かに風を吹き上げてくるので、雨と葉っぱは煽られて斜になるが、すぐまたまっすぐになる。ずっと見通す土手は点々とからかさ洋傘(こうもり)が続いて、みな向こうむきに歩く。朝はまだ早く、通学の学生と勤め人が村から町へ向けて出かけていくのである。
中村明さんの『名文』にとりあげてあった幸田文『おとうと』の文章の一部です。
映画のように場面が浮かんでくる文章と観察眼に憧れ、この本を読んでみたいと思っていました。もちろん自然描写だけでなく、中身がありそうな小説らしい。
そしたら、この小説を原作に市川監督が相当前に映画化し、それを山田洋次監督が敬意を払い今度、映画化したんですね。たぶん、スピルバーグも、この文章を読めば映画で表現すると思います。
二三日前から封切りされました。吉永小百合さんが姉役、弟が鶴瓶さん。吉永さん、いくつになってもきれいですね。
最近、なかなか映画のために時間をさく勇気がありませんが、行こうかな。それとも、『おとうと』を読んでみるか。山田監督はいつも期待に応えてくれるし・・・。

中村明さんの『名文』にとりあげてあった幸田文『おとうと』の文章の一部です。
映画のように場面が浮かんでくる文章と観察眼に憧れ、この本を読んでみたいと思っていました。もちろん自然描写だけでなく、中身がありそうな小説らしい。
そしたら、この小説を原作に市川監督が相当前に映画化し、それを山田洋次監督が敬意を払い今度、映画化したんですね。たぶん、スピルバーグも、この文章を読めば映画で表現すると思います。
二三日前から封切りされました。吉永小百合さんが姉役、弟が鶴瓶さん。吉永さん、いくつになってもきれいですね。
最近、なかなか映画のために時間をさく勇気がありませんが、行こうかな。それとも、『おとうと』を読んでみるか。山田監督はいつも期待に応えてくれるし・・・。

Posted by わくわくなひと at
14:35
│Comments(0)
2010年01月30日
途上国から世界に通用するブランドを・Motherhouse
28日(金)、アクロス福岡円形ホールで開催された「マザーハウスカレッジ」(福岡大学商学部主催?)に参加してきました。会場は満員。知った人の顔がちらほらしていて、地域社会の寄り合いを思い出してしまいました。
このカレッジでは、最貧国と言われるバングラディシュに自社工場を作り、そこから世界に通用するブランドを作っていこうとしている「Motherhouse」の副社長・山崎大祐さんの話を聞きました。
この会社はバングラディシュやネパールに工場を作って生産するだけでなく、商品企画・デザインから自社店舗での販売まで、すべて外注せずに自社で行っている会社ということです。大名の雁林町(がんりんのちょう)通りにある弊社事務所から、100㍍も離れていないところに、こんなすごい会社の店があることを、参加して初めて知りました。
企業理念は「途上国から世界に通用するブランドをつくる」です。この理念を見て、「オッ!」と閃くものがありましたので参加した次第です。というのも、私の会社では授産施設等の作業所で作られた製品の販売促進やネットショップを媒体とした販売業務を請け負っているからです。
このMotherhouseは、弱肉強食の資本主義体制に馴染まなかった途上国に着目した事業を展開されています。弊社は同様に日本国内で厳しい状況に置かれてきた地方や福祉分野の方々、そして障がいのある方々と、いっしょに仕事をさせていただいております。ただ、Motherhouseのように、しっかりした理念と筋書きがあったわけではありません。危ない会社の典型でしょうが、気づいたら、そうなっていたということです。
このカレッジで山崎副社長に「九州もある意味途上国であり、九州でいいものを作っていくアイデアは?」という質問が会場からありました。固定観念にとらわれなければ九州だけでなくたとえ東京や福岡などの都会の中にもMotherhouseのような会社がいくつも立ち上がっていくチャンスはいくらでもあると実感しました。山崎副社長は「モノを売ることは地域に関わることであり、その地域のことを真剣に考えろと社員に言っている」そうです。
カレッジのテーマは「社会性と経済性は両立するのか」でした。弊社でも少し言葉は違いますが、「障がい者の社会参加と授産施設等製品の売り上げアップは両立するのか」で議論、社員の一部では激論を重ねているようです。そういう意味で山崎副社長のお話は、感動的であり、不覚にも目頭が熱くなるものを感じてしまいました。
「社会性ということをご自身がどう位置づけられているのか」という問いに対し、山崎副社長は「社会性と経済性の両立は意味のない問いです。企業は社会から必要とされるから商品を提供する。教育関係は社会性があって、500円の定食屋は社会企業ではないのか。」と明快に回答されました。
「経済性と社会のはざまは賃金だと思う」という素晴らしく整理された質問もありました。
「経営者側から見れば給与を毎月払うのがいかに大変なことか。次の給与が払えるのかと何度も悩んできた。社会的な理想がなければ会社をやってはいけないなんて言いたくない。経済性を達成することがいかに大変なことか経営者は分かっている」との回答でした。別の質問に対して、「ビジネスの社会は本当戦争です。それに立ち向かうためには自分たちが強くなる意外にない。経済社会の暴力を知らないと社会貢献はできない」という回答もありました。
「続けていくためにはお金が必要。ある程度資金が必要だが、どうやって持続的に生きていくのか」という問いに対しては、「企業はキャッシュフローがすべて。リスクが高いビジネスをやっている。今はモノ余り金余りであり、お金はあるところにはある。組織のお金と個人のお金があり、組織にはルールがあり個人には哲学がある。個人の哲学は変わりにくいので法人からのお金を入れていない」そうです。ゴールドマンサックスご出身ですので、さすがです。
以上、カギ括弧の中の言葉は私がメモしたものですので不正確極まりないものです(悪しからず)。
私なりの結論は「社会性と経済性は両立するのか」ではなく、社会性と経済性のはざまで真剣に悩んでいくことが正しいし、持続性のある本物に近づく狭い道だということになりました。回答が簡単ではない狭い道だからこそ固定観念や常識を払拭することができるということです。キーワードは「○○でもかまわない」「○○のほうがむしろよい」という非常識な発想の自分自身への問いかけの繰り返しです。「障がい者の社会参加と授産施設等製品の売り上げアップ」のはざまで、腹を据えて考え抜きます。

このカレッジでは、最貧国と言われるバングラディシュに自社工場を作り、そこから世界に通用するブランドを作っていこうとしている「Motherhouse」の副社長・山崎大祐さんの話を聞きました。
この会社はバングラディシュやネパールに工場を作って生産するだけでなく、商品企画・デザインから自社店舗での販売まで、すべて外注せずに自社で行っている会社ということです。大名の雁林町(がんりんのちょう)通りにある弊社事務所から、100㍍も離れていないところに、こんなすごい会社の店があることを、参加して初めて知りました。
企業理念は「途上国から世界に通用するブランドをつくる」です。この理念を見て、「オッ!」と閃くものがありましたので参加した次第です。というのも、私の会社では授産施設等の作業所で作られた製品の販売促進やネットショップを媒体とした販売業務を請け負っているからです。
このMotherhouseは、弱肉強食の資本主義体制に馴染まなかった途上国に着目した事業を展開されています。弊社は同様に日本国内で厳しい状況に置かれてきた地方や福祉分野の方々、そして障がいのある方々と、いっしょに仕事をさせていただいております。ただ、Motherhouseのように、しっかりした理念と筋書きがあったわけではありません。危ない会社の典型でしょうが、気づいたら、そうなっていたということです。
このカレッジで山崎副社長に「九州もある意味途上国であり、九州でいいものを作っていくアイデアは?」という質問が会場からありました。固定観念にとらわれなければ九州だけでなくたとえ東京や福岡などの都会の中にもMotherhouseのような会社がいくつも立ち上がっていくチャンスはいくらでもあると実感しました。山崎副社長は「モノを売ることは地域に関わることであり、その地域のことを真剣に考えろと社員に言っている」そうです。
カレッジのテーマは「社会性と経済性は両立するのか」でした。弊社でも少し言葉は違いますが、「障がい者の社会参加と授産施設等製品の売り上げアップは両立するのか」で議論、社員の一部では激論を重ねているようです。そういう意味で山崎副社長のお話は、感動的であり、不覚にも目頭が熱くなるものを感じてしまいました。
「社会性ということをご自身がどう位置づけられているのか」という問いに対し、山崎副社長は「社会性と経済性の両立は意味のない問いです。企業は社会から必要とされるから商品を提供する。教育関係は社会性があって、500円の定食屋は社会企業ではないのか。」と明快に回答されました。
「経済性と社会のはざまは賃金だと思う」という素晴らしく整理された質問もありました。
「経営者側から見れば給与を毎月払うのがいかに大変なことか。次の給与が払えるのかと何度も悩んできた。社会的な理想がなければ会社をやってはいけないなんて言いたくない。経済性を達成することがいかに大変なことか経営者は分かっている」との回答でした。別の質問に対して、「ビジネスの社会は本当戦争です。それに立ち向かうためには自分たちが強くなる意外にない。経済社会の暴力を知らないと社会貢献はできない」という回答もありました。
「続けていくためにはお金が必要。ある程度資金が必要だが、どうやって持続的に生きていくのか」という問いに対しては、「企業はキャッシュフローがすべて。リスクが高いビジネスをやっている。今はモノ余り金余りであり、お金はあるところにはある。組織のお金と個人のお金があり、組織にはルールがあり個人には哲学がある。個人の哲学は変わりにくいので法人からのお金を入れていない」そうです。ゴールドマンサックスご出身ですので、さすがです。
以上、カギ括弧の中の言葉は私がメモしたものですので不正確極まりないものです(悪しからず)。
私なりの結論は「社会性と経済性は両立するのか」ではなく、社会性と経済性のはざまで真剣に悩んでいくことが正しいし、持続性のある本物に近づく狭い道だということになりました。回答が簡単ではない狭い道だからこそ固定観念や常識を払拭することができるということです。キーワードは「○○でもかまわない」「○○のほうがむしろよい」という非常識な発想の自分自身への問いかけの繰り返しです。「障がい者の社会参加と授産施設等製品の売り上げアップ」のはざまで、腹を据えて考え抜きます。

Posted by わくわくなひと at
22:58
│Comments(4)
2010年01月27日
思い当たることばかり・・・ドラッカー『経営者の条件』
ドラッカーの読書会が熊本でも始まりました。福岡では数年前から始まっており、私もたまに出ておりました。熊本では私も含め3人(経営者2人、公務員1人)に福岡のドラッカリアン1人に来てもらって、細々とですが4人で始めることになりました(まだ正式ではありませんが・・・)。
読書会は共通のドラッカーの著作(今回は『経営者の条件』の5章、6章、終章)を読んで線を引き、感想や疑問点を出し合うだけです。いろんな立場の人から、いろんな意見が聞けて、けっこうためになります。
以下は、今日の読書会のための私のメモです。
経営者となって三年目、人生で言えばまだ保育園の年少さんですが、「■訳者あとがき」に書いてあるように「思い当たることばかり」です。
■意思決定とは何か。
・「組織構造のための新しい理念を考え出」し、「決定においては何が正しいかを考えなければならない」。「何が受け入れられやすいか」からスタートしても得るところはない。
・事実、決定の実行が具体的な手順として誰か特定の人の仕事と責任になるまでは、いかなる決定も行われていないに等しい。それまでは意図があるだけである。
・軍では決定を行った者が自分で出かけて確かめることが唯一の信頼できるフィードバックであることを知っている。
■成果をあげる意思決定とは。
・「はるかに多いのは、一方が他方よりもたぶん正しいだろうとさえいえない二つの行動からの選択である。」・・・確かにいつもそうです。
・「決定において最も重要なことは、意見の不一致が存在しないときには決定を行うべきではない」。・・・これには驚いたが、会社の未来を創造する経営者は「意図的に意見の不一致をつくり」あげなければならない。
・「よい外科医が不要な手術を行わないように、不要な決定を行ってはならない。」。そうだと思う。短気を起こさず待つことも大事。もちろん「二股をかけたり両者の間をとろうとしたりしてはならない。」
・「一般的に成果を上げる決定は苦い。」・・・そうだ!私の言葉で言えば、「行くも地獄、残るも地獄」ということが日常だ。
・「一○回に一回は突然真夜中に目が覚め」・・・これも経験した。そして、朝の4時に決定して動きだしたことがあった。
■成果を上げる能力を修得せよ。
・「成果をあげることは教科ではなく修練である。」・・・経営もそうだと思う。
・「強みを生かすということは行動することである。人すなわち自らと他人を敬うということである。」・・・強み・弱みSWOTがどうもしっくり理解できなかったが、この言葉は深いと思う。
・「発展させるべきものは、情報ではなく、洞察、自立、勇気など人に関わるものである。・・・持続的なリーダーシップ、献身、決断、目的意識によるリーダーシップである。」・・・特にこれが必要と思う。
年中さんに向け「広くてはっきりした道は存在しない」。だから「責任ある判断を行えるよう自らを育て磨」いていきたいと思います。

読書会は共通のドラッカーの著作(今回は『経営者の条件』の5章、6章、終章)を読んで線を引き、感想や疑問点を出し合うだけです。いろんな立場の人から、いろんな意見が聞けて、けっこうためになります。
以下は、今日の読書会のための私のメモです。
経営者となって三年目、人生で言えばまだ保育園の年少さんですが、「■訳者あとがき」に書いてあるように「思い当たることばかり」です。
■意思決定とは何か。
・「組織構造のための新しい理念を考え出」し、「決定においては何が正しいかを考えなければならない」。「何が受け入れられやすいか」からスタートしても得るところはない。
・事実、決定の実行が具体的な手順として誰か特定の人の仕事と責任になるまでは、いかなる決定も行われていないに等しい。それまでは意図があるだけである。
・軍では決定を行った者が自分で出かけて確かめることが唯一の信頼できるフィードバックであることを知っている。
■成果をあげる意思決定とは。
・「はるかに多いのは、一方が他方よりもたぶん正しいだろうとさえいえない二つの行動からの選択である。」・・・確かにいつもそうです。
・「決定において最も重要なことは、意見の不一致が存在しないときには決定を行うべきではない」。・・・これには驚いたが、会社の未来を創造する経営者は「意図的に意見の不一致をつくり」あげなければならない。
・「よい外科医が不要な手術を行わないように、不要な決定を行ってはならない。」。そうだと思う。短気を起こさず待つことも大事。もちろん「二股をかけたり両者の間をとろうとしたりしてはならない。」
・「一般的に成果を上げる決定は苦い。」・・・そうだ!私の言葉で言えば、「行くも地獄、残るも地獄」ということが日常だ。
・「一○回に一回は突然真夜中に目が覚め」・・・これも経験した。そして、朝の4時に決定して動きだしたことがあった。
■成果を上げる能力を修得せよ。
・「成果をあげることは教科ではなく修練である。」・・・経営もそうだと思う。
・「強みを生かすということは行動することである。人すなわち自らと他人を敬うということである。」・・・強み・弱みSWOTがどうもしっくり理解できなかったが、この言葉は深いと思う。
・「発展させるべきものは、情報ではなく、洞察、自立、勇気など人に関わるものである。・・・持続的なリーダーシップ、献身、決断、目的意識によるリーダーシップである。」・・・特にこれが必要と思う。
年中さんに向け「広くてはっきりした道は存在しない」。だから「責任ある判断を行えるよう自らを育て磨」いていきたいと思います。

Posted by わくわくなひと at
21:39
│Comments(0)
2010年01月26日
ビルの上に巨大物体出現?
ビルの上に変なオブジェが載っかっている。
実は某飲料メーカーの本社ビルなんです。
同僚がそのビルに用事で行きました。帰りがおぼつかないということで、浅草まで迎えに行った時に撮りました。
せっかく浅草まで出向いたので、夜の浅草寺詣をしたところで、大学時代の友人から電話(おかしい。私が東京にいることは、仕事関係者以外誰にも伝えていない)!
何やら数人の同級生が渋谷で飲んでいるとのことで、渋谷ハチ公前で合流することに。
地下鉄銀座線の始発駅である浅草駅から終点の渋谷駅まで。まるで“鉄ちゃん”のような鉄道旅をしてしまいました。
ハチ公前からはいきなりタクシーで六本木に直行。「THE BEATLES LIVE CAVERN CLUB」に行きました。六本木交差点から芋洗坂を降りていき、次の小さな交差点を左に上がり途中で右折したところにあります。途中、売人にはご用心。
クラブはビートルズナンバーのオンパレード。私のような中高年の男性グループもいましたが、20から30歳代の女性が結構陶酔していました。
お酒は某飲料メーカーの展望ラウンジから飲み始め、六本木のクラブでは山崎の10年ものを飲みました。しかし、つまみはポテトチップスやフレンチフライ程度しか食べていません。
昨日、今日と、東京ではうまい食べ物にありつけませんでした。やっぱ食べ物は九州だね。


実は某飲料メーカーの本社ビルなんです。
同僚がそのビルに用事で行きました。帰りがおぼつかないということで、浅草まで迎えに行った時に撮りました。
せっかく浅草まで出向いたので、夜の浅草寺詣をしたところで、大学時代の友人から電話(おかしい。私が東京にいることは、仕事関係者以外誰にも伝えていない)!
何やら数人の同級生が渋谷で飲んでいるとのことで、渋谷ハチ公前で合流することに。
地下鉄銀座線の始発駅である浅草駅から終点の渋谷駅まで。まるで“鉄ちゃん”のような鉄道旅をしてしまいました。
ハチ公前からはいきなりタクシーで六本木に直行。「THE BEATLES LIVE CAVERN CLUB」に行きました。六本木交差点から芋洗坂を降りていき、次の小さな交差点を左に上がり途中で右折したところにあります。途中、売人にはご用心。
クラブはビートルズナンバーのオンパレード。私のような中高年の男性グループもいましたが、20から30歳代の女性が結構陶酔していました。
お酒は某飲料メーカーの展望ラウンジから飲み始め、六本木のクラブでは山崎の10年ものを飲みました。しかし、つまみはポテトチップスやフレンチフライ程度しか食べていません。
昨日、今日と、東京ではうまい食べ物にありつけませんでした。やっぱ食べ物は九州だね。



Posted by わくわくなひと at
22:30
│Comments(0)
2010年01月24日
文学者のような文章で語る歴史家・中島岳志
最近は歴史ブームだと言われる。昨年は“歴女”などの言い方も流行ったし、今年はあちこちで福山雅治の龍馬の姿を見かけるようになった。司馬遼太郎も再びブームだ。私の場合、周辺から司馬ファンとして認知されていることもあり、「竜馬がいく。読み出したら、結構面白いね」「坂の上の雲。緻密な描写がすごい!」など、よく耳にするようになった。
識者によれば、先が見通せない時に、人は歴史に関心を持つという。そう言われてみれば、国内外で極めてダイナミックな動きが見られ、今までとは違う世の中になってしまうかも知れない、今までの常識が通用しない世界になるかもしれないなど、半分不安な気持ちになってしまいがちである。もちろん、福山雅治のイケメンぶりが、それに拍車をかけているのだろうけど・・・。
しかし、いつまでも司馬遼太郎さんにネタを頼っているわけにはいかない。司馬さんが文章を書いた時と、国の成熟度合いも違うし、外交関係も中国やアジアの台頭により、大きな変化を見せてきている。
今の世の中がどうなっていくのかを考える際に、新たな状況の中で事実の発掘や解釈をする歴史家が必要とされている。
23日付けの西日本新聞に、北海道大学準教授の中島岳志さんが紹介されていた。北海道に住みながら九州にゆかりのある人物についての論文や著書が多い。このことが、西日本新聞がわざわざ取材した理由だろう。
しかし、記事を読んで驚いた。九州にゆかりのある人物を調べているということよりも、今の時代が要請している歴史家であることが分かったからである。
大佛次郎論壇賞を受賞した『中村屋のボース』の「ラース・ビハーリー・ボースは頭山満ら旧福岡藩士が中心となった政治団体「玄洋社」と関係が深かった」という。昨年出版した『朝日平吾の鬱屈』も佐賀県佐世保市で育った国粋主義者の生涯を追っているという。
私自身、30年ほど前は史学科の日本近代史専攻の学生だったので、右翼も左翼もなく、いろんな本を読んでいた。当時は左翼の本はまだ人前でも読みやすかったが、右翼の人を扱った本や資料は周りの人から勘違いされないか心配だったことをおぼえている。しかし、中島氏は橋川文三や竹内好といった思想家たちの「左や右といった思想的立場と関係なく、一方を断罪せずに内在的に理解を深めながら問題を探っていく手法に引かれた」と書いてある。今求められている新たな解釈や視点は、このような態度から生まれてくるのではなかろうか。
史学科の学生の時、“司馬遼太郎”は評価されていなかった。「あれは小説。歴史学は事実を探求する科学である」という理由からである。
しかし、中島さんの文章は、次の通りだと、西日本新聞に書いてあった。
「朝日-」は神奈川県・大磯の次のような描写で始まる。
<大磯の空は広い。海岸には、サーフィンを楽しむ若者があふれ、山側には閑静な住宅地が広がる>
文体も学者というよりは、文学者やジャーナリストのそれに近い。学者の文章としては「軽い」とみる向きもあるかもしれないが、平易な文章で読者に分かりやすく切り込んでくるのが彼の魅力でもある。
さっそく「中村屋のボース」と「朝日平吾の鬱屈」をアマゾンで注文してしまった。

識者によれば、先が見通せない時に、人は歴史に関心を持つという。そう言われてみれば、国内外で極めてダイナミックな動きが見られ、今までとは違う世の中になってしまうかも知れない、今までの常識が通用しない世界になるかもしれないなど、半分不安な気持ちになってしまいがちである。もちろん、福山雅治のイケメンぶりが、それに拍車をかけているのだろうけど・・・。
しかし、いつまでも司馬遼太郎さんにネタを頼っているわけにはいかない。司馬さんが文章を書いた時と、国の成熟度合いも違うし、外交関係も中国やアジアの台頭により、大きな変化を見せてきている。
今の世の中がどうなっていくのかを考える際に、新たな状況の中で事実の発掘や解釈をする歴史家が必要とされている。
23日付けの西日本新聞に、北海道大学準教授の中島岳志さんが紹介されていた。北海道に住みながら九州にゆかりのある人物についての論文や著書が多い。このことが、西日本新聞がわざわざ取材した理由だろう。
しかし、記事を読んで驚いた。九州にゆかりのある人物を調べているということよりも、今の時代が要請している歴史家であることが分かったからである。
大佛次郎論壇賞を受賞した『中村屋のボース』の「ラース・ビハーリー・ボースは頭山満ら旧福岡藩士が中心となった政治団体「玄洋社」と関係が深かった」という。昨年出版した『朝日平吾の鬱屈』も佐賀県佐世保市で育った国粋主義者の生涯を追っているという。
私自身、30年ほど前は史学科の日本近代史専攻の学生だったので、右翼も左翼もなく、いろんな本を読んでいた。当時は左翼の本はまだ人前でも読みやすかったが、右翼の人を扱った本や資料は周りの人から勘違いされないか心配だったことをおぼえている。しかし、中島氏は橋川文三や竹内好といった思想家たちの「左や右といった思想的立場と関係なく、一方を断罪せずに内在的に理解を深めながら問題を探っていく手法に引かれた」と書いてある。今求められている新たな解釈や視点は、このような態度から生まれてくるのではなかろうか。
史学科の学生の時、“司馬遼太郎”は評価されていなかった。「あれは小説。歴史学は事実を探求する科学である」という理由からである。
しかし、中島さんの文章は、次の通りだと、西日本新聞に書いてあった。
「朝日-」は神奈川県・大磯の次のような描写で始まる。
<大磯の空は広い。海岸には、サーフィンを楽しむ若者があふれ、山側には閑静な住宅地が広がる>
文体も学者というよりは、文学者やジャーナリストのそれに近い。学者の文章としては「軽い」とみる向きもあるかもしれないが、平易な文章で読者に分かりやすく切り込んでくるのが彼の魅力でもある。
さっそく「中村屋のボース」と「朝日平吾の鬱屈」をアマゾンで注文してしまった。

Posted by わくわくなひと at
14:27
│Comments(0)
2010年01月23日
さよならウェンディーズ!
いや~まったく知りませんでした。
福岡を含む全国のウェンディーズが昨年末でなくなっていたんですね。
昨日、件の女性社長のお招きで新年会に参加しました。
「ウェンディーズ好きだったのに」「チリビーンズはもう食えなくなるのか」
「え!みんなもウェンディーズファンだったとぅ?」など、店がなくなったという話でもちきりでした。
純朴なアメリカの女の子マーク。そして、オールドファッションスタイルのハンバーガー、そして人気メニューのチリビーンズ。
私も大好きでしたが、少なくともほかに4、5人の大ファンがいたことに驚きでした。そして、密かに今日の昼飯はウェンディーズを決めていたのに、行く店はもうない。去年の12月も行ったのに、そんなことにはまったく気づきませんでした。
79年から80年にかけて米国におりました。その時、数あるハンバーガー屋さんの中で一番ウェンディーズが好きでした。理由はパティ、レタス、オニオン、トマトなどを好きなだけ自分で選んで食べられるセミオーダー方式だったからです。もちろん、ケチャップやマスタードも自分で好きなだけ用意することができる方式です。
確か81年ごろ東京・新宿の東口にウェンディーズが日本で初めてオープンしたので、喜んで訪ねたことを思い出しました。アメリカのウェンディーズそのもの。床はニューイングランド風の絨毯敷き、もちろんセミオーダー方式でした。
確かに、この方式は非効率ですが、ハンバーガーにおいしさを求めるなら、これですよね。
しかし、マクドナルドとの競争を考えれば既製品にせざるを得なかったのでしょう。福岡に店が出来るころは、マクドと同じく既製品のメニューから客が選ぶ方式に代わっていました。
それでも、店の一部は絨毯敷き、メニューもオールドファッションスタイル、それにアメリカ人の生活には欠かせないチリビーンズもありました。
残念です。もうアメリカに行かないとお目にかかれません。
福岡を含む全国のウェンディーズが昨年末でなくなっていたんですね。
昨日、件の女性社長のお招きで新年会に参加しました。
「ウェンディーズ好きだったのに」「チリビーンズはもう食えなくなるのか」
「え!みんなもウェンディーズファンだったとぅ?」など、店がなくなったという話でもちきりでした。
純朴なアメリカの女の子マーク。そして、オールドファッションスタイルのハンバーガー、そして人気メニューのチリビーンズ。
私も大好きでしたが、少なくともほかに4、5人の大ファンがいたことに驚きでした。そして、密かに今日の昼飯はウェンディーズを決めていたのに、行く店はもうない。去年の12月も行ったのに、そんなことにはまったく気づきませんでした。
79年から80年にかけて米国におりました。その時、数あるハンバーガー屋さんの中で一番ウェンディーズが好きでした。理由はパティ、レタス、オニオン、トマトなどを好きなだけ自分で選んで食べられるセミオーダー方式だったからです。もちろん、ケチャップやマスタードも自分で好きなだけ用意することができる方式です。
確か81年ごろ東京・新宿の東口にウェンディーズが日本で初めてオープンしたので、喜んで訪ねたことを思い出しました。アメリカのウェンディーズそのもの。床はニューイングランド風の絨毯敷き、もちろんセミオーダー方式でした。
確かに、この方式は非効率ですが、ハンバーガーにおいしさを求めるなら、これですよね。
しかし、マクドナルドとの競争を考えれば既製品にせざるを得なかったのでしょう。福岡に店が出来るころは、マクドと同じく既製品のメニューから客が選ぶ方式に代わっていました。
それでも、店の一部は絨毯敷き、メニューもオールドファッションスタイル、それにアメリカ人の生活には欠かせないチリビーンズもありました。
残念です。もうアメリカに行かないとお目にかかれません。

Posted by わくわくなひと at
13:49
│Comments(0)
2010年01月21日
熊本が州都を目指すには?・・・熊日新聞を読んで
今日、つまり21日付けの熊本日日新聞を読みました。
一面に福岡の吉田市長のインタビュー記事が載っていました。
熊本では、蒲島知事を先頭に州都論議が盛んです。
熊本で「州都を熊本に」という声があることに対し、吉田市長は「熊本の方がそうおっしゃるのではそれはそれでいいのでは。ただ福岡の人たちはそもそも(福岡市の州都で)議論の余地はないと思っている」と認識されているようです(発言のニュアンスが今ひとつ分かりませんが・・・)。
私の知り合いの中に、福岡市役所の方など福岡の方々がたくさんおられますが、州都論議をしたことはまったくありません。ただ、話題の中心はほとんどが九州全体に関わることや、もちろん福岡のこと、それに熊本、長崎、大分、鹿児島、宮崎など他県のこともけっこう時間を割いています。
吉田市長も「人口が減る中、福岡だけが成長できるとは思っていない。福岡の富の源泉は九州全域。福岡は九州全体のことを考えなくてはいけないと思っている」と語っています。
福岡の方々は、仕事や個人的な趣味の分野でも、九州全体の方々との関わりがものすごく強いようです。それに、もう少し東の山口や広島の方々との交流もけっこうあります(もちろん、人それぞれで博多の町一筋の方などもおられますが・・・)。
熊本が州都になるためには、熊本の方々が、熊本を熱心に語るように九州のことを語るようにならないと、九州全体が「州都は熊本」という気運にならないのではないかと思います。
おそらく九州各県の人の意見を聞いて州都は決定されると思います。熊日新聞にも、九州の他県での大きな出来事を常に一面に持ってくるようにしてもらえば、熊本人が九州を語るようになるのではないかと思っています(新聞社の競争戦略としてみれば危ういかも知れませんが・・・)。
一面下の「新生面」でも「州都」に関わるコラムが掲載されていました。
『州都を目指し、「品格あるくまもと」になるにはどうしたらよいか。』『熊本市には、街のデザインの大本となる熊本城がある。黒、白、石垣、緑・・・。』などです。
熊本と福岡の間にある大牟田の複数の人が、「福岡より熊本の街が好き」と言ってます。その理由は街の真ん中に「品格あるくまもと」の象徴である熊本城があるからです。これはヨーロッパの品格ある都市と比べても遜色ないと思います。
この熊本城を中心とした「品格あるくまもと」と併せて、自分のところだけでなく他地域にも関心を示す心(意識)の品格も必要だと個人的には思います。
地域間交流が数倍になる九州新幹線全線開通が、心の品格づくりのきっかけになることを願っています。

一面に福岡の吉田市長のインタビュー記事が載っていました。
熊本では、蒲島知事を先頭に州都論議が盛んです。
熊本で「州都を熊本に」という声があることに対し、吉田市長は「熊本の方がそうおっしゃるのではそれはそれでいいのでは。ただ福岡の人たちはそもそも(福岡市の州都で)議論の余地はないと思っている」と認識されているようです(発言のニュアンスが今ひとつ分かりませんが・・・)。
私の知り合いの中に、福岡市役所の方など福岡の方々がたくさんおられますが、州都論議をしたことはまったくありません。ただ、話題の中心はほとんどが九州全体に関わることや、もちろん福岡のこと、それに熊本、長崎、大分、鹿児島、宮崎など他県のこともけっこう時間を割いています。
吉田市長も「人口が減る中、福岡だけが成長できるとは思っていない。福岡の富の源泉は九州全域。福岡は九州全体のことを考えなくてはいけないと思っている」と語っています。
福岡の方々は、仕事や個人的な趣味の分野でも、九州全体の方々との関わりがものすごく強いようです。それに、もう少し東の山口や広島の方々との交流もけっこうあります(もちろん、人それぞれで博多の町一筋の方などもおられますが・・・)。
熊本が州都になるためには、熊本の方々が、熊本を熱心に語るように九州のことを語るようにならないと、九州全体が「州都は熊本」という気運にならないのではないかと思います。
おそらく九州各県の人の意見を聞いて州都は決定されると思います。熊日新聞にも、九州の他県での大きな出来事を常に一面に持ってくるようにしてもらえば、熊本人が九州を語るようになるのではないかと思っています(新聞社の競争戦略としてみれば危ういかも知れませんが・・・)。
一面下の「新生面」でも「州都」に関わるコラムが掲載されていました。
『州都を目指し、「品格あるくまもと」になるにはどうしたらよいか。』『熊本市には、街のデザインの大本となる熊本城がある。黒、白、石垣、緑・・・。』などです。
熊本と福岡の間にある大牟田の複数の人が、「福岡より熊本の街が好き」と言ってます。その理由は街の真ん中に「品格あるくまもと」の象徴である熊本城があるからです。これはヨーロッパの品格ある都市と比べても遜色ないと思います。
この熊本城を中心とした「品格あるくまもと」と併せて、自分のところだけでなく他地域にも関心を示す心(意識)の品格も必要だと個人的には思います。
地域間交流が数倍になる九州新幹線全線開通が、心の品格づくりのきっかけになることを願っています。

Posted by わくわくなひと at
15:02
│Comments(0)
2010年01月19日
人をまるごとまいらせる文章とは・・・『名文』を読む
森沢明夫の小説を読んで、その美しい文章に感動した。そして、自分はどのような文章に感動するのか知りたくなってしまった。
そういういきさつで購入したのが、中村明『名文』ちくま学芸文庫(1999年8月25日第七刷)である。なるほど、いわゆる「名文」と言われる文章の一部が50も掲載されており、その秘密が紐解いてある。素直に、なるほどと思うし、すごい分析だと思った。美しい文章に感動すること(名文を読んだ時の刺激と反応)を、「ある人がある意図を持ってある形でおこなった表現によって、別のある人が刺激を受け、そこに積極的に参加する過程で起こる精神上の変化の総体」だと説明している。
まだ私が社会人になりたての頃、“分かりやすい”ということが金科玉条のような職場で長く過ごした。確かに“分かりやすい”ということは文章を書く上で一つの基本だろう。しかし、“分かりやすい”ということを余りにも強調してしまうと、文章の書き手の頭の中まで単純になってしまうのではないか?と思い続けてきた。文章の対象になる人の心や世の中の動きなどは、もっと複雑怪奇である。このため書き手は、書く対象を変に単純化するのではなく、真摯に向き合って書きつづっていくことが理想ではなかろうか!と小さくささやいてきた。
この本に、「間違いのない、ただ通じるだけの文章に、人は感動しない。」「名文とは、人をまるごとまいらせる文章だ」と書いてあった。
そんな文章は簡単に書けるものではないし、たぶん一生書けないだろう。しかし、そんな文章や本に少しでも多く出会いたいと強く思う。
50の名文に接して気づいたことがあった。名文を書く人は耳や目からだけの情報で書いていない。触覚、嗅覚、味覚も含めた五感を総動員して、書く対象と向き合っている。それに、だれも気づかないで通り過ぎてしまうようなことを捉えてしまう個性的な着眼点を持っている人たちが名文書きである。捉えたことを、別の人に刺激として伝え積極的に参加させてしまう表現力(確かな観察と内面描写など)も兼ね備えている。
死ぬまでに、少しでも多くの“まいってしまう”文章に出会いたい。
以下は50の名文のうち、読んでみたいと思った作品である。
・坪田譲治『風の中の子供』(昭和11年)
・掘辰雄『風立ちぬ』(昭和11~13年)・・・昔、読了
・網野菊『風呂敷』(昭和15年)
・永井龍男『風ふたたび』(昭和26年)
・小林信夫『小銃』(昭和27年)
・串田孫一『秋の組曲』(昭和29年)
・幸田文『おとうと』(昭和31~32年)
・円地文子『妖』(昭和31年)
・丸谷宰才一『笹まくら』(昭和41年)
・小沼丹『懐中時計』(昭和43年)
・阿部昭『大いなる日』(昭和44年)
・田宮虎彦『沖縄の手記から』(昭和47年)
・宮本輝『螢川』(昭和52年)・・・昔、読了

そういういきさつで購入したのが、中村明『名文』ちくま学芸文庫(1999年8月25日第七刷)である。なるほど、いわゆる「名文」と言われる文章の一部が50も掲載されており、その秘密が紐解いてある。素直に、なるほどと思うし、すごい分析だと思った。美しい文章に感動すること(名文を読んだ時の刺激と反応)を、「ある人がある意図を持ってある形でおこなった表現によって、別のある人が刺激を受け、そこに積極的に参加する過程で起こる精神上の変化の総体」だと説明している。
まだ私が社会人になりたての頃、“分かりやすい”ということが金科玉条のような職場で長く過ごした。確かに“分かりやすい”ということは文章を書く上で一つの基本だろう。しかし、“分かりやすい”ということを余りにも強調してしまうと、文章の書き手の頭の中まで単純になってしまうのではないか?と思い続けてきた。文章の対象になる人の心や世の中の動きなどは、もっと複雑怪奇である。このため書き手は、書く対象を変に単純化するのではなく、真摯に向き合って書きつづっていくことが理想ではなかろうか!と小さくささやいてきた。
この本に、「間違いのない、ただ通じるだけの文章に、人は感動しない。」「名文とは、人をまるごとまいらせる文章だ」と書いてあった。
そんな文章は簡単に書けるものではないし、たぶん一生書けないだろう。しかし、そんな文章や本に少しでも多く出会いたいと強く思う。
50の名文に接して気づいたことがあった。名文を書く人は耳や目からだけの情報で書いていない。触覚、嗅覚、味覚も含めた五感を総動員して、書く対象と向き合っている。それに、だれも気づかないで通り過ぎてしまうようなことを捉えてしまう個性的な着眼点を持っている人たちが名文書きである。捉えたことを、別の人に刺激として伝え積極的に参加させてしまう表現力(確かな観察と内面描写など)も兼ね備えている。
死ぬまでに、少しでも多くの“まいってしまう”文章に出会いたい。
以下は50の名文のうち、読んでみたいと思った作品である。
・坪田譲治『風の中の子供』(昭和11年)
・掘辰雄『風立ちぬ』(昭和11~13年)・・・昔、読了
・網野菊『風呂敷』(昭和15年)
・永井龍男『風ふたたび』(昭和26年)
・小林信夫『小銃』(昭和27年)
・串田孫一『秋の組曲』(昭和29年)
・幸田文『おとうと』(昭和31~32年)
・円地文子『妖』(昭和31年)
・丸谷宰才一『笹まくら』(昭和41年)
・小沼丹『懐中時計』(昭和43年)
・阿部昭『大いなる日』(昭和44年)
・田宮虎彦『沖縄の手記から』(昭和47年)
・宮本輝『螢川』(昭和52年)・・・昔、読了

Posted by わくわくなひと at
21:33
│Comments(0)
2010年01月18日
どこにでもあるメニューだからこそ違いが分かる!
二ヶ月ぶりくらいに、川を渡り、博多部に行った。
福岡部に事務所がある私は、年に数えるほどしか博多の街には行かない。
年末の忘年会も川を渡る一歩手前の春吉止まり。中洲とも縁がない。
博多の街に遊びに行くのは、決まって川端商店街の「せいもん払い」の料理を楽しむため。
いつ行っても、「幸せ!」という言葉が浮かんでくる。
どこがどう違うのか。そんな気持ちを晴らそうと、今回はどこにでもあるメニューを頼んでみた。
最初、福岡では定番メニューである「ごまさば」を頼む。何やら豊後水道でとれたサバらしく、実に太った脂満点のゴマサバが出てくる。「ぅうまい!」。
次に「めざし」はどうか。オスとメスがセットで皿に盛られて出てくる。これもやせ細っていない。「うまい!」。
まひとつ!「豚ばら」。脂が光り美しい。いおうて三度で「ポテトサラダ」はどうだ!このオブジェ風のしつらえが、何とも食欲をそそる。
もちろん、辛口の日本酒を冷やでいただき、間をとることを忘れるわけがない。
「あ~幸せ幸せ!」「祝いめでたの若松さま~よ。枝も栄えりゃ葉もしゅげる。」という気分で、再び川を渡る。無事、その日の22時ころには福岡部の大名に戻ってきた。
皆様、ありがとうございます!こうして酒が飲めるのは、お客様や社員様のお陰です。



福岡部に事務所がある私は、年に数えるほどしか博多の街には行かない。
年末の忘年会も川を渡る一歩手前の春吉止まり。中洲とも縁がない。
博多の街に遊びに行くのは、決まって川端商店街の「せいもん払い」の料理を楽しむため。
いつ行っても、「幸せ!」という言葉が浮かんでくる。
どこがどう違うのか。そんな気持ちを晴らそうと、今回はどこにでもあるメニューを頼んでみた。
最初、福岡では定番メニューである「ごまさば」を頼む。何やら豊後水道でとれたサバらしく、実に太った脂満点のゴマサバが出てくる。「ぅうまい!」。
次に「めざし」はどうか。オスとメスがセットで皿に盛られて出てくる。これもやせ細っていない。「うまい!」。
まひとつ!「豚ばら」。脂が光り美しい。いおうて三度で「ポテトサラダ」はどうだ!このオブジェ風のしつらえが、何とも食欲をそそる。
もちろん、辛口の日本酒を冷やでいただき、間をとることを忘れるわけがない。
「あ~幸せ幸せ!」「祝いめでたの若松さま~よ。枝も栄えりゃ葉もしゅげる。」という気分で、再び川を渡る。無事、その日の22時ころには福岡部の大名に戻ってきた。
皆様、ありがとうございます!こうして酒が飲めるのは、お客様や社員様のお陰です。




Posted by わくわくなひと at
20:30
│Comments(2)
2010年01月17日
ジューシーな肉がうまい!佐世保ログキットUSバーガー
先週は仕事で佐世保方面に2回も行きましたので、ハンバーガー三昧でした。
熊本、福岡、久留米、大牟田で言えば、個性的なラーメン屋さんが街のあちこちにあります。
佐世保では、そんな感じで、街のあちこちにハンバーガー屋さんがあるんですね。各店がアメリカでよく見る赤や黄色で装飾されているので、マクドナルドもありますが、そんなに目立たない。
そういった事情で昼は同僚と決まってハンバーガーを食べてしまいました。
その中でも、特に印象深かったのが「ログキット本店」の「USバーガー」です。
パティ、つまり肉がジューシーでおいしい。肉好きの私としては、ぱさぱさしたパティは×。肉汁を感じないと満足しません。
うまかったなぁ!それと、この店は米軍キャンプのすぐ近くにあるからか、アメリカの雰囲気そのまま。店の備品もそうですが、タバスコなんかも超ビッグ。客も兵隊さんでしょうか、アメリカ人がふつうに出入りしている感じです。
芸能人にも有名らしく、テレビで見るような人の写真が少なくとも50人分くらい貼ってありました。

熊本、福岡、久留米、大牟田で言えば、個性的なラーメン屋さんが街のあちこちにあります。
佐世保では、そんな感じで、街のあちこちにハンバーガー屋さんがあるんですね。各店がアメリカでよく見る赤や黄色で装飾されているので、マクドナルドもありますが、そんなに目立たない。
そういった事情で昼は同僚と決まってハンバーガーを食べてしまいました。
その中でも、特に印象深かったのが「ログキット本店」の「USバーガー」です。
パティ、つまり肉がジューシーでおいしい。肉好きの私としては、ぱさぱさしたパティは×。肉汁を感じないと満足しません。
うまかったなぁ!それと、この店は米軍キャンプのすぐ近くにあるからか、アメリカの雰囲気そのまま。店の備品もそうですが、タバスコなんかも超ビッグ。客も兵隊さんでしょうか、アメリカ人がふつうに出入りしている感じです。
芸能人にも有名らしく、テレビで見るような人の写真が少なくとも50人分くらい貼ってありました。


Posted by わくわくなひと at
18:09
│Comments(2)
2010年01月13日
モデルは誰か?・・・長部日出雄『「阿修羅像」の真実』文春新書
太宰府で「阿修羅像」を拝観して以来、写真を見ただけで反応するようになってしまった。
顔は三面あるが、もちろん正面の表情に、どうしても反応してしまう。それも、かつて青年期に経験していた感情が蘇ってしまうのである。
年末の書店でも同様の経験をしてしまった。帯に「阿修羅像」の写真が載っていたからである。最初は買うつもりはなかったが、別の本を購入した後、やっぱり買うことにした。
「日本人にもっとも愛された仏像のモデルは誰か-?」というテーマで書かれた本である。
何冊かの解説書を読んだが、多くは「少年」とされており、少数の説が「少女」とされている。そして、光明皇后という説もある。法隆寺論で有名な哲学者、梅原猛さんも、確か光明皇后がモデルであることをほのめかしていたような記憶がある。
個人的にモデルは女性であってほしいという願望もある。
この本は光明皇后がモデルであることを主張している。いろんな文献を参考に光明皇后のことが詳しく書かれている。
ただ、「これで決まりだ!」と思うほどの説得力はなかった。
個人的にも、「そうであって欲しい」と思うし、その方が、心が落ち着くというものである。

顔は三面あるが、もちろん正面の表情に、どうしても反応してしまう。それも、かつて青年期に経験していた感情が蘇ってしまうのである。
年末の書店でも同様の経験をしてしまった。帯に「阿修羅像」の写真が載っていたからである。最初は買うつもりはなかったが、別の本を購入した後、やっぱり買うことにした。
「日本人にもっとも愛された仏像のモデルは誰か-?」というテーマで書かれた本である。
何冊かの解説書を読んだが、多くは「少年」とされており、少数の説が「少女」とされている。そして、光明皇后という説もある。法隆寺論で有名な哲学者、梅原猛さんも、確か光明皇后がモデルであることをほのめかしていたような記憶がある。
個人的にモデルは女性であってほしいという願望もある。
この本は光明皇后がモデルであることを主張している。いろんな文献を参考に光明皇后のことが詳しく書かれている。
ただ、「これで決まりだ!」と思うほどの説得力はなかった。
個人的にも、「そうであって欲しい」と思うし、その方が、心が落ち着くというものである。

Posted by わくわくなひと at
09:35
│Comments(0)
2010年01月10日
今度はMcD New York Burgerをゲット!
今日は社員が健軍方面に出かけるという話しを小耳に挟んだ。速攻で電話した。
「New York Burgerセットを一つ。カネはいとわない」旨、連絡。
もうすぐ熊本では健軍店でしか売っていない限定品が手に入る。知らず知らず期待は高まっていく。
14時台。8日以来、気になっていたNew York Burgerをのさった!
見た目、おしゃれな感じ。パティの焦げ茶、トマトの赤、レタスの緑、都会的な雰囲気漂うバンズ?。うまそうだ。
一口食す。マヨネーズマスタードがピリッと効いていて、都会の大人の食感か?
食べ進むうち「ジューシーな肉の食感が欲しいかな」と、ふと思った。
大量生産、規格などの制約により、ジューシーな肉の実現は無理があるのか?
次はそんな新商品を期待します。
「New York Burgerセットを一つ。カネはいとわない」旨、連絡。
もうすぐ熊本では健軍店でしか売っていない限定品が手に入る。知らず知らず期待は高まっていく。
14時台。8日以来、気になっていたNew York Burgerをのさった!
見た目、おしゃれな感じ。パティの焦げ茶、トマトの赤、レタスの緑、都会的な雰囲気漂うバンズ?。うまそうだ。
一口食す。マヨネーズマスタードがピリッと効いていて、都会の大人の食感か?
食べ進むうち「ジューシーな肉の食感が欲しいかな」と、ふと思った。
大量生産、規格などの制約により、ジューシーな肉の実現は無理があるのか?
次はそんな新商品を期待します。

Posted by わくわくなひと at
15:15
│Comments(2)
2010年01月08日
McD テキサスバーガーをゲット!
今日から11日までマクドナルド白山店で限定販売する「テキサスバーガー」を食べてみた。
ボリューム十分過ぎ。マスタードなど味もワイルド。パティは少し焦げたような感じ。空腹感を瞬時に解消できる。
テキサスバーガーは、熊本では白山店だけ。
同時に、「New York Burger」が健軍店で限定販売されているらしい。こちらは私の好きなトマトも挟まれており、やはり気になる。
マクドナルドは規格化、大規模化で成功した20世紀型のハンバーガーチェーン。しかし、熊本で育まれたクォーターパウンダーや今回の企画を見ると、昔からあったハンバーガーに先祖帰りしているようにも感じる。
マクド日本法人の社長は、今もアップルのマック出身の人だと思う。次にどんな仕掛けに出てくるか楽しみだ。
ボリューム十分過ぎ。マスタードなど味もワイルド。パティは少し焦げたような感じ。空腹感を瞬時に解消できる。
テキサスバーガーは、熊本では白山店だけ。
同時に、「New York Burger」が健軍店で限定販売されているらしい。こちらは私の好きなトマトも挟まれており、やはり気になる。
マクドナルドは規格化、大規模化で成功した20世紀型のハンバーガーチェーン。しかし、熊本で育まれたクォーターパウンダーや今回の企画を見ると、昔からあったハンバーガーに先祖帰りしているようにも感じる。
マクド日本法人の社長は、今もアップルのマック出身の人だと思う。次にどんな仕掛けに出てくるか楽しみだ。

Posted by わくわくなひと at
15:23
│Comments(2)
2010年01月08日
McDの今年早々の仕掛け「Big America」・・・速報
今年早々、あのマックが仕掛けてきた。
社員の話によると、熊本では白山店と健軍店で何事か起こっているらしい。
弊社熊本事務所近くの白山店では、カウボーイ姿の店員が「Texas Burger」を売っているという。
そこで、銀行に向かっていた社員に急遽指示を出した。
「帰りにTexas Burgerを購入してくること。カネはいとわない!」
手に入るまで、後、30分以上はかかるだろう。
詳細は、気が向いたら後日報告する予定。
社員の話によると、熊本では白山店と健軍店で何事か起こっているらしい。
弊社熊本事務所近くの白山店では、カウボーイ姿の店員が「Texas Burger」を売っているという。
そこで、銀行に向かっていた社員に急遽指示を出した。
「帰りにTexas Burgerを購入してくること。カネはいとわない!」
手に入るまで、後、30分以上はかかるだろう。
詳細は、気が向いたら後日報告する予定。
Posted by わくわくなひと at
14:52
│Comments(0)
2010年01月05日
一週間は心がほかほか・・・森沢明夫『津軽百年食堂』
急に時間がぽっかり空いて、最寄りの書店をのぞいた時に出会った一冊。昭和を思わせる着物姿のイラストが目にとまった。
本の帯に「読んだあと、一週間は心がほかほかです」と書いてある。それが購入の決め手になったと思う。
この小説は次のように始まる。
【大森哲夫】
三月もいよいよ後半を迎えたけれど、すでに道路の積雪はほとんど消えていた。残ったのは、歩道の脇に雪かきで積みあげられ、小山のようになった雪の残骸だった。
自分が子供の頃は、まだこの時期は銀世界だったはずだ-大森哲夫は、自身が営む古びた食堂の窓から、まだほの暗い外の風景を眺め、幼少の頃に見た風景を憶った。
北風が吹き、ペンキのはげかけた木枠の窓がカタカタと鳴った。すきま風がすうっと忍び込んできて、哲夫の首筋をなでる。思わず着ていたどてらの襟を合わせて、ブルッと身震いした。
美しい映画のような描写だ。カメラの目線が“ペンキのはげかけた木枠の窓”に向けられ、北風でカタカタと鳴る様子が映る。“すきま風がすうっと忍び込んできて、哲夫の首筋をなでる”。視線、音、明暗などの感じ方が見事に表現されている。
これを書いている人はいくつの人なのか?つい確かめたくなった。
1969年千葉県生まれ。「ラストサムライ 片目のチャンピオン 武田幸三」で第17回ミズノスポーツライター賞優秀賞、ヒット小説「海を抱いたビー玉」は韓国語版にもなり人気を博す。」と書いてある。
目のつけどころ、音、そして触感。自分よりも10歳以上若い人なのに、表現力の豊かさに驚く。すっかりファンになりそうだ。
物語はプロローグの【大森哲夫】という節から始まり、【大森賢治】【大森陽一】【筒井七海】【藤川美月】【大森トヨ】など、登場人物の心象風景が交互に描かれていく。百年続く津軽の蕎麦屋さんに関わる人たちの思いや出来事が綴られていく。
登場人物は非常に限られるが、心理描写は非常に細かい。都会人のように薄くて複雑な人間関係でないところが、“ほかほか”する所以だろう。
弘前の桜など美しい光景の中で繰り広げられる100年の歴史を背負った人々の思いには、質感を伴う美しさを感じてしまった。
著者のブログを拝見すると、どうやら映画化されるらしい。今から楽しみだ。
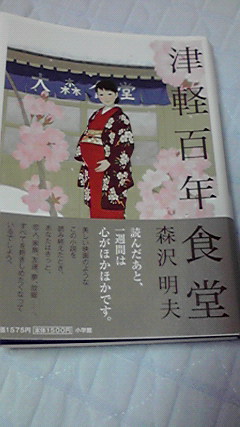
本の帯に「読んだあと、一週間は心がほかほかです」と書いてある。それが購入の決め手になったと思う。
この小説は次のように始まる。
【大森哲夫】
三月もいよいよ後半を迎えたけれど、すでに道路の積雪はほとんど消えていた。残ったのは、歩道の脇に雪かきで積みあげられ、小山のようになった雪の残骸だった。
自分が子供の頃は、まだこの時期は銀世界だったはずだ-大森哲夫は、自身が営む古びた食堂の窓から、まだほの暗い外の風景を眺め、幼少の頃に見た風景を憶った。
北風が吹き、ペンキのはげかけた木枠の窓がカタカタと鳴った。すきま風がすうっと忍び込んできて、哲夫の首筋をなでる。思わず着ていたどてらの襟を合わせて、ブルッと身震いした。
美しい映画のような描写だ。カメラの目線が“ペンキのはげかけた木枠の窓”に向けられ、北風でカタカタと鳴る様子が映る。“すきま風がすうっと忍び込んできて、哲夫の首筋をなでる”。視線、音、明暗などの感じ方が見事に表現されている。
これを書いている人はいくつの人なのか?つい確かめたくなった。
1969年千葉県生まれ。「ラストサムライ 片目のチャンピオン 武田幸三」で第17回ミズノスポーツライター賞優秀賞、ヒット小説「海を抱いたビー玉」は韓国語版にもなり人気を博す。」と書いてある。
目のつけどころ、音、そして触感。自分よりも10歳以上若い人なのに、表現力の豊かさに驚く。すっかりファンになりそうだ。
物語はプロローグの【大森哲夫】という節から始まり、【大森賢治】【大森陽一】【筒井七海】【藤川美月】【大森トヨ】など、登場人物の心象風景が交互に描かれていく。百年続く津軽の蕎麦屋さんに関わる人たちの思いや出来事が綴られていく。
登場人物は非常に限られるが、心理描写は非常に細かい。都会人のように薄くて複雑な人間関係でないところが、“ほかほか”する所以だろう。
弘前の桜など美しい光景の中で繰り広げられる100年の歴史を背負った人々の思いには、質感を伴う美しさを感じてしまった。
著者のブログを拝見すると、どうやら映画化されるらしい。今から楽しみだ。
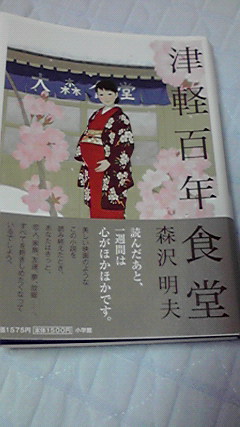
Posted by わくわくなひと at
19:05
│Comments(4)
2010年01月04日
Hal's Barのオムライスは熊本一です!
このところよくお邪魔します。
上通り手取神社参道にある「Hal's Bar」です。
スペイン風居酒屋さんなんですが、私の狙いはオムライスです。
この店が市役所裏のうどん屋さんの二階にある頃からファンでした。
昔は「てつ」?という名前でした。何年か前は上乃裏通り沿いにありました。
玉ねぎの微妙な焦げ具合、比較的サラッとしたライス。本当、この微妙さはほかの店ではなかなか真似ができないと思います。
それと、極めつけはデミグラスソースです。他の店に行くと、ケチャップソースなのかデミグラスなのか分からない。これがうまいんだな。
デミグラスがうまいから、当然、ハヤシライスも極上の味わいですよ。
上通り手取神社参道にある「Hal's Bar」です。
スペイン風居酒屋さんなんですが、私の狙いはオムライスです。
この店が市役所裏のうどん屋さんの二階にある頃からファンでした。
昔は「てつ」?という名前でした。何年か前は上乃裏通り沿いにありました。
玉ねぎの微妙な焦げ具合、比較的サラッとしたライス。本当、この微妙さはほかの店ではなかなか真似ができないと思います。
それと、極めつけはデミグラスソースです。他の店に行くと、ケチャップソースなのかデミグラスなのか分からない。これがうまいんだな。
デミグラスがうまいから、当然、ハヤシライスも極上の味わいですよ。

Posted by わくわくなひと at
21:36
│Comments(0)
2010年01月03日
ほのぼのとした話や見失っていた歴史を特集・・・西日本、熊日
昨年の途中から全国紙は購読していない。自分の主な行動範囲をカバーする西日本新聞と熊本日日新聞だけを読むようにしている。
この不況の中で新聞経営も相当厳しいということだが、西日本と熊日の元旦号を読み、「少し新聞が変わるかも知れない」と思ってしまった。
西日本新聞で最も印象深かったのは、「デスク日記」である。新年企画のきっかけが「社会面ばかり読んでいると、世の中の少年がみんな悪(わる)に見えてくる」という警察官の言葉だったことを披露している。
社会面は「残念ながら今も心温まる話題は少ない。話題がないわけではなく、ニュースかどうかが紙面掲載の優先順位だからだ」そうである。「だったら固定のコーナーを作りましょうよ」から新コーナー「あなたの物語 青空」を始めたという。
第一回目は、地域の見守りを日課にしている73歳の男性の話。筑紫野市の562世帯を軽トラックで回っているという。もちろんボランティアである。「あなたを支えますよと言うなら、言葉だけでなく、こちらが繰り返し繰り返し出向いていこうと思うんです。そうすれば必ず返ってきます」。8年前の冬、中学生が自死。その前の冬には高校生が犯罪に遭う。もう一人の不幸も見逃したくない。その思いが体を動かしているという話だ。
このコーナーでは、「この世は捨てたもんじゃない」というメッセージを発信していくという。
勝ち組や優秀な人の話など競争社会のエリート話だけでなく、目立たないけど人間らしい取組みを拾っていこうという視点だと思う。
西日本の記事を読んで、「たぶん熊日の記者たちも今年は違った動きをするだろう」と期待を持って読んでみた。
すると、やはり。「時代のコントラスト 熊本・1960年から半世紀」というシリーズ企画がスタートしていた。
記事は50年前の岩戸景気の繁盛ぶりを書いた後、熊本の有名企業「コンゴー」の創業者の談話を載せていた。
「今のような派遣労働もなく、社員は兄弟や家族のようなものだった」。増産続きの工場はランニング姿の従業員の熱気であふれ、新製品の開発・改良などで徹夜の残業もしょっちゅうだった。・・・確かに規則通り型にはまった仕事では売れる商品なんて作れない。
「人が人らしく泣き、笑い、怒っていた60年代の幕開けから半世紀。あらゆる分野でシステム化が進む一方、不況と社会の閉そく感が長引く中で、人々の心から喜怒哀楽がかすれてしまったように思える。世の中の色が「明」も「暗」もくっきりしていたころを振り返り、置き去りにしてきたもの、見失っていたものを考える」そうである。
だれかのせいにしたり、自分の責任は果たさずに権利ばかり主張、仲間意識も皆無で第3者的で評論家的な話を長々とする、規則や法律をすぐ盾に取る・・・。こんな雰囲気では「夢や熱」(コンゴーの創業者)などは出てこない。
個人的には、置き去りにしたもの、見失っていたものをシリーズで紹介してもらうことで、“あのころは”でなく“今”夢と熱のある人づくりのヒントを得たいと思っている。
この不況の中で新聞経営も相当厳しいということだが、西日本と熊日の元旦号を読み、「少し新聞が変わるかも知れない」と思ってしまった。
西日本新聞で最も印象深かったのは、「デスク日記」である。新年企画のきっかけが「社会面ばかり読んでいると、世の中の少年がみんな悪(わる)に見えてくる」という警察官の言葉だったことを披露している。
社会面は「残念ながら今も心温まる話題は少ない。話題がないわけではなく、ニュースかどうかが紙面掲載の優先順位だからだ」そうである。「だったら固定のコーナーを作りましょうよ」から新コーナー「あなたの物語 青空」を始めたという。
第一回目は、地域の見守りを日課にしている73歳の男性の話。筑紫野市の562世帯を軽トラックで回っているという。もちろんボランティアである。「あなたを支えますよと言うなら、言葉だけでなく、こちらが繰り返し繰り返し出向いていこうと思うんです。そうすれば必ず返ってきます」。8年前の冬、中学生が自死。その前の冬には高校生が犯罪に遭う。もう一人の不幸も見逃したくない。その思いが体を動かしているという話だ。
このコーナーでは、「この世は捨てたもんじゃない」というメッセージを発信していくという。
勝ち組や優秀な人の話など競争社会のエリート話だけでなく、目立たないけど人間らしい取組みを拾っていこうという視点だと思う。
西日本の記事を読んで、「たぶん熊日の記者たちも今年は違った動きをするだろう」と期待を持って読んでみた。
すると、やはり。「時代のコントラスト 熊本・1960年から半世紀」というシリーズ企画がスタートしていた。
記事は50年前の岩戸景気の繁盛ぶりを書いた後、熊本の有名企業「コンゴー」の創業者の談話を載せていた。
「今のような派遣労働もなく、社員は兄弟や家族のようなものだった」。増産続きの工場はランニング姿の従業員の熱気であふれ、新製品の開発・改良などで徹夜の残業もしょっちゅうだった。・・・確かに規則通り型にはまった仕事では売れる商品なんて作れない。
「人が人らしく泣き、笑い、怒っていた60年代の幕開けから半世紀。あらゆる分野でシステム化が進む一方、不況と社会の閉そく感が長引く中で、人々の心から喜怒哀楽がかすれてしまったように思える。世の中の色が「明」も「暗」もくっきりしていたころを振り返り、置き去りにしてきたもの、見失っていたものを考える」そうである。
だれかのせいにしたり、自分の責任は果たさずに権利ばかり主張、仲間意識も皆無で第3者的で評論家的な話を長々とする、規則や法律をすぐ盾に取る・・・。こんな雰囲気では「夢や熱」(コンゴーの創業者)などは出てこない。
個人的には、置き去りにしたもの、見失っていたものをシリーズで紹介してもらうことで、“あのころは”でなく“今”夢と熱のある人づくりのヒントを得たいと思っている。
Posted by わくわくなひと at
15:28
│Comments(0)
2010年01月02日
晦日と元日は屠蘇風呂をいただきました!
いや~世の中には粋な女性社長がいるもんです。
年末のご挨拶に行った帰りに、手土産として「屠蘇風呂」をいただきました。
屠蘇の香りのする入浴剤なんですが、オシャレな紙箱に手拭いのような布でくるまれています。
一風呂入ったら、もちろん、浴室は屠蘇の香りが濃密に漂います。それだけでなく、部屋中が屠蘇というよりも、なつかしい樹木のような香りにつつまれてしまいます。
こちらは手土産一つ持たずに行ったのに、最高の贈り物をいただいて心苦しい限りです。
福岡は直方市にある阿部東岡堂薬院がつくっています。
年末のご挨拶に行った帰りに、手土産として「屠蘇風呂」をいただきました。
屠蘇の香りのする入浴剤なんですが、オシャレな紙箱に手拭いのような布でくるまれています。
一風呂入ったら、もちろん、浴室は屠蘇の香りが濃密に漂います。それだけでなく、部屋中が屠蘇というよりも、なつかしい樹木のような香りにつつまれてしまいます。
こちらは手土産一つ持たずに行ったのに、最高の贈り物をいただいて心苦しい限りです。
福岡は直方市にある阿部東岡堂薬院がつくっています。

Posted by わくわくなひと at
13:14
│Comments(0)



