2010年03月24日
コリイ・ドクトロウ『マジック・キングダムで落ちぶれて』
『ツイッターノミクス(TwitterNomics)』(文藝春秋、2010年3月10日第一刷、原書名『THE WHUFFIE FACTOR Using the power of social networks to build your business by Tara Hunt』)の著者タラ・ハントが、Web2.0で世の中や人がどのように変化していくかを想像する時、最も参考になったとしているSF小説である。
2003年の発表で、日本語版は2005年8月31日に早川書房から初版が出ている。
タラ・ハントが“ウッフィー”をキーワードにしてWeb2.0の世界を描いているが、“ウッフィー”は恐らくこのSF小説から拝借したものだろう。この小説によると、21世紀の後半はお金ではなく“ウッフィー”を交換する世の中になっている。
ウッフィーは与えることによって増え、貢献することによってたまっていく、人や企業にとっての消費者の気持ちの有り様のようなものである。ウッフィーとは、信頼、評判、尊敬、影響力、人脈、好意などなどの積み重ねの中から生まれる。そんな性格を持った通貨のようなものである。
この小説の中では資本主義経済のお金は駆逐されたはずだが、ウッフィーを悪用する人が出てきて、ディズニーワールドを乗っ取ろうとする。主人公は、そういう輩に抵抗するが一時はまんまとはめられて悪い評判を立てられ、手持ちのウッフィーがほとんどなくなってしまう。手持ちのウッフィーの量は他の人に見えるようになっており、乗り物やホテルなどに泊まれないばかりか、「ウッフィーが少ない=この人は悪い人だ」と思われ、多くの人が主人公から遠ざかってしまう。
しかし、最後はハッピーエンドで終わる。
21世紀後半は脳の記憶はパソコンなどに保存することができるし、ケガをしたり老化した体はクローンで再生できる。脳のバックアップさえしておけば、人は死なない。今の世の中はいやだと思えば、100年くらい眠っておくこともできる。
今は弱肉強食の市場原理主義やお金に対する風当たりが強く、そうでない世の中が求められるようになってきている。ネット世界での自己中心的活動は批判の的であり、信頼、評判、尊敬、影響力、絆、好意などが強く求められるようになってきたようだ。
しかし、どんな世の中になっても、悪用する者がいるので、100%バラ色の世界を描くのは要注意だということを、このSF小説から学んだような気がする。
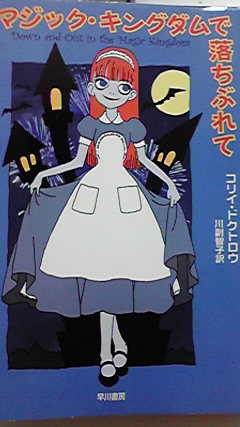
2003年の発表で、日本語版は2005年8月31日に早川書房から初版が出ている。
タラ・ハントが“ウッフィー”をキーワードにしてWeb2.0の世界を描いているが、“ウッフィー”は恐らくこのSF小説から拝借したものだろう。この小説によると、21世紀の後半はお金ではなく“ウッフィー”を交換する世の中になっている。
ウッフィーは与えることによって増え、貢献することによってたまっていく、人や企業にとっての消費者の気持ちの有り様のようなものである。ウッフィーとは、信頼、評判、尊敬、影響力、人脈、好意などなどの積み重ねの中から生まれる。そんな性格を持った通貨のようなものである。
この小説の中では資本主義経済のお金は駆逐されたはずだが、ウッフィーを悪用する人が出てきて、ディズニーワールドを乗っ取ろうとする。主人公は、そういう輩に抵抗するが一時はまんまとはめられて悪い評判を立てられ、手持ちのウッフィーがほとんどなくなってしまう。手持ちのウッフィーの量は他の人に見えるようになっており、乗り物やホテルなどに泊まれないばかりか、「ウッフィーが少ない=この人は悪い人だ」と思われ、多くの人が主人公から遠ざかってしまう。
しかし、最後はハッピーエンドで終わる。
21世紀後半は脳の記憶はパソコンなどに保存することができるし、ケガをしたり老化した体はクローンで再生できる。脳のバックアップさえしておけば、人は死なない。今の世の中はいやだと思えば、100年くらい眠っておくこともできる。
今は弱肉強食の市場原理主義やお金に対する風当たりが強く、そうでない世の中が求められるようになってきている。ネット世界での自己中心的活動は批判の的であり、信頼、評判、尊敬、影響力、絆、好意などが強く求められるようになってきたようだ。
しかし、どんな世の中になっても、悪用する者がいるので、100%バラ色の世界を描くのは要注意だということを、このSF小説から学んだような気がする。
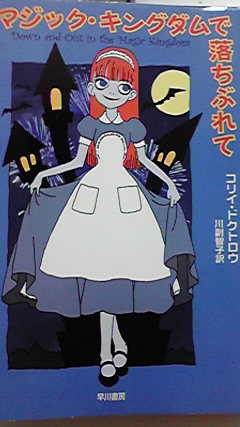
Posted by わくわくなひと at
20:28
│Comments(0)
2010年03月22日
“eコマースのインパクト”の影響はまだ続いています!
「これらのことは、eコマースのインパクトについてもう一つ重要なことを教える。
流通チャネルは、顧客が誰かを変える。顧客がどのように買うかだけでなく、何を買うかを変える。消費者行動を変え、貯蓄パターンを変え、産業構造を変える。ひとことで言えば、経済全体を変える。」( P・Fドラッカー『ネクスト・ソサエティ』1999年初出)。
このドラッカーの言葉に触発されて、私の頭は新たな情報収集を始めてしまいました。Eコマースが盛んになってきた今の時代、資本主義経済の後に来る価値観や人々の行動とは、どのようなものだろうと言うことです。
娘が購読している「Mainichi Weekly」を眺めても、そんなことに関係する情報が引っかかってきます。
3月13日付けの同紙を見ると、ウディ・アレン(Woody Allen)監督の「Cassandra’s Dream」が今月20日から封切られるという記事に目が止まりました。
テーマはLife is nothing if not totally ironic.(人生はとても皮肉だ)です。大金持ちは例えそんなに資質が伴わない人であっても政府に影響を与える。富豪の言うことであれば、あなたは耳を傾ける、ということをテーマにした映画だそうです。
イギリスの兄弟が経営不振のレストランの勤勉なオーナーである父親の話よりも、成功しているが、たちの悪いビジネスマンの叔父の方の話を聞き、悲劇の引き金を引いてしまう。カネと成功にしか目がいかない世の中のもとでの人生の皮肉を描いた作品です。Woody Allenのことですから、笑わせながら考えさせる作品になるかと思います。キャナルシティあたりで上映されていたら、ぜひ見たいと思います。
また、3月20日付けの同紙には、フリーランスライター・シェリル・チャウ(Cheryl Chow)のHurry up and slow down(ゆっくり急がず生きてみる)という記事が載っていました。
長引く不況がもたらすのは負の影響ばかりではなく、ゆっくり急がず生きている人がたくさん出てきていることを伝えています。
一昔前なら変人か過激派の人たちのやることと思う人もいたと聞いていますが、今はそこまで変人ではない人も新たな動きを見せ始めています。これもeコマースが消費者行動を変え、経済の構造を変えたからと言えるでしょう。
例えば、アメリカではかつてビデオプロデューサーだった人が高齢者センターで太極拳を教えているそうです。収入は大幅に減ったがミーティングや人とつながりができることを楽しんでいるそうです。大企業のリタイヤ組の行動というと、田舎で有機農業というのがお決まりのパターンですが、街の中でも新たな人生を踏み出すことができるという事例だと思いました。これ以外にも日本の事例をあげており、景気後退が新たな連帯感を生み、もはや大量消費が人々の基本的なニーズを充たさなくなっていることをリポートしています。
Good-bye, corporate warriors. Good-bye, salary men and women. Hello, sloths! だそうです。slothは怠け者のことです。
たぶんいつの日か、国の豊かさを測る物差しは国民総生産からgross national happinessになるだろうと、シェリル・チャウは予想しています。

流通チャネルは、顧客が誰かを変える。顧客がどのように買うかだけでなく、何を買うかを変える。消費者行動を変え、貯蓄パターンを変え、産業構造を変える。ひとことで言えば、経済全体を変える。」( P・Fドラッカー『ネクスト・ソサエティ』1999年初出)。
このドラッカーの言葉に触発されて、私の頭は新たな情報収集を始めてしまいました。Eコマースが盛んになってきた今の時代、資本主義経済の後に来る価値観や人々の行動とは、どのようなものだろうと言うことです。
娘が購読している「Mainichi Weekly」を眺めても、そんなことに関係する情報が引っかかってきます。
3月13日付けの同紙を見ると、ウディ・アレン(Woody Allen)監督の「Cassandra’s Dream」が今月20日から封切られるという記事に目が止まりました。
テーマはLife is nothing if not totally ironic.(人生はとても皮肉だ)です。大金持ちは例えそんなに資質が伴わない人であっても政府に影響を与える。富豪の言うことであれば、あなたは耳を傾ける、ということをテーマにした映画だそうです。
イギリスの兄弟が経営不振のレストランの勤勉なオーナーである父親の話よりも、成功しているが、たちの悪いビジネスマンの叔父の方の話を聞き、悲劇の引き金を引いてしまう。カネと成功にしか目がいかない世の中のもとでの人生の皮肉を描いた作品です。Woody Allenのことですから、笑わせながら考えさせる作品になるかと思います。キャナルシティあたりで上映されていたら、ぜひ見たいと思います。
また、3月20日付けの同紙には、フリーランスライター・シェリル・チャウ(Cheryl Chow)のHurry up and slow down(ゆっくり急がず生きてみる)という記事が載っていました。
長引く不況がもたらすのは負の影響ばかりではなく、ゆっくり急がず生きている人がたくさん出てきていることを伝えています。
一昔前なら変人か過激派の人たちのやることと思う人もいたと聞いていますが、今はそこまで変人ではない人も新たな動きを見せ始めています。これもeコマースが消費者行動を変え、経済の構造を変えたからと言えるでしょう。
例えば、アメリカではかつてビデオプロデューサーだった人が高齢者センターで太極拳を教えているそうです。収入は大幅に減ったがミーティングや人とつながりができることを楽しんでいるそうです。大企業のリタイヤ組の行動というと、田舎で有機農業というのがお決まりのパターンですが、街の中でも新たな人生を踏み出すことができるという事例だと思いました。これ以外にも日本の事例をあげており、景気後退が新たな連帯感を生み、もはや大量消費が人々の基本的なニーズを充たさなくなっていることをリポートしています。
Good-bye, corporate warriors. Good-bye, salary men and women. Hello, sloths! だそうです。slothは怠け者のことです。
たぶんいつの日か、国の豊かさを測る物差しは国民総生産からgross national happinessになるだろうと、シェリル・チャウは予想しています。

Posted by わくわくなひと at
15:35
│Comments(0)
2010年03月22日
高校野球の女子マネジャーがドラッカーの・・・
岩崎夏海『もし高校野球の女子マネジャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』ダイヤモンド社(2009年12月3日第1刷、2010年1月22日第4刷)。
昨年の12月前後から私の周りで話題になっていた本です。東京の書店では今でもベストセラーにランクインしています。女子高生の漫画が表紙に描かれていて、おじさんには買いにくい本ですが、同僚から借りてついに読んでしまいました。
この本を読んで最初にとった行動は、自宅の本棚の隅でほこりをかぶっていた『マネジメント』を取りだしたことです。『マネジメント【エッセンシャル版】』は、私がまだサラリーマンだったころ、まだ新米管理職だったころに買い、パラッパラッと読んでいました。2001年12月13日発行の初版です。蛍光ペンで今では引かないようなところにも線を引いています。
『もし高校野球の・・・』を読んで再び読みたくなりました。今では正真正銘のマネジャーになっていますが、ドラッカーの『マネジメント』に書いてあることが血肉になっていないことを実感したからです。本に出てくる女子マネジャーのようにぼろぼろになるまで何度も読むのが、この『マネジメント』の読み方だと思うからです。
女子マネジャーは、本当に強い意志と行動力を持った人です。周りの登場人物たちもすごい。心のどこかから「そんな人間いるわけないやん?」という声が聞こえてきます。しかし、組織をあずかる者はそれだけの責任を負っているわけですから、そんな言い訳は通用しません。
『マネジメント』に書いてあること、人の話をどれだけ理解し実践できるかが問われているわけです。引退するまでは逃げられません。
今度はドラッカーの『マネジメント』を読み直します。
昨年の12月前後から私の周りで話題になっていた本です。東京の書店では今でもベストセラーにランクインしています。女子高生の漫画が表紙に描かれていて、おじさんには買いにくい本ですが、同僚から借りてついに読んでしまいました。
この本を読んで最初にとった行動は、自宅の本棚の隅でほこりをかぶっていた『マネジメント』を取りだしたことです。『マネジメント【エッセンシャル版】』は、私がまだサラリーマンだったころ、まだ新米管理職だったころに買い、パラッパラッと読んでいました。2001年12月13日発行の初版です。蛍光ペンで今では引かないようなところにも線を引いています。
『もし高校野球の・・・』を読んで再び読みたくなりました。今では正真正銘のマネジャーになっていますが、ドラッカーの『マネジメント』に書いてあることが血肉になっていないことを実感したからです。本に出てくる女子マネジャーのようにぼろぼろになるまで何度も読むのが、この『マネジメント』の読み方だと思うからです。
女子マネジャーは、本当に強い意志と行動力を持った人です。周りの登場人物たちもすごい。心のどこかから「そんな人間いるわけないやん?」という声が聞こえてきます。しかし、組織をあずかる者はそれだけの責任を負っているわけですから、そんな言い訳は通用しません。
『マネジメント』に書いてあること、人の話をどれだけ理解し実践できるかが問われているわけです。引退するまでは逃げられません。
今度はドラッカーの『マネジメント』を読み直します。

Posted by わくわくなひと at
14:01
│Comments(0)
2010年03月21日
北村薫『鷺と雪』
私にとって東京は立体を感じてしまう街である。福岡もそうだが、空中には高速道路、地中には地下鉄、地上には高層ビルがあり、限られた空間を余すところなく人間が使っている。20世紀の英知?を最大限に表現した遺産だと思う。
それと、私の場合、東京というと何故だかもう一つ立体的に見えてしまう。長らく政治、経済の中心であった東京にいると、一つの風景を眺めてみただけで、実際に体験したり見たわけでもないのに、数十年前の光景が脳裏に浮かぶことがよくある。
二月初めに隅田川沿いの某大手飲料メーカーの展望レストランにいた。眼下に広がる下町の夜景を眺めながら、昭和20年3月10日の夜のことを思ってしまった。この後、浅草寺詣でをし、突然、大学の友人から電話がかかり急遽渋谷に向かうことになった。浅草から渋谷までは地下鉄銀座線で一本で結ばれている。この地下鉄は戦前から開通しており、むき出しの大きな鋲がいくつも打ち付けられている大きな鉄骨が長い歴史をイメージさせる。日本橋の三越あたりも、昭和の東京や戦前の東京を思わせる建物や構造物がいくつも残っている。
前置きが長くなったが、北村薫『鷺と雪』は昭和初期から226事件が起こった雪の朝までの華族の話をミステリータッチで描いた小説である。今も残る地下鉄銀座線、日本橋の三越、銀座の服部時計店、上野周辺のことがきれいな文章で再現されている。
主人公は良家の令嬢で麹町に屋敷があるという設定。大学時代はかなりの時間、紀尾井町や麹町周辺で過ごした。今も旧伯爵邸や車寄せのある洋館などが残されている街であり、北村氏の文章と自分の記憶が重なり合って、かなりリアルな映像と香りを思い浮かべながら読むことができた。
ルンペン、ブッポウソウ、ドッペルゲンガー、三越のライオン像にまつわる都市伝説、昭和11年2月26日の雪の朝。これらをキーワードに話は進む。当時の地方は東北を中心に凶作、世の中全体が未曾有の不況。娘の身売りなど悲惨な出来事があふれる世の中だったとされている。しかし、昭和の初めまでの華族はモダンで優雅な暮らしをしていたという。そんな華やかな暮らしに忍び寄る不穏な予兆が、華族出身のルンペンの死、東京では聞くことはできないと思われていた不吉なブッポウソウの鳴き声などとして起こってしまう。そして、昭和11年2月26日、雪の朝の出来事がつづられ余韻を残しながら物語は終わる。
ルンペンの死は「男爵松平斉の失踪事件」、三越のライオン像に人から見られずにまたがると念願かなうという都市伝説、昭和10年、夏の帝都の夜空を(声の)ブッポウソウが泣き渡ったこと、細川家能楽堂で梅若万三郎が慣例を破り面をつけて『鷺』を舞ったこと。作者はこういった歴史的事実を題材にして、この小説を創作した。
「ことを見つめるのは人である。これらの様々な出来事の中に、登場人物たちはいた。」という。
直木賞受賞作。史実から広げていく創造力と文章力。読み進まないではいられない、人を引き込んでいくストーリー。今後、北村薫という作家の名前を見聞きしたら、少しは関心を持つことになりそうだ。
この小説で一番印象深かった表現は、以下の通り。小林秀雄の「当麻(たえま)」の文章を思い出した。
「上がって強く打ち下ろされると見えた足が、床に届く時、すっとどこかで勢いを断たれ、音は虚空に吸われる。しんしんと静かだ。そこで音がしないから、鷺は中空にいるようであり、この世のものの持つ重さからも解放される。着ている白も、能楽師の装束ではなく、何かそれを越えたものに見えて来た。現実にそこで動いているのだから、あり得ない話だが、万三郎の袖は、引力の法則を越えスローモーションで動いているようだった。演ずる者の命は、まとう衣装の袖の端にまで行き渡り、精妙に震えていた。」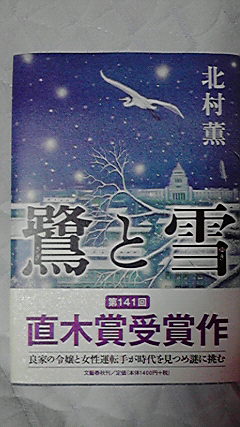
それと、私の場合、東京というと何故だかもう一つ立体的に見えてしまう。長らく政治、経済の中心であった東京にいると、一つの風景を眺めてみただけで、実際に体験したり見たわけでもないのに、数十年前の光景が脳裏に浮かぶことがよくある。
二月初めに隅田川沿いの某大手飲料メーカーの展望レストランにいた。眼下に広がる下町の夜景を眺めながら、昭和20年3月10日の夜のことを思ってしまった。この後、浅草寺詣でをし、突然、大学の友人から電話がかかり急遽渋谷に向かうことになった。浅草から渋谷までは地下鉄銀座線で一本で結ばれている。この地下鉄は戦前から開通しており、むき出しの大きな鋲がいくつも打ち付けられている大きな鉄骨が長い歴史をイメージさせる。日本橋の三越あたりも、昭和の東京や戦前の東京を思わせる建物や構造物がいくつも残っている。
前置きが長くなったが、北村薫『鷺と雪』は昭和初期から226事件が起こった雪の朝までの華族の話をミステリータッチで描いた小説である。今も残る地下鉄銀座線、日本橋の三越、銀座の服部時計店、上野周辺のことがきれいな文章で再現されている。
主人公は良家の令嬢で麹町に屋敷があるという設定。大学時代はかなりの時間、紀尾井町や麹町周辺で過ごした。今も旧伯爵邸や車寄せのある洋館などが残されている街であり、北村氏の文章と自分の記憶が重なり合って、かなりリアルな映像と香りを思い浮かべながら読むことができた。
ルンペン、ブッポウソウ、ドッペルゲンガー、三越のライオン像にまつわる都市伝説、昭和11年2月26日の雪の朝。これらをキーワードに話は進む。当時の地方は東北を中心に凶作、世の中全体が未曾有の不況。娘の身売りなど悲惨な出来事があふれる世の中だったとされている。しかし、昭和の初めまでの華族はモダンで優雅な暮らしをしていたという。そんな華やかな暮らしに忍び寄る不穏な予兆が、華族出身のルンペンの死、東京では聞くことはできないと思われていた不吉なブッポウソウの鳴き声などとして起こってしまう。そして、昭和11年2月26日、雪の朝の出来事がつづられ余韻を残しながら物語は終わる。
ルンペンの死は「男爵松平斉の失踪事件」、三越のライオン像に人から見られずにまたがると念願かなうという都市伝説、昭和10年、夏の帝都の夜空を(声の)ブッポウソウが泣き渡ったこと、細川家能楽堂で梅若万三郎が慣例を破り面をつけて『鷺』を舞ったこと。作者はこういった歴史的事実を題材にして、この小説を創作した。
「ことを見つめるのは人である。これらの様々な出来事の中に、登場人物たちはいた。」という。
直木賞受賞作。史実から広げていく創造力と文章力。読み進まないではいられない、人を引き込んでいくストーリー。今後、北村薫という作家の名前を見聞きしたら、少しは関心を持つことになりそうだ。
この小説で一番印象深かった表現は、以下の通り。小林秀雄の「当麻(たえま)」の文章を思い出した。
「上がって強く打ち下ろされると見えた足が、床に届く時、すっとどこかで勢いを断たれ、音は虚空に吸われる。しんしんと静かだ。そこで音がしないから、鷺は中空にいるようであり、この世のものの持つ重さからも解放される。着ている白も、能楽師の装束ではなく、何かそれを越えたものに見えて来た。現実にそこで動いているのだから、あり得ない話だが、万三郎の袖は、引力の法則を越えスローモーションで動いているようだった。演ずる者の命は、まとう衣装の袖の端にまで行き渡り、精妙に震えていた。」
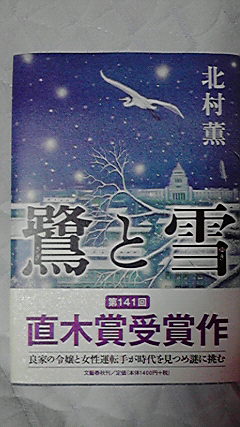
Posted by わくわくなひと at
15:46
│Comments(2)
2010年03月19日
鉄道の影響力!九州新幹線全通の影響はどうか?
P・Fドラッカー『ネクスト・ソサエティ』(2002年6月7日第二刷)から、もう一つ。
「鉄道こそ、産業革命を真の革命にするものだった。経済を変えただけでなく、心理的な地理概念を変えた。人類が初めて本当の移動能力を得た。初めて普通の人の世界が広がった。しかも、その結果生じた世界観の変化は、ただちに広く認識された。」(76P)
「フランスの歴史家フェルナン・ブローデルの『フランスのアイデンテティ』(1986年)によれば、フランスを一つの国、一つの文化にしたものが鉄道だった。それまでフランスは、政治的には統一されていたものの、自己完結した地域の集合体にすぎなかった。」
上記の文章はeコマースが社会や経済を変えていくことの歴史上の例えとして書かれたものである。21世紀は確かにeコマースが19世紀の鉄道のように世の中や経済を変えてきている。
九州でもeコマースによる変化が進行しているが、来年3月には九州新幹線博多・八代間が開通し、博多から鹿児島までが極めて短い時間で行き来することができるようになる。恐らくドラッカーが言うように、鉄道により経済や心理的な地理概念が一変することになりそうだ。
山陽新幹線が博多まで来たのは昭和51年だったと思う。この影響で福岡は大きく発展した。福岡にとっては山陽新幹線ほどのインパクトはないという見方もあるが、熊本や鹿児島にとってはたぶん大きなインパクトになるに違いない。
そこで重要なことは“地理的な概念”が変わることではなかろうか。この概念が変わると、人々の行動や意識が大きく変化し、その結果、経済の構造が大きく変化することになる。「九州は一つひとつ」と言われることもあるが、人々の意識の面で一つの地域になるほどインパクトがあるかどうかまでは分からない。
「鉄道こそ、産業革命を真の革命にするものだった。経済を変えただけでなく、心理的な地理概念を変えた。人類が初めて本当の移動能力を得た。初めて普通の人の世界が広がった。しかも、その結果生じた世界観の変化は、ただちに広く認識された。」(76P)
「フランスの歴史家フェルナン・ブローデルの『フランスのアイデンテティ』(1986年)によれば、フランスを一つの国、一つの文化にしたものが鉄道だった。それまでフランスは、政治的には統一されていたものの、自己完結した地域の集合体にすぎなかった。」
上記の文章はeコマースが社会や経済を変えていくことの歴史上の例えとして書かれたものである。21世紀は確かにeコマースが19世紀の鉄道のように世の中や経済を変えてきている。
九州でもeコマースによる変化が進行しているが、来年3月には九州新幹線博多・八代間が開通し、博多から鹿児島までが極めて短い時間で行き来することができるようになる。恐らくドラッカーが言うように、鉄道により経済や心理的な地理概念が一変することになりそうだ。
山陽新幹線が博多まで来たのは昭和51年だったと思う。この影響で福岡は大きく発展した。福岡にとっては山陽新幹線ほどのインパクトはないという見方もあるが、熊本や鹿児島にとってはたぶん大きなインパクトになるに違いない。
そこで重要なことは“地理的な概念”が変わることではなかろうか。この概念が変わると、人々の行動や意識が大きく変化し、その結果、経済の構造が大きく変化することになる。「九州は一つひとつ」と言われることもあるが、人々の意識の面で一つの地域になるほどインパクトがあるかどうかまでは分からない。
Posted by わくわくなひと at
12:32
│Comments(0)
2010年03月18日
広告はもういらない!・・・ツイッターノミクス
~eコマースが消費者行動を変え経済全体を変える~
P・Fドラッカー『ネクスト・ソサエティ』の中で、次の箇所が気になっていた。
「これらのことは、eコマースのインパクトについてもう一つ重要なことを教える。
流通チャネルは、顧客が誰かを変える。顧客がどのように買うかだけでなく、何を買うかを変える。消費者行動を変え、貯蓄パターンを変え、産業構造を変える。ひとことで言えば、経済全体を変える。」(1999年初出)
この文章は10年前に書かれたものであり、確かにeコマースのインパクトを十分感じる世の中になってきた。
“消費者行動を変え、・・・産業構造を変える。”その姿はおぼろげながら見えてきている。かつて繁栄し憧れの対象でもあった百貨店、新聞、広告代理店などが構造不況業種と言われる世の中になってきている。
~今の大きな流れ、要因、構造のダイナミックな変化が分かる本~
世の中がどんな風にダイナミックに変化していっているのか?百貨店や新聞などの不振について現象面に関わる情報は多い。しかし、それがどのような大きな流れで、どのような要因や構造でダイナミックに変化しているのか、掴みかねていた。
タラ・ハント『ツイッターノミクス(TwitterNomics)』(文藝春秋、2010年3月10日第一刷、原書名『THE WHUFFIE FACTOR Using the power of social networks to build your business by Tara Hunt』)は、私にとって、そんな疑問に答えてくれる感動的な本になった。Web2.0の数々のツールで、米国の消費者行動が変わり、産業構造も変わり、ビジネスのやり方が革命的に変わっていく様が克明に綴られている。
~ウッフィーがキーワード~
今、ツイッターがけっこう話題になっているが、ツイッターのノウハウ本ではない。
この本のキーワードは、“ウッフィー”である。ウェブの世界では「お金」よりはるかに価値のある「通貨」とも言える、このウッフィーが重要であるとする。ウッフィーは与えることによって増え、貢献することによってたまっていく、人や企業にとっての消費者の気持ちの有り様のようなものである。ウッフィーとは、信頼、評判、尊敬、影響力、人脈、好意などなどの積み重ねの中から生まれるものという。ウッフィーを増やすのに資本金や規模は関係ない。ホームワーカーも、小さなお店の店主も、アーティストも、NPOも、ソーシャルネットワークを使ってウッフィーを増やし、ビジネスを広げている状況が語られる。
~Twitterはテレビ広告よりも時には効く~
かつて、物を買わせようとするならば、テレビや新聞などのマスメディアの広告を使うしかなかった。SNSの登場は消費者の購買行動に劇的な変化を起こした。Twitterはテレビ広告よりも時には効くという事例も示されている。Webの世界でお金をもらって記事を書いたら、信頼を失う。何よりも信頼を勝ち得ること、つながりを維持し拡げ、頼れる友になる。背信行為は絶対にしない。ほんものの絆、ほんものの関係を育てることが掟であることが述べられている。
~広告は無視。ウッフィーを増やすマーケティングへ~
企業は「自分の声を聞かせる」から「ユーザーの声を聞く」姿勢に転換することが大事。インターネットがすべてを変えた。「人々がさまざまなメディアを使って発言できるようになると、人々は作られた広告を無視するようになった。インターネットは、小さなささやきを何千倍、何万倍にも増幅するクチコミ製造メディアとみなすことができる。かつて企業が「大声でわめく」ために持っていたメガホンは、いまや顧客の側にある」。「大声でわめくマーケティングから、コストは少ないが顧客忠誠を高められるマーケティング、そう、ウッフィーを増やすマーケティングへ」変わっていくことが求められている。「ふつうの人の情報発信力は日増しに強力になっているし、誰もが賢くお金を使いたいと考えるようになっている。もし同じような商品が二つあって、一方は広告主体の伝統的なブランド戦略に基づいて売られ、もう一方は多くのコミュニティで取り上げられ、支持され、愉快なコミュニティが生まれていたら、あなたはどちらを選ぶだろうか」。
~ただ一人の顧客を描き商品を設計する~
「旧来のマーケティング手法、グループセグメントはウェブではうまく機能しない。ただ一人の顧客を思い描いて、商品を設計し語りかける。するとうまくいく」。ウォルマートはある一人の女性客にフォーカスしている。グーグルは「せっかちな検索者」、アマゾンは「ベストセラーでは満足せず、広くあるいは深く読書をするタイプ」を想定しており、「時間をかけて顧客のニーズを見きわめ、強いつながりをつくってきた」という。「一部の専門家は、こうした顧客プロフィールの分析手法を、人口統計学的なデモグラフィックス、心理学的なサイコグラフィックスに対比させて、ソーシャルグラフィックス」と呼んでいる。
~リサーチもマスリサーチから個別リサーチへ~
実のところ、私が関係するリサーチのやり方も、米国ほどではないが日々変化してきている。コア・カスタマーをハンティングし、例えば4人のカスタマーをよく知って友だちになり、商品開発や改良のヒントを得ていく。日本においても、商品コンセプトの評価の段階では1対1のデプスインタビューや、何重もの抽出条件を満たした人たちに自由に雑談してもらうグループインタビューが主流になってきている。つまり、例えばネットリサーチなど400人のサンプルから得られた人物像ではなく、実在の人物から、「こんなことが好きで、こんなことがきらいで、こんな夢を持っていて、こんな悩みを抱えていて、こんな友達がいる」などの話を聞いて、「こんなのを待っていた」と言われるような多くの発見をしていくのがリサーチの主流になろうとしている(これは私自身が今経験していることである)。
~ギフト経済の原理で動くオンライン・コミュニティ~
さらに、この本ではSNSの世界をギフト経済の考え方で説明している。「ギフト経済は市場経済と並行して機能し、市場経済でお金をやりとりするように、贈りものをやりとりする。贈りもののやりとりが増えれば増えるほど、ウッフィーが増えるのがギフト経済の原理だ。お金と贈りもののちがいは、お金は使えば貯金は減るが、贈りものをあげるとウッフィーが増える点にある。」という。「贈りものは、人と人とを結びつける。そして、ギブ・アンド・テイクの精神を生む。」。オンライン・コミュニティは、このギフト経済の原理で動いているという。
そして、この世界で生きていく企業の大事な視点として、以下の点をあげており、自らの会社の方針を考える際の参考にさせてもらいたいと思っている。
○よいことをして成功する
○まず顧客のことを考える
○顧客にパワーを与える
○顧客が誰かを助けるのを助ける
○事業活動の枠を超えたことをする
○コミュニティ全体に大きな贈りものをする
なお、この本があまりにも感動的でしたので、いくつかの参考文献を読みたくなりました。それも、古本ばかりですがアマゾンですぐ手配できるほど、私の周りも様変わりしていることを改めて実感しております。
■リック・レバレインほか『これまでのビジネスのやり方は終わりだ』日本経済新聞社(2001年3月23日第1刷)・・・アマゾンの古本を購入
■コリイ・ドクトロウ『マジック・キングダムで落ちぶれて』ハヤカワ文庫・・・アマゾンで古本を購入
■マット・リドレー『徳の起源-他人を思いやる遺伝子』・・・10,000円以上するので様子見
■ロバート・パットナム『孤独なボウリング-米国コミュニティの崩壊と再生』・・・これからアマゾンで検索
■ミハイ・チクセントミハイ『フロー体験 喜びの現象学』・・・これからアマゾンで検索
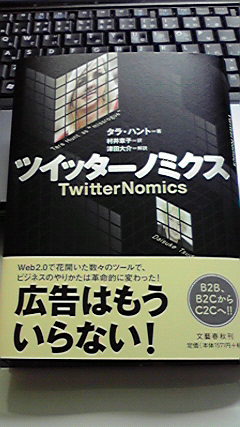
P・Fドラッカー『ネクスト・ソサエティ』の中で、次の箇所が気になっていた。
「これらのことは、eコマースのインパクトについてもう一つ重要なことを教える。
流通チャネルは、顧客が誰かを変える。顧客がどのように買うかだけでなく、何を買うかを変える。消費者行動を変え、貯蓄パターンを変え、産業構造を変える。ひとことで言えば、経済全体を変える。」(1999年初出)
この文章は10年前に書かれたものであり、確かにeコマースのインパクトを十分感じる世の中になってきた。
“消費者行動を変え、・・・産業構造を変える。”その姿はおぼろげながら見えてきている。かつて繁栄し憧れの対象でもあった百貨店、新聞、広告代理店などが構造不況業種と言われる世の中になってきている。
~今の大きな流れ、要因、構造のダイナミックな変化が分かる本~
世の中がどんな風にダイナミックに変化していっているのか?百貨店や新聞などの不振について現象面に関わる情報は多い。しかし、それがどのような大きな流れで、どのような要因や構造でダイナミックに変化しているのか、掴みかねていた。
タラ・ハント『ツイッターノミクス(TwitterNomics)』(文藝春秋、2010年3月10日第一刷、原書名『THE WHUFFIE FACTOR Using the power of social networks to build your business by Tara Hunt』)は、私にとって、そんな疑問に答えてくれる感動的な本になった。Web2.0の数々のツールで、米国の消費者行動が変わり、産業構造も変わり、ビジネスのやり方が革命的に変わっていく様が克明に綴られている。
~ウッフィーがキーワード~
今、ツイッターがけっこう話題になっているが、ツイッターのノウハウ本ではない。
この本のキーワードは、“ウッフィー”である。ウェブの世界では「お金」よりはるかに価値のある「通貨」とも言える、このウッフィーが重要であるとする。ウッフィーは与えることによって増え、貢献することによってたまっていく、人や企業にとっての消費者の気持ちの有り様のようなものである。ウッフィーとは、信頼、評判、尊敬、影響力、人脈、好意などなどの積み重ねの中から生まれるものという。ウッフィーを増やすのに資本金や規模は関係ない。ホームワーカーも、小さなお店の店主も、アーティストも、NPOも、ソーシャルネットワークを使ってウッフィーを増やし、ビジネスを広げている状況が語られる。
~Twitterはテレビ広告よりも時には効く~
かつて、物を買わせようとするならば、テレビや新聞などのマスメディアの広告を使うしかなかった。SNSの登場は消費者の購買行動に劇的な変化を起こした。Twitterはテレビ広告よりも時には効くという事例も示されている。Webの世界でお金をもらって記事を書いたら、信頼を失う。何よりも信頼を勝ち得ること、つながりを維持し拡げ、頼れる友になる。背信行為は絶対にしない。ほんものの絆、ほんものの関係を育てることが掟であることが述べられている。
~広告は無視。ウッフィーを増やすマーケティングへ~
企業は「自分の声を聞かせる」から「ユーザーの声を聞く」姿勢に転換することが大事。インターネットがすべてを変えた。「人々がさまざまなメディアを使って発言できるようになると、人々は作られた広告を無視するようになった。インターネットは、小さなささやきを何千倍、何万倍にも増幅するクチコミ製造メディアとみなすことができる。かつて企業が「大声でわめく」ために持っていたメガホンは、いまや顧客の側にある」。「大声でわめくマーケティングから、コストは少ないが顧客忠誠を高められるマーケティング、そう、ウッフィーを増やすマーケティングへ」変わっていくことが求められている。「ふつうの人の情報発信力は日増しに強力になっているし、誰もが賢くお金を使いたいと考えるようになっている。もし同じような商品が二つあって、一方は広告主体の伝統的なブランド戦略に基づいて売られ、もう一方は多くのコミュニティで取り上げられ、支持され、愉快なコミュニティが生まれていたら、あなたはどちらを選ぶだろうか」。
~ただ一人の顧客を描き商品を設計する~
「旧来のマーケティング手法、グループセグメントはウェブではうまく機能しない。ただ一人の顧客を思い描いて、商品を設計し語りかける。するとうまくいく」。ウォルマートはある一人の女性客にフォーカスしている。グーグルは「せっかちな検索者」、アマゾンは「ベストセラーでは満足せず、広くあるいは深く読書をするタイプ」を想定しており、「時間をかけて顧客のニーズを見きわめ、強いつながりをつくってきた」という。「一部の専門家は、こうした顧客プロフィールの分析手法を、人口統計学的なデモグラフィックス、心理学的なサイコグラフィックスに対比させて、ソーシャルグラフィックス」と呼んでいる。
~リサーチもマスリサーチから個別リサーチへ~
実のところ、私が関係するリサーチのやり方も、米国ほどではないが日々変化してきている。コア・カスタマーをハンティングし、例えば4人のカスタマーをよく知って友だちになり、商品開発や改良のヒントを得ていく。日本においても、商品コンセプトの評価の段階では1対1のデプスインタビューや、何重もの抽出条件を満たした人たちに自由に雑談してもらうグループインタビューが主流になってきている。つまり、例えばネットリサーチなど400人のサンプルから得られた人物像ではなく、実在の人物から、「こんなことが好きで、こんなことがきらいで、こんな夢を持っていて、こんな悩みを抱えていて、こんな友達がいる」などの話を聞いて、「こんなのを待っていた」と言われるような多くの発見をしていくのがリサーチの主流になろうとしている(これは私自身が今経験していることである)。
~ギフト経済の原理で動くオンライン・コミュニティ~
さらに、この本ではSNSの世界をギフト経済の考え方で説明している。「ギフト経済は市場経済と並行して機能し、市場経済でお金をやりとりするように、贈りものをやりとりする。贈りもののやりとりが増えれば増えるほど、ウッフィーが増えるのがギフト経済の原理だ。お金と贈りもののちがいは、お金は使えば貯金は減るが、贈りものをあげるとウッフィーが増える点にある。」という。「贈りものは、人と人とを結びつける。そして、ギブ・アンド・テイクの精神を生む。」。オンライン・コミュニティは、このギフト経済の原理で動いているという。
そして、この世界で生きていく企業の大事な視点として、以下の点をあげており、自らの会社の方針を考える際の参考にさせてもらいたいと思っている。
○よいことをして成功する
○まず顧客のことを考える
○顧客にパワーを与える
○顧客が誰かを助けるのを助ける
○事業活動の枠を超えたことをする
○コミュニティ全体に大きな贈りものをする
なお、この本があまりにも感動的でしたので、いくつかの参考文献を読みたくなりました。それも、古本ばかりですがアマゾンですぐ手配できるほど、私の周りも様変わりしていることを改めて実感しております。
■リック・レバレインほか『これまでのビジネスのやり方は終わりだ』日本経済新聞社(2001年3月23日第1刷)・・・アマゾンの古本を購入
■コリイ・ドクトロウ『マジック・キングダムで落ちぶれて』ハヤカワ文庫・・・アマゾンで古本を購入
■マット・リドレー『徳の起源-他人を思いやる遺伝子』・・・10,000円以上するので様子見
■ロバート・パットナム『孤独なボウリング-米国コミュニティの崩壊と再生』・・・これからアマゾンで検索
■ミハイ・チクセントミハイ『フロー体験 喜びの現象学』・・・これからアマゾンで検索
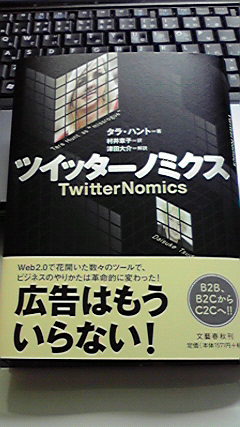
Posted by わくわくなひと at
20:53
│Comments(0)
2010年03月16日
州都の場所で論議するようでは駄目だ!
新聞には閑話休題のように、ところどころ新聞記者やデスクが書いたコラムがあります。新聞を編集する人たちの息づかいが分かるような気がして、けっこうムフッと思うようなことが多いですね。
3月13日付け西日本新聞の「気流」に、九州経済連合会などが福岡市で開いた「道州制シンポジウム」のことが書いてありました。
前鳥取県知事の片山義博・慶応大学教授の講演は、予想に違わず聴衆を引きつけたそうです。コラム氏も面白かったと書いていますが、私も読んだだけですが記憶に残りました。
「面白かったのは「州都」論議への問題提起だ。米国では小都市の州都が多いことを例に挙げ、「基礎的自治体がちゃんと機能すれば、住民らが州都もうでする必要などない」「州都で論議するようでは駄目だ」と歯切れがいい。少し耳が痛かった。」
そうかも知れません。都があるところにカネと権力があり、そうでないところは都詣でする。21世紀の政治と経済は、そんなことを目指すべきではないし、そんなことが頭にあるとしたら少し寂しいような気がしました。
見出し付きの情報ではありませんが、私にとっては13日付けの西日本新聞で最も重要な視点を教えてくれたコラムでした。
3月13日付け西日本新聞の「気流」に、九州経済連合会などが福岡市で開いた「道州制シンポジウム」のことが書いてありました。
前鳥取県知事の片山義博・慶応大学教授の講演は、予想に違わず聴衆を引きつけたそうです。コラム氏も面白かったと書いていますが、私も読んだだけですが記憶に残りました。
「面白かったのは「州都」論議への問題提起だ。米国では小都市の州都が多いことを例に挙げ、「基礎的自治体がちゃんと機能すれば、住民らが州都もうでする必要などない」「州都で論議するようでは駄目だ」と歯切れがいい。少し耳が痛かった。」
そうかも知れません。都があるところにカネと権力があり、そうでないところは都詣でする。21世紀の政治と経済は、そんなことを目指すべきではないし、そんなことが頭にあるとしたら少し寂しいような気がしました。
見出し付きの情報ではありませんが、私にとっては13日付けの西日本新聞で最も重要な視点を教えてくれたコラムでした。
Posted by わくわくなひと at
00:21
│Comments(0)
2010年03月15日
TENJIN MAGAZINE EPが雁林町通りを紹介
西鉄高速バスの車内誌「TENJIN MAGAZINE EP」が大名を特集していました。
タイトルは「I ラブ(ハート) DAIMYO まちあるきツアー」で、何とウチの事務所がある雁林町(がんりんのちょう)通りの名物店が紹介されていました。
雁林町通りは別名ボンジュール通りと言われます。27年前からあるそうで、午前7時の開店。朝から通りにパンの香りが漂います。写真付きで紹介されていました。
ただ、この冊子のライターさん!愛嬌でしょうが「新雁林町通り」と間違って書いてありました。「新雁林町通り」は天神西通りのケンタッキーから大正通りに向けての通りのことで、有名な「一風堂」ラーメンがある通りです。雁林町通りは、この通りよりも少し奥まったところにある通りです。
それと、二年前一度入ったきりでご無沙汰しておりました「海鮮食堂すいか」も載ってました。ウチの事務所のあるビルのとんと真向かい。出張族も目を丸くする「いわしの梅揚げ」が紹介されており、「それなら」と食べに行ってきました。
若い気合いの入ったおにいさんたちが店を切り盛りしており、まあいいじゃないですか。
このほかウチの事務所のお客さん向けによく買う駒屋の「豆大福」、昭和の定食が味わえる「一膳めし 青木堂」、あのガラスケースをガラッと開けて好きなおかずが選べる店ですよ。
若い男女がうろうろしてて、楽しいまちです。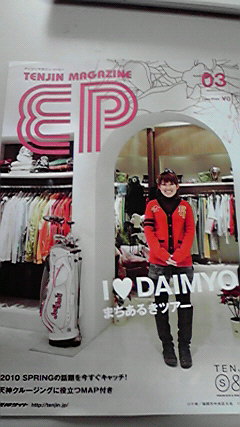

タイトルは「I ラブ(ハート) DAIMYO まちあるきツアー」で、何とウチの事務所がある雁林町(がんりんのちょう)通りの名物店が紹介されていました。
雁林町通りは別名ボンジュール通りと言われます。27年前からあるそうで、午前7時の開店。朝から通りにパンの香りが漂います。写真付きで紹介されていました。
ただ、この冊子のライターさん!愛嬌でしょうが「新雁林町通り」と間違って書いてありました。「新雁林町通り」は天神西通りのケンタッキーから大正通りに向けての通りのことで、有名な「一風堂」ラーメンがある通りです。雁林町通りは、この通りよりも少し奥まったところにある通りです。
それと、二年前一度入ったきりでご無沙汰しておりました「海鮮食堂すいか」も載ってました。ウチの事務所のあるビルのとんと真向かい。出張族も目を丸くする「いわしの梅揚げ」が紹介されており、「それなら」と食べに行ってきました。
若い気合いの入ったおにいさんたちが店を切り盛りしており、まあいいじゃないですか。
このほかウチの事務所のお客さん向けによく買う駒屋の「豆大福」、昭和の定食が味わえる「一膳めし 青木堂」、あのガラスケースをガラッと開けて好きなおかずが選べる店ですよ。
若い男女がうろうろしてて、楽しいまちです。
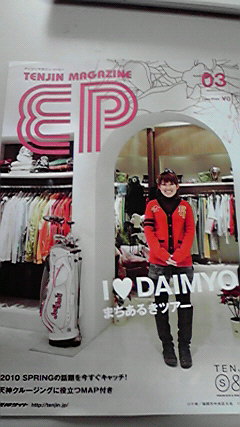

Posted by わくわくなひと at
23:55
│Comments(0)
2010年03月14日
それでも、日本人は「戦争」を選んだ
加藤陽子さんという東大文学部の教授が書いた本である。
表紙には、『普通のよき日本人が、世界最高の頭脳たちが、「もう戦争しかない」と思ったのはなぜか?高校生に語る-日本近現代史の最前線』と書いてある。
2009年7月に初版第一刷、同12月に第十一刷。けっこう売れている。
内容は日清、日露、第一次世界大戦、満州事変・日中戦争、太平洋戦争について、「自分が作戦計画の立案者であったなら」、「自分が満州移民として送り出される立場であったなら」と高校生に考えさせるための講義内容をまとめている。
後世、人々の思いや行動の結果が分かっている立場で、その時の人々を「何と愚かなことをしたことか」と指弾したり、嘆くような内容ではない。かといって戦争を肯定したり、日本人の行動を一方的に美化するような内容でもない。
「なぜ日本は300万人の犠牲者を出すような戦争を始めたのか」という根源的な問いの話、多くの人が意志決定に際し、過去の人々の行動をけっこう参考にしている事例など、歴史が単なる暗記科目ではなく、その人が人生を送っていく際に非常に重要な知識であることを教えてくれる本だと思った。
今年に入り、かつての史学科の同級生とお酒を飲む機会があった。同級生の四分の一程度は高校や大学の教師になっている。その時も、日本の戦争をどう教えるのかということがけっこう話題になる。
人々の認識が暗記科目から重要な科目へと変わる日が、いつか来るかも知れないと、この本を読んで、そう思ってしまった。

表紙には、『普通のよき日本人が、世界最高の頭脳たちが、「もう戦争しかない」と思ったのはなぜか?高校生に語る-日本近現代史の最前線』と書いてある。
2009年7月に初版第一刷、同12月に第十一刷。けっこう売れている。
内容は日清、日露、第一次世界大戦、満州事変・日中戦争、太平洋戦争について、「自分が作戦計画の立案者であったなら」、「自分が満州移民として送り出される立場であったなら」と高校生に考えさせるための講義内容をまとめている。
後世、人々の思いや行動の結果が分かっている立場で、その時の人々を「何と愚かなことをしたことか」と指弾したり、嘆くような内容ではない。かといって戦争を肯定したり、日本人の行動を一方的に美化するような内容でもない。
「なぜ日本は300万人の犠牲者を出すような戦争を始めたのか」という根源的な問いの話、多くの人が意志決定に際し、過去の人々の行動をけっこう参考にしている事例など、歴史が単なる暗記科目ではなく、その人が人生を送っていく際に非常に重要な知識であることを教えてくれる本だと思った。
今年に入り、かつての史学科の同級生とお酒を飲む機会があった。同級生の四分の一程度は高校や大学の教師になっている。その時も、日本の戦争をどう教えるのかということがけっこう話題になる。
人々の認識が暗記科目から重要な科目へと変わる日が、いつか来るかも知れないと、この本を読んで、そう思ってしまった。

Posted by わくわくなひと at
15:57
│Comments(0)
2010年03月14日
宮本輝の芥川賞選評“行間のない文学”
二十一年度下半期の芥川賞は該当者なしだった。このような事態は十数年ぶりという。
例によって、文藝春秋三月特別号に芥川賞選評が載っており、同僚が宮本輝の選評は“さすが”と教えてくれた。
宮本氏の選評の見出しは、「行間のない文学」。同氏曰く、『委員ひとりひとりは、言葉は違っても、どの候補作に対しても「何かが足りない」という意味の、それもかなり辛辣な評価をした。』。さらに『だが、残念ながら、「何かが足りない」と言うしかないのだ。これはなにも文学に限ったことではない。芸能の世界においても、物を作る職人の世界においても、スポーツの世界においても、あるいはひとりの人間の領域においても同じである。自分にとって決定的に足りない何かがいったい何であるのかについて、結局は、自分で考え抜いて掴んだものしか現場では役に立たないのだ。』。
そうだと思う。私は小説家ではなく“ものづくり屋”だが、この宮本氏の言っていることが心に響いた。
自分流の解釈で言えば、宮本氏の思いは、“わかる”“ひらめき”などのことを言っているのではないかと思った。
通り一遍の文章や情報などを得て、「わかりました」ということとは違う。テストやゲームで正解したこととは違う次元の話ではないか。
自分の周りのことで言えば、商品企画、事業のアイデア、スポーツなどに打ち込んで、悩み抜いたり、夢中になって体を何度も動かしていくうちに、ある時、“これだ!”“わかった!”という瞬間がある。この世界のことを宮本氏は言っているのではなかろうか。
三週間前に、鮮魚小売りの社長さんから話を聞いた。天草から熊本市内に魚を生きたまま運んで販売する事業で成功した社長さんの話である。
この事業を思いついた時は、海運業をやっておられ、莫大な借金を抱えておられたという。魚を生きたまま都市に運んで売るというアイデアは、来島海峡を通り抜けている時、突然ひらめいたそうである。もちろん、追い詰められ悩み抜いた末の瞬間だったと思う。

例によって、文藝春秋三月特別号に芥川賞選評が載っており、同僚が宮本輝の選評は“さすが”と教えてくれた。
宮本氏の選評の見出しは、「行間のない文学」。同氏曰く、『委員ひとりひとりは、言葉は違っても、どの候補作に対しても「何かが足りない」という意味の、それもかなり辛辣な評価をした。』。さらに『だが、残念ながら、「何かが足りない」と言うしかないのだ。これはなにも文学に限ったことではない。芸能の世界においても、物を作る職人の世界においても、スポーツの世界においても、あるいはひとりの人間の領域においても同じである。自分にとって決定的に足りない何かがいったい何であるのかについて、結局は、自分で考え抜いて掴んだものしか現場では役に立たないのだ。』。
そうだと思う。私は小説家ではなく“ものづくり屋”だが、この宮本氏の言っていることが心に響いた。
自分流の解釈で言えば、宮本氏の思いは、“わかる”“ひらめき”などのことを言っているのではないかと思った。
通り一遍の文章や情報などを得て、「わかりました」ということとは違う。テストやゲームで正解したこととは違う次元の話ではないか。
自分の周りのことで言えば、商品企画、事業のアイデア、スポーツなどに打ち込んで、悩み抜いたり、夢中になって体を何度も動かしていくうちに、ある時、“これだ!”“わかった!”という瞬間がある。この世界のことを宮本氏は言っているのではなかろうか。
三週間前に、鮮魚小売りの社長さんから話を聞いた。天草から熊本市内に魚を生きたまま運んで販売する事業で成功した社長さんの話である。
この事業を思いついた時は、海運業をやっておられ、莫大な借金を抱えておられたという。魚を生きたまま都市に運んで売るというアイデアは、来島海峡を通り抜けている時、突然ひらめいたそうである。もちろん、追い詰められ悩み抜いた末の瞬間だったと思う。

Posted by わくわくなひと at
13:12
│Comments(2)
2010年03月14日
本屋には、ネットやメディアにない最新情報がありますね!
ここ二ヶ月近く土曜日も日曜日もなく仕事していました。
その間も本は読んでおりましたが、書店まで出かけるほどの心の余裕はありませんでした。
その代わり、新聞などの書評を見て、アマゾンで一万円近くを費やし、いろんな本を買い込んできました。
久々に今日は天神の丸善に行き、やはり本屋には行くものだと、つくづく思いました。
というのが、新聞やネットなどのメディアからの情報だけでは、自分の関心のほんの一部しかカバーできないということを思い知りました。
新聞やネットに流れる情報以外にも、自分にはたくさん関心のある分野があると、今日は思い知らされました。
その中で今日、丸善で自分のアンテナに引っかかったのは、次の本です。
■岩崎夏海『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』ダイヤモンド社、2009年12月3日第1刷、2010年1月22日第4刷
・昨年の11月ごろから私の周りのよく話題になる本でした。私の周りと言えばおじさんが多いのですが、女子高生のマンガの挿絵がある本をオヤジが書店で購入している。そんな本です。東京の書店では、この数ヶ月の間、常にベストセラーのトップ10にランクインしている本です。熊本では火の国銀行が常にランクインしていますが、全国的にはこの本がオヤジによく読まれています。とうとう会社の同僚がこの本を買うことになりました。
■タラ・ハント『ツイッターノミクス』文藝春秋、2010年3月10日第1刷
・最近、私の周りでもツイッターの有効性を話す人が増えてきました。これは何なんだろう。社会に相当インパクトがあるツールなのかどうか。ツイッターにはまっている人たちは夢中になって、目を丸くして話ます。あまりにも周りがそうなので、やはり読んでみようという気になりました。個人的には、あまり時代に流されたくないのですが・・・。
■成田龍一『<歴史>はいかに語られるか』ちくま文芸文庫、2010年3月10日第1刷
・いろんな意志決定に際し、その人が持つ歴史認識が影響を与えていることが次第に自覚されるようになってきました。今までは「自分は過去や歴史とは関係ない。今の時代の流れや未来に生きる。」。そんな人が大勢を占めていたような気がします。しかし、一人の人間が蓄えることができる経験や知識は知れたものです。これからは過去の歴史のことを知らなければ、まともな意志決定はできません。たぶん、そんな歴史学復興の書だと思います。
■梅澤伸嘉『ヒット商品開発第2版 MIPパワーの秘密』同文舘出版、平成21年12月25日第2版
・僭越ですが私の師匠の本です。少し高い本です。昨年12月に丸善に平積みされていましたが、あえて買いませんでした。第1版は平成16年第1刷で同20年7月に第5刷ですから、まあまあ読まれている本だと改めて気づきました。昨年末に買わなくて今頃買う気になったのは、もちろん第1版は持っていますが、今回は企業の導入事例が10ケース余り書いてあるからです。大手メーカーさんの間では“梅澤理論”ということで共通語になっていますが、最近、大手メーカーさんのリサーチの仕事をして改めて気づいたことがあったからです。私が携わった大手メーカーさんは、梅澤理論をかじった人がいますが、ほんの一部の単語程度しか知らないで我流で商品を開発していることに戦慄が走る思いをしたからです。この本を読んで、改めて“梅澤理論”を本当に生かす方法を考えてみたいと思っています。
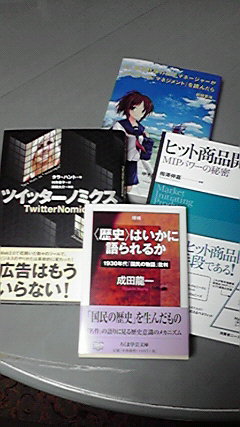
その間も本は読んでおりましたが、書店まで出かけるほどの心の余裕はありませんでした。
その代わり、新聞などの書評を見て、アマゾンで一万円近くを費やし、いろんな本を買い込んできました。
久々に今日は天神の丸善に行き、やはり本屋には行くものだと、つくづく思いました。
というのが、新聞やネットなどのメディアからの情報だけでは、自分の関心のほんの一部しかカバーできないということを思い知りました。
新聞やネットに流れる情報以外にも、自分にはたくさん関心のある分野があると、今日は思い知らされました。
その中で今日、丸善で自分のアンテナに引っかかったのは、次の本です。
■岩崎夏海『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』ダイヤモンド社、2009年12月3日第1刷、2010年1月22日第4刷
・昨年の11月ごろから私の周りのよく話題になる本でした。私の周りと言えばおじさんが多いのですが、女子高生のマンガの挿絵がある本をオヤジが書店で購入している。そんな本です。東京の書店では、この数ヶ月の間、常にベストセラーのトップ10にランクインしている本です。熊本では火の国銀行が常にランクインしていますが、全国的にはこの本がオヤジによく読まれています。とうとう会社の同僚がこの本を買うことになりました。
■タラ・ハント『ツイッターノミクス』文藝春秋、2010年3月10日第1刷
・最近、私の周りでもツイッターの有効性を話す人が増えてきました。これは何なんだろう。社会に相当インパクトがあるツールなのかどうか。ツイッターにはまっている人たちは夢中になって、目を丸くして話ます。あまりにも周りがそうなので、やはり読んでみようという気になりました。個人的には、あまり時代に流されたくないのですが・・・。
■成田龍一『<歴史>はいかに語られるか』ちくま文芸文庫、2010年3月10日第1刷
・いろんな意志決定に際し、その人が持つ歴史認識が影響を与えていることが次第に自覚されるようになってきました。今までは「自分は過去や歴史とは関係ない。今の時代の流れや未来に生きる。」。そんな人が大勢を占めていたような気がします。しかし、一人の人間が蓄えることができる経験や知識は知れたものです。これからは過去の歴史のことを知らなければ、まともな意志決定はできません。たぶん、そんな歴史学復興の書だと思います。
■梅澤伸嘉『ヒット商品開発第2版 MIPパワーの秘密』同文舘出版、平成21年12月25日第2版
・僭越ですが私の師匠の本です。少し高い本です。昨年12月に丸善に平積みされていましたが、あえて買いませんでした。第1版は平成16年第1刷で同20年7月に第5刷ですから、まあまあ読まれている本だと改めて気づきました。昨年末に買わなくて今頃買う気になったのは、もちろん第1版は持っていますが、今回は企業の導入事例が10ケース余り書いてあるからです。大手メーカーさんの間では“梅澤理論”ということで共通語になっていますが、最近、大手メーカーさんのリサーチの仕事をして改めて気づいたことがあったからです。私が携わった大手メーカーさんは、梅澤理論をかじった人がいますが、ほんの一部の単語程度しか知らないで我流で商品を開発していることに戦慄が走る思いをしたからです。この本を読んで、改めて“梅澤理論”を本当に生かす方法を考えてみたいと思っています。
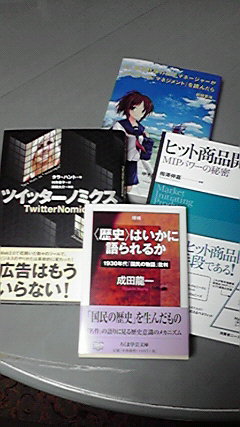
Posted by わくわくなひと at
00:26
│Comments(0)
2010年03月13日
今日から福岡、東京での行動が便利に!
いやはや待ってました。この日を長く待ってました。
今日からIC乗車券の「SUGOKA」「はやかけん」「nimoca」「Suica」の相互利用が始まりました。
実は「はやかけん」「nimoca」「PASMO」の3つのIC乗車券を持っているのです。一番使うのが西鉄の「nimoca」。たまに福岡の地下鉄に乗るために「はやかけん」、平均して月に一度は東京に行ってますので「PASMO」(東京の私鉄、バス、JRが使える)を持っていました。
三枚もIC乗車券があると財布が膨れますので、早く相互利用にならないかと、今日3月13日を待ち望んでおりました。
東京は数年前から相互利用できるのに、まだ福岡ではできない。イライラしていました。
今日から一番使用頻度の高い「nimoca」一枚で、福岡県内と首都圏で行動できることになります。やれやれ!
この「nimoca」が熊本県内で使えるのは、JR荒尾駅と高速バス「ひのくに号」の西鉄バスだけ。
IC乗車券の導入はお金がかかるらしく、それなりの乗降客数がいないと実現できないそうです。熊本市内がそうなるのは、いつになるのでしょうか。
けっこう便利ですよ。

今日からIC乗車券の「SUGOKA」「はやかけん」「nimoca」「Suica」の相互利用が始まりました。
実は「はやかけん」「nimoca」「PASMO」の3つのIC乗車券を持っているのです。一番使うのが西鉄の「nimoca」。たまに福岡の地下鉄に乗るために「はやかけん」、平均して月に一度は東京に行ってますので「PASMO」(東京の私鉄、バス、JRが使える)を持っていました。
三枚もIC乗車券があると財布が膨れますので、早く相互利用にならないかと、今日3月13日を待ち望んでおりました。
東京は数年前から相互利用できるのに、まだ福岡ではできない。イライラしていました。
今日から一番使用頻度の高い「nimoca」一枚で、福岡県内と首都圏で行動できることになります。やれやれ!
この「nimoca」が熊本県内で使えるのは、JR荒尾駅と高速バス「ひのくに号」の西鉄バスだけ。
IC乗車券の導入はお金がかかるらしく、それなりの乗降客数がいないと実現できないそうです。熊本市内がそうなるのは、いつになるのでしょうか。
けっこう便利ですよ。

Posted by わくわくなひと at
20:57
│Comments(0)
2010年03月05日
本の編集の実験?松本清張・向田邦子『駅路/最後の自画像』
『駅路/最後の自画像』新潮社(2009年12月20日)。本や編集をテーマとした、これまでにない実験のような印象を受けた。
著者は松本清張と向田邦子。少し齢を重ねた人なら、どちらもご存じのはずである。
松本清張の本は少し読んだことがある。向田邦子脚本のテレビドラマも意識はしていないが、たぶん数多く見ているはずである。
この本は二人の有名作家がコラボしたできあがった本である。と言っても、二人とも亡くなっている。二人の作品が一冊に収められ、この名作品をテレビのプロデューサーと新潮社?の編集者が解説している。
ちょうど映画の封切り時に売られている解説書みたいな本である。いろんな人が作品を語る。いろんな視点で一つの作品が見られるので、案外面白い。この本もそんなおもむきである。
松本清張が『駅路』を書き、向田邦子がそれをもとに脚本『最後の自画像』を書き、テレビドラマとして放映された。あらすじや表現、描写、登場人物の違いがよくわかる。
先週、東京で仕事だったので飛行機の中で往路に1回、帰路に1回、計2回読んだ。1回目は素読、2回目は、どこがどう違うのかを味わうことができた。
テーマは「ゴーガンが言ったじゃないか。人間は絶えず子供の犠牲になる、それを繰り返していく、とね。それでどこに新しい芸術が出来、どこに創造があるかと彼は言うのだが、芸術の世界は別として、普通の人間にも平凡な永い人生を歩き、或る駅路に到着したとき、今まで耐え忍んだ人生を、ここらで解放してもらいたい、気儘な旅に出直したいということにならないかね。」だと思う。
松本さんの表現や描写より、向田さんのそれが艶めかしかったですね。男と女の違いでしょうか。
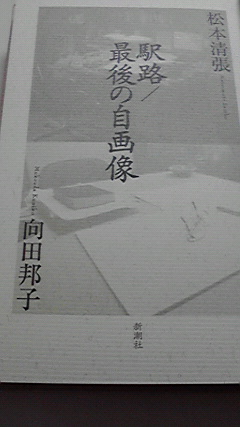
著者は松本清張と向田邦子。少し齢を重ねた人なら、どちらもご存じのはずである。
松本清張の本は少し読んだことがある。向田邦子脚本のテレビドラマも意識はしていないが、たぶん数多く見ているはずである。
この本は二人の有名作家がコラボしたできあがった本である。と言っても、二人とも亡くなっている。二人の作品が一冊に収められ、この名作品をテレビのプロデューサーと新潮社?の編集者が解説している。
ちょうど映画の封切り時に売られている解説書みたいな本である。いろんな人が作品を語る。いろんな視点で一つの作品が見られるので、案外面白い。この本もそんなおもむきである。
松本清張が『駅路』を書き、向田邦子がそれをもとに脚本『最後の自画像』を書き、テレビドラマとして放映された。あらすじや表現、描写、登場人物の違いがよくわかる。
先週、東京で仕事だったので飛行機の中で往路に1回、帰路に1回、計2回読んだ。1回目は素読、2回目は、どこがどう違うのかを味わうことができた。
テーマは「ゴーガンが言ったじゃないか。人間は絶えず子供の犠牲になる、それを繰り返していく、とね。それでどこに新しい芸術が出来、どこに創造があるかと彼は言うのだが、芸術の世界は別として、普通の人間にも平凡な永い人生を歩き、或る駅路に到着したとき、今まで耐え忍んだ人生を、ここらで解放してもらいたい、気儘な旅に出直したいということにならないかね。」だと思う。
松本さんの表現や描写より、向田さんのそれが艶めかしかったですね。男と女の違いでしょうか。
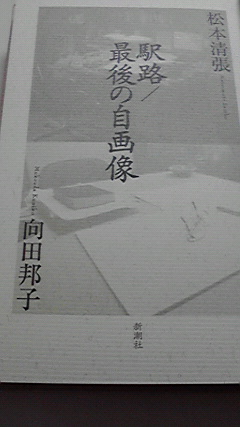
Posted by わくわくなひと at
15:02
│Comments(0)



