2010年03月18日
広告はもういらない!・・・ツイッターノミクス
~eコマースが消費者行動を変え経済全体を変える~
P・Fドラッカー『ネクスト・ソサエティ』の中で、次の箇所が気になっていた。
「これらのことは、eコマースのインパクトについてもう一つ重要なことを教える。
流通チャネルは、顧客が誰かを変える。顧客がどのように買うかだけでなく、何を買うかを変える。消費者行動を変え、貯蓄パターンを変え、産業構造を変える。ひとことで言えば、経済全体を変える。」(1999年初出)
この文章は10年前に書かれたものであり、確かにeコマースのインパクトを十分感じる世の中になってきた。
“消費者行動を変え、・・・産業構造を変える。”その姿はおぼろげながら見えてきている。かつて繁栄し憧れの対象でもあった百貨店、新聞、広告代理店などが構造不況業種と言われる世の中になってきている。
~今の大きな流れ、要因、構造のダイナミックな変化が分かる本~
世の中がどんな風にダイナミックに変化していっているのか?百貨店や新聞などの不振について現象面に関わる情報は多い。しかし、それがどのような大きな流れで、どのような要因や構造でダイナミックに変化しているのか、掴みかねていた。
タラ・ハント『ツイッターノミクス(TwitterNomics)』(文藝春秋、2010年3月10日第一刷、原書名『THE WHUFFIE FACTOR Using the power of social networks to build your business by Tara Hunt』)は、私にとって、そんな疑問に答えてくれる感動的な本になった。Web2.0の数々のツールで、米国の消費者行動が変わり、産業構造も変わり、ビジネスのやり方が革命的に変わっていく様が克明に綴られている。
~ウッフィーがキーワード~
今、ツイッターがけっこう話題になっているが、ツイッターのノウハウ本ではない。
この本のキーワードは、“ウッフィー”である。ウェブの世界では「お金」よりはるかに価値のある「通貨」とも言える、このウッフィーが重要であるとする。ウッフィーは与えることによって増え、貢献することによってたまっていく、人や企業にとっての消費者の気持ちの有り様のようなものである。ウッフィーとは、信頼、評判、尊敬、影響力、人脈、好意などなどの積み重ねの中から生まれるものという。ウッフィーを増やすのに資本金や規模は関係ない。ホームワーカーも、小さなお店の店主も、アーティストも、NPOも、ソーシャルネットワークを使ってウッフィーを増やし、ビジネスを広げている状況が語られる。
~Twitterはテレビ広告よりも時には効く~
かつて、物を買わせようとするならば、テレビや新聞などのマスメディアの広告を使うしかなかった。SNSの登場は消費者の購買行動に劇的な変化を起こした。Twitterはテレビ広告よりも時には効くという事例も示されている。Webの世界でお金をもらって記事を書いたら、信頼を失う。何よりも信頼を勝ち得ること、つながりを維持し拡げ、頼れる友になる。背信行為は絶対にしない。ほんものの絆、ほんものの関係を育てることが掟であることが述べられている。
~広告は無視。ウッフィーを増やすマーケティングへ~
企業は「自分の声を聞かせる」から「ユーザーの声を聞く」姿勢に転換することが大事。インターネットがすべてを変えた。「人々がさまざまなメディアを使って発言できるようになると、人々は作られた広告を無視するようになった。インターネットは、小さなささやきを何千倍、何万倍にも増幅するクチコミ製造メディアとみなすことができる。かつて企業が「大声でわめく」ために持っていたメガホンは、いまや顧客の側にある」。「大声でわめくマーケティングから、コストは少ないが顧客忠誠を高められるマーケティング、そう、ウッフィーを増やすマーケティングへ」変わっていくことが求められている。「ふつうの人の情報発信力は日増しに強力になっているし、誰もが賢くお金を使いたいと考えるようになっている。もし同じような商品が二つあって、一方は広告主体の伝統的なブランド戦略に基づいて売られ、もう一方は多くのコミュニティで取り上げられ、支持され、愉快なコミュニティが生まれていたら、あなたはどちらを選ぶだろうか」。
~ただ一人の顧客を描き商品を設計する~
「旧来のマーケティング手法、グループセグメントはウェブではうまく機能しない。ただ一人の顧客を思い描いて、商品を設計し語りかける。するとうまくいく」。ウォルマートはある一人の女性客にフォーカスしている。グーグルは「せっかちな検索者」、アマゾンは「ベストセラーでは満足せず、広くあるいは深く読書をするタイプ」を想定しており、「時間をかけて顧客のニーズを見きわめ、強いつながりをつくってきた」という。「一部の専門家は、こうした顧客プロフィールの分析手法を、人口統計学的なデモグラフィックス、心理学的なサイコグラフィックスに対比させて、ソーシャルグラフィックス」と呼んでいる。
~リサーチもマスリサーチから個別リサーチへ~
実のところ、私が関係するリサーチのやり方も、米国ほどではないが日々変化してきている。コア・カスタマーをハンティングし、例えば4人のカスタマーをよく知って友だちになり、商品開発や改良のヒントを得ていく。日本においても、商品コンセプトの評価の段階では1対1のデプスインタビューや、何重もの抽出条件を満たした人たちに自由に雑談してもらうグループインタビューが主流になってきている。つまり、例えばネットリサーチなど400人のサンプルから得られた人物像ではなく、実在の人物から、「こんなことが好きで、こんなことがきらいで、こんな夢を持っていて、こんな悩みを抱えていて、こんな友達がいる」などの話を聞いて、「こんなのを待っていた」と言われるような多くの発見をしていくのがリサーチの主流になろうとしている(これは私自身が今経験していることである)。
~ギフト経済の原理で動くオンライン・コミュニティ~
さらに、この本ではSNSの世界をギフト経済の考え方で説明している。「ギフト経済は市場経済と並行して機能し、市場経済でお金をやりとりするように、贈りものをやりとりする。贈りもののやりとりが増えれば増えるほど、ウッフィーが増えるのがギフト経済の原理だ。お金と贈りもののちがいは、お金は使えば貯金は減るが、贈りものをあげるとウッフィーが増える点にある。」という。「贈りものは、人と人とを結びつける。そして、ギブ・アンド・テイクの精神を生む。」。オンライン・コミュニティは、このギフト経済の原理で動いているという。
そして、この世界で生きていく企業の大事な視点として、以下の点をあげており、自らの会社の方針を考える際の参考にさせてもらいたいと思っている。
○よいことをして成功する
○まず顧客のことを考える
○顧客にパワーを与える
○顧客が誰かを助けるのを助ける
○事業活動の枠を超えたことをする
○コミュニティ全体に大きな贈りものをする
なお、この本があまりにも感動的でしたので、いくつかの参考文献を読みたくなりました。それも、古本ばかりですがアマゾンですぐ手配できるほど、私の周りも様変わりしていることを改めて実感しております。
■リック・レバレインほか『これまでのビジネスのやり方は終わりだ』日本経済新聞社(2001年3月23日第1刷)・・・アマゾンの古本を購入
■コリイ・ドクトロウ『マジック・キングダムで落ちぶれて』ハヤカワ文庫・・・アマゾンで古本を購入
■マット・リドレー『徳の起源-他人を思いやる遺伝子』・・・10,000円以上するので様子見
■ロバート・パットナム『孤独なボウリング-米国コミュニティの崩壊と再生』・・・これからアマゾンで検索
■ミハイ・チクセントミハイ『フロー体験 喜びの現象学』・・・これからアマゾンで検索
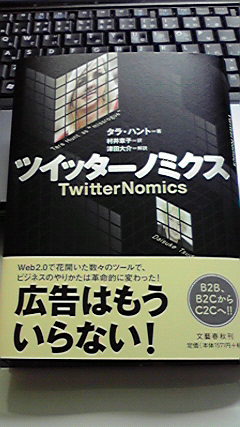
P・Fドラッカー『ネクスト・ソサエティ』の中で、次の箇所が気になっていた。
「これらのことは、eコマースのインパクトについてもう一つ重要なことを教える。
流通チャネルは、顧客が誰かを変える。顧客がどのように買うかだけでなく、何を買うかを変える。消費者行動を変え、貯蓄パターンを変え、産業構造を変える。ひとことで言えば、経済全体を変える。」(1999年初出)
この文章は10年前に書かれたものであり、確かにeコマースのインパクトを十分感じる世の中になってきた。
“消費者行動を変え、・・・産業構造を変える。”その姿はおぼろげながら見えてきている。かつて繁栄し憧れの対象でもあった百貨店、新聞、広告代理店などが構造不況業種と言われる世の中になってきている。
~今の大きな流れ、要因、構造のダイナミックな変化が分かる本~
世の中がどんな風にダイナミックに変化していっているのか?百貨店や新聞などの不振について現象面に関わる情報は多い。しかし、それがどのような大きな流れで、どのような要因や構造でダイナミックに変化しているのか、掴みかねていた。
タラ・ハント『ツイッターノミクス(TwitterNomics)』(文藝春秋、2010年3月10日第一刷、原書名『THE WHUFFIE FACTOR Using the power of social networks to build your business by Tara Hunt』)は、私にとって、そんな疑問に答えてくれる感動的な本になった。Web2.0の数々のツールで、米国の消費者行動が変わり、産業構造も変わり、ビジネスのやり方が革命的に変わっていく様が克明に綴られている。
~ウッフィーがキーワード~
今、ツイッターがけっこう話題になっているが、ツイッターのノウハウ本ではない。
この本のキーワードは、“ウッフィー”である。ウェブの世界では「お金」よりはるかに価値のある「通貨」とも言える、このウッフィーが重要であるとする。ウッフィーは与えることによって増え、貢献することによってたまっていく、人や企業にとっての消費者の気持ちの有り様のようなものである。ウッフィーとは、信頼、評判、尊敬、影響力、人脈、好意などなどの積み重ねの中から生まれるものという。ウッフィーを増やすのに資本金や規模は関係ない。ホームワーカーも、小さなお店の店主も、アーティストも、NPOも、ソーシャルネットワークを使ってウッフィーを増やし、ビジネスを広げている状況が語られる。
~Twitterはテレビ広告よりも時には効く~
かつて、物を買わせようとするならば、テレビや新聞などのマスメディアの広告を使うしかなかった。SNSの登場は消費者の購買行動に劇的な変化を起こした。Twitterはテレビ広告よりも時には効くという事例も示されている。Webの世界でお金をもらって記事を書いたら、信頼を失う。何よりも信頼を勝ち得ること、つながりを維持し拡げ、頼れる友になる。背信行為は絶対にしない。ほんものの絆、ほんものの関係を育てることが掟であることが述べられている。
~広告は無視。ウッフィーを増やすマーケティングへ~
企業は「自分の声を聞かせる」から「ユーザーの声を聞く」姿勢に転換することが大事。インターネットがすべてを変えた。「人々がさまざまなメディアを使って発言できるようになると、人々は作られた広告を無視するようになった。インターネットは、小さなささやきを何千倍、何万倍にも増幅するクチコミ製造メディアとみなすことができる。かつて企業が「大声でわめく」ために持っていたメガホンは、いまや顧客の側にある」。「大声でわめくマーケティングから、コストは少ないが顧客忠誠を高められるマーケティング、そう、ウッフィーを増やすマーケティングへ」変わっていくことが求められている。「ふつうの人の情報発信力は日増しに強力になっているし、誰もが賢くお金を使いたいと考えるようになっている。もし同じような商品が二つあって、一方は広告主体の伝統的なブランド戦略に基づいて売られ、もう一方は多くのコミュニティで取り上げられ、支持され、愉快なコミュニティが生まれていたら、あなたはどちらを選ぶだろうか」。
~ただ一人の顧客を描き商品を設計する~
「旧来のマーケティング手法、グループセグメントはウェブではうまく機能しない。ただ一人の顧客を思い描いて、商品を設計し語りかける。するとうまくいく」。ウォルマートはある一人の女性客にフォーカスしている。グーグルは「せっかちな検索者」、アマゾンは「ベストセラーでは満足せず、広くあるいは深く読書をするタイプ」を想定しており、「時間をかけて顧客のニーズを見きわめ、強いつながりをつくってきた」という。「一部の専門家は、こうした顧客プロフィールの分析手法を、人口統計学的なデモグラフィックス、心理学的なサイコグラフィックスに対比させて、ソーシャルグラフィックス」と呼んでいる。
~リサーチもマスリサーチから個別リサーチへ~
実のところ、私が関係するリサーチのやり方も、米国ほどではないが日々変化してきている。コア・カスタマーをハンティングし、例えば4人のカスタマーをよく知って友だちになり、商品開発や改良のヒントを得ていく。日本においても、商品コンセプトの評価の段階では1対1のデプスインタビューや、何重もの抽出条件を満たした人たちに自由に雑談してもらうグループインタビューが主流になってきている。つまり、例えばネットリサーチなど400人のサンプルから得られた人物像ではなく、実在の人物から、「こんなことが好きで、こんなことがきらいで、こんな夢を持っていて、こんな悩みを抱えていて、こんな友達がいる」などの話を聞いて、「こんなのを待っていた」と言われるような多くの発見をしていくのがリサーチの主流になろうとしている(これは私自身が今経験していることである)。
~ギフト経済の原理で動くオンライン・コミュニティ~
さらに、この本ではSNSの世界をギフト経済の考え方で説明している。「ギフト経済は市場経済と並行して機能し、市場経済でお金をやりとりするように、贈りものをやりとりする。贈りもののやりとりが増えれば増えるほど、ウッフィーが増えるのがギフト経済の原理だ。お金と贈りもののちがいは、お金は使えば貯金は減るが、贈りものをあげるとウッフィーが増える点にある。」という。「贈りものは、人と人とを結びつける。そして、ギブ・アンド・テイクの精神を生む。」。オンライン・コミュニティは、このギフト経済の原理で動いているという。
そして、この世界で生きていく企業の大事な視点として、以下の点をあげており、自らの会社の方針を考える際の参考にさせてもらいたいと思っている。
○よいことをして成功する
○まず顧客のことを考える
○顧客にパワーを与える
○顧客が誰かを助けるのを助ける
○事業活動の枠を超えたことをする
○コミュニティ全体に大きな贈りものをする
なお、この本があまりにも感動的でしたので、いくつかの参考文献を読みたくなりました。それも、古本ばかりですがアマゾンですぐ手配できるほど、私の周りも様変わりしていることを改めて実感しております。
■リック・レバレインほか『これまでのビジネスのやり方は終わりだ』日本経済新聞社(2001年3月23日第1刷)・・・アマゾンの古本を購入
■コリイ・ドクトロウ『マジック・キングダムで落ちぶれて』ハヤカワ文庫・・・アマゾンで古本を購入
■マット・リドレー『徳の起源-他人を思いやる遺伝子』・・・10,000円以上するので様子見
■ロバート・パットナム『孤独なボウリング-米国コミュニティの崩壊と再生』・・・これからアマゾンで検索
■ミハイ・チクセントミハイ『フロー体験 喜びの現象学』・・・これからアマゾンで検索
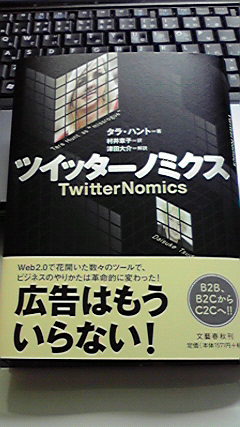
Posted by わくわくなひと at 20:53│Comments(0)



