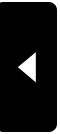2010年09月05日
九州新幹線で鹿児島県知事「みずほ」に不満 熊本発着を想起?
4日付けの南日本新聞に以下の記事が載ったようです。ネットで見つけました。
同床異夢、呉越同舟。このところ九州新幹線を巡る有力者の発言を見ると、何か不安感がもたげてきます。
鹿児島県の伊藤祐一郎知事は3日の定例会見で、来春の九州新幹線全線開業に合わせ、鹿児島中央-新大阪を最短の3時間47分で直通運転することが検討されている新列車「みずほ」について、「シンボル的に短い時間でつなぐ列車は必要だが、名前は好きではない」と不満を見せた。
知事は、「みずほ」がかつて熊本-東京を結んでいた寝台特急(ブルートレイン)と名称が同じだと指摘。新大阪直通の「さくら」が熊本発着になることを懸念し、地元経済界とともにJR九州に鹿児島中央発着を要請してきた経緯もあり、熊本止まりを想起させる列車名に「相談があったら否定しますね」などと述べた。
「さくら」が公募で決まったことから「3時間47分のさくらと、そうでないさくらがあってもよかった」とした上で、県へ連絡がないまま名称が報道されたことに、「不思議なことが起こった」と疑問を呈した。
最後は「もう変えられないのだからあまり騒がないで」と配慮しつつも「変えてくれるなら、(報道の)みなさん方が指摘してもいい」と未練ものぞかせた。
確かに「みずほ」は、もともと熊本から東京への参勤交代寝台列車の象徴的な名称でした。「はやぶさ」とか「富士」ならOKなんでしょうか?
このところ沿線各地の綱引きはすごい。こういった動きの中、熊本県知事や熊本市長が「好きではない」「さくらは熊本発着で」とか言ったという記事を私は見たことがありません。見識、品格を思わせ、熊本のリーダーたちは、それはそれで「よし!」という感じです。
そんな紳士面をしていると、「やられてしまう」というのが世の中の常識でしょうか。
博多-熊本間は、今でも1時間に「リレーつばめ」2本、「有明」1本が運行中であり、高速バスは1日100往復という莫大な需要があります。
「リレーつばめ」に乗っていていつも思うのですが、乗降客数は博多-熊本間は多いけど、熊本以南の乗降客数はかなり少ないですね。今の需要を見て、ふつうに企業的に判断すると熊本駅止まりの本数が増えかねないといのが、鹿児島の危機感の背後にあるようで、知事の発言も過激になるのかと思いました。ビジネスでよく言う、「ウインウインの関係で行こうよ」という風にはならないでしょうか。
JR九州の社長さん、お疲れ様です。
同床異夢、呉越同舟。このところ九州新幹線を巡る有力者の発言を見ると、何か不安感がもたげてきます。
鹿児島県の伊藤祐一郎知事は3日の定例会見で、来春の九州新幹線全線開業に合わせ、鹿児島中央-新大阪を最短の3時間47分で直通運転することが検討されている新列車「みずほ」について、「シンボル的に短い時間でつなぐ列車は必要だが、名前は好きではない」と不満を見せた。
知事は、「みずほ」がかつて熊本-東京を結んでいた寝台特急(ブルートレイン)と名称が同じだと指摘。新大阪直通の「さくら」が熊本発着になることを懸念し、地元経済界とともにJR九州に鹿児島中央発着を要請してきた経緯もあり、熊本止まりを想起させる列車名に「相談があったら否定しますね」などと述べた。
「さくら」が公募で決まったことから「3時間47分のさくらと、そうでないさくらがあってもよかった」とした上で、県へ連絡がないまま名称が報道されたことに、「不思議なことが起こった」と疑問を呈した。
最後は「もう変えられないのだからあまり騒がないで」と配慮しつつも「変えてくれるなら、(報道の)みなさん方が指摘してもいい」と未練ものぞかせた。
確かに「みずほ」は、もともと熊本から東京への参勤交代寝台列車の象徴的な名称でした。「はやぶさ」とか「富士」ならOKなんでしょうか?
このところ沿線各地の綱引きはすごい。こういった動きの中、熊本県知事や熊本市長が「好きではない」「さくらは熊本発着で」とか言ったという記事を私は見たことがありません。見識、品格を思わせ、熊本のリーダーたちは、それはそれで「よし!」という感じです。
そんな紳士面をしていると、「やられてしまう」というのが世の中の常識でしょうか。
博多-熊本間は、今でも1時間に「リレーつばめ」2本、「有明」1本が運行中であり、高速バスは1日100往復という莫大な需要があります。
「リレーつばめ」に乗っていていつも思うのですが、乗降客数は博多-熊本間は多いけど、熊本以南の乗降客数はかなり少ないですね。今の需要を見て、ふつうに企業的に判断すると熊本駅止まりの本数が増えかねないといのが、鹿児島の危機感の背後にあるようで、知事の発言も過激になるのかと思いました。ビジネスでよく言う、「ウインウインの関係で行こうよ」という風にはならないでしょうか。
JR九州の社長さん、お疲れ様です。
Posted by わくわくなひと at
15:09
│Comments(0)
2010年09月03日
駅間5キロ・・・最速新幹線「みずほ」も各停?【産経新聞】
 情報はメディアの視点によって、いくぶん違った印象になるという例を見つけました。
情報はメディアの視点によって、いくぶん違った印象になるという例を見つけました。今日3日付けの産経新聞の配信記事もそうだと思います。見出しは「駅間5キロ・・・最速新幹線「みずほ」も各停?九州自治体が綱引き」というものです。
産経新聞の情報は、JR九州、JR西日本、九州内の自治体の動きを俯瞰して見ている感じです。九州の新聞社にはJR九州のコメントがよく出てきますが、産経は一応全国紙、それも特に大阪あたりが強い新聞社だと思いますのでJR西日本のコメントや情報が載っているところが特徴です。
先週8月24日付け西日本新聞夕刊1面トップに、新大阪-鹿児島中央間を3時間47分で走る「みずほ」の運行が検討されていることが載りました。3時間47分は停車駅が鹿児島中央、熊本、博多の3駅ということが前提です。
この「みずほ」を久留米駅と新鳥栖駅にも停車するよう、久留米市長と鳥栖市長が熱望していることが書かれています。久留米駅と新鳥栖駅の距離はわずか5キロ。鳥栖の背後からは佐賀、長崎両県は合同で新鳥栖駅への停車をJR九州に要望するなど新たな軍勢が加わっていることも書いてありました。
「停車駅の綱引きはまさに真剣勝負だ。」。JR九州によると、9月1日までに寄せられた停車駅や利便性に関する要望は実に34件にのぼっているそうです。
その結果、産経新聞は次の記事を書いています。
来年3月に全線開業する九州新幹線鹿児島ルートの停車駅をめぐり、JR九州に沿線自治体から「わが駅に停車を」と要望が相次いでいる。山陽新幹線を運行するJR西日本は「停車駅を減らし、航空機に勝てる新幹線を」との姿勢を崩さない。JR九州は、地域の熱意と対航空機競争との狭間(はざま)で苦しんでいる。
「われわれは『対航空機』をイメージしているが、JR九州には、なかなか分かってもらえない」。JR西の関係者はこう打ち明ける。
JR西は、これまで「のぞみ」や「ひかりレールスター」といったスピード重視の車両を導入した経緯から、航空機に対抗できるようなダイヤ編成を想定。極力停車駅を減らしたい意向だが、九州新幹線は、国や自治体が事業費を負担した「整備新幹線」と位置づけられているため、九州内でのダイヤを決めるJR九州は、駅を抱える自治体から停車を求める要望が相次いでおり、スピードか地元の利便性か、選択を迫られる可能性もある。
九州の新聞ではJR西日本のコメントはあまり見られませんので、新鮮です。
「みずほ」は博多、熊本、鹿児島中央の3駅だけに停車する可能性が高い。熊本市の幸山政史市長は「みずほが熊本~新大阪間3時間を切れば、関西方面に与えるインパクトは大きい」と大歓迎。これに対し、佐賀県の古川知事は「みずほ」についても、新鳥栖停車を求めていくとしている。
この記事は熊本ゆかりの者として少し心配になってきました。こんな心配です。
3時間47分という時間が最も重要なことであれば、「みずほ」のうちの何本かは熊本駅を停車せず、博多、新鳥栖、鹿児島中央とする案も選択肢として浮上しないか?
-という心配です。佐賀・長崎連合軍からの要望ですよ。
それにしても、九州は一つ、九州のためには何が一番か、民主党の党首選ではありませんが、九州分裂にならないよう願いたいものです。
Posted by わくわくなひと at
20:32
│Comments(0)
2010年09月02日
海外と比べる福岡市、地理的優位性を生かそうとする熊本
 今日2日付け西日本新聞の「九州」面を見て、福岡市と熊本県のポジショニングの違いを感じました。
今日2日付け西日本新聞の「九州」面を見て、福岡市と熊本県のポジショニングの違いを感じました。この面は九州各地の動きが捉えられていて、よく目を通す紙面です。
今日の私が注目した内容は、次の通りです。
■福岡-釜山 連携強化 4日、フォーラム開幕 新幹線生かす交流探る
・福岡市と韓国釜山市の各界リーダーが日韓海峡圏の発展策を探る「福岡-釜山フォーラム」(福岡側代表世話人・石原進JR九州会長)が4、5両日、釜山市で第5回会合を開くそうです。韓国高速鉄道もソウル-釜山間全線が年内に専用線で直結するそうで、九州新幹線との連携や交流を話し合うと書いてありました。九州大学学長、JR九州会長、福岡市医師会会長、西日本新聞社長、福岡商工会議所会頭、西日本シティ銀行頭取、テレビ西日本社長、九州電力副社長など、蒼々たるメンバーが参加します。釜山側も大学、経済界、メディアの重鎮たちが参加します。
■「知識経済都市」実現へ 福岡市でフォーラム 実働組織 年明けにも
・福岡市は、シアトルやバルセロナなど世界10都市で、知識経済を取り込んだまちづくりを目指す「国際地域ベンチマーク協議会」のメンバーです。今年7月に福岡市で開かれた「国際知識経済都市会議」の議論の内容を市民に伝える「地域戦略フォーラム」が1日に開催され、その内容が紹介されていました。
■熊本駅拠点に九州の観光を 蒲島知事が期待
・1日の知事記者会見で、来年3月の九州新幹線鹿児島ルートの全線開通に関連して「今は九州のハブ(拠点)機能は福岡だが、地理的に優位な熊本から九州各地に行ってもらえるようにしたい」と述べ、JR熊本駅の観光拠点化に期待を示したと書いてありました。「県は全線開通に合わせ、熊本駅の貸し切り・高速バスの乗り場を集約・拡充する計画を進めている。」そうです。
この面に福岡と熊本の情報のすべてが載っているわけではありませんが、福岡は海外の都市との切磋琢磨や連携に関心があり、具体的なレベルまで話が進んでいる。熊本は九州の中での地理的優位性を何とか生かしたいと動いている。ポジショニングの違いでしょうが、関心の対象がずいぶん違うと感じてしまいました。
Posted by わくわくなひと at
20:17
│Comments(0)
2010年09月02日
市長選挙 福岡市激戦!熊本市ほぼ無風か?
 西日本新聞を見ていると、11月14日投開票の福岡市長選が賑わってきましたね。
西日本新聞を見ていると、11月14日投開票の福岡市長選が賑わってきましたね。現職の吉田宏市長(53)は民主党が推薦。自民党は九州朝日放送(KBC)アナウンサーの高島宗一郎氏の擁立を決めたそうです。高島氏は何と35歳で大分市出身です。元佐賀市長の木下敏之氏(50)も出馬する意向であり、前市教育長の植木とみ子氏ほか2人も立候補。計6人が立候補する見通しだそうです。
二大政党の一騎打ち。それに元佐賀市長や市の教育長も出馬するなど、何か成長する都市のエネルギーを感じてしまいます。
熊本市長選挙も確か11月ですよね。幸山市長は合併を成功させ政令市を確実なものするなど実績十分でほぼ無風選挙となりそうです。
個人的には幸山市長支持派の私ですが、幸山市長が余りにも強すぎるのか、それとも福岡のように、明日のまちづくりについての議論が盛り上がらないのか、どちらが大きな要因なんでしょうか。後者の要因ではないことを願います。
ところで、いろんな将来推計人口による予測を見ると、熊本市の人口は今年(2010年)あたりがピークで、これから人口減少社会に突入してしまいます。これに対し福岡市の人口のピークは2025年(平成37年)ごろの150万人前後とされています。
人口のピークを今年迎えそうなのは、仙台市、名古屋市、神戸市、広島市などの大都市もそうです。千葉市と横浜市が2020年ごろのピークで、福岡市と同じく2025年まで人口が増えていく大都市は川崎市くらいしかありません。
成長信仰が通用するのは九州では福岡市及びその都市圏くらいです。熊本市のまちづくりには違った価値観と視点が必要だと思いました。
Posted by わくわくなひと at
19:12
│Comments(0)
2010年09月02日
テレビ現場のノウハウを覗く!報道のもう一つの楽しみ方
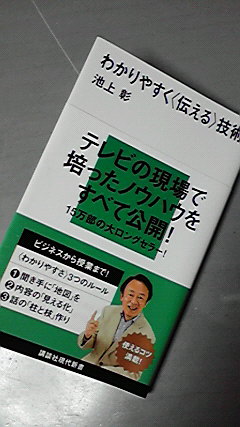 池上彰『わかりやすく<伝える>技術』講談社現代新書(2009年7月20日第1刷、2010年6月10日第19刷)を読みました。
池上彰『わかりやすく<伝える>技術』講談社現代新書(2009年7月20日第1刷、2010年6月10日第19刷)を読みました。最近の書店を覗くと、この方の本がたくさん並べられています。テレビで見た顔だし、「そうそう!子ども向けのニュースの解説をしている」人だと気づきました。まさに池上ブームですね。一頃の茂木健一郎ブームにも匹敵しそうな勢いです。
帯には「テレビの現場で培ったノウハウをすべて公開!15万部の大ロングセラー」と書いてあります。私はプレゼンとか人前で話す機会も多いし、商売でそういうことをしているわけだから、この手の本もある程度読んできているにも関わらず、初心に戻り、池上プレゼン術を盗むことにしました。
話にはリードをつける、聞き手に地図を示す、内容を見える化する、話の柱と枝づくりなど、一度は聞いたり読んだりした内容であり、特に目新しさは感じませんでした。ただ、今の自分がそれらの基本を見事に実践しているかというと、はなはだ不安であり、リスタートするという意味では大いにためになりました。
パワーポイントはキーワードだけに、講演用のメモは30分までならA4一枚、1時間半の講演ならA4二枚半、ざっと話したい要素を書き出す、リードを作る、目次を作る、一回書いてみる、どこを図解にすればいいか考える、パワーポイントを作る、パワーポイントにそった原稿に書き直す、その原稿を箇条書きのメモにする、パワーポイントの画面は1枚40秒で見せていく、つかみ、三つの魔術、一瞬ずつでも一人ひとりに視線を合わせる・・・など、今、自分が実践できているかどうか?ためになりました。
それよりも、この本の中でもっと面白いと思ったのは記者やキャスターのくだりです。
「報道の世界では、視聴者や読者よりも、取材先のほうを向いて原稿を書いている記者がいるものです。・・・政治部の記者は、取材先の政治家に知らせる原稿を書く。経済部の記者は、中央官庁の役人や財界人が納得するような文章を書く。社会部の記者は、警察官や検察官に認めてもらえるようなリポートする。」
この視点は面白いですよね。視聴者や読者よりも、日頃接している人を意識した文章になりがちというのは分かるような気がします。
みのもんたや久米宏の話術、間のとり方、質問の仕方などの凄さについての記述もありました。明日から、みのもんたや久米宏が出ているテレビ、記者がテレビの前でどのようにしゃべっているか、腹式呼吸で声を出している人とそうでない人の違いなど、テレビを見る楽しみがもう一つ増えてしまいました。
Posted by わくわくなひと at
00:17
│Comments(0)