2010年08月27日
中島京子『小さいおうち』・・・今年一番の収穫かも?
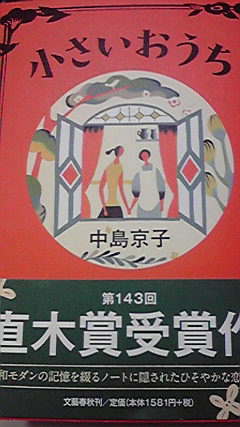 西日本新聞のインタビュー記事を読んで買った本です。
西日本新聞のインタビュー記事を読んで買った本です。中島京子『小さいおうち』文藝春秋。第143回直木賞受賞作。
作者は1964年、東京オリンピックの年の生まれ。東京女子大、今も言うと思いますが名門“とんじょ”の史学科卒の才女。
この作者が大学時代、歴史のどこを専攻していたか知りませんが、昭和10年代の東京近郊の裕福な家庭を、ここまでさりげなく再現していることに驚きました。私も学生の時は昭和10年前後を専攻していたことから、この時代について書かれた本を読むと、ちょっとしたことに違和感を持ってしまいますが、この本では「そうだ!そうだよな!」と思って読んでしまいました。この作者は、おそらく膨大な資料を読み込んでいるし、両親や縁者からの膨大な話を聞いている。そうでないと書けない小説だと思いました。作者の両親は、ともにフランス文学者であり、さりげなく育ちがよさそうであり、戦前の山の手の暮らしについての暗黙知も吸収して育ったことと思います。
もちろん私も戦前の東京の山の手の暮らしを見たわけではありませんが、「恐らくこうであったろう」と共感しました。戦前は都会と地方の暮らしの差が今の何百倍もあり、都会の山の手の暮らしについては、モダンで知的で裕福な暮らしがあったことを祖母や叔母、母から聞いています。父や叔父、父の戦友からは戦闘の話を聞いて育ちましたが、祖母や叔母、母からは日々の暮らしの話をずいぶん聞いていました。そんな話を聞いている時に、背後にシミが入った円本や世界文学全集などの古い書籍と古い書棚を見て、戦前に今では考えられないモダンで知的で裕福な暮らしがあったことに思いを馳せていた自分を思い出しました。
世の中は戦争で大変なことになっているのに、戦争が終わる1年くらい前にならないと、その影が及んでこない。外地で戦闘があって、その内容は聞こえてくるが、日々の暮らしには笑いと楽しみだけでなく恋愛もある。「・・・その時代全体が「のほほん」一色だったとは、書きたくもなければ書いたつもりもない。・・・悲惨な戦争が進行している世界を生きていた人々は、けっして土気色の顔をして打ちひしがれた人々でも、狂信的な人々でもなく、私たちとよく似た感情や生活感覚を持った人々だったのだということに、思いを馳せるべきでないだろうか。」(西日本新聞のインタビュー)。
昭和20年3月10日の東京大空襲の後くらいから戦後にかけて、「この先はどうなるんだ!」と話しは急展開していきます。読み終わるまで目が離せない展開ですので、読み終えたのは25時をまわっていました。それから2時間くらい眠れませんでした。
『永遠の0』を書いた百田尚樹も1956年生まれ。中島京子も1964年生まれ。戦争を知らない世代が、いろんな思いで、その時代を書く時期になってきました。
悪者でも善人でもなく「私たちとよく似た感情や生活感覚を持った人々だった」という視点で歴史に思いを馳せる態度に共感します。
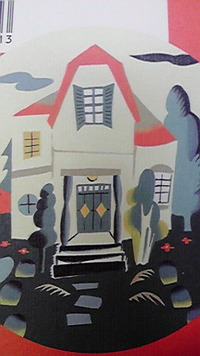
Posted by わくわくなひと at
13:37
│Comments(2)



