2010年07月16日
焼酎に血栓溶解効果!WHO指針は逆風
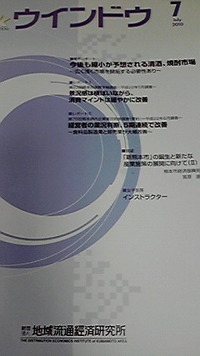 地域流通経済研究所の冊子「ウインドウ」2010年7月号を読みました。
地域流通経済研究所の冊子「ウインドウ」2010年7月号を読みました。なかでも、業界レポート「今後も縮小が予想される清酒、焼酎市場 ~広く浅く市場を開拓する必要性あり~」は興味深く読ませてもらいました。
サブタイトルの「広く浅く市場を開拓する必要性あり」という処方箋が正しいかどうか分かりませんが、長期トレンドをみると、今後、清酒や焼酎市場は縮小に向かうことが予想されていることは理解できました。それも、フランスやイタリアなど多くの欧州の国々のアルコール消費量が激減していること、アメリカも減少しているそうです。これらに比べれば日本の減少傾向は小さいということです。
私の事務所がある福岡・大名周辺を眺めると、若い世代の酔っぱらいがたくさん闊歩しています。しかし、世界的な傾向をみると、人が酒をだんだん飲まなくなってきているということでしょうね。日本や九州も、いずれそうなるのでしょうか?酒好きの私としはあまり想像したくありません。
それと、知りませんでしたが、今年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、飲酒による健康被害や未成年者の飲酒を防ぐことを目的して、「酒税の引き上げ、飲食店での飲み放題の制限、安売り防止、広告の内容と量の制限など」を盛り込んだ指針が全会一致で採択されたと、このレポートに書いてありました。「強制力はないが、各国の業界は自主規制に向かうものと思われる」らしいですが、世界の趨勢としてはタバコ並の業界バッシングへと進むのでしょうか?これは球磨焼酎をはじめ関係業界や地場産業にとっては由々しき事態ですね。
もう一つ、「本格焼酎(単式焼酎の別名)は、血栓溶解効果が高いということが科学的に
証明」されているそうです。このレポートには、科学的と言うにはやや標本数が少ないと思いますが、「血栓溶解酵素の平均活性」という数値が本格焼酎1160、ビール712、ワイン801、日本酒855、ウイスキー(標本数18人)510となっています。よく分かりませんが、本格焼酎の血栓溶解効果が高いということを示す数値だと思います。
酒は百薬の長と言いますように、本格焼酎を薬用化した新商品やカプセルなど、今後、これまでにない新商品の開発を予感させる内容だと思います。芋や麦焼酎よりも米焼酎の方が血栓溶解効果が高いという科学的な結果が得られれば、もっと熊本が盛り上がると思いますが、そんな結果はないのでしょうか。
Posted by わくわくなひと at
14:37
│Comments(0)
2010年07月16日
【ニュース】生活保護者が激増中!問われる地域経営と地域自治
私が参加しているメーリングリストからの情報です。
少子高齢化・人口減少が進展していく中で、生活保護世帯がもの凄い勢いで増加し続けているそうです。
厚生労働省の発表によると、今年3月に生活保護を受けた世帯は前の月より増え、全国で134万3944世帯に上り、過去最多。月平均でみると、09年度は約127万世帯で、前年度の約115万世帯を約12万世帯上回っている。一方、生活保護を受けている人数は、09年度が約176 万人で、前年度のより約17万人増加。増加傾向に歯止めがかかっていないそうです。
福岡市の博多区だけで21年度は前年度比1,000世帯増加、約100億円の補正予算をつぎ込んだそうです。
自己責任、実力主義・・・。エリートさんに都合のよいルールが世の中の基準となって、社会が急速に二極分化し始めています。
そうでなくても、少子高齢・人口減少社会では、構造的に社会保障費が増加の一途をたどることが予想されます。(専門家曰く、)このため、これまでのように国や誘致企業に頼ってばかりでは成り立たず、地域経営や地域自治が不可欠になってくるそうです。地域が自律的に支え合う仕組みをしっかり構築し、税金の使い方を抜本的に変えていかないと、大変なことになりそうです。
こういった中で、福岡市では、この3月、人口減少・少子高齢社会に対応していくための全国初の議員提案条例が可決されています。
「公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例」という名称で、行政と市民や事業者が「共働」して、コミュニティバスや乗合タクシーなど、さまざまな手段で市民生活に欠かせない生活交通を守り、地域社会の再生を目指すことを目的にしているそうです。
具体的には、この条例の成立によって、路線バスや鉄道駅から1キロ以上離れている地域を「公共交通空白地」、バス停から500メートル以上離れた地域を「公共交通不便地」として指定し、高齢者や障がい者等のうち移動に関し制約を受ける人たちの生活交通を確保するような施策・取組みが行われることになりそうです。
この福岡市の取組みは、地域経営、地域自治の典型的な例ではないでしょうか。
熊本市が現在、策定中の「わくわくシルバープラン」の構想を見ても、このような生活交通の確保策や高齢の生活保護者の住宅確保策など、地域経営や地域自治の視点がたくさん盛り込まれており、これまでの老人保健福祉計画とは違った画期的な計画になりそうな感じがしました。最終的にどのような計画になるか楽しみです。
ある意味、今は地域の知恵比べの時代ですね。
少子高齢化・人口減少が進展していく中で、生活保護世帯がもの凄い勢いで増加し続けているそうです。
厚生労働省の発表によると、今年3月に生活保護を受けた世帯は前の月より増え、全国で134万3944世帯に上り、過去最多。月平均でみると、09年度は約127万世帯で、前年度の約115万世帯を約12万世帯上回っている。一方、生活保護を受けている人数は、09年度が約176 万人で、前年度のより約17万人増加。増加傾向に歯止めがかかっていないそうです。
福岡市の博多区だけで21年度は前年度比1,000世帯増加、約100億円の補正予算をつぎ込んだそうです。
自己責任、実力主義・・・。エリートさんに都合のよいルールが世の中の基準となって、社会が急速に二極分化し始めています。
そうでなくても、少子高齢・人口減少社会では、構造的に社会保障費が増加の一途をたどることが予想されます。(専門家曰く、)このため、これまでのように国や誘致企業に頼ってばかりでは成り立たず、地域経営や地域自治が不可欠になってくるそうです。地域が自律的に支え合う仕組みをしっかり構築し、税金の使い方を抜本的に変えていかないと、大変なことになりそうです。
こういった中で、福岡市では、この3月、人口減少・少子高齢社会に対応していくための全国初の議員提案条例が可決されています。
「公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例」という名称で、行政と市民や事業者が「共働」して、コミュニティバスや乗合タクシーなど、さまざまな手段で市民生活に欠かせない生活交通を守り、地域社会の再生を目指すことを目的にしているそうです。
具体的には、この条例の成立によって、路線バスや鉄道駅から1キロ以上離れている地域を「公共交通空白地」、バス停から500メートル以上離れた地域を「公共交通不便地」として指定し、高齢者や障がい者等のうち移動に関し制約を受ける人たちの生活交通を確保するような施策・取組みが行われることになりそうです。
この福岡市の取組みは、地域経営、地域自治の典型的な例ではないでしょうか。
熊本市が現在、策定中の「わくわくシルバープラン」の構想を見ても、このような生活交通の確保策や高齢の生活保護者の住宅確保策など、地域経営や地域自治の視点がたくさん盛り込まれており、これまでの老人保健福祉計画とは違った画期的な計画になりそうな感じがしました。最終的にどのような計画になるか楽しみです。
ある意味、今は地域の知恵比べの時代ですね。
Posted by わくわくなひと at
11:24
│Comments(0)



