2011年01月27日
経営の原則は一つ。小宮さんも安江さんも同じことを指南!
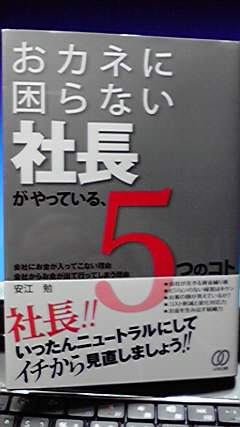 安江勉『おカネに困らない社長がやっている、5つのコト』ぱる出版(2010年9月7日初版)。あからさまなタイトルですけど、中身はまともなことが書いてありました。
安江勉『おカネに困らない社長がやっている、5つのコト』ぱる出版(2010年9月7日初版)。あからさまなタイトルですけど、中身はまともなことが書いてありました。内容は小宮一慶さんの『社長の教科書』とほぼ同じ。大学受験の時を思い出しますが、同じ参考書を20~100回くらいは読んだり書いたりしないといけないものかも知れません。だから、経営や社長業の真髄、真実は一つということになるのかなと思いました。「本でなくても、みんな同じことを言ってるもんね」とも思いました。しかし、実践すること実現することは別の次元です。なかなかできることではないので、みんなが同じことを指南する。当たり前のことを実践するのは難しい。しかし、私は少しでも実践し、夢を実現する義務がありますので、こんな本を何度でも繰り返し読むことになりそうです。小宮さんの本より安江さんの本の方が中小零細企業の社長さん向けのような気配を感じました。要は実践、行動すること。
以下は、特に体に染みこませたいことです。
・会社に「お金」が流れる状態にするには、①しっかりと売上を確保して会社に入るお金を増やすこと、②コストを抑えて会社から出て行くお金を減らすこと、③次の成長機会のために会社にお金を残すこと、
経営の原則を理解し、当たり前のことを徹底的に行っているかどうか。
会社が「儲け」を生み出すための原則は、
①数字で正確に把握する
②ビジョン・戦略・計画を明確にする
③お客様を知る
④変化を当然のこととする
⑤強い組織をつくる
■ビジョンをつくる
・理念やビジョンはただあるだけでなく、組織に浸透して初めて効果を発揮する
・「経営理念」とは、会社の存在理由や使命、基本的な価値観を明にしたもので、組織にあっては行動規範のようなもの
・「経営ビジョン」とは会社が目指すべき理想的な将来像であり、期限の明確な到達点といったもの
・経営理念は追い求め続けるもので、その過程として将来のある特定の時点で、こうあるべき・こうありたいという状態がビジョンになる
・経営理念やビジョンはしっかりと明文化する。さらに内容的に共感でき、社員の腑に落ちるものでなければならない。こうした姿勢や考え方がお客様にも伝われば、信頼や評価につながり、最終的には会社の「儲け」になる。
■自社の強みは必ずある
・お客様がなぜ自社の商品を買ってくれるのかを考えれば、そこには他社と比べた何らかの競争優位なポイントがある。そのポイントこそ、お客様に貢献するポイントであり、「儲け」を生み出す源泉である。
・Q(クオリティ・品質)・C(コスト・価格)・D(デリバリー・納期)・S(サービス)の視点は強みを探すときに役立つ
・自社の強みを継続していくことが大事
・経営資源に乏しい中小企業では、強みにフォーカスして資源集中を図り、強みをより強くすることは効果的な戦略である
■外部環境の変化を捉えたうえで、自社の内部環境を整えていくことは、会社の今後の戦略、つまり事業の方向性を決めていくために必要不可欠
・今の事業領域にとどまらず、今ある強みをさらに活かせる事業機会は他にないかを検討
・環境変化に合わせて社内体制を整え、厳しい中で生き残っていくためには社長としての視野の広さが問われる
・業界のみならず社会全体の状況をチェックし、今後はどのように変化していくのかを見極める
■目標には根拠が必要
・会社として設定する目標が備えるべき要件は、①必要性②具体性③測定可能性④期限⑤実現可能性
・②具体性③測定可能性については具体的な到達点を描かなければ社員に伝わらず目標が組織に浸透しない
・数値目標を盛り込んだ目標とし、定性的な内容であっても到達した状態が具体的にイメージできるようにしておかなければ期限を迎えたときに到達の可否やレベルが判断できず、その努力の成果を正確に測ることができない
・期限のない目標は単なるスローガンである
・いつまで達成するのかが明確でなければ本気で取り組めない
・目標に関してはその設定プロセスに社員を巻き込むということが非常に有効
■頑張れば達成できると確信できるか
・達成できない要因の一つは設定プロセスに写真が関与せず、目標達成の必要性を理解していないこと。達成しても自分自身に得るものはないと感じていること
・簡単な目標ではないけれど頑張れば達成できなくもないと感じられるレベルを設定
・目標レベルを成り行きから少し伸ばして成果を大きくする。この目標達成を目指して頑張ると、取り組んだ自分自身のスキルも伸ばすことができるもの
・会社の変革、経営革新といったものは、挑戦姿勢がないと為し得ない
・変えてはいけないものは経営理念と挑戦する文化
■本当のお客様は誰なのか
(全米マーケティング協会の1985年のマーケティングの定義)
・マーケティングとは、個人や組織の目標を満足させる交換を創造するための、アイデア・製品・サービスのコンセプト、価格、プロモーション、流通を計画し、実行するプロセスである。単に市場調査や広告宣伝といったものではなく、お客様のニーズに基づいた製品を企画・生産し、お客様に買っていただくまでのプロセス全般を表すもの
(P・ドラッカー『マネジメント』より)
・「マーケティングの理想は販売を不要にすることである。」。つまり、単に「売る仕組み」ではなく、「いかにお客様の潜在的なニーズをくみ取り、製品として具現化し、世間に知らしめ、お客さまが買わずにいられないという状況をつくるか」というもの。
・「真のマーケティングは、(中略)顧客からスタートする。『われわれは何を売りたいのか』ではなく、『顧客は何を買いたいか』を考える。」つまり、お客様視点で考えるということがマーケティングには必要
・(下請け企業は)元請企業と一緒にその先のエンドユーザーに貢献する製品作りを行うことができれば、真のパートナーシップを築くことができる
以下は3日の夜に抜き書きした内容です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
1.会社を数字で把握する
「良い会社」とは「継続する会社」
・会社に「お金」が流れる状態にするには、①しっかりと売上を確保して会社に入るお金を増やすこと、②コストを抑えて会社から出て行くお金を減らすこと、③次の成長機会のために会社にお金を残すこと、
経営の原則を理解し、当たり前のことを徹底的に行っているかどうか。
会社が「儲け」を生み出すための原則は、
①数字で正確に把握する
②ビジョン・戦略・計画を明確にする
③お客様を知る
④変化を当然のこととする
⑤強い組織をつくる
・自社の商品やサービスはどのような特徴があり、どのような点が評価されているのか。
・受注を優先するあまり取引先から提示される支払条件を無条件で受け入れていないか。
・「売掛金」「受取手形」「在庫(棚卸資産)」は入ってくるはずのお金。「買掛金」「支払手形」は出ていくはずのお金。この差額のことを「必要運転資金」といいますが、この金額はあらかじめ用意しておくことが必要。
・売上高の80%は顧客の20%からの受注で構成されている。常に新しい得意先が開拓できていれば、思いがけない成長機会を得る可能性が高まります。
・多くのお客様の要望を聴いていると、自社の製品やサービスを新しい視点で改善していくヒントが得られます。業界動向にも強くなり、既存の得意先の考え方や戦略をより理解し先読みすることができるようになります。
・きちんと交渉できる立場を築きあげるためには、普段から緊張感を持って営業活動を行っていくこと、新規開拓を怠らないことが重要なのです。
・値下げするのは簡単ですが、入ってくるお金を同じにするためには、値下げの割合以上多く売る努力が必要となってくるのです。
・「営業担当者が悪い」とするのではなく、「営業担当者のやる気向上策を今まで考えてこなかった(実施してこなかった)自分自身が悪い」と考えるべきです。・・・自分自身に原因を求めれば、改善していく道が見えてくるはずです。
・小さなことでもまずはやってみる、これが大きな変革を実現するための第一歩なのです。
・仕入先や購買先を評価し、取引の見直しを行っていく姿勢がなければ、緊張感のない関係となって変化のきっかけを失ってしまいます。
・「販売費及び一般管理費」は、「粗利益」から支払わねばなりません。基本原則は「もらうお金はなるべく早く、払うお金はなるべく遅く」です。
・常に内製か外製かを適切に判断し、外注先をしっかり管理している会社は、外注によって利益を獲得できているはずです。
■借入金の返済は費用ではない
・「借入」に対する返済金は、いわゆる損益計算書上に勘定科目としては登場してきません。つまり、その期の経費として計上できる訳ではないのです。ですが、月々の返済というのは、まさに固定費と同じような性格を持っています。損益計算書上、今期は何とか黒字だから大丈夫だと考えていても借入金の返済によって現金は減ってしまっているという事態になるのです。
・借入金の返済は、考え方としては「税引後利益+減価償却費」からなされます。「減価償却費」とは、機械などを取得した金額を各期の費用として按分したお金です。機械などを購入した際に既に支払ってしまっているはずの金額を、使っている間に支払ったことにするという、いわば実態を伴ったお金ではありません。つまり、減価償却費として計上している時は、実際はお金として流出していないのです。ですから、「税引後当期利益」という今期獲得した利益と、実際には流出していない「減価償却費」という非資金費用を足したものが借入金返済の原資となるのです。
・もちろん借入金は短期よりも長期で借りる方が金利負担が小さく、資金繰りは楽になります。「出ていくお金はできる限り小さく、遅く」した方がよいのは原理原則です。
■「損益計算書」のポイントは「利益」
・最低限「売上総利益」と「営業利益」は確認
・「粗利」を把握して経営を行うことは、自社の儲けの仕組みが機能しているかどうかを判断する材料にもなるのです。
・「売上高」「費用」そして「粗利」の関係全体で捉える必要があります。少なくとも、「売上高」と「粗利率(粗利÷売上高)」には注目してほしいと思います。
・もう一つ確認すべきは「営業利益」です。これは「売上総利益」から「販売費及び一般管理費」を引いたもので、その会社の事業そのものが生み出している利益のことです。
・「販管費」とは、販売活動にかかる費用(例えば営業担当者の人件費や交通費、広告宣伝費など)と管理活動にかかる費用(例えば事務員の人件費や建物の減価償却費など)を足したものです。いわゆる「固定費」と呼ばれる費用ですが、この分は何としても利益を確保して賄う必要があります。でないと、お金に困るのは必至です。
・ではどこまで価格を下げられるのか。それは固定費が賄えるだけの利益が確保できるところが限界です。このラインを算出しておくことは、重要なポイントになります。
■貸借対照表こそがおカネの状態を示す
・貸借対照表は、ある時点での企業の財政状態を示す
・右側(貸方)は「負債の部」と「純資産の部」で、資金をどのように調達したのかが表示されます。銀行などから借り入れた場合は「負債の部」に表され、資本金など自らが用意した資金や今までの利益の内部留保が「純資産の部」に表されます。
・左側(借方)は「資産の部」で、調達した資金をどのような形で運用(保有)しているのかが示されます。
・銀行などから調達したお金(右側)が、ある時点で現金のままなのか手形なのか、建物や機械設備になっているのかといった、どんな状態になっているか(左側)を示したものです。
・左側の「資産の部」は、その中で上から大きく「流動資産」「固定資産」「繰延資産」に区分され、固定資産はさらに、上から「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」に分かれています。実はこの並びに意味があります。「流動資産」とは文字通り、動きやすい資産です。固定的な資産よりも現金に近い資産です。さらにこの「流動資産」の中でも、上から現金化しやすい順に並んでいます。つまり、上にあるほど資金繰りには良いと理解できると思います。
・右側(貸方)は上から「負債の部」「純資産の部」と並んでいます。資金調達の理想は無利息です。となると、自己資金である資本金や内部留保が多い方が良いはずです。借入してもすぐに返済しなければならない短期借入金よりも、長期借入金や社債の方が資金繰りには良いと理解できると思います。つまり、下に行くほど資金繰りには良いということです。
・重要なのはこれまで説明した構造を知ることです。そのうえで、分かっている勘定科目がどう変化しているのかをつかんでください。特に「現金預金」「受取手形」「売掛金」「棚卸資産」といった流動資産、「支払手形」「買掛金」「短期借入金」といった流動負債の動きは確認してほしいと思います。
・貸借対照表は決算だけでなく、損益計算書とともに毎月確認して変化を捉えておくことが必要です。
■経営分析
・より会社の実態をつかむためには、「額」だけでなく「率」の変化もつかんでおく必要があります。
・重要な指標は、①流動比率②当座比率③手元流動性比率④経常収支比率⑤自己資本比率です。
・①流動比率とは、流動資産÷流動負債で、会社の短期的な安全性を示します。流動資産とは現預金、売掛金、受取手形、すぐに現金化できる有価証券、棚卸資産など、1年以内に現金になると考えられる資産のことです。流動負債とは、支払手形、買掛金、短期借入金など、1年以内に支払いを行わなければならない負債です。理想としては2(200%)が望ましいと言われますが、日本ではそこまで高い数字の会社は多くありません。おおよそ1.2を目安にすると良いでしょう。
・②当座比率とは、当座資産÷流動負債で、これも会社の短期的な安全性を示します。当座資産は、流動資産から棚卸資産を引いたものと考えれば結構です。棚卸資産とは、すなわち在庫のことですが、在庫というのはすぐに現金化できるとは限りません。ですから、より確実性の高い流動資産に限ったものを当座資産として、よりシビアに短期の支払い能力を評価する指標となっているのです。
・③手元流動性比率とは、現預金に流動資産にある有価証券を足したものを月商(月平均売上高)で割ったものです。有価証券を考慮せず、よりシビアに現預金を月商で割ったもので考えても結構です。つまり、毎月の売上に対してどのくらいの現金を保有しているかを管理する指標です。目安とすれば、1.5~2ヶ月分は確保したいところです。
・④経常収支比率とは、経常収入を経常支出で割ったもの(経常収入÷経常支出)で、まさに資金繰りの状況を示す指標です。経常収入とは経常的な活動で入ってくるお金(営業収入+営業外収入)です。特別に発生した収入、例えば土地を売ったお金などは含まれません。経常支出(営業支出+営業外支出)も同様です。「売上高」と「収入」は同じではありません。売上高のうち、売掛金や受取手形になったものは現金ではありませんので省くことになります。また前期の売上で売掛金や受取手形になっていたもので、今期回収して現金となったものでは「収入」に入ります。「支出」に関しても同様に、実際に現金で支払った金額が対象です。つまり、実際の現金ベースで、入ってきた金額と出ていった金額の割合を見ているのです。もし1(100%)を切っていれば、借入などで運転資金を調達しなければ活動できないということになります。
・⑤自己資本比率とは、自己資本÷総資産で長期的な安全性を示す指標です。自己資本とは、総資産から負債を引いたものです。純資産の合計だと考えれば結構です。会社の資産を返済の必要のない自己資本で賄っていれば、余力のある会社と判断できます。自己資本比率は15~20%を目安に一定の比率を保っていければ良いと思います。自己資本には、毎期の利益の累計が剰余金として加算されています。むしろ重要なのは、この利益の内部留保です。赤字が極端に累積すると自己資本も減っていきます。減り続けると自己資本自体がマイナスになってしまいます。これがすなわち債務超過という状態です。債務超過になると、銀行からの借入は非常に厳しくなり、倒産のリスクが高まります。
2.ビジョン・戦略・計画を明確にする
■ビジョンをつくる
・理念やビジョンはただあるだけでなく、組織に浸透して初めて効果を発揮する
・「経営理念」とは、会社の存在理由や使命、基本的な価値観を明にしたもので、組織にあっては行動規範のようなもの
・「経営ビジョン」とは会社が目指すべき理想的な将来像であり、期限の明確な到達点といったもの
・経営理念は追い求め続けるもので、その過程として将来のある特定の時点で、こうあるべき・こうありたいという状態がビジョンになる
・経営理念やビジョンはしっかりと明文化する。さらに内容的に共感でき、社員の腑に落ちるものでなければならない。こうした姿勢や考え方がお客様にも伝われば、信頼や評価につながり、最終的には会社の「儲け」になる。
■自社の強みは必ずある
・お客様がなぜ自社の商品を買ってくれるのかを考えれば、そこには他社と比べた何らかの競争優位なポイントがある。そのポイントこそ、お客様に貢献するポイントであり、「儲け」を生み出す源泉である。
・Q(クオリティ・品質)・C(コスト・価格)・D(デリバリー・納期)・S(サービス)の視点は強みを探すときに役立つ
・自社の強みを継続していくことが大事
・経営資源に乏しい中小企業では、強みにフォーカスして資源集中を図り、強みをより強くすることは効果的な戦略である
■外部環境の変化を捉えたうえで、自社の内部環境を整えていくことは、会社の今後の戦略、つまり事業の方向性を決めていくために必要不可欠
・今の事業領域にとどまらず、今ある強みをさらに活かせる事業機会は他にないかを検討
・環境変化に合わせて社内体制を整え、厳しい中で生き残っていくためには社長としての視野の広さが問われる
・業界のみならず社会全体の状況をチェックし、今後はどのように変化していくのかを見極める
■目標には根拠が必要
・会社として設定する目標が備えるべき要件は、①必要性②具体性③測定可能性④期限⑤実現可能性
・②具体性③測定可能性については具体的な到達点を描かなければ社員に伝わらず目標が組織に浸透しない
・数値目標を盛り込んだ目標とし、定性的な内容であっても到達した状態が具体的にイメージできるようにしておかなければ期限を迎えたときに到達の可否やレベルが判断できず、その努力の成果を正確に測ることができない
・期限のない目標は単なるスローガンである
・いつまで達成するのかが明確でなければ本気で取り組めない
・目標に関してはその設定プロセスに社員を巻き込むということが非常に有効
■頑張れば達成できると確信できるか
・達成できない要因の一つは設定プロセスに写真が関与せず、目標達成の必要性を理解していないこと。達成しても自分自身に得るものはないと感じていること
・簡単な目標ではないけれど頑張れば達成できなくもないと感じられるレベルを設定
・目標レベルを成り行きから少し伸ばして成果を大きくする。この目標達成を目指して頑張ると、取り組んだ自分自身のスキルも伸ばすことができるもの
・会社の変革、経営革新といったものは、挑戦姿勢がないと為し得ない
・変えてはいけないものは経営理念と挑戦する文化
■数字で計画に落とし込む
・売上目標と利益目標を同時に設定
・現状からその理想的な姿に到達するために何をしたらよいかを考える
・売上を伸ばすにはどのような方法があるか
・新規事業も視野に入れるべきかどうか
・既存のお客様で足りなければ新規のお客様をどうやって獲得していくのか
・そのために資源をどれだけ割くのか
・利益目標を達成するために削減できるコストはないか、そのために効率的な業務プロセスはどのようなものか
・管理職を中心に社員の参加を促してアイデア出しをさせるのも有効
■中期経営計画の策定
・組織が一丸となって同じ方向を目指すもの
・経営の質を高め、儲かる会社にしていくためにも絶対に必要
・3年~5年程度で立案
・基本となるのは①販売計画②費用計画③利益計画④資金計画
・①販売計画は最終的な目標数値に対して年ごとに売上目標を設定する。その際、商品・サービス別、顧客別、地域別と細分化して考える。どこを攻めるか、何で攻めるかを考えることは営業戦略の基本となる。新規事業や新商品開発が予定されていれば、それも盛り込む必要がある。
・②費用計画は、流通業であれば仕入れ条件をどのように見直すか、製造業であれば製造コストをどうやって下げるかなど、原価に対する見積りを行う。販管費については費用を算出しておく。特に大きいのは人件費となるので、部門別、スタッフ別に見積もっておく。
・③利益計画は予定した利益目標を達成できるかどうか確認する。そのうえで予定損益計算書を計画書とすると分かりやすくなる
・④資金計画は、資金調達と設備投資についての計画が必要。借入金については返済計画も必要不可欠。
・中期経営計画書は日頃から何度も何度も目を通し、必要な修正を加えながらブラッシュアップを図っていく
・経営計画の中で、「いつまでにこれだけの売上・利益が達成できない場合は撤退する」「売上がここまで下がり利益が確保できなかったら撤退する」といった撤退基準を明確にしておく
3.お客様を知る
■本当のお客様は誰なのか
(全米マーケティング協会の1985年のマーケティングの定義)
・マーケティングとは、個人や組織の目標を満足させる交換を創造するための、アイデア・製品・サービスのコンセプト、価格、プロモーション、流通を計画し、実行するプロセスである。単に市場調査や広告宣伝といったものではなく、お客様のニーズに基づいた製品を企画・生産し、お客様に買っていただくまでのプロセス全般を表すもの
(P・ドラッカー『マネジメント』より)
・「マーケティングの理想は販売を不要にすることである。」。つまり、単に「売る仕組み」ではなく、「いかにお客様の潜在的なニーズをくみ取り、製品として具現化し、世間に知らしめ、お客さまが買わずにいられないという状況をつくるか」というもの。
・「真のマーケティングは、(中略)顧客からスタートする。『われわれは何を売りたいのか』ではなく、『顧客は何を買いたいか』を考える。」つまり、お客様視点で考えるということがマーケティングには必要
・(下請け企業は)元請企業と一緒にその先のエンドユーザーに貢献する製品作りを行うことができれば、真のパートナーシップを築くことができる
■売上はお客様からの信頼の結果
・儲けようと思うのなら儲けを第一の目的としないという姿勢が必要。儲けようと思うのなら、お客様の満足を第一の目的にする
・具体的には、徹底的にお客様と対話していくこと
■儲けの仕組みはこう考える
・ビジネスモデルとは儲けの仕組みと捉える。具体的には、「どのようなお客様のニーズを把握し、自社のどんな強みを活かして、どんな商品をいくらで、どんな工夫を加えて売るのか」を表したもの
・ビジネスモデルを要素分解すると、①お客様ニーズ②自社の強み③商品④価格⑤販売方法の5つ
・自社の強みを活かしてお客様ニーズという市場機会を捉えることをまず考え、あとは商品や価格、販売方法などを工夫していくこと
■自社の主力商品が分かっているか
・既存の商品の売れ行きをしっかりとデータで確認し、その都度その商品の利益貢献度をつかんでおく
(相乗積)
・戦略的な商品管理として、商品ごとの売上構成比と粗利率を算出し、それぞれを掛け合わせた相乗積で利益貢献度を把握する。
■安売りは簡単にはできない
・経営資源が乏しい中小企業が採り得る戦略は限られている。基本はお客様を絞り込んで、そのお客様が望むものを徹底的に実現して高く売ること
・粗利率30%の商品を15%値下げしようとする場合、200個つまり値下げ前の2倍も販売しなければ、値下げ前の粗利は確保できない
・特定品を目当てに来店していただいたお客様が他の商品を購入してくださることもあるので、トータルで売るという発想は大事
■利益を確保するための販路開拓
・できない理由を考えず、どうしたらできるのかを考えると道は開ける
・中小企業であっても、エンドユーザーへの直販を目指すべき
・営業なくして、「儲け」は獲得できない
■WEBの活用
・独自の自社ブランド商品を開発し、専用のWEBサイトを立ち上げてブランド化を図る
・基本は新鮮な情報。更新に手間をかけるほど価値が高くなる。まずまじめに伝えるべきことを伝えるということに徹する。人がやっていないことをやれば、確実に一歩前進する
4.コスト削減のための取り組み
■裏紙を使うよりも大切なこと
・最初に行うべきことは、コストとしてどの項目が大きいかを発見すること。会社の費用全体で、どの部分を削減すると最も効果が大きいかということを、ゼロベースで考えるべき
・人件費の次に大きなコストといったら何になるか。ロイヤリティ、通信費、旅費・交通費、広告宣伝費・・・
・あくまでターゲットは総コストに占める割合の大きなものから順位付けする
・簡単に給料カットすべきではない
■取引先の管理
・入りを量りて、出づるを制す
・「入り」としてお客様を管理し、収入の見込みをきちんと立てる
・「出づる」として仕入・購買先や外注先等を管理し、支出を抑える
・「もらうお金はなるべく早く、払うお金はなるべく遅く」
・仕入先や購買先は重要なパートナー。支払いをなるべき待ってくれる、支払いが遅くてもよいという条件に常に留意しておく。逆に支払いを早めるときはその分安くしてもらう条件を出す
・仕入先や購買先、外注先は複数持っておく。常に新たな購買先や仕入先、外注先は探す姿勢を持つ。前年踏襲のままでは条件変更もできない。複数持っていればこそ、さまざまな交渉も可能になり、真のパートナー企業も確保できる
・厳しい時は可能な限り会社の現状を社員に開示する。どんな問題があり、業績がどれだけ下がっているのか、資金繰り状況からどのくらいの売上を達成しないと会社がもたないのかを知らせる
■お金を借りること
・事業を継続するうえで借入は必要不可欠。集めたお金を運用して、さらに大きなお金を生み出すのが企業活動の本質
・無借金経営は必要な時に資金が調達できないという事態に。本当に困った時に、借りられないリスクというのは相当大きなもの。そのときのための保険として借り入れるというのも必要。借入のプレッシャーによる、その危機感がビジネスへの取り組みに緊張感を生み出す。この力も会社の成長には欠かせない。
■銀行は最も身近な支援者
・金融機関とは複数付き合う
・銀行や信用金庫には報告に行く。日本政策金融公庫や信用保証協会にも説明に行く。
・社内では経営計画発表会を行う。この社内の発表会に銀行など金融機関も招く
・中小企業支援センターや商工会議所などに相談に行く
5.強い組織をつくる
■社員は社長の危機感を共有できないか
・社長の思うように社員が意識を持たない、行動しないということは、結局のところ社長にその力量がないのだと考えた方が妥当
・相手が悪いと考えるよりも、自分自身に原因を求めた方が解決策・打開策は考えられるもの。他社のせいにするのを「他責」というのに対し、自らに責任や原因を求めるのを「自責」という。常に「自責」で物事を捉えることが、改善・改革の第一歩です。
・社長には、バラバラな意識を持った社員を束ね、同じ方向に向かわせるリーダーシップが必要。組織が向かうべき方向をきちんと定め、個々のフォロワーのやる気を高め、能力を引き出して目標を達成していく
・目指すべき方向や目標を明確に提示できること、社員を奮い立たせるエネルギーと熱意、きちんと説明でき、行動できる論理一貫性、率先して取り組む姿勢が必要
・相手の立場で考える、コミュニケーションを図る、正しい行うを心がける、人一倍努力し自分自身を磨く
■社員のやる気はお金だけでは買えない
・最も重要なことはどのような社員になってほしいかという人材像を明確にすること
■社員とのコミュニケーション
・義務的に感じられるような面談や懇談会では、本質的には距離は縮まらない
・1回1時間の面談をみっちり行うよりも、毎日数分の立ち話をした方が信頼関係はつくられる。毎日ちょっとした声かけをする方が効果的
・きちんと職場を回り、一人ひとりに声をかける。社員を名前で呼ぶ
・働きやすい環境とは労働条件だけではない。実は人間関係が最も大切な要素である。社員に声をかけるなど、できる範囲のことはやってみる。
■人材を育成する
・5~10年を必要とする。「ものをつくる前に人をつくる」(松下幸之助)
・人材育成は投資。人材の成長が止まれば、会社の成長も止まる
・儲かる会社は、人を大切にする会社、社員のモチベーションが高く組織としての力がしっかりと発揮できている会社
・少ない人数で多くの儲けを生み出す会社が優れた会社であり、その源泉となるうのはやはり人。社長がこの意識を忘れたとき、会社の成長は止まる
Posted by わくわくなひと at
21:26
│Comments(10)
2011年01月27日
ドラッカーやビジョナリーカンパニーをベースにした実践書
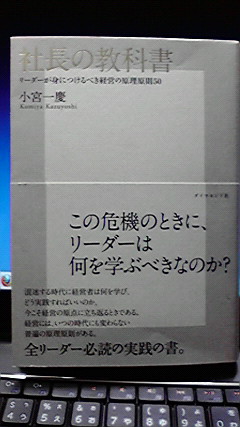 小宮一慶『社長の教科書 リーダーが身につけるべき経営の原理原則50』ダイヤモンド社(2010年2月18日第1刷)。
小宮一慶『社長の教科書 リーダーが身につけるべき経営の原理原則50』ダイヤモンド社(2010年2月18日第1刷)。これも年末に読んで、2日の夜に線を引いたところを書き抜いた社長業自習本の一つです。松下幸之助、ドラッカー、ビジョナリーカンパニーを土台に、コンサルタントとしてのご自分の経験を踏まえた書かれた本です。ドラッカーの教えやビジョナリーカンパニーに書いてあることを、具体的にどう自分のものにしていくか分かりやすく書いてありました。
特に、心に残ったのは、以下の内容です。これらの部分を再読することで、これから自分が何に関心を持って何をしようとしているのかが整理されて分かってきました。
・良書をたくさん読む。松下幸之助『道をひらく』、渋沢栄一『論語と算盤』、安岡正篤『論語の活学』
■明日のために投資する
・5年後、10年後にこの会社をどうしようかと考えることは経営者の仕事
(ドラッカーによる経営者のやるべきこと)
①現在の事業の業績向上・・・既存の事業、市場、商品サービスをもっと深掘りする。これは徹底できるかどうかということ
②機会の追求・・・現在よりも一歩進めた商品やサービスを開発したり、販売地域を拡大する
③新規事業・・・まったく新しい事業を立ち上げる、まったく新しいことを始める
・どの会社も何をやればいいかは知っているが、それを従業員にやらせることができるかどうかが肝心
2 ビジョン・理念が会社の根本
■土台は考え方・目標よりも目的が大事
・儲けるためだけの会社に命をかけてまで働いてくれる人は少ない。それは使命感がないから
・会社にとってビジョンとは存在意義のこと。その存在意義をいかに明確にし、徹底するかということが経営者に求められる
■ビジョン・理念を確立し、徹底する
・大切なことは、それらを働く人すべてに徹底しているかどうか
・ビジョン・理念は「目的」であって、儲ける手段ではない
■ビジョンは自分の頭で考える
・「自分の目の黒いうちは、絶対にこのビジョン・理念は変えない、絶対やり抜く」-そのくらいの信念を持ったときに、社内にそれを発表する
・信念とは、自分の目が黒いうちは絶対に変えないもの
3 戦略立案の基本原則
・何をやって、何をやめるかということを決めるのが経営の重要な仕事
・他社のマネができない非常に付加価値の高い製品が作れるか
■戦略の基本は「他社との違い」を明確にすること
・大切なのは自社の強みを生かすこと
・強みがどこにあるのか、将来にわたってその強みを維持できるのかについての見極め
・お客さまが求めるQPSの組み合わせを見極め
・変わった世の中でも自社の強みが強みとしてあり続けられるのか
・自分達の強みが生かせる領域はどこなのか
■自分の得意分野に集中し徹底する
・外部環境を分析し、内部環境を分析して、自社の強みを生かせる分野はどこなのかを知り、そこにヒト、モノ、カネや時間などの資源を集中していく
■オンリーワンではなくナンバーワン
・ライバルが沢山ある中で、「あなたの会社しかない」と言われる会社づくりを
・比較されてもより良いと分かるQPSの組み合わせを創り出すことが、オンリーワンではなく「ナンバーワン」を目指すということ
■成功する経営者の五つの特徴
・せっかち。内心はせっかちだが、それは表に出さず、表面的にはゆったり構えている
・人を心から褒められる。人を褒められる人は相手の長所を見つけられる人
・悪いことは全部自分のせいと思えるか。うまくいったときは窓の外を見て、失敗したときは鏡を見る
・優しくて厳しい
・素直さ
以下は2日夜に書き抜いた箇所です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 経営という仕事と経営に対する考え方
■経営者がやるべき三つのこと
・企業の方向付け
・資源の最適配分
・人を動かす
■企業の方向付け
・何をやるか、やめるかを決めること
・自社のお客さまが何を求めているのかを見つけ出すこと。クォリティ(品質)、プライス(価格)、サービスのQPSの視点で見つけ出すこと
・QPSを見極めるためにお客さまのところへ行く
・ライバル会社の動向を知る
・素直な目でライバル会社のQPSを見極める
・小さいリスクを取りながら、アイデアや仮説を検証し、できるだけ早く検証結果を出して、次のステップへ進む
■資源の最適配分
・失敗の最大の原因は私利私欲。良い会社をつくり、儲けて、給料を沢山取ること
・「For the company」で働く
・真のリーダーとは会社全体のことを考えて発言できる人
・私利私欲だけでは会社は続かない。食べるのに困らなくなった後、それでもお金のために働くのか、それとも、仕事にもっと高い目的や目標を見いだせるかで、仕事の質やレベルが上がるかどうかが決まる
・良い仕事をして、お客さまに喜んでいただいて、従業員さんにも喜んでいただいて、社会に貢献して、その結果儲かる-そういう気持ちになれるかどうか
・「良い仕事をしよう」という良い欲を持てば、会社はうまくいく。利益は結果。良い会社をつくれば、結果として儲かる
■お客さま第一を徹底する
・いかにお客さま志向の会社をつくれるか
・伸びる会社は「お客さま第一」が目的になっている。「お客さま第一」が儲ける手段になっていると、儲かってしまえば「そろそろいいか」となってしまう。もしくは、より効率的に儲ける手段を考えることになる。
・お客さまのために、最良のQPSを常に提供し続けることを目的としていれば、終わりがない。それが伸びる会社と、そうでない会社の差となる。
・従業員は毎日楽しく仕事をしているか
・良い仕事をしなければ儲からない。良い仕事とは、結果として稼ぐことができる仕事
・目的は存在意義。目標とはその通過点
・企業の目的は何か。本来、企業は良い商品やサービスを社会に提供し、お客さまに喜んでいただくことを目的の一つとしている。さらに、それを通じて一緒に働いてくれる仲間を幸せにすることも目的の一つ。地域社会に貢献することも存在意義である。1億円分売れるくらいの良い仕事をする。
・数字が目的化してしまう会社は危ない。目標とすべきことが目的化している。働くのも楽しくない
・小さな行動を徹底する。大切なお客さまに対してはどんなときでも「さん」付けで呼ぶ、かかってきた電話は3コール以内に必ずとる。凡人は同じ行動を何度も繰り返すことによって意識や思想が高まる。
・リーダーが持つ優しさとは、中長期的にみんなを幸せにしてあげられるかどうかということ。お客さまを幸せにして、自分も含めて働いている人達を幸せにできるかどうかは、リーダーが持つ優しさにかかっている
・正しい信念を持つ。勇気は信念から生まれる。この会社を良くして、お客さまに喜んでいただいて、働いてくれている人にも幸せになってもらおうという信念があれば、厳しいことも言える
・正しい信念は長く読み継がれた本から学ぶ。聖書、仏教聖典、論語、老子、松下幸之助、稲森和夫
・良書をたくさん読む。松下幸之助『道をひらく』、渋沢栄一『論語と算盤』、安岡正篤『論語の活学』
・「みんなで幸せになろう」「会社を成功させることで、社会に貢献しよう」といった考え方は、「教える」のではなくて「伝える」こと。人に伝わるのは、伝えるべきことを自分が信じたとき
■「ダム経営」を心がける
・ヒト、モノ、カネにいつも余裕を持った経営をする。そのためには、良いときに貯めておく習慣をつける
■利益よりキャッシュ
・キャッシュポジションの低い会社は、借りられるうちに借りておいた方がいい
■明日のために投資する
・5年後、10年後にこの会社をどうしようかと考えることは経営者の仕事
(ドラッカーによる経営者のやるべきこと)
①現在の事業の業績向上・・・既存の事業、市場、商品サービスをもっと深掘りする。これは徹底できるかどうかということ
②機会の追求・・・現在よりも一歩進めた商品やサービスを開発したり、販売地域を拡大する
③新規事業・・・まったく新しい事業を立ち上げる、まったく新しい始める
・どの会社も何をやればいいかは知っているが、それを従業員にやらせることができるかどうかが肝心
2 ビジョン・理念が会社の根本
■土台は考え方・目標よりも目的が大事
・儲けるためだけの会社に命をかけてまで働いてくれる人は少ない。それは使命感がないから
・会社にとってビジョンとは存在意義のこと。その存在意義をいかに明確にし、徹底するかということが経営者に求められる
■ビジョン・理念を確立し、徹底する
・大切なことは、それらを働く人すべてに徹底しているかどうか
・ビジョン・理念は「目的」であって、儲ける手段ではない
■ビジョンは自分の頭で考える
・「自分の目の黒いうちは、絶対にこのビジョン・理念は変えない、絶対やり抜く」-そのくらいの信念を持ったときに、社内にそれを発表する
・信念とは、自分の目が黒いうちは絶対に変えないもの
■ソニーの社是
・今までにないもの、世の中にないユニークな商品を作って、日本の文化の向上に貢献する
・自分達の存在意義をしっかり持っている会社は、どんな時代にもブレない
↓
(案)生活者の心からの願いを意味のあるものに翻訳し、人々の豊かで幸せな暮らしの実現に貢献する
(案)生活者のニーズをかたちにし、人々の豊かで幸せな暮らしの実現に奉仕する
3 戦略立案の基本原則
・何をやって、何をやめるかということを決めるのが経営の重要な仕事
・他社のマネができない非常に付加価値の高い製品が作れるか
■戦略の基本は「他社との違い」を明確にすること
・大切なのは自社の強みを生かすこと
・強みがどこにあるのか、将来にわたってその強みを維持できるのかについての見極め
・お客さまが求めるQPSの組み合わせを見極め
・変わった世の中でも自社の強みが強みとしてあり続けられるのか
・自分達の強みが生かせる領域はどこなのか
■自分の得意分野に集中し徹底する
・外部環境を分析し、内部環境を分析して、自社の強みを生かせる分野はどこなのかを知り、そこにヒト、モノ、カネや時間などの資源を集中していく
■オンリーワンではなくナンバーワン
・ライバルが沢山ある中で、「あなたの会社しかない」と言われる会社づくりを
・比較されてもより良いと分かるQPSの組み合わせを創り出すことが、オンリーワンではなく「ナンバーワン」を目指すということ
4 マーケティングでお客さま第一を具体化する
・一度お客さまになっていただいた方に、いかにして「一生のお客さま」になっていただくかについて考えること
・ダメな会社というのは、新規営業が上手い
・既存顧客の売上げの増減が会社のバロメーター
・既存のお客さまをより大切にする方が、結果的に儲かる
・口コミ、いわゆる代弁者が増えると、下手な広告宣伝をしなくても、売上げは伸びていく
・そのためには①一番は偉い!②あなたは特別③感動を生むを実践すること
■一番は偉い!
・お客さまにとっての「主観的一番」になる。主観的一番でないと関係を深めてもらえない
■あなたは特別
・一人ひとりのお客さまを「特別」に扱えるかどうか
・従業員にも「あなたは特別」を実践する
・お客さまでも従業員でも、一人ひとりが「自分は特別だ」と思えるような会社の仕組みを作れるどうかが、会社がうまくいくかどうかを左右する
■感動を生む
・いかにして感動を生み出すか
・マニュアル通りやっても感動は生まれる
・「このサービスは良かった」「この商品はよかった」と感じたら、書き留めることを繰り返していると、自分が満足するとき、感動するときの感覚が分かるようになる
■感謝と工夫
・「有難い」という感覚のない会社、経営者は、長期的に良い商品やサービスを提供できない
・自分がやれる範囲の中でベストなことは何かということを常に考え、それをお客さまに提供すること
5 会計と財務の本質
■財務諸表は、安全性、収益性、将来性の三つを見る
・安全性の指標でいちばん大切な手元流動性
・自己資本比率、流動比率、手元流動性を必ず一定以上に保つ
・資産利益率は5%以上が目安
■ファイナンスの基本はダム経営
・何にせよ大切なことは、キャッシュをできるだけ多く持っておくこと
■売上ではなく利益
・利益を伴わない売上げは資金繰りを圧迫するだけ
・売上高も上げ、利益も出して、さらにはキャッシュフローもプラスにするような経営を
■手元流動性を確保する
・手元に現金がどれだけあるかを知っておくこと。
・月商1ヶ月分の手元流動性は必須
・資金繰りを心配しなくていいだけの現金を持つ
■月初には預金残高を確認する
・キャッシュこそが会社の実力
6 ヒューマンリソース・マネジメント
■人は理屈では動かない
・人は「幸せ」についてくる
・会社は働く幸せと経済的な幸せを提供
■モチベーションより働きがいアップ
・働きがいが上がればモチベーションは自然に上がる
・お金や地位では働きがいは高められない
・褒めることで働きがいは高められる
・売上高や利益は目標であって目的ではない
・「褒める」社風を、会社の中に築いていく
■楽しく働ける仕組みをつくる
・従業員がよく集まる場所に、大きめのポストイットで、「○○さん、ありがとう」のコーナーをつくる
7 リーダーシップとリーダーの姿勢
■指揮官先頭
■成功する人は素直
・聞く姿勢、聞く態度を見れば、その人の練れ具合が分かる
・部下に対しても、会社に対しても、ちょっとしたことを徹底できる、もう一歩踏み込めるかどうかで、会社の行く末は変わる
・部下の話にメモが取れるか
・成功する人に共通するのは気配りや小さな行動を徹底すること
■素直の3ステップ
・第一ステップは「聞く」こと
・第二ステップは「良いと思ったことは、やる」こと
・第三ステップは「やり続ける」こと
■成功する経営者の五つの特徴
・せっかち。内心はせっかちだが、それは表に出さず、表面的にはゆったり構えている
・人を心から褒められる。人を褒められる人は相手の長所を見つけられる人
・悪いことは全部自分のせいと思えるか。うまくいったときは窓の外を見て、失敗したときは鏡を見る
・優しくて厳しい
・素直さ
Posted by わくわくなひと at
20:48
│Comments(2)
2011年01月27日
つねに黒字に導き、大いに働き、そして遊び、人生を謳歌する!
 長谷川和廣『社長の財布』経済界(2010年12月22日初版第1刷)。
長谷川和廣『社長の財布』経済界(2010年12月22日初版第1刷)。昨年末、TSUTAYAで背表紙を見かけ一度手に取りました。しかし、その時は買うまでに至らず、「やはり読んでみたい、のぞき見したい」という気持ちになり、1週間後に買いました。そう思わせたのは、たぶん“社長の財布”というネーミングでしょう。
ところで、年末年始は1日しか休みがとれませんでした。ありがたいことに、年末に年度末までの新たな仕事、それも自分たちの強みが生かせそうな仕事が3つも舞い込み、いきなりトップギアを入れました。それでも年末年始は社長業の勉強をしようと決めていましたので、3冊の本を読みました。この本は社長業の自習本の一つです。
お金や利益は自分の行動の結果と先輩経営者たちからよくご指摘を受けます。ときどきは、こういう書物を読んで気持ちを新たにすべきですね。と言っても、私は読んだことはすぐ忘れますので、何とか体で憶える必要があります。それで、1日の夜だったか、本に線を引いた箇所をワードに打ち込みました。
ほとんどがお金と人の話です。お金と人とに真摯に向き合います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・経営とは全社員の努力をいかに効率よく、“お金という数字”に置き換えるかという作業
・黒字と赤字の差、それはたった1円の差でも天と地を分ける差である
・何がなんでも黒字にするという執着心、1円でもムダ金を使わないという心構え
・Work hardを肝に銘じて会社や自分の部署をつねに黒字に導き、心に余裕を持って大いに働き、そして遊び、人生を謳歌する
第1章 お金で成功する人、失敗する人
01 人は感情の生き物。だから心からの感謝の気持ちがお金につながる!
・人は褒めて育てろ
02 金は不思議なものだ。借りるときは得した気分に、返すときは損した気分になる
・お金の場合は、相手の本心が「目元と口元に出る」
03 お金をもらう側の考え方、お金を払う側の考え方
・「自分の給料は自分で決める」という考えを強く持っている人を育てる
04 やる気が出るまで待っていたら何ひとつできない!
・やる気が出ないときほど、ムリに働いてみる-。
第2章 できる人は「情報」をお金に変えるのがうまい
01 「知」や「情報」に払う労力や金額を惜しみすぎるな!
・自腹を切る人と切らない人の間には、実際の成果に大きな差がある
・毎日必ず直帰する人と、たまには帰りに取引先と食事をして情報交換している人とでは、たったの半年で大きな能力の差が出てしまう
02 締め切った社長室だと都合のよい情報しか入ってこない
03 仕事に必要な情報の90%以上は自分の身の回りで揃えることができる
・一途に仕事をしていれば、必要な情報の90~95%は勝手に入ってくる
04 多くの人が手にできない情報を一人占めするには?
・お金持ち同士が金持ちでいられるのは、そこに情報が集まるから
05 “本当の儲け”というものは何か?それを知らない人はマネジメントに失敗する
・利益を優先的に考えて逆算していく発想が、業績を上げるノウハウである
06 合理的、かつ迅速に仕事をするための究極のツールは?
・知恵を絞って考え抜かれたフォーマットやテンプレート
07 戦略家がいる会社、いない会社
・組織内に企業戦略家を育てれば社長の財産に
・自社を有利な立場に導くことができる人。具体的には中長期のスパンで、シェアを取って利益を上げることのできる人
08 ライバルと比べて微妙な差を見つけてくれば財布はふくらんでいく!
・マーケットを拡大する手法のひとつが、いかに“微妙な差”を見つけて新たな商品を作り出すかにある
・新しい市場を見つけ出すということは、「独占的なスタートを切ることができる」という大きなアドバンテージを持つことになる
09 値下げ競争に突入すると、会社の財布はスッカラカンになる
・ライバル会社が値下げをしたら、「チャンス到来!」と思え。その間に、高品質の商品を高い値段設定で発売し、差別化を計ると同時に、しっかり利益を確保する
10 糖尿病会社に気をつけろ!
・「これくらいの経費を使っても大丈夫だろう」「少々赤字になったけど問題ないだろう」「今月は目標に達しなかったけど、まぁいいだろう」という会社は糖尿病
・貸借対照表の数値をしっかり見ると、危ない部分がわかり、素早い対応できるもの
11 会社のカルテは貸借対照表と損益計算書。危ない兆候は、必ずココに表れる!
・損益計算書に財務で特に重要になる項目や経営戦略などを書き加えた『戦略経営会計書』を作成し、全社員に徹底させる
12 公私混同は社長の特権なのか?
・中小企業は自腹を切ったり、保証人になったりして、大いに公私混同をして、やっと会社を回しているのが実情。しかし、儲かったときほどフンドシを締め直すのが商売の鉄則
13 従業員たちは一番のコストに気づかない。社員と経営者の感覚の違いが表れるのはこの部分!
・社員というのは、人件費に対して無頓着。給料が天から降ってくると思っている社員もいるくらい
・しかし、真っ先にリストラは考えない。まず従業員を効率的に使うことを考える。
14 下手な経費削減をすると利益のほうが削減されるリスクも!
・経営で『節約』を考えるとき、それは『効率化』という言葉と置き換えて考えなければならない
15 タイム・イズ・マネーの本当の意味とは?
・ひとつは「時間はコストである」
・もうひとつは「時間はお金を生産する」
16 時間はお金!ムダを作り出しているのは自分自身なのだ!
①仕事には、必ず優先順位をつける
②達成目標時間を設定する
③多くの仕事を一度に抱えない
④一日の計画を立てる
⑤書類やメモ、机などを整理しておく
⑥先延ばしにする性格を改める
⑦あせらない、短気は損気と心得る
17 一日のスタートが大切!たった5分の出遅れで大差がついてしまう
①今日も気分よく、前向きにクヨクヨしないでやろう
②今日の計画をもう一度、確認しよう
③ただちに仕事に取り組もう
④やりかけの仕事はさっさと片付けよう
⑤新しい企画を3つは考えよう
第3章 節約やリストラでは“利益”は出ない!
01 社員を減らしても赤字は減らない!
・従業員は資産であり、多くの価値を生み出すパワーであると考えて、それを十二分に有機的に動かすシステムをつくっていく
02 結果を出す人ばかりを厚遇していると、組織は必ず壊れていく
・日頃スポットライトが当たらない仕事を忠実にこなしている人や目立たない部署で懸命に働いている人たちがモチベーションをなくさない職場づくり
03 会社を経営するには高等数学なんか必要ない。現状把握できればいい
・大胆に方向転換すべきか、方針は間違っていないのだからこのまま勝負するか
・現状を把握できる貸借対照表や損益計算書から浮かび上がる数字を一瞥して問題点や修正点をイメージする能力が、社長には必要
04 ピカピカのベンツとクタクタの社員
05 知的腕力を持たない社長はいつまでたっても社員からなめられる
・バカ殿状態にしてくる社員がいる。論理的に問題点を挙げて厳しく糾弾できる、そんな知力と腕力が必要
06 儲けから考えると儲からない。人に何かを与えることから思考しなさい!
・商売の鉄則はまず、「お客様に何を与えるのか」を考えること
・調子が落ちたときこそ、実績を上げようと焦る前に、自分がお客様や上司、取引先の“役に立っているかどうか”を考えてみること。すると道は必ず開けてくる
07 誇りを持って社員たちが働く。そのための金と労力を惜しんではいけない
・全社員を集めて「皆さんのお子さんたちが『うちのお父さんはこの会社に勤めているんだ』と自慢できる会社にしましょう」と訴えかけると同時に、不正やごまかしを許さない体制づくりをする。そしてお客様のみならず、社会の利益になるような商品開発や事業展開を心がける。すると、みるみる社員たちの目の色ややる気に満ちあふれてくる
08 “感受性”が鈍い会社は弱い。儲ける会社はどこも問題発見能力が高い
・強い会社とは、問題発見者が問題解決者になっている会社
・「こんな問題が起きたけど、自分ならこうするべきだと思う」と、問題の解決法までに頭が及ぶ社員ばかりの会社が強い
・一人ひとりが現場で起こった問題点とその解決策を考えることは、商機を逃さない会社になるための条件
09 財布をふくらませるために、ますはあなたの人格をふくらませなさい!
・金より何より大切なのは人格。信用がないために引き出せないのは、何もお金だけではない。情報や才能、アイデアや商機・・・、これらを信用できない人に提出しようという人はいない
10 社長が社内をウロウロしている会社ほど実は儲かる!
・陣頭に立って闘う姿は、何よりも部下たちを鼓舞する
第4章 考える前に行動。動かなければお金は手に入らない!
01 頭がよくなると大儲けができなくなる。無能でもいいから、“動く人”になりなさい
・どうしたらできるか工夫し、何回もチャレンジする。実はこういうトライ&エラーを繰り返すことほど仕事の能力を伸ばす訓練はない。
02 大ヒット商品は現実感覚や皮膚感覚を持っている経営者から生まれる
03 失敗から学べない経営者からは新たな失敗しか生まれない!
04 部下のモチベーションこそ利益に直結する。それがわかっていない経営者は最悪です
05 社長の技能は“目標設定能力”に表れる・・・
06 経費削減効果がもっとも高いのは決断のスピードを上げること
07 買収されるくらい魅力な人になりなさい!しかし、買収されそうな人を優遇するのは止めなさい!
08 “損か得か”の判断スピードを上げれば上げるほど、成功する機会が増えてくる!
09 楽天やユニクロが社内文書を英文化した理由を考えてみました・・・
・「やるか、やらないか」をハッキリと述べなくてはならないから
10 頼られる人になれないなら、せめて“頼まれる人”になりなさい
・社長営業ができるのは大きなメリット。契約の前段階から社長が顔を出して経緯を把握することで、相手も信用してビッグビジネスを成立しやすい
11 意識的に会話の中に数字を入れる。それだけで“真剣さと厳しさ”が身につく!
12 ストックばかりに目がいく会社は儲からない。フローにも目を向けて、お金の流れに勢いをつけよう
・お金は使ってナンボ。ため込みすぎると腐ってしまって、いざというときに役に立たない水のようなもの
・ムダに見えても、設備を充実させたりすると社員のモチベーションも上がるし、周囲にも伸びている会社というイメージを植え付けることになる
第5章 残業代を惜しむ会社は生き残れない!
01 “ちょっと成功した後”が一番危ない!
・ちょっとした成功を元手に、新たな成功を勝ち取り、社員に還元するくらいの気持ちは持たないと、かえって会社を傾ける結果になりかねない
02 価値を演出するからお客様が手を出してくれる
03 マラソンの高橋尚子さんが強かったのは、猛練習の中から自分の限界を知ったから
・ハードワークを経験して自分のできるところできないところの見極めがついている社員は、ムリそうなら他人に仕事を任せる、または上司に手伝ってもらうことをいとわない。マラソンと同じように、自分の限界から逆算して、ゴールまでどういう作戦でたどり着くかを上手にマネジメントすること
04 世界に飛び出すために知っておいてもらいたいたったひとつのこと
・お金に固執するような人を高く評価する社会は、どんな国にもない
05 信用しすぎて痛い目に合うな!
06 ビジネスは魚釣り。喰いついたら、その勢いに乗れ!
07 取引先との食事・・・。会計の場面ですぐに財布を引っ込める人は信用できません!
08 簡単な話術で相手の気持ちを鷲づかみにする方法
09 社員の残業代を惜しむな。誤ったコスト意識が経営をダメにする
・仕事にはコストがかかって当然-そんな腹が定まってない人物に経営を任せていると、会社は決して発展しない
10 儲かっていない会社ほど、他人のムダ遣いを気にとめていない
11 ビジネスでは拙速を尊ぶべし!そして、指示を出す場合は3つのポイントを守るべし!
①何をして欲しいか
②いつまでにその作業を完遂して欲しいか
③何のためにその作業が必要なのか(目的を示す)
第6章 ゴールを示せば、お金は後からついてくる
01 怒鳴るよりも褒めるほうが儲かる!
02 叱責しても直らない部下の悪癖。見捨てる前に、現実的な解決策を探ってみよう
03 社員たちを小役人化してしまうとビジネスの迫力が生まれない!
04 ビジョンを示さないトップは社内に混乱をもたらす
05 使いっぱなしで「はい、ご苦労さん!」では絶対に人は育たない
06 本人がやる気にならない限り才能は開花しない
07 やる気や熱意をうわべだけで計るマネージャーは、もっとも無能な管理職!
・口先だけの熱意では意味がない。評価の基準は具体的な戦略イメージと戦略計画を持ち、それを実践に移す能力があるかどうかが決め手
08 上司こそ礼儀正しく。「おい、お前!」では部下は動かない
・キチンと名前を呼ぶ
09 わずかな傾きに気づくか気づかないか。経営センスはそこで測れる!
①間違った予測に基づく戦略ミス
②収益性の管理が下手
③仕事を徹底的にやり込んでいない
④製品に競争力がなくなっているのに気づかない
⑤社長が遊びなどに夢中で社員を顧みない
第7章 “財布”を見れば経営能力がわかる
01 不況のときこそ、経営者は社員より苦労しなさい
・自分が相手の2倍3倍働き、その姿を見せる
02 権力で人を動かそうとすると、パフォーマンスを落としてしまう!
・権力とは強制力を背景に人を従わせるパワー、そして権威とは強制力がなくても人を納得させることができるパワー
03 理念があるかないか。それが企業の強さを決める
04 会社の体質改善を図りたいなら、若手社員の意識を変えよう!
・社内の5%の人を意識改革できれば、その熱い火は社内全体に広がっていく
05 経営を支える力は8つのチェックですぐわかる!
①社長はもともと営業部や企画部などの現場出身である
②会議では、社員よりも社長から企画を出すことが多い
③たとえ利益が出ても、筋が通らないことは部下にさせない
④異例の人事を断行することがある
⑤社員が社長の悪口を言うのをほとんど聞いたことがない
⑥社長の言葉遣いや発言内容を、すぐに思い浮かべることができる
⑦上層部の人間が会社の夢や目標をよく語っている
⑧社長の言うことが首尾一貫している
06 営業に強い経営者こそ学ぶところが多い!
・マーケティングや営業の実務能力こそが求められる。なぜなら、どんな仕事にもお客様があり、それらはすべて利益に結びつく営業活動であり、この能力がなければ重要な決断など何ひとつ下せない。
・新規事業や新製品を自分で企画立案できるくらいの発想力や構想力も必要。単に金勘定や組織づくりに長けているだけでは有能な社長とは言えない
07 誰からも好かれるために“お金にきれいな人”と呼ばれたい!
・経営力や財政センスを身につけるための第一歩は財布の整理
08 意味もわからずに“戦略”という言葉を使っていませんか?
・戦略とは“自社を有利に導く計画実行力”
09 企業の財布の中身はこんなところに表れる!
①重要な社員や有能な社員が突然退社していく
②社長の名刺に本業以外の肩書きがたくさん書かれている
③社長が外国車を何台も所有している
④ビジネス経験のない二代目が社長を継いでいる
⑤支払いが現金から手形に変わる
⑥手形の決済までの期間が長くなる
⑦仲間取引が急激に増える(反対に急に減るにも危ない兆候)
⑧経営者がほとんど会社にいない
⑨会社に見慣れないに人間が出入りしている
⑩トイレやゴミ箱の中など、見えない部分が汚い
10 安売り競争を仕掛けるなら製造コストを極限まで絞ってからでないと自分の首を絞めるだけ!
①競合他社に負けない価格
②最終消費者が値ごろ感を持てる価格
③製造コストに利益を乗せた価格
11 ツキを呼び込む会社とツキに見放される会社。その差はココにある!
①数年に1度は新規事業を展開している
②会議で提案される企画数がかなり多い
③ライバル社のヒット商品に敏感。ヒット要因をすぐに分析・研究する
④社長の交際半径が広い。話題の人物にもコネを持っている
⑤今、売れている製品・サービスに経営資源を集中させる柔軟性がある
⑥実績を上げた社員を抜擢する(組織が年功序列ではない)
・ツキというものを分析すれば、他より多くの機会を作り出し、その機会から生まれた成功の芽を大きく育てることができる力
12 叱られ役をつくるときは有能な人から選びなさい!
13 社長の財布の作り方
・財布をズボンの尻ポケットに入れない
・お札はきれいにそろえてから財布にしまう
・1円を笑う者は1円に泣く
Posted by わくわくなひと at
20:00
│Comments(5)



