2011年02月23日
芥川賞!「きことは」書き写すと凄い。「苦役列車」は強烈
 第144回昭和22年度下半期芥川賞が決定。数週間前に同僚から「文藝春秋」を借りて読みました。
第144回昭和22年度下半期芥川賞が決定。数週間前に同僚から「文藝春秋」を借りて読みました。受賞したのは、文学の名門で育った朝吹真理子の「きことわ」と、中卒・逮捕歴ありの西村賢太「苦役列車」。
「きことわ」の洗練された文章と、社会の底辺でうごめく「苦役列車」の文章。素人判断では「朝吹真理子がもっと人生の経験を積めば、読みたくなる小説を書くかも知れない」。これが宮本輝の表現になると、「誰に言われなくても、朝吹さん自身が、みずからそれを求めて、作風に鑿や鉋を深く加え始めるときが必ず訪れるであろう。」。しかし、書き写してみると、この人の凄さが分かりそうな気がします。西村賢太は強烈!青汁を飲んで、「まずい!もう一杯」というよりも、今度はどんな刺激で勝負してくるか気になりました。
「きことわ」で線を引いたのは、以下のところ。
居間からひろがる一面の庭、柳に美男葛、百日紅、名を知らない丈高の草木がきりなく葉擦れし、敷石の青苔が石目をくくむ。はやばやと葉を落とした裸木のあるところは光線がじかに落ち、土がひかりを吸う。
“土がひかりを吸う”。この言葉に痺れました。書き写していたら、ボキャブラリーと感受性が並みの人ではないことが分かってきました。
「苦役列車」は最初からストレートパンチを食らったような感じ。
・・・パンパンに朝勃ちした硬い竿に指で無理矢理角度をつけ、腰を引いて便器に大量の尿を放ったのちには、・・・
「文藝春秋」には選評が載るから面白い。以下は記憶しておきたい箇所。
▼島田雅彦「はじめてのおつかい」
・・・本当に新規な作品は過半数の支持など得られはしない。芥川賞も基本、保守である。だが、保守こそ「わかりやすくて目新しいもの」を求めるのも事実だ。・・・
▼高樹のぶ子「五感の冴え」
「きことは」は触覚、味覚、聴覚、嗅覚、そして視覚を、間断なく刺激する作品、この感受性の鋭さは天性の資質だ。感覚で摑まえたものを物や事象に置き換え、そこに時間の濃淡や歪みを加えて、極彩色の絵画を描いてみせた。・・・身体の実感を言語化するとき、ともすれば自分流儀な表現に陥りがちだが、具体的な物や事象に置き換える、つまり客観性を与えて提示できる力がある。・・・文章に韻律というかリズムがあり、これも計算されたというより、作者の体内から出てくるもののように感じた。・・・良い文章とは、音楽的な抑揚に富んでいるもので、そこに「空」や「無常」の感覚がうっすらと、しかも明るく加わっているのだから・・・
▼池澤夏樹「時間をめぐる離れ業」
一般に小説とはストーリーである。一人または複数の人々の身の上に何かが起こり、それがいろいろに推移して、結果に至る。時は一方へと流れる。
しかし、この通常の方法では書けないテーマが一つだけある。人間にとって時間とは何か、という大きな問題。
ただ事象の後ろを追って走るだけではつかみきれない、過去と今、今と未来の間の意識の頻繁な行き来、が我々にとっての時間というものの本当の姿ではないか。
朝吹真理子さんの「きことは」は時間というテーマを中心に据えた作品である。
▼石原慎太郎「現代のピカレスク」
・・・
朝吹氏の作品に対比して西村賢太氏の「苦役列車」は、これはまた体臭の濃すぎる作品だが、この作者の「どうせ俺は-」といった開き直りは、手先の器用さを超えた人間のあるジェニュインなるものを感じさせてくれる。
超底辺の若者の風俗といえばそれきりだが、それにまみえきった人間の存在は奇妙な光を感じさせる。
▼黒井千次「淡い光と濃い闇」
・・・「きことは」が・・・更に記憶や夢がその世界の時間を切り刻み、混ぜ合わせ、過去と現在とを重ね合わそうとする。これだけの独自の時空を生み出すのは、淡い色合いを思わせる言葉の力であるらしい。何が書かれているかより、いかに書かれているかにより強い興味が引かれるような候補作は珍しい。・・・「苦役列車」は、・・・一つ一つの行為にどこかで微妙なブレーキがかけられ、それが破滅へと進む身体をおしとどめるところにリアリティーが隠されているように思われる。・・・
▼宮本輝「小説の濃淡」
ジグソーパズルの小さなピースに精密でイメージ喚起力の強い図版が描かれてあって、そのピースを嵌め込んで完成した全体図は奇妙に曖昧模糊とした妖しい抽象画だというのが朝吹真理子さんの「きことわ」である。・・・
誰に言われなくても、朝吹さん自身が、みずからそれを求めて、作風に鑿や鉋を深く加え始めるときが必ず訪れるであろう。・・・
Posted by わくわくなひと at
21:49
│Comments(2)
2011年02月23日
ドラッカー読むだけで会社は良くなるの?
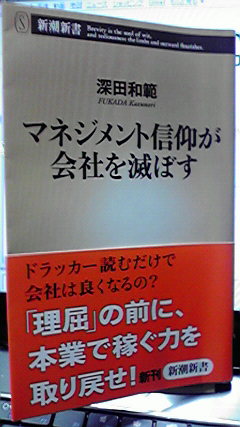 やっぱり出ましたね。深田和範『マネジメント信仰が会社を滅ぼす』新潮新書(2010年12月20日第1刷)。
やっぱり出ましたね。深田和範『マネジメント信仰が会社を滅ぼす』新潮新書(2010年12月20日第1刷)。“もしドラ”がたくさん売れて、経営に関係ない人たちまでドラッカーが読まれた一年でした。当然、副作用もありそうなので、こんな本は必要です。ドラッカーを好んで読んでいる人も余計なお世話だけど読んだ方がいいと思いました。いきなり、「こんな本読めるか」と思った方は、この本が言う「マネジメント信仰」の信者かも知れないと思ったりもしました。
そういう私は、けっこうドラッカーを読んでますし、ドラッカーはすごいと思います。自分にはちょっと難しくて、どうやったら頭で理解するのではなく腹で理解することができるかで悩んでいます。つまり、実行、実践したいと思いますが、会社は自分一人ではないし生ものですので、さてどうするか。「そう簡単ではないぞ」と思ってしまうのであります。
この本の「まえがき」に、『もしドラ』を読んで「すぐに実践できる」と思い込んで、書いてあることを真似している。そんな人が急激に増えているというように書いてありました。私は少数派かも知れませんけど、『もしドラ』読んで、「確かにそうだが、実行するのは並大抵のことじゃない」と即刻思いました。会社経営を経験していると、腹の底から分かるじゃないかと思いますが、ドラッカーが書いていることを実践できることは凄いことです。というよりも、小学生にも笑われるような当たり前のことができたら、凄い会社になれると、今では思ってます。
ドラッカーが書いていることではないでしょうが、「社員にトイレ掃除を徹底的にやらせて倒産した会社」があると書いてありました。これに私は、ぴったり該当しましたが、まだ皆様のおかげで生き延びております。ただ、社員にやらせたわけではなく、トイレクイックルを即刻買ってきて自分でトイレ掃除をしました。きれいなトイレは気分がいいですね。少なくともマイナス思考にはなりませんので、長く続けていると悪いことは少なくなりますよ。断言します。
ただ、この本で深田さんが言いたかったことは、分かります。共鳴する部分が相当ありました。
三言で言うなら、生身の仕事をしている者、経営している者、そして真剣に組織を預かっている者は、「単なる評論家や学者になるな!」「そんなことをしていたら会社潰れるよ」「理屈を言う前に稼ぎなさい」ということだと思います。
構造的な不況が長く続いているので、みんな自信を失い、何かの指南にすがりつきたい。そんな時代が招いた『もしドラ』ブームの一面もあったことと思います。
「ドラッカーはこう言っている。だから、自分の言っていることは正しい。」。そんな議論もよく見かけるようになりました。こんな議論を聞いて、数十年前の「マルクスはこう言っている。だから、こうなんだ」という記憶が蘇ってきました。
それぞれのドラッカーがあっていい。ドラッカーをいっぱい読んでいるから、その人の考えや行動が正しいとか偉いとか、権威があるとは言えない。なぜなら、たとえ何度読んだとしても、経験や真剣味がないと腹の底から理解できないことがドラッカーの言葉の中にはたくさんあるからです。少なくとも、評論家や学者のためにドラッカーは書いていないと思います。日々、真剣勝負している人に向けて書いていると思います。
あなたが属する組織や集まりは「マネジメント信仰」症状にどこまで冒されているか?この本からピックアップしてチェックリストを一つだけ作りました。
あなたの周りに、こんな組織や集まりがありませんか?
~意見はあっても意志はなし症状~
□経営者や管理職が、「あるべき論」や「一般論」を言うばかりで意志を示さない。
□意志を示すべき人が議論を本質から外そうとする。細かいことや表現方法にこだわり、議論を集約して、次の段階に移ろうという動きが見えない。あわよくば、うやむやにしようという意図すら感じられることがある。
□他社事例やマネジメントの本に書いてあったことによって物事を決めようとする。「他社でもこうしているから」「一般的にこういうものだから」(「ドラッカーの本にこう書いてあるから」)という理由がまかり通るようになる。
□体系的な理論や手法を重んじ、「経験、勘、度胸」を馬鹿にする。「理論的、客観的」であることが正しく、「経験論や主観に基づく判断」は誤ったものと決め付けている。
□「~戦略」「~改革」等の用語を好んで使う。「具体的にどうなるか」よりも、関係者に「どのように受け止められるか」「どうすればスマートな表現になるか」ということばかり気にする。
□同じようなテーマのプロジェクトが数年おきに立ち上がる。前回のプロジェクトが中途半端な状態で終わっていても、その反省もないまま次のプロジェクトが始まる。
□消去法で物事を判断する。いくつかの選択肢をあげて最もリスクの少ないものを選ぼうとする。その結果、ありきたりな案しか選ぶことができなくなっている。
Posted by わくわくなひと at
18:40
│Comments(6)
2011年02月23日
頑張れ!クライストチャーチNZ
 クライストチャーチの地震にびっくりしました。
クライストチャーチの地震にびっくりしました。今日の新聞はいつもと違って眺めるのではなく読みました。
イギリスよりもイギリスっぽい街。ガーデンシティ。
あの美しい街が大地震に遭うなんて。あの煉瓦づくりの大聖堂も壊れた。
クライストチャーチの人々、そして訪れていた日本人にも死者が出ている。
自分には何にもできませんが、早く地震がおさまって復興してもらいたい。
気のせいか。最近、贔屓にしている街で惨事が起こり続けています。
ツーソンAZ、クライストチャーチNZ・・・。
ずいぶん前になりますが、プーケットに行って、その二三ヶ月後にプーケットは大津波に遭いました。
あの時の人たち、地中海クラブの人たちはどうなったのかと思っていると、三ヶ月後に、大変だったけど笑顔で生きているという写真付きのクリスマスカードが来ました。
新聞のクライストチャーチの記事にはコンクリートだったら、こんな惨事にならなかったと書いてありました。でも、煉瓦じゃないとクライストチャーチではないと思います。簡単にコンクリートにせず耐震対策を十分にした煉瓦とイングリッシュガーデンを復活させてもらいたいと願っています。
Posted by わくわくなひと at
13:19
│Comments(0)



